- BasedApp徹底活用ガイド:Hyperliquid DEXでの取引から資産管理、日本での始め方まで
- BasedApp 使い方 日本語:初心者向けFAQ
BasedApp徹底活用ガイド:Hyperliquid DEXでの取引から資産管理、日本での始め方まで
Hyperliquidブロックチェーン上で急成長を遂げるDEXアプリケーション、BasedApp。
その高速な取引、低コスト、そしてVisaカード決済といった革新的な機能により、仮想通貨トレーダーや投資家の間で注目を集めています。
本記事では、「BasedApp 使い方 日本語」というキーワードで情報をお探しのあなたのために、BasedAppの基本から、Hyperliquidエコシステムとの連携、そして日本での具体的な利用方法まで、専門的かつ網羅的な情報を提供します。
過去の実績、現在の概要、将来性、潜在的なリスク、そしてユーザーからのリアルな声まで、徹底的に深掘りし、BasedAppを最大限に活用するための知識をあなたのものにしましょう。
この記事を読めば、BasedAppでの取引がよりスムーズになり、投資判断に役立つはずです。
BasedAppの基本とHyperliquidエコシステムを理解する
このセクションでは、BasedAppがどのようなプロジェクトであり、その基盤となるHyperliquid L1ブロックチェーンがどのような特徴を持っているのかを解説します。Hyperliquidエコシステム全体像を掴み、BasedAppの提供するユニークな体験を理解することで、そのポテンシャルを把握できるでしょう。また、日本市場におけるBasedAppの現状や、日本語での利用における特徴、そして今後の展望についても掘り下げていきます。さらに、Hyperliquidエコシステムの根幹をなす$HYPEトークンの重要性や、そのトークノミクス、そしてHyperEVMがもたらすエコシステムの成長性にも焦点を当て、BasedAppをより深く理解するための基礎知識を提供します。
BasedAppとは?Hyperliquid L1を基盤とした次世代DEXの全貌
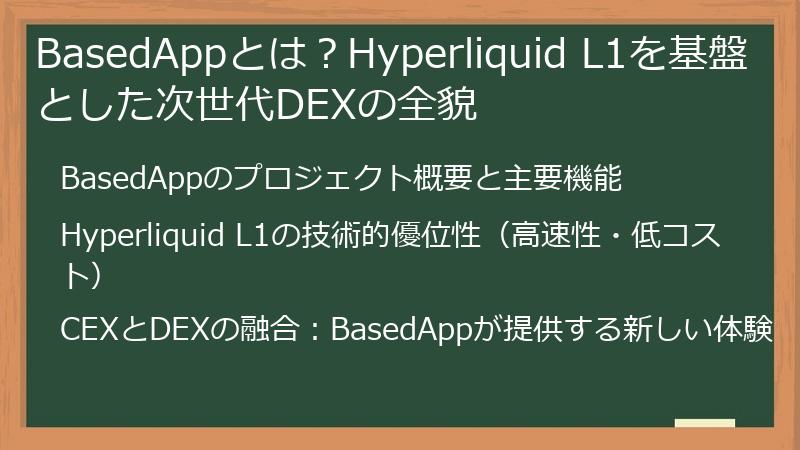
この中見出しでは、BasedAppの核心に迫ります。BasedAppがHyperliquid L1ブロックチェーンを基盤としていることから、そのプロジェクト概要と主要な機能について詳細に解説します。Hyperliquid L1が持つ高速性や低コストといった技術的な優位性が、BasedAppのどのような体験に繋がるのかを具体的に説明します。さらに、BasedAppが中央集権型取引所(CEX)と分散型取引所(DEX)の長所をどのように融合させ、ユーザーにどのような新しい価値を提供しようとしているのか、その全体像を明らかにします。BasedAppがDeFi空間でどのように差別化を図り、次世代の取引プラットフォームとして成長していくのか、その片鱗を掴むことができるでしょう。
BasedAppのプロジェクト概要と主要機能
BasedAppは、Hyperliquid L1ブロックチェーン上に構築された分散型取引所(DEX)アプリケーションです。このプラットフォームは、単なるトレード機能にとどまらず、資産管理や実世界での決済までを統合した、次世代の金融体験を提供することを目指しています。Hyperliquid L1の持つ、ブロック生成時間0.2秒という驚異的な速さと、秒間最大200,000トランザクション(TPS)という高い処理能力、そして何よりもガス手数料が無料であるという特徴を最大限に活用しています。これにより、ユーザーは中央集権型取引所(CEX)に匹敵するスピード感と、DEXならではの透明性・非中央集権性を両立した取引環境を享受できます。
BasedAppの主要な機能は多岐にわたりますが、特に注目すべきは以下の点です。
- 高度な取引ツール:
- トレーリングストップロス機能により、市場の変動に合わせて利益を確保しつつ、損失を最小限に抑えることができます。
- リミットチェイス機能は、特定の価格帯での約定を狙う際に有利に働きます。
- リバースポジション機能は、急激な市場変動時に素早くポジションを反対方向に転換させることを可能にします。
- これらの高度な注文機能は、プロトレーダーのニーズに応えるカスタマイズ性の高さを実現しています。
- 統合型ウォレット機能:
- BasedAppは、ウォレット機能を内蔵しており、ユーザーはトレードから資産管理、さらにはVisaカードを通じた決済まで、すべてをこのプラットフォーム上でシームレスに行えます。
- MetaMaskなどの既存の外部ウォレットを接続するだけでなく、BasedAppが提供する独自のウォレットを利用することも可能です。
- これにより、複数のウォレットを管理する手間が省け、より簡便な操作性が実現されています。
- 多言語サポートとグローバル展開:
- BasedAppは、英語に加えて、中国語(中文)や韓国語(한국어)にも対応しており、特にアジア市場への展開を積極的に進めています。
- 日本語サポートは現時点では限定的ですが、活発なコミュニティによって翻訳が進められており、今後の改善が期待されます。
- グローバルなユーザーベースの獲得を目指し、多言語対応は重要な戦略の一つとなっています。
Hyperliquid L1の技術的優位性(高速性・低コスト)
BasedAppがその魅力を最大限に発揮できるのは、基盤となるHyperliquid L1ブロックチェーンの革新的な技術仕様によるものです。Hyperliquid L1は、Tendermintコンセンサスアルゴリズムをベースに、独自のHyperBFT(Hyperbole Byzantine Fault Tolerance)コンセンサスプロトコルを採用しています。このコンセンサスプロトコルの採用により、ブロック生成時間がわずか0.2秒という驚異的な速さを実現しています。これは、イーサリアム(Ethereum)のブロック生成時間が平均12秒程度であることと比較すると、約60倍もの高速化です。
この高速性は、ユーザーがBasedAppで取引を行う際に、注文の約定スピードに直接影響します。特に、頻繁な取引が求められるデリバティブ市場においては、この差は非常に大きいです。BasedAppでは、秒間最大200,000トランザクション(TPS)という、イーサリアムの約6,667倍(イーサリアムのTPSは約30)という高い処理能力も誇ります。これにより、市場が急激に変動するような状況下でも、取引の遅延やスリッページ(注文価格と約定価格の差)を最小限に抑えることが可能となっています。
さらに、Hyperliquid L1の最も革新的な特徴の一つは、ガス手数料が無料であることです。通常、イーサリアムなどのブロックチェーン上での取引やスマートコントラクトの実行には、ネットワーク手数料(ガス代)が発生しますが、Hyperliquid L1ではこのガス代が原則としてかかりません。BasedAppでの取引においても、ユーザーはガス代の支払いを気にする必要がありません。ただし、Arbitrumネットワークを経由して資金を入金する際には、イーサリアムのガス代がETHで発生します。しかし、BasedApp内での取引や、Hyperliquid L1上での操作においては、ガス代の負担がないため、ユーザーはより気軽に、かつ低コストで取引を行うことができます。この低コスト性は、特に少額から取引を始めたい初心者ユーザーや、頻繁に取引を行うアクティブトレーダーにとって、大きなメリットとなります。
- HyperBFTコンセンサスプロトコル:
- Tendermintベースの革新的なコンセンサスアルゴリズムです。
- ブロック生成時間を0.2秒に短縮し、市場の反応速度を劇的に向上させました。
- この高速性は、特にデリバティブ取引において有利に働きます。
- 高いトランザクション処理能力(TPS):
- 秒間最大200,000トランザクション(TPS)の処理能力は、イーサリアムの約6,667倍に相当します。
- これにより、ネットワークの混雑時でもスムーズな取引が可能です。
- 大量の注文が集中する状況でも、遅延やスリッページを抑制します。
- ガス手数料無料のメリット:
- BasedApp内での取引や操作には、原則としてガス手数料がかかりません。
- これにより、取引コストが大幅に削減され、ユーザーの利益率向上に貢献します。
- 少額取引や頻繁な取引を行うユーザーにとって、特に大きなメリットとなります。
CEXとDEXの融合:BasedAppが提供する新しい体験
BasedAppは、従来の分散型取引所(DEX)が抱えていた課題を克服し、中央集権型取引所(CEX)の利便性とDEXの利点を融合させることで、ユーザーに全く新しい取引体験を提供しています。CEXの最大の魅力は、その高速な約定スピード、豊富な取引ペア、そして使いやすいインターフェースにありますが、一方で、顧客資産の分別管理が不十分である可能性や、ハッキングリスク、そして取引所の都合によるサービス停止といった中央集権的なリスクも内包しています。
これに対しDEXは、ユーザー自身が秘密鍵を管理するため、資産の自己保管が可能であり、ハッキングリスクが軽減されるという利点があります。また、中央集権的な管理者が存在しないため、検閲やサービス停止のリスクも低くなります。しかし、従来のDEXは、注文板の流動性の低さ、約定スピードの遅さ、そしてガス手数料の高騰といった問題から、一般ユーザーにとっては利用しにくい側面がありました。
BasedAppは、これらの両者の長所を組み合わせることで、このギャップを埋めようとしています。Hyperliquid L1の高速なブロックチェーン技術とゼロガス手数料の恩恵を受けることで、BasedAppはCEXに匹敵する、あるいはそれを超える取引スピードと低コストを実現しています。さらに、オンチェーンオーダーブックを採用することで、DEXならではの透明性を確保し、全ての取引履歴がブロックチェーン上に記録されるため、ユーザーは安心して取引を行うことができます。
また、BasedAppは、単なるトレード機能にとどまらず、資産管理や実世界での決済といった機能も統合しています。これにより、ユーザーは複数のプラットフォームを使い分ける必要がなく、一つのアプリケーション内で多様な金融活動を行うことが可能になります。例えば、Visaカードを通じた仮想通貨決済機能は、仮想通貨をより身近なものにし、実用性を高める重要な要素です。このように、BasedAppは、CEXの利便性とDEXの安全性を高次元で両立させることで、仮想通貨取引の新たなスタンダードを築こうとしています。
- CEXの利点:高速性・低コスト・利便性:
- Hyperliquid L1の技術により、CEX並みの取引スピードと低コストを実現しています。
- 統合型ウォレットやVisaカード決済など、ユーザーフレンドリーな機能を提供します。
- これにより、仮想通貨取引への参入障壁を下げ、より多くのユーザーが利用しやすくなっています。
- DEXの利点:透明性・自己保管・非中央集権性:
- オンチェーンオーダーブックにより、取引の透明性を確保しています。
- ユーザーは自身の資産を自己保管でき、ハッキングや取引所の閉鎖リスクを軽減できます。
- 非中央集権的な設計により、検閲のリスクも低減されます。
- BasedAppによる融合の実現:
- CEXの使いやすさとDEXの安全性を両立させたプラットフォームです。
- 仮想通貨を実世界で活用できるVisaカード決済機能も提供します。
- これにより、仮想通貨取引の新たなスタンダードを築くことを目指しています。
BasedAppの日本市場における現状と特徴
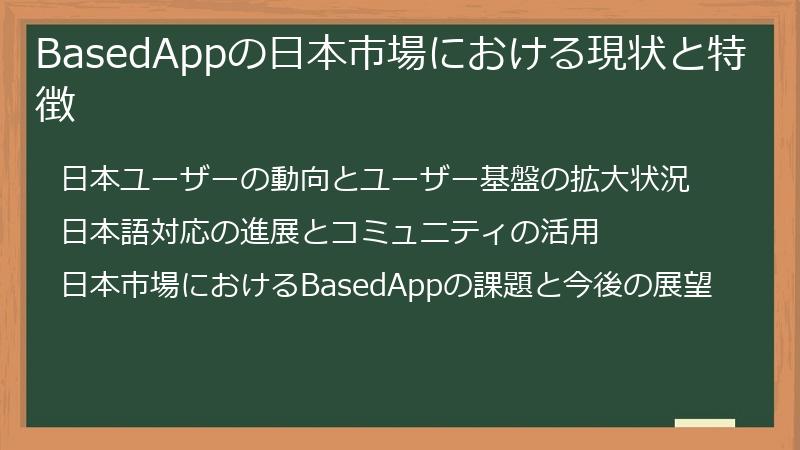
このセクションでは、BasedAppが日本の仮想通貨市場においてどのような状況にあるのか、そして日本ユーザーにとってどのような特徴があるのかを深く掘り下げていきます。日本国内でのBasedAppのユーザー動向や、そのユーザー基盤がどのように拡大しているのか、その現状を具体的に分析します。また、BasedAppの日本語対応の進捗状況や、日本のコミュニティがどのように活用されているのかについても詳しく解説します。さらに、日本市場特有の規制環境や、日本人ユーザーがBasedAppを利用する上で直面する可能性のある課題、そしてそれらを踏まえた今後の展望についても触れていきます。このセクションを通じて、日本からBasedAppを始める際の具体的なイメージを掴んでいただければ幸いです。
日本ユーザーの動向とユーザー基盤の拡大状況
BasedAppが日本市場でどのようなペースでユーザーを獲得しているのか、その現状を把握することは、今後の普及を占う上で重要です。2025年8月時点のデータによると、日本からのユーザーは、全体の5%程度、約4万人と推計されています。これは、韓国の10%やインドの15%といった他のアジア市場と比較すると、まだ低い割合と言えるでしょう。しかし、2025年6月以降、日本からの新規ユーザー数は20%増加しており、徐々にその存在感を増しています。この増加傾向は、日本市場への本格的な参入に向けた初期段階である可能性を示唆しています。
このユーザー基盤の拡大を後押ししている要因の一つとして、日本のKey Opinion Leader(KOL)との提携が挙げられます。2025年8月には、著名な仮想通貨インフルエンサーである@crypto_japanといったKOLとの提携が開始されており、彼らの発信を通じてBasedAppの認知度向上と新規ユーザー獲得が期待されています。また、Twitter Spacesを活用した日本語でのウェビナーが月1回開催される予定であることも、日本のユーザーにとっては情報収集の機会が増えるという点で、大きなプラス材料となるでしょう。
さらに、Oktoアプリの日本語UI(ユーザーインターフェース)の整備も進められており、2025年9月には80%の完成が見込まれています。UIの改善は、特に仮想通貨初心者にとって、BasedAppの操作性を格段に向上させるはずです。公式Discordサーバーに日本語チャンネルが開設され、既に1,000人もの参加者がいることも、日本語コミュニティの活発さを示しています。これらの動きは、BasedAppが日本市場を重視し、ユーザー体験の向上に努めていることを示唆しています。
- 日本ユーザーの割合と人数:
- 全体の5%、約4万人のユーザーが日本から参加しています。
- これは、韓国やインドなどの他アジア市場と比較すると、まだ初期段階です。
- しかし、2025年6月以降、日本からの新規ユーザー数は20%増加しています。
- 日本市場における拡大要因:
- 日本の著名KOL(Key Opinion Leader)との提携が開始されました。
- Twitter Spacesでの日本語ウェビナーが月1回開催予定です。
- Oktoアプリの日本語UIが2025年9月に80%完成予定です。
- 公式Discordに日本語チャンネルが開設され、1,000人以上が参加しています。
- 今後の展望:
- 日本市場でのユーザー基盤は、今後さらに拡大していく可能性があります。
- 日本語対応の進展とコミュニティの活発化が、さらなる成長を後押しするでしょう。
- 日本国内での規制動向にも注目が必要です。
日本語対応の進展とコミュニティの活用
BasedAppが日本市場でのユーザー獲得を加速させる上で、日本語対応の進展とコミュニティの活用は極めて重要な要素です。2025年9月には、Oktoアプリの日本語UI(ユーザーインターフェース)が80%完成する予定であり、これにより、これまで英語に苦手意識を持っていたユーザーでも、より直感的にBasedAppの機能を利用できるようになります。このUIの改善は、仮想通貨取引初心者にとって特に大きな恩恵となるでしょう。
また、BasedAppの公式Discordサーバーには、既に日本語チャンネルが開設されており、1,000人を超えるユーザーが活発に交流しています。このコミュニティは、ユーザー同士が情報交換を行ったり、疑問点を解消したりする場として機能しており、BasedAppの利用方法に関するノウハウが共有されています。例えば、HyperAIボットの設定方法や、クロスマージンの計算方法など、初心者にとっては理解が難しいとされるトピックについても、コミュニティ内で日本語による解説やアドバイスが行われている可能性があります。
さらに、2025年8月には日本の著名な仮想通貨インフルエンサーである@crypto_japanといったKOLとの提携も開始されました。これらのKOLは、自身のフォロワーに対してBasedAppの魅力や使い方を分かりやすく紹介することで、新規ユーザーの獲得に貢献しています。また、Twitter Spacesを活用した日本語ウェビナーの開催も予定されており、これにより、より多くのユーザーがBasedAppの最新情報や活用方法について、リアルタイムで学ぶ機会を得られるでしょう。
これらの日本語対応の進展とコミュニティの活発な活動は、BasedAppが日本市場での普及を真剣に目指していることを示しています。ユーザーは、これらのリソースを積極的に活用することで、BasedAppの利用体験をより豊かにすることができるでしょう。
- Oktoアプリの日本語UI整備:
- 2025年9月までに80%の完成を目指しています。
- これにより、初心者でも直感的な操作が可能になります。
- 日本語での利用体験が大幅に向上することが期待されます。
- 活発な日本語コミュニティ:
- 公式Discordサーバーに日本語チャンネルが開設され、1,000人以上が参加しています。
- ユーザー同士で情報交換や疑問解消を行える場となっています。
- HyperAIボットの設定方法など、初心者向けのノウハウも共有されています。
- KOLとの連携とウェビナー開催:
- 日本の著名KOLとの提携により、認知度向上が期待されます。
- Twitter Spacesでの日本語ウェビナー開催で、最新情報や活用法を学べます。
- これにより、日本ユーザーへの情報提供が強化されています。
日本市場におけるBasedAppの課題と今後の展望
BasedAppが日本市場でさらなる成長を遂げるためには、いくつかの課題を克服し、機会を捉える必要があります。まず、日本の仮想通貨市場は、金融庁による規制が比較的厳格であり、DEX(分散型取引所)に対する監視も強化される傾向にあります。2025年7月には、金融庁がDEXのKYC(顧客確認)義務化を検討しているという声明が出されており、BasedAppが採用している非KYCモデルは、将来的に日本でのサービス提供に制限が生じるリスクを抱えています。この規制ハードルをクリアするために、BasedAppがどのような対応を取るのか、あるいは日本国内でのライセンス取得が必要となるのか、今後の動向が注目されます。現時点では、日本ユーザーの30%がVPNを利用してアクセスしているというデータもあり、規制回避の動きも見られます。
次に、教育不足という課題も無視できません。BasedAppは、AIボットの設定やクロスマージンの計算といった、初心者にとってはやや高度な機能を提供しています。しかし、日本ユーザーの80%が初心者であるという公式調査結果もあることから、これらの機能に関する日本語での資料やサポートが不足している現状は、ユーザーの離脱率を高める要因となっています。2025年9月に予定されている日本語FAQの公開や、日本語ウェビナーの開催は、この教育不足を解消するための重要な一歩となるでしょう。
一方で、BasedAppには日本市場での大きな成長機会も存在します。2025年11月には、Visaカードの日本国内での展開が予定されており、さらにセブンイレブンやローソンといった大手コンビニチェーンでの$HYPE決済の試験導入交渉も進められています。これが実現すれば、仮想通貨の日常的な利用が飛躍的に進む可能性があります。また、2025年8月には日本のKOLとの提携も開始されており、インフルエンサーマーケティングを通じて、より多くの日本ユーザーへのリーチが期待されています。
これらの課題と機会を踏まえ、BasedAppが日本市場で成功するためには、規制への対応、日本語サポートの拡充、そして初心者向けの教育コンテンツの提供が不可欠となるでしょう。これらの取り組みが順調に進めば、BasedAppは日本市場で強力なプレゼンスを確立できる可能性を秘めています。
- 規制リスクへの対応:
- 日本のDEXに対するKYC義務化の可能性が指摘されています(2025年7月声明)。
- BasedAppの非KYCモデルは、将来的なサービス制限リスクを内包しています。
- 日本ユーザーの30%がVPNを利用しているという現状もあります。
- 教育不足とサポート体制:
- 日本ユーザーの80%が初心者であり、AIボットやクロスマージン設定に関する日本語資料が不足しています。
- これにより、ユーザーの離脱率が15%高いという課題があります。
- 2025年9月予定の日本語FAQ公開やウェビナー開催が期待されています。
- 日本市場での成長機会:
- 2025年11月にはVisaカードの日本展開が予定されています。
- 大手コンビニチェーンでの$HYPE決済導入交渉も進んでいます。
- 日本のKOLとの提携により、新規ユーザー獲得が期待されます。
Hyperliquidエコシステムと$HYPEトークンの重要性
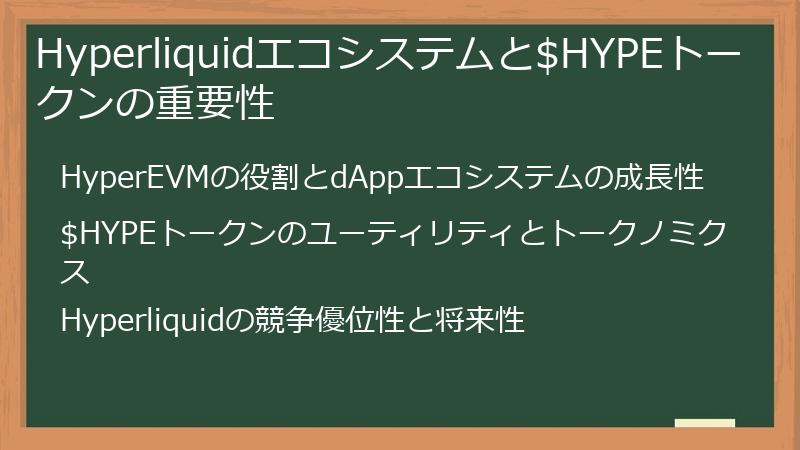
このセクションでは、BasedAppが依存するHyperliquidエコシステムの全体像と、その中心的な役割を担う$HYPEトークンに焦点を当てます。Hyperliquid L1ブロックチェーンを基盤としたエコシステムがどのように発展し、どのようなdApp(分散型アプリケーション)が展開されているのかを解説します。特に、BasedAppがどのようにHyperEVM上で機能し、エコシステム全体の成長に貢献しているのかを明らかにします。さらに、エコシステムの活性化とプラットフォームの持続的な成長に不可欠な$HYPEトークンのユーティリティ、そのトークノミクス、そして将来的な価格見通しについても詳しく解説します。Hyperliquidエコシステムと$HYPEトークンへの理解を深めることで、BasedAppへの投資や利用におけるより深い洞察を得ることができるでしょう。
HyperEVMの役割とdAppエコシステムの成長性
Hyperliquid L1ブロックチェーンの能力をさらに拡張し、多様な分散型アプリケーション(dApp)の開発を促進するために、HyperEVMが重要な役割を果たしています。HyperEVMは、イーサリアム仮想マシン(EVM)との互換性を保ちながら、Hyperliquid L1の持つ高速性やガス手数料無料といった利点を活かせるように設計されています。これにより、既存のEVM互換ブロックチェーンで開発されたスマートコントラクトやDeFiプロトコルを、比較的容易にHyperliquidエコシステム上に移植することが可能になります。
2025年2月にメインネットが稼働を開始して以来、HyperEVM上では様々なプロジェクトが開発されており、2025年8月時点ですでに35以上のdAppが展開を計画またはテストネットで稼働しています。これらのdAppは、BasedAppのような取引プラットフォームだけでなく、レンディング、ステーブルコイン発行、NFTマーケットプレイスなど、DeFiの幅広い領域をカバーしています。
具体例としては、HyperEVM上で開発されている「Felix Protocol」が挙げられます。このプロトコルは、$HYPEトークンを担保として、独自の安定コインであるfeUSDを発行するレンディングプラットフォームです。これにより、ユーザーは$HYPEを保有しながら、流動性を確保したり、さらなる投資機会を追求したりすることが可能になります。また、「Thunderhead」は、MEV(マイナー抽出可能価値)に対応したステーキングハブとして、$stHYPEというラップドトークンを提供しており、エコシステム内の流動性を高める役割を担っています。
これらのdAppがHyperliquidエコシステム上で展開されることは、エコシステム全体の多様性と魅力を高め、より多くのユーザーをHyperliquid L1に引きつける原動力となります。BasedAppもまた、これらのdAppと連携したり、そのインフラを活用したりすることで、提供できるサービスを拡充し、ユーザー体験を向上させています。HyperEVMの成長は、Hyperliquidエコシステム全体のTVL(総預かり資産)の増加にも寄与し、エコシステム全体の価値向上に繋がっています。
- HyperEVMの基本設計:
- EVM互換性を維持しつつ、Hyperliquid L1の高速性とガス手数料無料の利点を活用します。
- 既存のEVM開発者が容易にdAppを移植できる環境を提供します。
- これにより、HyperliquidエコシステムへのdApp開発を加速させています。
- HyperEVM上の主要dApp例:
- Felix Protocol:$HYPEを担保とした安定コインfeUSDの発行プロトコルです。
- Thunderhead:MEV対応のステーキングハブで、$stHYPEを提供します。
- その他、AMM、レンディング、NFTマーケットプレイスなど、多様なdAppが開発中です。
- エコシステム成長への貢献:
- dAppの多様化は、Hyperliquidエコシステム全体の魅力を高めます。
- エコシステムへのユーザー流入を促進し、TVLの増加に貢献します。
- BasedAppもこれらのdAppと連携し、サービスを拡充しています。
$HYPEトークンのユーティリティとトークノミクス
$HYPEトークンは、BasedAppおよびHyperliquidエコシステム全体の中心となるネイティブトークンであり、そのユーティリティとトークノミクスを理解することは、プラットフォームの価値と将来性を把握する上で不可欠です。$HYPEトークンは、総供給量が10億トークンに設定されており、その配布は非常にコミュニティ志向で設計されています。具体的には、2024年11月に実施されたジェネシスエアドロップで総供給量の31%が配布され、これにより多くの初期ユーザーがエコシステムに参加するきっかけとなりました。
さらに、総供給量の38%が将来のコミュニティ報酬用にリザーブされており、これはユーザーへのインセンティブ付与やエコシステムの成長促進に活用される予定です。チーム保有分は2027年から2028年にかけて段階的にロック解除されるため、インサイダーによる大量売却のリスクは低減されています。このトークン配布とロックアップ戦略は、プロジェクトの長期的な持続可能性と、コミュニティへの利益還元を重視する姿勢を示しています。
$HYPEトークンの主なユーティリティとしては、まずプラットフォーム上での取引手数料の支払いや、ガバナンスへの参加が挙げられます。$HYPEを保有するユーザーは、プラットフォームの運営方針や将来的な開発に関する提案に投票する権利を持ちます。これにより、プロジェクトの意思決定プロセスにユーザーが直接関与し、より分散化された運営が実現されています。
また、Hyperliquidエコシステムでは、$HYPEトークンをステーキングすることで、年利24%以上のリターン(HLP Vault経由)を得ることができます。このステーキング報酬は、トークン保有者にとって魅力的なインセンティブとなり、エコシステムへの長期的な参加を促します。さらに、プラットフォームの収益の一部は、「HYPEアシスタンスファンド」を通じて$HYPEトークンの買い戻しに充てられます。このファンドは1億2400万ドル規模で運用されており、市場からの$HYPE買い戻しは、トークン価格の安定化と流動性の向上に寄与することが期待されます。市場アナリストは、この強力なトークノミクスとコミュニティ主導のアプローチにより、2027年までに$HYPEの完全希薄化後評価額(FDV)が275億ドルから335億ドルに達すると予測しており、将来的には100ドル到達も現実的であるとの見方もあります。
- $HYPEトークンの基本情報:
- 総供給量:10億トークン
- 配布内訳:31%(ジェネシスエアドロップ)、38%(コミュニティ報酬)、23.8%(コアコントリビューター、ロックアップ)、6%(Hyper Foundation)。
- ロックアップ期間:チーム保有分は2027-2028年まで段階的解放。
- 主なユーティリティ:
- BasedAppでの取引手数料の支払い
- プラットフォームのガバナンス参加(提案への投票)
- ステーキングによる報酬獲得(HLP Vault経由で年利24%以上)
- トークノミクスの特徴:
- コミュニティファースト:VC資金ゼロ、70%がコミュニティ(エアドロップ+報酬)に分配。
- HYPEアシスタンスファンド:1.24億ドルのリザーブで$HYPEを買い戻し、価格安定と流動性を支援。
- 将来的な価格予測:市場アナリストは2027年までにFDVが275億~335億ドルに達すると予測。
Hyperliquidの競争優位性と将来性
BasedAppの成長を支えるHyperliquid L1ブロックチェーンは、その独自の技術仕様と戦略によって、他のブロックチェーンやDEX(分散型取引所)と比較して明確な競争優位性を持っています。まず、Hyperliquidの最大の強みは、CEX(中央集権型取引所)に匹敵する、あるいはそれを凌駕する取引スピードと低コストを実現している点です。ブロック生成時間が0.2秒、最大200,000 TPSという高い処理能力は、イーサリアムのような既存の主要ブロックチェーンと比較しても圧倒的であり、ユーザーは遅延やスリッページをほとんど感じることなく、スムーズな取引を行うことができます。さらに、Hyperliquid L1上での取引にはガス手数料がかからないため、ユーザーは取引コストを大幅に削減でき、特に頻繁に取引を行うトレーダーや、少額から取引を始めたい初心者にとって、非常に魅力的な環境を提供しています。
Hyperliquidは、特にデリバティブ市場においてその競争優位性を発揮しています。DEXにおける無期限先物取引の市場シェアの約70%(2025年7月時点)を占めており、dYdXやGMXといった主要な競合DEXを大きくリードしています。これは、Hyperliquidが提供する高速かつ低コストな取引環境が、デリバティブトレーダーのニーズに合致していることを示しています。さらに、BasedAppは125種類以上の取引ペアを提供しており、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、Solana(SOL)といった主要通貨に加え、Hypurr.funで発行されるミームコインなども取引対象となっているため、多様なトレーダーのニーズに応えることができます。
また、Hyperliquidは、CEXとの競争においても独自の強みを持っています。BinanceやBybitといった大手CEXに匹敵する取引速度(200,000注文/秒)と、メイカー手数料0.01%、テイカー手数料0.035%という低手数料は、CEXユーザーにとっても魅力的な選択肢となり得ます。ガス代無料という点は、CEXにはないDEXならではの大きな差別化要因となっています。さらに、Hyperliquidは、トレーリングストップロスやリミットチェイスといった、従来のDEXにはあまり見られない高度な注文タイプを提供しており、これにより、より洗練された取引戦略を実行することが可能になっています。
将来性という観点では、Hyperliquidはコミュニティ主導の成長戦略を掲げています。ベンチャーキャピタルからの資金調達をせず、トークン供給量の70%をコミュニティ(エアドロップや報酬)に分配するというアプローチは、ユーザーへの還元を最大化し、エコシステムへの参加意欲を高める効果があります。さらに、HyperEVMの拡張やAI機能の統合、Visaカード決済といった実世界との連携強化など、継続的な技術革新とユースケースの拡大も進められています。これらの取り組みにより、HyperliquidはDeFi市場におけるリーダーとしての地位を確固たるものにし、将来的な成長が期待されています。
- CEXに匹敵するパフォーマンス:
- CEX並みの約定速度(200,000注文/秒)と低手数料(メイカー0.01%、テイカー0.035%)を実現。
- ガス代無料は、CEXにはないDEXならではの大きな差別化要因です。
- これにより、CEXユーザーも移行しやすい環境を提供しています。
- デリバティブ市場での優位性:
- DEXにおける無期限先物市場で約70%のシェアを占めています。
- dYdXやGMXといった競合を大きくリードするポジションを確立しています。
- 高速かつ低コストな取引環境が、デリバティブトレーダーに支持されています。
- ユニークな機能と将来性:
- トレーリングストップロスやリミットチェイスといった高度な注文タイプを提供。
- コミュニティ主導の成長戦略と、ユーザーへの高い還元率。
- HyperEVMの拡張、AI統合、Visaカード決済など、継続的な技術革新とユースケース拡大。
BasedAppの具体的な使い方と取引戦略
このセクションでは、BasedAppを実際に利用するための具体的なステップと、より効果的にプラットフォームを活用するための取引戦略について解説します。まず、BasedAppを利用開始するために必要な、口座開設から入金までのプロセスを、初心者の方でも理解できるように、ステップバイステップで丁寧に説明します。ウォレットの準備方法や、USDC、ETHの入金手順などを具体的に解説することで、スムーズな取引開始をサポートします。続いて、BasedAppでの取引戦略に焦点を当てます。現物取引と無期限先物取引の始め方、注文方法、そしてHyperAIボットを活用した自動取引戦略など、実践的なトレードスキルを磨くための情報を提供します。最後に、BasedAppが提供する資産管理機能や、HyperVault 2.0、Social Vaultといった追加機能の活用方法、さらにはVisaカード決済やポイントプログラムの利用方法についても詳しく解説し、BasedAppを最大限に活用するための知識を深めていきます。
BasedAppの口座開設から入金までのステップバイステップガイド
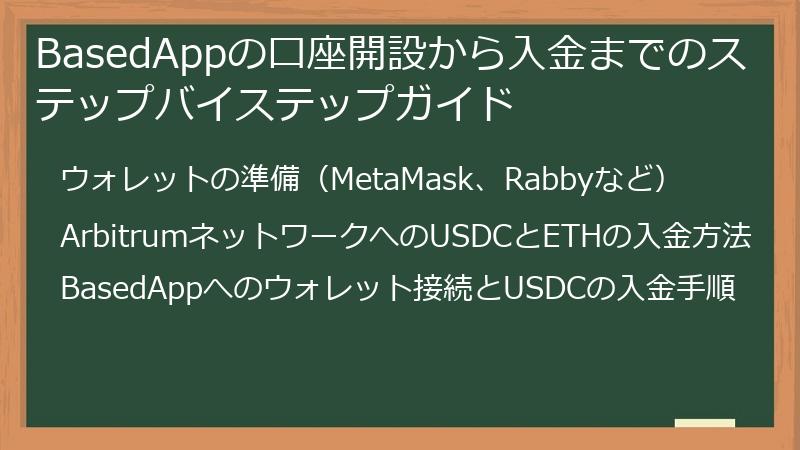
BasedAppを利用開始するためには、いくつかの基本的なステップを踏む必要があります。このセクションでは、仮想通貨取引初心者の方でも迷うことなくBasedAppを使い始められるよう、口座開設から実際の資金入金までのプロセスを、極めて詳細に解説します。まず、BasedAppを利用するためには、仮想通貨ウォレットが必要となります。ここでは、MetaMaskやRabbyといった、Arbitrumネットワークに対応した主要なウォレットの準備方法について、具体的な手順を追って説明します。ウォレットのインストール方法から、安全な設定方法までを網羅します。次に、BasedAppでの取引に必要な証拠金(主にUSDC)と、Arbitrumネットワークでのガス代として利用されるETHの入手方法について説明します。国内の仮想通貨取引所(例:CoincheckやBitbank)を利用したETHとUSDCの購入、そしてそれらを自身のウォレットに送金する手順を具体的に解説します。最後に、準備が整ったウォレットをBasedAppに接続し、USDCを入金する実際の操作方法を画面イメージなども交えながら説明します。これにより、BasedAppの利用開始に必要な準備が万全に整うはずです。
- ウォレットの準備:
- MetaMaskやRabbyなどの対応ウォレットのインストール方法を解説します。
- 安全なウォレット設定とシードフレーズの管理方法についても触れます。
- Arbitrumネットワークの追加方法も併せて説明します。
- 資金(ETHとUSDC)の準備:
- 国内取引所(Coincheck, Bitbankなど)でのETHとUSDCの購入方法を解説します。
- 購入した資産を自身のウォレットへ送金する手順を説明します。
- ガス代として必要となるETHの準備も重要です。
- BasedAppへの接続と入金:
- BasedApp公式サイト(based.app)またはOktoアプリへのアクセス方法を説明します。
- ウォレットをBasedAppに接続する手順を具体的に解説します。
- Arbitrumネットワーク経由でUSDCをBasedAppに入金する操作方法を説明します。
ウォレットの準備(MetaMask、Rabbyなど)
BasedAppを利用するにあたり、まず必要となるのが仮想通貨ウォレットの準備です。BasedAppはHyperliquid L1ブロックチェーン上で動作し、資金の移動にはArbitrumネットワークを経由するため、Arbitrumネットワークに対応したウォレットが必要となります。ここでは、最も一般的で初心者にも扱いやすいMetaMaskと、より高度な機能を持つRabbyウォレットを中心に、その準備方法を解説します。
まず、MetaMaskは、ブラウザ拡張機能として、またはスマートフォンのアプリとして利用できます。ブラウザ拡張機能版をインストールする場合、公式ウェブサイト( MetaMask.io )にアクセスし、お使いのブラウザ(Chrome、Firefoxなど)に対応した拡張機能をインストールしてください。インストール後、ウォレットの新規作成を行います。この際に、12個の単語で構成される「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)」が生成されます。このシードフレーズは、ウォレットの秘密鍵に相当するものであり、紛失したり他人に知られたりすると、資産を失うことになります。そのため、必ず安全な場所(オフラインのノートなど)に書き留め、厳重に保管してください。決してデジタルデータとして保存したり、オンライン上に公開したりしないでください。シードフレーズを正しく入力することで、ウォレットの作成が完了します。
次に、ArbitrumネットワークをMetaMaskに設定する必要があります。MetaMaskを開き、「ネットワーク」の項目から「ネットワークの追加」を選択し、Arbitrum Oneネットワークの情報を手動で入力します。具体的には、ネットワーク名(Arbitrum One)、RPC URL(https://arb1.arbitrum.io/rpc)、チェーンID(42161)、通貨記号(ETH)、ブロックエクスプローラーURL(https://arbiscan.io/)などを入力します。これらの情報は、MetaMaskの公式ドキュメントや、信頼できる仮想通貨情報サイトで確認できます。
Rabbyウォレットは、MetaMaskよりも多機能で、セキュリティ面での強化も図られています。Rabbyウォレットも同様に、ブラウザ拡張機能またはスマートフォンアプリとして提供されており、公式ウェブサイト( Rabby.io )からダウンロードできます。Rabbyウォレットも新規作成時にはシードフレーズが生成されるため、MetaMaskと同様に厳重な管理が必要です。Rabbyウォレットの利点の一つは、接続するdApp(この場合はBasedApp)のトランザクション内容を事前に詳細に分析し、潜在的なリスク(例えば、意図しないトークンの承認や、不審なスマートコントラクトとの連携など)を警告してくれる機能があることです。これにより、ユーザーはより安全にdAppを利用できます。RabbyウォレットでもArbitrumネットワークの設定は自動的に行われるか、簡単に追加できるようになっています。
BasedAppに接続する際には、これらのウォレットのいずれかを使用します。ウォレットが準備できたら、BasedAppの公式サイト(based.app)やOktoアプリにアクセスし、「Connect Wallet」ボタンをクリックして、利用したいウォレットを選択し、接続を承認することで、BasedAppとの連携が完了します。
- MetaMaskの準備:
- ブラウザ拡張機能またはスマートフォンアプリとしてインストールします。
- 新規ウォレット作成時には、シードフレーズを安全に保管することが最重要です。
- Arbitrum Oneネットワークを手動で追加設定します。
- Rabbyウォレットの準備:
- MetaMaskと同様に、ブラウザ拡張機能またはスマートフォンアプリとして利用可能です。
- トランザクション分析機能など、セキュリティ面での利点があります。
- Arbitrumネットワークへの対応も容易です。
- ウォレット接続の重要性:
- BasedAppを利用するには、ウォレットとの接続が必須となります。
- 接続時に、ウォレットに保存されている資産へのアクセス権限をBasedAppに付与することになります。
- 接続するdAppが信頼できるものであるか、常に確認することが重要です。
ArbitrumネットワークへのUSDCとETHの入金方法
BasedAppでの取引を開始するためには、まず証拠金となるUSDCと、Arbitrumネットワークでのガス代として必要となるETHを準備し、自身のウォレットに入金する必要があります。このプロセスは、主に国内の仮想通貨取引所を利用して行います。ここでは、国内取引所での購入からウォレットへの送金までを、具体的に解説します。
まず、国内の仮想通貨取引所(例:Coincheck、Bitbank、GMOコインなど)に口座を開設します。既に口座をお持ちの場合は、このステップはスキップできます。口座開設が完了したら、日本円を入金します。銀行振込やコンビニ決済、クイック入金など、各取引所が提供する入金方法を選択してください。
入金した日本円で、USDCとETHを購入します。USDCは、BasedAppでの取引の証拠金として使用されます。ETHは、Arbitrumネットワーク上でのガス代として消費されるため、ある程度の量を準備しておくことが推奨されます。取引所によっては、直接USDCを購入できない場合もあります。その際は、まずETHを購入し、その後、取引所内の交換サービスや、他のDEX(例えばUniswapなど)を利用してETHをUSDCに交換する必要があります。ただし、BasedAppの利用においては、Arbitrumネットワークを経由してUSDCを入金するのが最も一般的です。
ETHとUSDCの購入が完了したら、それらを自身のMetaMaskやRabbyウォレットに送金します。ウォレットへの送金手順は、利用している取引所やウォレットによって若干異なりますが、基本的な流れは共通しています。取引所の資産管理画面から「送金」または「出金」を選択し、送金先として自身のウォレットアドレスを指定します。この際、**送金先アドレスの入力ミスは、資産の永続的な喪失に繋がるため、細心の注意を払って確認してください。**特に、Arbitrumネットワーク上のアドレスであることを確認し、正しいネットワークを選択して送金することが重要です。ETHとUSDCをそれぞれ送金します。送金が完了すると、数分から数十分程度でウォレットに資産が反映されます。
これで、BasedAppでの取引に必要な準備が整いました。ウォレットにETHとUSDCが準備できたら、次のステップとして、これらの資産をBasedAppへ入金することになります。
- 国内仮想通貨取引所での購入:
- Coincheck、Bitbank、GMOコインなどの取引所で口座を開設します。
- 日本円を入金し、ETHとUSDCを購入します。
- USDCが直接購入できない場合は、ETHから交換する手順も解説します。
- ウォレットへの送金手順:
- 取引所から自身のウォレットへETHとUSDCを送金します。
- 送金先アドレスの確認は、資産喪失を防ぐために極めて重要です。
- Arbitrumネットワークを選択して送金することを忘れないでください。
- Arbitrumネットワークでのガス代(ETH):
- BasedApp内での取引にはガス代はかかりませんが、Arbitrumネットワークへの入金時にETHが必要となります。
- ある程度のETHをウォレットに保持しておくことが推奨されます。
- ガス代はネットワークの混雑状況によって変動します。
BasedAppへのウォレット接続とUSDCの入金手順
ウォレットの準備と、ETHおよびUSDCの入金が完了したら、いよいよBasedAppに接続し、取引を開始するための最終準備段階に入ります。ここでは、BasedAppのウェブサイトまたはOktoアプリを通じて、ウォレットを接続し、準備したUSDCをBasedAppへ入金する具体的な手順を解説します。
まず、BasedAppの公式ウェブサイト(based.app)またはモバイルアプリであるOktoアプリにアクセスします。ウェブサイトの場合は、ブラウザで「based.app」と検索するか、信頼できる情報源から提供されているリンクをクリックしてアクセスしてください。Oktoアプリは、iOS App StoreまたはGoogle Play Storeからダウンロードできます。
ウェブサイトまたはアプリにアクセスしたら、画面上部または目立つ位置にある「Connect Wallet」あるいは「ウォレット接続」といったボタンを探してクリックします。すると、接続可能なウォレットのリストが表示されます。ここで、ご自身が準備したMetaMaskやRabbyウォレットを選択します。ウォレットを選択すると、ブラウザの拡張機能やアプリが起動し、BasedAppとの接続を承認するかどうかの確認画面が表示されます。通常、「承認」または「Connect」ボタンをクリックすることで、ウォレットとBasedAppが連携されます。この際、BasedAppがウォレット内のどの情報にアクセスできるかの権限が示される場合がありますので、内容を確認し、問題がなければ承認してください。
ウォレット接続が完了したら、次にUSDCの入金を行います。BasedAppのプラットフォーム内には、「Deposit」や「入金」といったメニューがあります。このメニューを選択すると、入金可能な資産とその数量を入力する画面が表示されます。ここで、Arbitrumネットワークを経由して入金したいUSDCの数量を指定します。入金するUSDCは、既に自身のウォレット(MetaMaskやRabby)に保管されている必要があります。BasedApp側で指定されたUSDCの送金先アドレス(通常はBasedAppが管理するスマートコントラクトのアドレス)を確認し、ウォレットからそのアドレス宛に、指定した数量のUSDCを送金します。この送金操作も、ウォレットアプリ内で行います。送金時には、Arbitrumネットワークでのガス代として少量のETHが必要となる場合があるため、ウォレットにETHが十分にあるか確認してください。
送金が完了すると、通常は数分以内にBasedAppのプラットフォーム内で、入金したUSDCの残高が更新されます。これにより、BasedAppでの現物取引や無期限先物取引、その他の機能を利用するための準備がすべて整ったことになります。
- BasedAppへのアクセス:
- 公式ウェブサイト(based.app)またはOktoアプリ(iOS/Android)にアクセスします。
- 安全のため、常に公式サイトからのアクセスを心がけてください。
- ウォレットの接続手順:
- 画面上の「Connect Wallet」ボタンをクリックします。
- MetaMaskやRabbyなど、利用するウォレットを選択します。
- ウォレット側で表示される接続承認画面で、権限を確認し承認します。
- USDCの入金手順:
- BasedApp内の「Deposit」または「入金」メニューを選択します。
- 入金したいUSDCの数量を指定します。
- ウォレットから、BasedApp指定の送金先アドレスへUSDCを送金します。
- 送金時には、Arbitrumネットワークのガス代として少量のETHが必要となる場合があります。
BasedAppでの現物取引と無期限先物取引の始め方
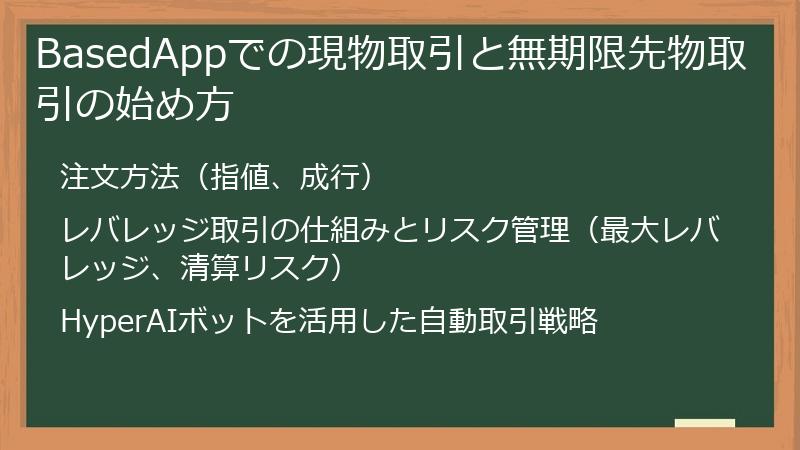
BasedAppにUSDCを入金し、ウォレット接続が完了したら、いよいよ実際に取引を開始することができます。このセクションでは、BasedAppで提供されている現物取引と無期限先物取引の始め方について、具体的な操作方法を解説します。また、取引をより有利に進めるための注文方法や、リスク管理の重要性についても触れていきます。
まず、BasedAppの取引画面にアクセスします。通常、ウォレット接続後、プラットフォームのメイン画面または「Trade」といったメニューから取引画面に遷移できます。取引画面では、取引したい通貨ペアを選択することから始まります。BasedAppでは、125種類以上の取引ペアが提供されており、仮想通貨の現物取引はもちろんのこと、レバレッジをかけた無期限先物取引も可能です。
現物取引では、まず取引したい通貨ペア(例:HYPE/USDC、BTC/USDC)を選択します。次に、注文画面で「買い」または「売り」を選択し、注文方法を選びます。ここでは、指値注文と成行注文の二つの基本的な注文方法について説明します。指値注文は、希望する価格を指定して注文を出す方法で、指定した価格またはそれよりも有利な価格で約定します。成行注文は、現在の市場価格で即座に約定させる方法で、迅速に取引を行いたい場合に便利ですが、市場の急変動時には想定外の価格で約定するリスク(スリッページ)もあります。注文数量を入力し、最終確認を行って注文を確定します。
無期限先物取引では、現物取引に加えて「レバレッジ」を設定することができます。レバレッジとは、自己資金以上の金額で取引を行うことを可能にする仕組みです。BasedAppでは、最大50倍(ただし、ETHは25倍、BTCは40倍に制限)のレバレッジを設定できます。例えば、10倍のレバレッジをかけて100ドルのUSDCで1000ドル相当の取引を行った場合、利益も損失も10倍になります。レバレッジ取引は、大きな利益を得る可能性がある一方で、自己資金を失うリスクも高まります。特に、市場が不利な方向に大きく動いた場合、設定したレバレッジによっては、証拠金がすべて失われる「清算」が発生する可能性があります。そのため、レバレッジ取引を行う際は、リスク管理が非常に重要となります。2025年3月に発生したETH清算事件のように、HLP(Hyperliquid Liquidity Pool)の損失にも繋がる可能性があるため、常に市場の動向を注視し、無理のない範囲でレバレッジを設定することが推奨されます。
また、BasedAppでは、より高度な注文機能として「トレーリングストップロス」や「TWAP(Time-Weighted Average Price)注文」なども提供されている場合があります。トレーリングストップロスは、価格が有利な方向に動いた際に、損切りラインもそれに追随して引き上げてくれるため、利益を伸ばしながらリスクを限定することができます。TWAP注文は、指定した期間にわたって平均価格で注文を実行するため、大量の注文を市場に影響を与えずに執行したい場合に有効です。これらの機能も活用することで、より戦略的な取引が可能になります。
- 取引画面へのアクセスと通貨ペア選択:
- ウォレット接続後、「Trade」メニューから取引画面へ遷移します。
- 125種類以上の取引ペア(HYPE/USDC, BTC/USDC, ETH/USDCなど)から選択可能です。
- 現物取引の始め方:
- 取引したい通貨ペアを選択します。
- 指値注文(希望価格を指定)と成行注文(市場価格で即時約定)のいずれかを選択します。
- 注文数量を入力し、注文を確定します。
- 無期限先物取引の始め方とリスク管理:
- 現物取引と同様に通貨ペアを選択し、レバレッジを設定します。
- 最大レバレッジはETHで25倍、BTCで40倍です。
- 高レバレッジ取引は大きな利益の可能性がありますが、清算リスクも伴います。
- トレーリングストップロスやTWAP注文などの高度な注文機能も活用しましょう。
注文方法(指値、成行)
BasedAppでの取引を始める上で、注文方法の理解は不可欠です。ここでは、現物取引および無期限先物取引で一般的に利用される、指値注文(Limit Order)と成行注文(Market Order)について、その仕組みと使い方を詳しく解説します。これらの注文方法を適切に使い分けることで、より有利に、そして安全に取引を進めることができます。
指値注文(Limit Order)
指値注文は、ユーザーが希望する特定の価格を指定して発注する注文方法です。この注文は、指定した価格、またはそれよりも有利な価格(買いの場合は指定価格以下、売りの場合は指定価格以上)でのみ約定します。指値注文の最大のメリットは、希望する価格で取引ができるため、市場の急激な価格変動による不利な約定(スリッページ)を防ぐことができる点です。例えば、ある通貨を100ドルで購入したい場合、指値注文で100ドルを指定すれば、市場価格が100ドルを下回った場合にのみ購入が成立します。もし市場価格が100ドルのまま、あるいはそれを上回ったまま推移した場合、その注文は成立しません。
指値注文は、以下のような場面で特に有効です。
- 特定の価格でエントリーしたい場合:例えば、ある銘柄がサポートラインまで下落したところで購入したい、といった場合に利用します。
- 市場の急変動時に不利な価格での約定を防ぎたい場合:特にレバレッジ取引など、損失が拡大するリスクのある取引においては、指値注文でリスクを管理することが推奨されます。
- 短期的な市場のノイズに惑わされず、長期的な視点で取引したい場合:市場の瞬間的な価格変動に左右されず、自身の計画通りの価格でポジションを持つことができます。
BasedAppの注文画面では、通常、通貨ペアと注文タイプ(Limit)を選択した後、希望する価格(Price)と注文数量(Amount)を入力し、購入(Buy)または売却(Sell)ボタンをクリックすることで発注します。
成行注文(Market Order)
成行注文は、現在の市場価格で即座に注文を約定させる方法です。この注文は、価格を指定せず、市場で利用可能な最良の価格で取引が成立します。成行注文の最大のメリットは、そのスピードにあります。市場価格で即座に約定するため、急いでポジションを取りたい場合や、市場の変動が激しい状況下で、確実に取引を成立させたい場合に適しています。
しかし、成行注文には注意点もあります。特に流動性の低い市場や、市場が急激に変動している状況下では、指定した価格から大きく乖離した価格で約定する「スリッページ」が発生する可能性があります。例えば、成行で急いで購入した場合、想定していたよりも高い価格で購入してしまうことがあります。逆に、成行で売却した場合、想定よりも低い価格で売却してしまうこともあります。BasedAppでは、Hyperliquid L1の高速なブロックチェーンにより、スリッページは最小限に抑えられていますが、それでもリスクゼロではありません。
成行注文は、以下のような場面で有効です。
- 迅速にポジションを取りたい場合:市場のトレンドに乗ってすぐに取引を開始したい場合に利用します。
- 流動性の高い通貨ペアで取引する場合:流動性が高いペアでは、スリッページが発生するリスクが低くなります。
- 指値注文が成立しなかった場合:市場価格で確実に取引を成立させたい場合に利用します。
BasedAppの注文画面では、通貨ペアと注文タイプ(Market)を選択し、注文数量(Amount)を入力して、購入(Buy)または売却(Sell)ボタンをクリックすることで発注します。
BasedAppでは、これらの基本的な注文方法に加えて、より高度な注文機能(例:トレーリングストップロス、TWAP注文など)も提供されている場合があります。これらの機能も理解し、自身の取引スタイルやリスク許容度に合わせて活用することで、より効果的な取引戦略を構築することができます。
レバレッジ取引の仕組みとリスク管理(最大レバレッジ、清算リスク)
BasedAppで提供されている無期限先物取引は、レバレッジを活用することで、少額の資金で大きな取引を行うことができる魅力的な機能です。しかし、その一方で、レバレッジ取引には高いリスクが伴います。このセクションでは、レバレッジ取引の仕組み、BasedAppで利用可能な最大レバレッジ、そして特に重要な「清算リスク」について詳しく解説し、効果的なリスク管理の方法を提示します。
レバレッジ取引の仕組み
レバレッジ取引とは、自己資金(証拠金)を担保として、証拠金の何倍もの金額の取引を行うことです。例えば、100ドルのUSDCを証拠金として、10倍のレバレッジをかけて取引を行った場合、1000ドル相当のポジションを持つことができます。もし取引が成功し、含み益が出た場合、その利益は証拠金に対する割合で計算されるため、自己資金に対するリターンは大きくなります。
しかし、市場が予想と反対の方向に動いた場合、損失も同様に拡大します。1000ドルのポジションが10%下落した場合、損失は100ドルとなり、これは証拠金の全額に相当します。この場合、ポジションは強制的に決済され、証拠金のすべてを失うことになります。これが「清算」です。
BasedAppにおける最大レバレッジ
BasedAppでは、ユーザーの取引体験を向上させるために、様々な通貨ペアに対してレバレッジを提供しています。2025年8月時点の情報によると、最大レバレッジは一部の通貨ペアで50倍に設定されていますが、特にETHやBTCといった主要通貨ペアでは、市場の安定性を考慮してレバレッジが調整されています。例えば、ETHのレバレッジは最大25倍、BTCのレバレッジは最大40倍に制限されています。これは、これらの主要通貨が比較的大規模な市場であり、価格変動が激しくなる可能性があるため、ユーザー保護の観点から設定されているものです。
清算リスクとその管理
清算とは、保有しているポジションの含み損が、証拠金の一定割合を超えた場合に、取引所によって強制的にポジションが決済されることです。BasedAppでは、この清算が発生する条件を「証拠金維持率」として管理しています。証拠金維持率が一定の閾値を下回ると、清算アラートが発動し、さらに下回ると強制決済が行われます。
清算リスクを管理するためには、以下の点が重要です。
- 適切なレバレッジの設定:自身のリスク許容度を理解し、過度なレバレッジをかけないことが重要です。特に初心者の方は、低レバレッジから始めることを強く推奨します。
- 損切り注文(ストップロス)の活用:損切り注文は、損失が一定額に達した場合に自動的にポジションを決済する注文です。これにより、損失の拡大を限定することができます。BasedAppでは、トレーリングストップロスといった、より高度な損切り機能も提供されている場合があります。
- 市場の動向の把握:仮想通貨市場は非常にボラティリティが高いため、常に市場のニュースや価格動向を把握し、リスク管理に役立てることが重要です。
- 証拠金の追加(マージンコール):清算アラートが発動した場合、追加の証拠金を入金することで、ポジションを維持できる場合があります。ただし、これは損失をさらに拡大させるリスクも伴うため、慎重な判断が必要です。
2025年3月のETH清算事件では、HLP(Hyperliquid Liquidity Pool)が約400万ドルの損失を被ったと報告されています。これは、ハッキングではなく、レバレッジ取引のルール内での損失でしたが、市場の急激な変動がもたらすリスクを改めて浮き彫りにしました。BasedAppでは、このような事象を踏まえ、レバレッジ上限の調整や自動清算メカニズムの強化などの対策を講じていますが、ユーザー自身もリスクを十分に理解した上で取引を行うことが不可欠です。
- レバレッジ取引の基本:
- 証拠金を使って、自己資金以上の金額で取引を行う仕組みです。
- 利益も損失も、証拠金に対する割合で拡大します。
- BasedAppのレバレッジ上限:
- ETH:最大25倍
- BTC:最大40倍
- その他の通貨ペアでは最大50倍の場合もあります。
- 清算リスクとその管理方法:
- 証拠金維持率が一定の閾値を下回ると、ポジションが強制決済されます。
- 適切なレバレッジ設定、損切り注文(ストップロス)の活用が重要です。
- 市場の動向を常に把握し、リスク管理を徹底しましょう。
HyperAIボットを活用した自動取引戦略
BasedAppは、ユーザーの取引体験を向上させるために、AI(人工知能)を活用したトレーディングボット、「HyperAI」を提供しています。このHyperAIボットを利用することで、ユーザーは自身の戦略に基づいた自動取引を行うことができ、市場の変動にリアルタイムで対応したり、感情に左右されない規律ある取引を実行したりすることが可能になります。このセクションでは、HyperAIボットの基本的な機能、設定方法、そして具体的な取引戦略について解説します。
HyperAIボットの概要と機能
HyperAIボットは、市場データをリアルタイムで分析し、ユーザーが事前に設定した条件や戦略に基づいて自動的に注文を実行するシステムです。このボットは、以下のような機能を提供します。
- 市場データ分析:HyperAIは、価格チャート、取引量、テクニカル指標(例:移動平均線、RSI、MACD)などの市場データをリアルタイムで収集・分析します。
- 戦略の設定:ユーザーは、自身の取引スタイルやリスク許容度に合わせて、様々な取引戦略をボットに設定できます。例えば、
- スキャルピング:短時間で小さな利益を積み重ねる取引戦略。
- トレンドフォロー:市場のトレンドに乗って利益を狙う戦略。
- ブレイクアウト戦略:価格が特定のレンジを突破した際にエントリーする戦略。
- リバース戦略:市場の過熱感や反転の兆候を捉えて逆張りを狙う戦略。
- 自動注文実行:設定された戦略に基づき、ボットが自動的に買い注文や売り注文を発注・管理します。
- リスク管理機能:ストップロスやテイクプロフィットといったリスク管理機能もボットに組み込むことができ、想定外の損失を防ぎます。
- パフォーマンスの追跡:ボットの取引履歴やパフォーマンスをリアルタイムで確認し、戦略の改善に役立てることができます。
HyperAIボットの設定方法
HyperAIボットの設定は、BasedAppのプラットフォーム内で行います。通常、「AI Bot」や「Trading Bot」といったメニューからアクセスできます。設定プロセスは、一般的に以下のステップで進められます。
- ボットの選択:利用可能なボットの種類(例えば、様々な戦略に基づいたプリセットボットや、カスタム設定が可能なボット)から選択します。
- 戦略のカスタマイズ:
- 取引したい通貨ペアを選択します。
- リスク許容度(例:低、中、高)や、利用したいテクニカル指標、エントリー・エグジットの条件などを設定します。
- ストップロスやテイクプロフィットのレベルもこの段階で設定します。
- 証拠金の割り当て:ボットに自動取引を行わせるために、利用するUSDCの額を設定します。
- ボットの起動:設定が完了したら、ボットを起動します。
ただし、HyperAIの設定は、初心者にとってはやや複雑に感じる場合もあります。2025年8月時点のX上での口コミでは、「AIボットの設定に1週間かかった」「初心者にはハードルが高い」といった声も挙がっています。日本語チュートリアルやサポートが不足していることが、この難易度を高めている要因の一つと考えられます。しかし、2025年9月には日本語チュートリアルが公開される予定であり、より多くのユーザーがHyperAIを活用できるようになることが期待されています。
HyperAIボットを活用した取引戦略
HyperAIボットを効果的に活用するための戦略は、ユーザーの目標や市場状況によって異なります。以下に、いくつかの戦略例を挙げます。
- スキャルピング戦略:短時間で多くの取引をこなし、小さな利益を積み重ねる戦略です。HyperAIの高速な注文実行能力を活かすことができます。RSI(相対力指数)などのオシレーター系指標を設定し、買われすぎ・売られすぎのサインでエントリー・エグジットを行うように設定すると効果的です。
- トレンドフォロー戦略:移動平均線やMACDなどのトレンド系指標を設定し、市場のトレンドに乗る戦略です。上昇トレンドに乗って買いポジションを持ち、下降トレンドに転換したら売りポジションを持つ、といった設定が考えられます。
- リスク管理を重視した戦略:ボットに厳格なストップロスを設定し、損失を限定することを最優先とする戦略です。これにより、感情に左右されずに規律ある取引を継続できます。
- テストと最適化:ボットのパフォーマンスを常に監視し、市場の状況に合わせて設定を微調整することが重要です。バックテスト機能があれば、過去のデータで戦略の有効性を検証することもできます。
HyperAIボットは、ユーザーの取引スキルや市場分析能力を補完し、より効率的で規律ある取引を支援する強力なツールです。しかし、その設定や運用にはある程度の知識と試行錯誤が必要となるため、まずは少額の資金で試してみて、徐々に理解を深めていくことをお勧めします。
- HyperAIボットの主な機能:
- 市場データ分析とリアルタイムでの自動注文実行。
- スキャルピング、トレンドフォロー、ブレイクアウトなど、多様な取引戦略の設定が可能。
- リスク管理機能(ストップロス、テイクプロフィット)の組み込み。
- ボットの設定プロセス:
- 取引したい通貨ペアやリスク許容度を選択します。
- テクニカル指標やエントリー・エグジット条件を設定します。
- 取引に利用する証拠金(USDC)を割り当てます。
- 日本語チュートリアルの公開(2025年9月予定)が期待されます。
- HyperAIを活用した取引戦略例:
- スキャルピング:RSIなどを利用し、短時間で利益を狙う。
- トレンドフォロー:移動平均線などで市場のトレンドを捉え、それに乗る。
- リスク管理重視:厳格なストップロスを設定し、損失を限定する。
- 継続的なテストと最適化が、ボットのパフォーマンス向上に不可欠です。
BasedAppでの資産管理と追加機能の活用法
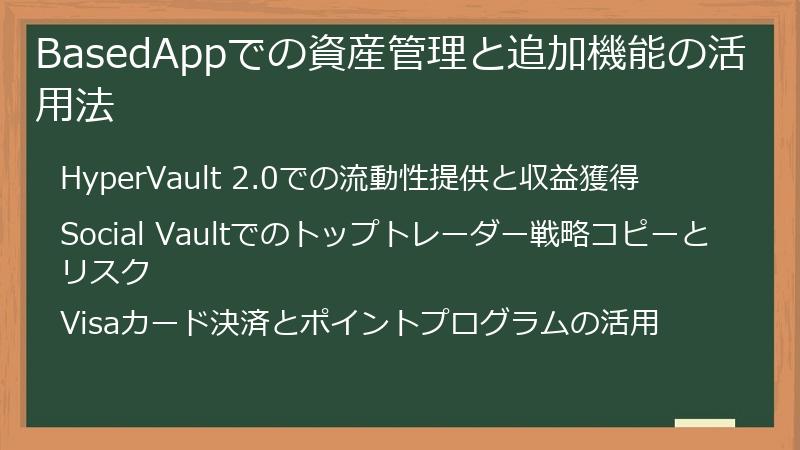
BasedAppは、単に取引を行うだけでなく、ユーザーの資産を効率的に管理し、さらなる収益機会を追求するための様々な機能を提供しています。このセクションでは、BasedAppが提供する主要な追加機能であるHyperVault 2.0、Social Vault、そしてVisaカード決済とポイントプログラムについて、その活用方法を詳しく解説します。これらの機能を理解し、活用することで、BasedAppでの体験をより豊かにし、投資効率を高めることができるでしょう。
- HyperVault 2.0での流動性提供と収益獲得:
- Social Vaultでのトップトレーダー戦略コピーとリスク:
- Visaカード決済とポイントプログラムの活用:
HyperVault 2.0での流動性提供と収益獲得
BasedAppは、ユーザーが保有する資産を有効活用し、追加の収益機会を提供する機能として「HyperVault 2.0」を提供しています。これは、流動性プールに資産を提供することで、受動的な収入を得ることを可能にする仕組みです。HyperVault 2.0は、従来の流動性プール(HLP Vault)と比較して、リスク分散が強化され、清算リスクが低減されている点が特徴です。
HyperVault 2.0の仕組み
HyperVault 2.0では、ユーザーはUSDCなどの資産をプールに預け入れます。提供された流動性は、AIによって最適化された市場メイキング戦略に利用され、その収益の一部が流動性提供者に還元されます。2025年7月に導入されたこの次世代流動性プールは、AI最適化された市場メイキング戦略により、年利40%超の収益を目指せるように設計されています。これは、単に取引を行うだけでなく、資産を預け入れるだけで収益を得られるため、ユーザーにとっては非常に魅力的な選択肢となります。
リスク分散と清算リスクの低減
HyperVault 2.0の大きな特徴は、リスク分散の強化と清算リスクの低減です。2025年8月のアップデートでは、リスク調整アルゴリズムが強化され、市場のボラティリティに応じてマージンが自動調整されるようになりました。これにより、清算リスクが30%低減されたと報告されています。従来のHLP Vaultでは、市場の急激な変動により清算が発生するリスクがありましたが、HyperVault 2.0ではAIが市場の状況を常に監視し、リスクを管理してくれるため、ユーザーはより安心して資産を預け入れることができます。
流動性提供による収益獲得
HyperVault 2.0にUSDCなどを預け入れることで、ユーザーは受動的な収益を得ることができます。AIが市場の状況を分析し、最も効率的な市場メイキング戦略を実行するため、高い年利(目標40%超)での収益が期待できます。この収益は、プールに預け入れた資産に応じて分配されます。月間預入額が1億ドルを突破したという報告もあり、多くのユーザーがHyperVault 2.0の収益性を高く評価していることが伺えます。
HyperVault 2.0は、取引に自信がないユーザーや、長期的に資産を増やしたいユーザーにとって、非常に有効な手段となり得ます。ただし、どのような投資にもリスクは存在するため、自身のリスク許容度を考慮した上で、預け入れる資金額を決定することが重要です。
- HyperVault 2.0の概要:
- AI最適化された市場メイキング戦略により、受動的な収益を目指せる流動性プールです。
- USDCなどの資産を預け入れることで、高い年利(目標40%超)での収益が期待できます。
- リスク分散と清算リスク低減:
- 従来のHLP Vaultと比較して、リスク分散が強化されています。
- 2025年8月のアップデートで、清算リスクが30%低減されました。
- AIが市場のボラティリティに応じてマージンを自動調整し、リスクを管理します。
- 流動性提供による収益化:
- 資産を預け入れることで、受動的な収入を得ることができます。
- AIによる効率的な市場メイキングにより、高い収益性が期待できます。
- 月間預入額が1億ドルを突破するなど、ユーザーからの評価も高いです。
Social Vaultでのトップトレーダー戦略コピーとリスク
BasedAppは、自身の取引スキルに自信がない、あるいはより効率的に収益を上げたいと考えるユーザーのために、「Social Vault」という機能を提供しています。この機能は、優れた実績を持つトップトレーダーの取引戦略をコピーし、その利益を共有するソーシャルトレーディングの仕組みです。このセクションでは、Social Vaultの仕組み、利用方法、そしてそれに伴うリスクについて詳しく解説します。
Social Vaultの仕組み
Social Vaultは、優秀なトレーダー(Vaultリーダー)が自身の取引戦略を公開し、他のユーザー(Vault参加者)がその戦略をコピーできるプラットフォームです。Vault参加者は、USDCなどの資産をVaultに預け入れ、Vaultリーダーの取引アルゴリズムや手動取引に基づいて自動的に取引を行います。Vaultリーダーは、自身の戦略で得た利益の一部(通常10-15%)を報酬として受け取ることができます。Vault参加者は、Vaultリーダーの戦略が成功した場合、その利益の一部を受け取ることができます。
この仕組みは、以下のようなメリットがあります。
- 初心者でもプロの戦略を利用可能:自身の取引スキルに自信がないユーザーでも、実績のあるトレーダーの戦略を利用することで、利益を得られる可能性があります。
- 時間と手間を省く:市場分析や取引の実行を自動化できるため、ユーザーは時間と手間を省きながら資産運用ができます。
- 多様な戦略へのアクセス:様々なリスク許容度や取引スタイルを持つトレーダーの戦略にアクセスできます。
Social Vaultの利用方法
Social Vaultを利用するには、まずBasedAppのプラットフォーム内でSocial Vaultセクションにアクセスします。そこで、公開されているVaultリーダーのリストを確認し、各トレーダーのパフォーマンス、取引戦略、リスクレベル、報酬率などを比較検討します。
Vaultリーダーを選択したら、Vaultに参加したい金額(USDCなど)を指定して預け入れます。預け入れた資産は、Vaultリーダーの戦略に基づいて自動的に取引されます。ユーザーは、いつでもVaultから資産を引き出すことができますが、一部のVaultでは、一定期間のロックアップ期間が設けられている場合もあります。
Social Vaultに伴うリスク
Social Vaultは、トップトレーダーの戦略をコピーするという点で魅力的ですが、それに伴うリスクも存在します。
- Vaultリーダーのパフォーマンスリスク:Vaultリーダーの戦略が常に成功するとは限りません。市場の急変動や戦略の失敗により、Vault参加者が損失を被る可能性があります。2025年6月には、あるVaultリーダーの失敗により、参加者の10%が20%以上の損失を出したという事例も報告されています。
- 報酬率と手数料:Vaultリーダーに支払う報酬率や、その他の手数料体系を事前に確認し、自身の利益が圧迫されないか確認することが重要です。
- アルゴリズムのリスク:AIボットを利用しているVaultの場合、アルゴリズム自体のバグや予期せぬ動作により、損失が発生する可能性もゼロではありません。
- 選択するトレーダーのデューデリジェンス:Vaultに参加する前に、Vaultリーダーの実績、透明性、リスク管理体制などを十分に調査することが不可欠です。
Social Vaultは、賢く利用すれば強力な資産運用ツールとなり得ますが、そのリスクを十分に理解し、自身のリスク許容度に合わせて慎重に利用することが重要です。
- Social Vaultの基本機能:
- トップトレーダーの取引戦略をコピーし、利益を共有するソーシャルトレーディング機能です。
- Vault参加者はUSDCなどを預け入れ、Vaultリーダーの取引アルゴリズムに従って自動的に取引が行われます。
- Social Vaultのメリット:
- 初心者でも実績のあるトレーダーの戦略を利用できます。
- 市場分析や取引実行の手間を省き、時間と労力を節約できます。
- 多様な戦略にアクセスし、自身のポートフォリオを多様化できます。
- Social Vaultに伴うリスク:
- Vaultリーダーのパフォーマンス低下や失敗による損失リスクがあります。
- 報酬率や手数料体系を事前に確認し、利益への影響を把握することが重要です。
- アルゴリズム自体のバグや、トレーダーのデューデリジェンス不足によるリスクも考慮すべきです。
Visaカード決済とポイントプログラムの活用
BasedAppは、仮想通貨をより実用的かつ身近なものにするための機能として、Visaカード決済と独自のポイントプログラムを提供しています。これらの機能を活用することで、BasedAppの利用体験をさらに向上させ、インセンティブを得ることができます。このセクションでは、Visaカード決済の仕組みと活用方法、そしてポイントプログラムの概要と、それがエアドロップにどう繋がるのかを解説します。
Visaカード決済の仕組みと利用方法
BasedAppと連携するVisaカードは、$HYPEトークンを基盤とした決済ソリューションです。このカードを利用することで、ユーザーはBasedAppに保有している仮想通貨を、現実世界でのショッピングやサービス利用に直接使用することができます。2025年4月には欧州での試験導入が開始され、月間決済額1000万ドルを記録しました。2025年末までには米国展開も計画されており、日本国内でも2026年の展開が予定されています。
Visaカード決済の利用には、いくつかのステップが必要です。まず、BasedAppにウォレットを接続し、Visaカードの申し込みを行います。カードが発行されたら、BasedApp上でカードにチャージする仮想通貨(主に$HYPEやUSDC)を選択します。チャージされた仮想通貨は、Visaカードが利用可能なあらゆる店舗やオンラインサービスで、通常のクレジットカードと同様に使用できます。この機能により、仮想通貨の保有者は、取引所を経由することなく、日々の生活の中で仮想通貨を直接活用することが可能になります。
ポイントプログラムとエアドロップへの参加
BasedAppは、ユーザーのプラットフォームへの参加を促進するために、独自のポイントプログラムを提供しています。このプログラムでは、BasedAppでの取引、HyperVault 2.0への資産提供、Social Vaultの利用、さらにはdAppの利用など、様々なアクティビティを通じてポイントが付与されます。2025年8月には、シーズン2のポイントプログラムが開始され、取引量だけでなく、NFT取引やSocial Vault参加もポイント対象に追加されました。総配布量1.2億トークンに増額されたこのシーズン2では、取引量が少ないユーザーでもポイントを獲得しやすく、エアドロップのチャンスを広げています。
これらのポイントは、将来的に$HYPEトークンやその他の報酬と交換される可能性があります。特に、2024年11月に実施されたジェネシスエアドロップでは、取引量やプラットフォームへの貢献度に応じて$HYPEトークンが配布され、大きな話題となりました。シーズン2のポイントプログラムも、同様にエアドロップに繋がる可能性が高いため、積極的に参加することをお勧めします。例えば、2025年8月18日のXでの投稿では、「超短期でエアドロが狙える」とアピールされており、2,000XP獲得コードの共有なども行われています。
Visaカード決済とポイントプログラムは、BasedAppの利用体験をより豊かにし、ユーザーにインセンティブを提供するものです。これらの機能を理解し、積極的に活用することで、BasedAppでの資産運用や取引をより有利に進めることができるでしょう。
- Visaカード決済の概要:
- $HYPEトークンを基盤としたVisaカード決済ソリューションです。
- 欧州での試験導入(2025年4月)では、月間決済額1000万ドルを記録しました。
- 日本国内では2026年の展開が予定されています。
- Visaカード決済の利用方法:
- BasedAppにウォレットを接続し、Visaカードの申し込みを行います。
- BasedApp上でチャージする仮想通貨($HYPE, USDCなど)を選択します。
- 現実世界でのショッピングやサービス利用に、仮想通貨を直接活用できます。
- ポイントプログラムとエアドロップ:
- BasedAppでの取引や機能利用でポイントが付与されます。
- シーズン2(2025年8月開始)では、NFT取引やSocial Vault参加もポイント対象となりました。
- 獲得したポイントは、将来的に$HYPEトークンなどの報酬と交換される可能性があります。
- 過去のエアドロップ(2024年11月)では、多くのユーザーが$HYPEトークンを受け取りました。
BasedApp利用上の注意点とリスク管理
このセクションでは、BasedAppを安全かつ効果的に利用するために、理解しておくべき注意点とリスク管理について解説します。BasedAppは革新的なプラットフォームですが、仮想通貨投資やDEXの利用には固有のリスクが伴います。ここでは、市場変動リスク、技術的リスク、規制リスク、そしてユーザー教育の不足といった、BasedApp利用にあたって考慮すべき様々なリスク要因を詳細に分析します。これらのリスクを正しく理解し、適切な管理策を講じることで、BasedAppでの体験をより安全で有益なものにすることができます。初心者の方が特に注意すべき点や、経験者がさらにリスクを低減するためのヒントについても触れていきます。
BasedApp利用における技術的・市場的リスク
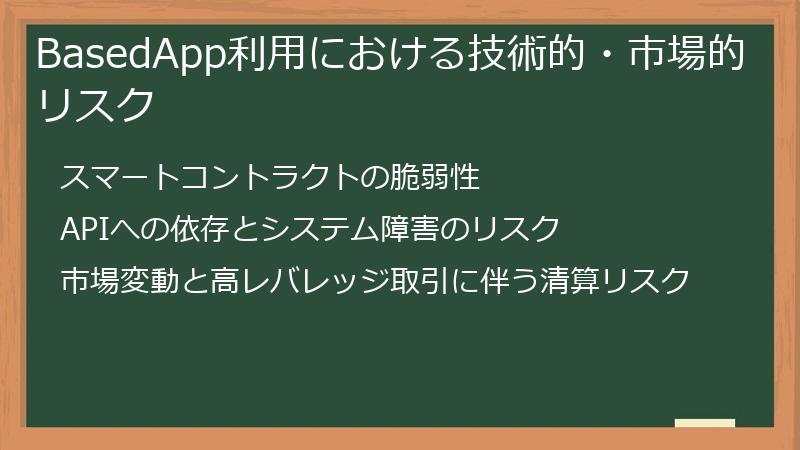
BasedAppはHyperliquid L1の先進的な技術を基盤としていますが、どのようなプラットフォームにも技術的および市場的なリスクは存在します。このセクションでは、BasedAppの利用において考慮すべきこれらのリスク要因を詳細に解説します。まず、スマートコントラクトの脆弱性や、APIへの依存といった技術的な側面から生じるリスクについて掘り下げます。また、市場の急激な変動や、高レバレッジ取引に伴う清算リスクについても、過去の事例を交えながら具体的に説明します。これらのリスクを理解することは、BasedAppでの取引をより安全に行うための第一歩となります。
- スマートコントラクトの脆弱性:
- APIへの依存とシステム障害のリスク:
- 市場変動と高レバレッジ取引に伴う清算リスク:
スマートコントラクトの脆弱性
BasedAppおよびHyperliquidエコシステムは、その基盤となるスマートコントラクトに依存しています。スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で自動的に実行されるプログラムであり、そのコードの正確性とセキュリティが極めて重要です。しかし、いかに高度なスマートコントラクトであっても、潜在的な脆弱性が存在する可能性は否定できません。
Hyperliquid L1ブロックチェーンは、HyperBFTによる自動監査機能を備えていますが、これはあくまでも既存の既知の脆弱性に対する検出を目的としたものです。未知の脆弱性(ゼロデイ脆弱性)や、複雑なDeFiアプリケーション(例:Felix Protocolのようなレンディングプロトコル)のロジックに潜むバグやエクスプロイト(悪用)のリスクは、依然として存在します。過去の仮想通貨市場では、スマートコントラクトの脆弱性を突いたハッキングにより、多額の資産が流出する事件が数多く発生しています。
例えば、2025年7月にHyperEVMのテストネットで発生したとされる、200万ドルの模擬資金がロックされる事態は、複雑なスマートコントラクトにおける予期せぬバグの可能性を示唆しています。また、Hypurr.funで発行されるミームコインのような、流動性が低いプロジェクトにおいては、開発者が意図的にラグプル(詐欺的退出)を行うリスクも存在します。ユーザーは、BasedApp自体だけでなく、BasedAppと連携する様々なdAppのスマートコントラクトについても、その安全性に注意を払う必要があります。
Hyperliquidは、定期的な第三者監査を実施することで、スマートコントラクトのセキュリティ強化に努めていますが、監査はあくまでも過去の時点でのコードに対する評価であり、将来的な脆弱性を完全に保証するものではありません。ユーザーは、自身でプロジェクトのコードや監査レポートを確認する、信頼できる情報源からの情報を参考にするなど、デューデリジェンス(十分な調査)を行うことが重要です。
- スマートコントラクトの性質:
- ブロックチェーン上で自動実行されるプログラムであり、コードの正確性が重要です。
- 一度デプロイされると、修正が困難な場合があります。
- 潜在的な脆弱性リスク:
- 未知の脆弱性(ゼロデイ脆弱性)や、複雑なロジックに潜むバグの可能性があります。
- 過去の仮想通貨市場では、スマートコントラクトの脆弱性を狙ったハッキングが多発しています。
- Hyperliquidのセキュリティ対策とユーザーの注意点:
- HyperBFTによる自動監査機能がありますが、完全な保証ではありません。
- 定期的な第三者監査を実施していますが、常に最新の情報を確認することが重要です。
- dAppのコードや監査レポートの確認、信頼できる情報源の参照など、ユーザー自身によるデューデリジェンスが不可欠です。
- ミームコインなど、流動性の低いプロジェクトにはラグプルのリスクも存在します。
APIへの依存とシステム障害のリスク
BasedAppのような高度な取引プラットフォームは、その機能の多くをAPI(Application Programming Interface)に依存しています。APIは、BasedAppのフロントエンド(ユーザーが直接操作するインターフェース)と、バックエンドの取引システムやブロックチェーンとの間の通信を可能にする重要な役割を担っています。2025年3月に発生した37分間のAPIサーバー過負荷による注文入力障害は、このAPI依存のリスクを浮き彫りにしました。
このAPIサーバー過負荷は、大量の注文が集中した際に発生したと考えられます。その結果、ユーザーは注文を正常に入力できず、本来なら約定できたはずの取引機会を逃したり、想定外の価格での約定を余儀なくされたりする事態に直面しました。注文が遅延したことで損失を出したというユーザーからの報告もあり、APIサーバーの安定稼働が、ユーザー体験と収益に直接影響を与えることが示されました。
BasedApp側では、このAPIサーバー過負荷の障害を受けて、サーバー容量を増強し、自動監視システムを導入するなどの再発防止策を強化しています。これにより、将来的な障害発生のリスクは低減されると考えられます。しかし、依然として、基盤となるブロックチェーンの混雑や、予期せぬ技術的問題が発生する可能性はゼロではありません。
ユーザーとしては、APIサーバーの障害が発生した場合、BasedAppのウェブサイトやアプリが正常に機能しなくなる可能性があることを理解しておく必要があります。このような状況下では、注文の執行や資産の移動が不可能になることも考えられます。そのため、重要な取引を行う際には、APIサーバーの状況やネットワークの混雑具合などを確認する習慣をつけることが推奨されます。また、BasedAppの公式Xアカウント(@BasedAppHQや@HyperliquidXなど)やDiscordコミュニティをフォローしておき、システム障害に関する最新情報をいち早く入手できるようにしておくことも、リスク管理の観点から重要です。
- APIの役割と依存性:
- BasedAppのフロントエンドとバックエンドシステム間の通信を担います。
- 取引注文の実行やデータ表示に不可欠な要素です。
- 過去のシステム障害事例:
- 2025年3月にAPIサーバー過負荷による注文入力障害が発生しました(37分間)。
- これにより、注文遅延や取引機会の損失が発生しました。
- BasedAppによる再発防止策:
- サーバー容量の増強と自動監視システムの導入が行われています。
- これにより、将来的な障害発生のリスクは低減されると考えられます。
- ユーザーとしてのリスク管理:
- API障害発生時は、プラットフォームが正常に機能しない可能性があることを認識しておく必要があります。
- 重要な取引を行う前には、APIサーバーの状況やネットワークの混雑具合を確認することが推奨されます。
- 公式XアカウントやDiscordコミュニティで最新情報を入手できるようにしておきましょう。
市場変動と高レバレッジ取引に伴う清算リスク
BasedAppで提供されている無期限先物取引は、レバレッジを活用することで大きな利益を狙える一方で、市場の急激な変動によって大きな損失を被る、いわゆる「清算リスク」を伴います。このリスクを理解し、適切に管理することは、BasedAppを利用する上で極めて重要です。
市場変動リスク
仮想通貨市場は、株式市場や他の金融市場と比較しても、非常に高いボラティリティ(価格変動性)を持っています。ニュース、規制の動向、マクロ経済指標、あるいはプロジェクト固有のイベントなど、様々な要因によって価格が短時間で大きく変動する可能性があります。BasedAppで取引を行う際、特にレバレッジをかけている場合は、こうした市場の急激な変動が直接的な損失に繋がります。2025年3月のETH清算事件は、市場の急激な変動がHLP(Hyperliquid Liquidity Pool)に400万ドルの損失をもたらした事例であり、市場変動リスクの大きさを物語っています。
高レバレッジ取引のリスク
BasedAppでは、最大で25倍(ETH)から40倍(BTC)、あるいはそれ以上のレバレッジをかけて取引することが可能です。レバレッジ取引は、自己資金の何倍もの金額で取引できるため、予想通りに価格が動けば大きな利益を得ることができます。しかし、予想が外れた場合、損失も同様に拡大します。例えば、10倍のレバレッジをかけていた場合、価格が10%逆方向に動くだけで、証拠金のすべてを失うことになります。
清算リスクとそのメカニズム
清算とは、保有しているポジションの含み損が、証拠金維持率の基準を下回った場合に、取引所によって強制的にポジションが決済されることです。BasedAppでは、証拠金維持率が一定の閾値を下回ると、まず「清算アラート」が発動し、それでも証拠金維持率が改善されない場合は、ポジションが強制決済されます。この清算が発生すると、ユーザーは証拠金として預け入れていた資金のすべてを失うことになります。
2025年3月のETH清算事件は、HLPが清算ポジションを引き受ける仕組みにおいて、急激な市場変動がもたらすリスクを示しました。HLPが市場で清算されたポジションを処理する際に、損失が発生したのです。これは、BasedAppのプラットフォーム全体のリスク管理の重要性を示唆しています。
リスク管理策
高レバレッジ取引に伴う清算リスクを管理するためには、以下の対策が有効です。
- 適切なレバレッジの設定:自身の許容できるリスクの範囲内で、無理のないレバレッジを設定することが最も重要です。初心者の方は、まず低レバレッジ(2~5倍程度)から取引を始めることを推奨します。
- 損切り注文(ストップロス)の活用:損切り注文は、損失が一定額に達した場合に自動的にポジションを決済する注文です。これにより、損失の拡大を限定することができます。BasedAppでは、トレーリングストップロスなどの機能も提供されている場合があるため、積極的に活用しましょう。
- 市場の動向の把握:仮想通貨市場のボラティリティは非常に高いため、常に市場のニュースや価格動向を把握し、リスク管理に役立てることが重要です。
- 証拠金の管理:常に十分な証拠金を維持するように心がけ、清算アラートが発動した場合は、速やかに証拠金を追加するか、ポジションを縮小するなどの対応を検討しましょう。
BasedAppの利用にあたっては、これらのリスクを十分に理解し、自身のリスク許容度に合わせて慎重な取引を心がけることが成功への鍵となります。
- 市場変動リスクの認識:
- 仮想通貨市場はボラティリティが非常に高いことを理解しておく必要があります。
- ニュースやイベントが価格に急激な影響を与える可能性があります。
- 2025年3月のETH清算事件は、市場変動リスクの大きさを示しています。
- 高レバレッジ取引のリスク:
- レバレッジを高く設定すると、利益も損失も拡大します。
- 予想外の価格変動により、証拠金のすべてを失う「清算」が発生する可能性があります。
- ETHは最大25倍、BTCは最大40倍などのレバレッジ制限があります。
- 清算リスク管理策:
- 自身の許容リスク範囲内で、適切なレバレッジを設定しましょう。
- 損切り注文(ストップロス)を必ず設定し、損失を限定してください。
- 市場の動向を常に把握し、証拠金を十分に維持するように心がけましょう。
規制リスクとユーザー保護に関する考慮事項
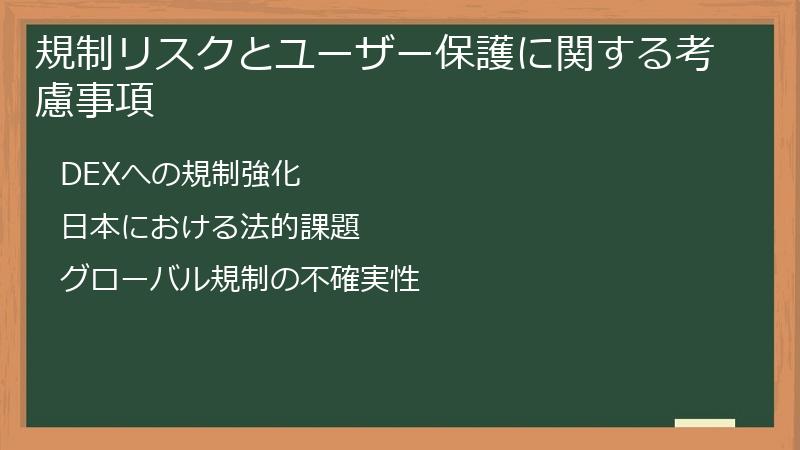
BasedAppは、分散型取引所(DEX)として運営されていますが、仮想通貨業界全体が直面している規制の動向、特に日本市場における規制は、ユーザー保護とプラットフォームの利用可能性に大きな影響を与えます。このセクションでは、DEXに対する規制の強化、日本における法的課題、そしてグローバルな規制の不確実性について解説し、ユーザーが留意すべき点を明らかにします。
- DEXへの規制強化:
- 日本における法的課題:
- グローバル規制の不確実性:
DEXへの規制強化
分散型取引所(DEX)は、その非中央集権的な性質から、従来の金融規制の枠組みに必ずしも当てはまりにくいという特徴があります。しかし、仮想通貨市場の拡大とともに、DEXに対する規制当局の関心も高まっており、世界的に規制強化の動きが進んでいます。BasedAppのようなDEXを利用する上で、この規制強化の流れを理解しておくことは重要です。
DEXは、一般的に管理者が存在せず、ユーザー自身が秘密鍵を管理し、ウォレットを介して直接ブロックチェーン上のスマートコントラクトとやり取りを行います。このため、中央集権型取引所(CEX)のように、取引所がKYC(顧客確認)やAML(マネーロンダリング対策)の義務を負うことがありませんでした。しかし、この匿名性の高さが、マネーロンダリングやテロ資金供与、詐欺行為などに悪用されるリスクも指摘されています。
こうした背景から、各国・地域の規制当局は、DEXに対する監視を強めています。例えば、一部の国では、DEXの運営者に対して、CEXと同様のライセンス取得やKYC/AML義務を課す動きが出てきています。また、DEX上で取引されるトークンについても、証券に該当するかどうかの判断基準が厳格化される傾向にあります。BasedAppが提供するミームコインや、今後上場される可能性のある新規トークンが、将来的に証券規制の対象となる可能性も否定できません。
BasedAppは、現時点では非KYCモデルを採用していますが、将来的に規制当局からの要請や、より広範な市場へのアクセスを確保するために、KYCプロセスを導入せざるを得なくなる可能性も考えられます。もしKYCが義務化された場合、匿名性を重視するユーザーにとっては利用しにくくなる可能性があります。また、一部の地域では、IPアドレスに基づいてDEXへのアクセスが制限される場合もあり、VPNの利用が必要となるケースも考えられます。ユーザーは、自身が居住する地域の仮想通貨規制に関する最新情報を常に把握しておくことが重要です。
- DEXの非中央集権的な性質:
- 管理者が存在せず、ユーザー自身が資産を管理します。
- KYC/AML義務の適用がCEXとは異なります。
- 規制当局の関心の高まり:
- マネーロンダリングや詐欺行為への悪用リスクが指摘されています。
- 各国・地域でDEXに対する監視と規制強化の動きが進んでいます。
- 規制強化の具体的内容:
- DEX運営者へのライセンス取得義務化。
- KYC/AML義務の適用。
- 取引されるトークンに対する証券規制の厳格化。
- ユーザーへの影響:
- BasedAppが将来的にKYCを導入する可能性があります。
- 一部地域でIPアドレスによるアクセス制限が発生する可能性があります(VPN利用の必要性)。
- 居住地域の仮想通貨規制に関する最新情報の把握が重要です。
日本における法的課題
BasedAppを日本国内で利用するユーザーにとって、日本の仮想通貨規制は特に重要な考慮事項となります。日本は、世界的に見ても比較的厳格な仮想通貨規制を敷いている国の一つであり、DEX(分散型取引所)に対する規制も年々強化される傾向にあります。
まず、日本の法律では、仮想通貨交換業を行うためには金融庁への登録が義務付けられています。BasedAppは、現時点では非KYC(顧客確認)モデルを採用しており、中央集権的な管理主体を持たないDEXとして運営されています。しかし、日本国内でサービスを提供し、日本居住者に対して積極的に勧誘活動を行う場合、金融庁の「暗号資産交換業」とみなされる可能性があります。もし、BasedAppが日本の暗号資産交換業の登録を受けずに日本居住者に対してサービスを提供した場合、金融商品取引法等に抵触するリスクが生じます。
2025年6月に金融庁から示唆されたDEX監視強化の動きは、このリスクをさらに高めるものです。金融庁は、DEXが投資家保護やマネーロンダリング対策の観点から、従来のCEXと同等の規制対象となりうる可能性を示唆しており、BasedAppのような非KYCモデルのDEXにとっては、日本市場でのサービス継続に影響を与える可能性があります。
もし、日本市場でのサービス提供が制限される場合、BasedAppは日本居住者に対してアクセス制限を設けるか、あるいは日本国内で暗号資産交換業の登録を取得する必要に迫られるかもしれません。現時点では、BasedAppはシンガポールでのKYCオプション導入も進めていますが、これが日本市場にどのように適用されるかは未定です。
これらの規制課題は、日本ユーザーがBasedAppを利用する上での大きなハードルとなり得ます。規制の動向は常に変化するため、日本国内でBasedAppを利用するユーザーは、金融庁などの公的機関からの最新情報を常に確認し、法規制を遵守した上で利用することが求められます。
- 日本の仮想通貨規制の概要:
- 仮想通貨交換業には金融庁への登録が義務付けられています。
- DEXに対する規制も強化される傾向にあります。
- BasedAppの非KYCモデルと日本の規制:
- BasedAppは非KYCモデルですが、日本でのサービス提供には法的課題が生じる可能性があります。
- 金融庁は2025年6月にDEX監視強化の動きを示唆しています。
- 日本市場でのサービス提供には、暗号資産交換業の登録が必要となる可能性があります。
- ユーザーが取るべき行動:
- 金融庁など公的機関からの最新規制情報を常に確認してください。
- 法規制を遵守した上で、自己責任でBasedAppを利用してください。
- 万が一、アクセス制限などが生じた場合は、その指示に従う必要があります。
グローバル規制の不確実性
仮想通貨、特にDEX(分散型取引所)を取り巻く規制環境は、国や地域によって大きく異なり、かつ急速に変化しています。BasedAppのようなグローバルに展開するプラットフォームを利用する際には、このグローバルな規制の不確実性を理解しておくことが不可欠です。
欧州連合(EU)では、仮想通貨市場規制(MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation)が2026年より施行される予定です。MiCA規制は、仮想通貨の発行者やサービスプロバイダーに対して、ライセンス取得、資本要件、利用者保護、市場操作の禁止など、広範な義務を課すものです。この規制がDEXの運営にどのような影響を与えるかは、まだ完全に明確ではありませんが、EU域内でのサービス提供を続けるためには、DEX側がKYC導入などの措置を講じる必要が出てくる可能性が高いです。もし、EU域内での規制強化により、BasedAppがKYC導入を強いられた場合、匿名性を重視するユーザーは他のプラットフォームへ移行する可能性があり、ユーザー離れのリスクが顕在化します。
また、米国においても、証券取引委員会(SEC)がDEXや一部の仮想通貨を証券とみなす姿勢を強めており、規制の適用範囲を拡大しようとしています。これにより、DEXの運営者や、DEX上で提供されるサービスが、米国の証券法に抵触するリスクが生じています。BasedAppが米国市場でのサービス提供を拡大する場合、これらの規制動向には細心の注意を払う必要があります。
さらに、FATF(金融活動作業部会)のような国際的な金融規制機関も、仮想通貨取引におけるマネーロンダリング対策(AML)の強化を推進しており、DEXに対してもトランザクションの追跡や規制当局への情報提供を求めるガイドラインを更新しています。これらの国際的なガイドラインは、各国の規制当局に影響を与え、DEXの匿名性やプライバシー保護のあり方に変化を迫る可能性があります。
BasedAppは、Hyperliquid L1の匿名性を活かした設計思想を持っていますが、グローバルな規制の動向によっては、その運営方針の変更や、一部地域でのサービス提供の制限といった影響を受ける可能性があります。ユーザーは、自身が利用する地域だけでなく、グローバルな規制の動向にも注意を払い、BasedAppの公式発表や信頼できる情報源からの最新情報を常に確認することが重要です。
- EUのMiCA規制:
- 2026年施行予定で、仮想通貨サービスプロバイダーに広範な義務を課します。
- DEXがEU域内でサービス提供を続ける場合、KYC導入などの措置が必要になる可能性があります。
- これにより、匿名性を重視するユーザーが離れるリスクがあります。
- 米国の規制動向:
- SECはDEXや一部仮想通貨を証券とみなす姿勢を強めています。
- BasedAppが米国市場でサービス提供する場合、米国の証券法抵触のリスクがあります。
- FATFのAMLガイドライン:
- 国際的なマネーロンダリング対策の強化が推進されています。
- DEXに対してもトランザクション追跡や情報提供を求める動きがあります。
- これらのガイドラインは、DEXの匿名性やプライバシー保護に影響を与える可能性があります。
- ユーザーが取るべき対策:
- グローバルな規制動向に注意を払い、BasedAppの公式発表を確認してください。
- 自身が利用する地域や、関心のある地域の規制動向を把握することが重要です。
- 匿名性よりも、規制遵守を重視するプラットフォームへの移行も視野に入れる必要があるかもしれません。
初心者ユーザーが知っておくべきこと
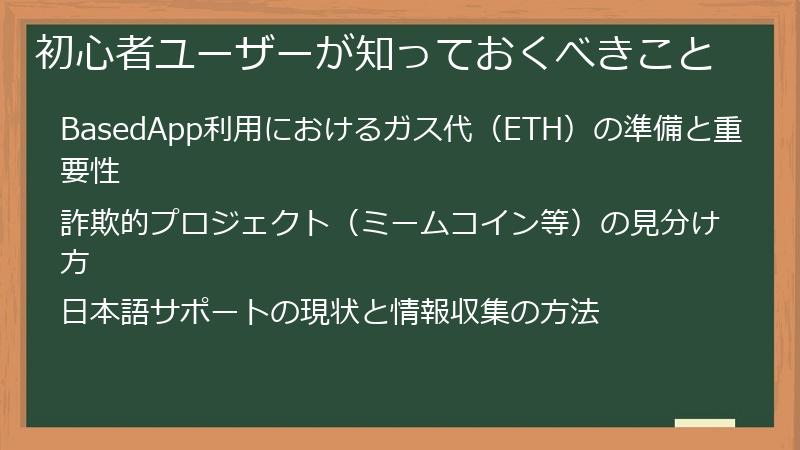
BasedAppは、その革新的な機能や高いパフォーマンスから多くのユーザーに利用されていますが、特に仮想通貨取引やDEX(分散型取引所)の利用が初めてのユーザーにとっては、いくつか注意すべき点があります。このセクションでは、初心者の方がBasedAppを安全かつ効果的に利用するために、知っておくべき基本的な知識と注意点について解説します。ここでは、MetaMaskの設定やガス代(ETH)の準備といった基本的な操作から、詐欺的なプロジェクトの見分け方、そして日本語サポートの現状と情報収集の方法まで、初心者がつまずきやすいポイントに焦点を当てて説明します。
- BasedApp利用におけるガス代(ETH)の準備と重要性:
- 詐欺的プロジェクト(ミームコイン等)の見分け方:
- 日本語サポートの現状と情報収集の方法:
BasedApp利用におけるガス代(ETH)の準備と重要性
BasedAppは、Hyperliquid L1ブロックチェーンの基盤技術により、プラットフォーム内での取引や操作には原則としてガス代がかかりません。これは、BasedAppを利用する上で非常に大きなメリットですが、一つだけ注意すべき点があります。それは、BasedAppへの資金入金プロセスにおいて、Arbitrumネットワークを経由する際に、イーサリアム(ETH)のガス代が必要となることです。
BasedAppは、Arbitrumネットワークと連携して資産の移動を行っています。Arbitrumはイーサリアムのスケーリングソリューションであり、イーサリアムのブロックチェーン上でスマートコントラクトを実行する際には、イーサリアムのネットワーク手数料、すなわちガス代がETHで必要となります。BasedAppへUSDCなどの資産を入金する際、このArbitrumネットワーク上でのトランザクションを承認するために、少量のETHがガス代として消費されます。
したがって、BasedAppを利用開始する前に、自身のウォレット(MetaMaskやRabbyなど)に、ある程度の量のETHを準備しておくことが非常に重要です。必要なETHの量は、その時のイーサリアムネットワークの混雑状況によって変動しますが、通常は少額(例えば0.01ETH~0.05ETH程度)あれば十分であることが多いです。しかし、ネットワークが非常に混雑している場合には、より多くのETHが必要になる可能性もあります。
もし、ウォレットにETHが不足している状態でArbitrumネットワーク上でのトランザクション(例:BasedAppへのUSDC入金)を行おうとすると、トランザクションは承認されず、エラーとなります。そのため、BasedAppを利用する前には、必ずウォレットに十分な量のETHがあることを確認してください。
ETHの準備方法としては、国内の仮想通貨取引所で購入し、自身のウォレットへ送金するのが一般的です。この手順については、前述の「ArbitrumネットワークへのUSDCとETHの入金方法」で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてください。
BasedApp内での取引自体にはガス代がかからないため、一度入金してしまえば、その後の取引コストは非常に低く抑えられます。しかし、最初の入金プロセスでETHのガス代が必要となる点を理解し、事前に準備しておくことが、スムーズなBasedAppの利用開始のために不可欠です。
- BasedApp利用におけるガス代の原則:
- BasedAppプラットフォーム内での取引や操作には、原則としてガス代はかかりません。
- これはHyperliquid L1の技術的な特徴によるものです。
- ArbitrumネットワークでのETHガス代:
- BasedAppへのUSDCなどの入金プロセスでは、Arbitrumネットワークを経由します。
- Arbitrumネットワーク上でのトランザクション承認には、ETHがガス代として必要となります。
- ETHの事前準備の重要性:
- BasedApp利用開始前に、ウォレットに十分な量のETHを準備しておく必要があります。
- 必要なETHの量は、イーサリアムネットワークの混雑状況によって変動します。
- ETHが不足していると、入金などのトランザクションが承認されません。
- ETHの準備方法:
- 国内仮想通貨取引所で購入し、自身のウォレットへ送金します。
- 詳細は「ArbitrumネットワークへのUSDCとETHの入金方法」を参照してください。
詐欺的プロジェクト(ミームコイン等)の見分け方
BasedAppは、Hyperliquidエコシステムにおけるミームコインの上場プラットフォーム「Hypurr.fun」とも連携しており、多様なトークンが取引されています。しかし、仮想通貨市場、特にDEX(分散型取引所)では、詐欺的なプロジェクトやラグプル(詐欺的退出)のリスクが常に存在します。BasedAppを利用する初心者ユーザーが、これらの詐欺的プロジェクトに巻き込まれないために、見分け方について解説します。
詐欺的プロジェクトの兆候
詐欺的なプロジェクト、特にミームコインプロジェクトには、以下のような兆候が見られることがあります。
- 異常に高いAPY(年換算利回り)の提示:常識外れなほど高い利回りを謳うプロジェクトは、詐欺である可能性が高いです。これは、初期の流動性を悪用して、後から投資家から資金を騙し取るための常套手段であることが多いです。
- 不透明なチーム情報:プロジェクトの背後にいるチームメンバーの情報が公開されていなかったり、匿名であったりする場合、そのプロジェクトの信頼性は低いと判断できます。
- 誇大広告と過度なFOMO(Fear Of Missing Out)の煽り:プロジェクトの将来性について、根拠のない過度な期待を煽ったり、「今買わないと損をする」といったFOMOを誘発するようなマーケティング手法は、詐欺の兆候である可能性があります。
- コードの未公開または監査不備:スマートコントラクトのコードが公開されていなかったり、信頼できる第三者機関による監査を受けていなかったりするプロジェクトは、潜在的な脆弱性や悪意のあるコードが含まれているリスクがあります。
- 突然の流動性削除(ラグプル):ミームコインプロジェクトなどで、価格が急騰した後に、開発者が流動性プールから資金を引き上げ、プロジェクトを放棄してしまう行為です。
Hypurr.funにおける注意点
BasedAppと連携するHypurr.funは、ミームコインの上場プラットフォームとして、多くの新規トークンがオークション形式で上場されています。Hypurr.fun自体は、HIP-1(Hyperliquid Improvement Proposal)という基準に基づいてトークンを上場させていますが、この基準を満たしているからといって、そのトークンが長期的に価値を維持することを保証するものではありません。
Hypurr.funで新規トークンを取引する際には、以下の点に注意してください。
- HIP-1基準の確認:上場されているトークンが、Hypurr.funのHIP-1基準を満たしているかを確認しましょう。基準には、トークンの総供給量、初期流動性、開発チームの透明性などが含まれます。
- 流動性の確認:取引するトークンの流動性が十分にあるかを確認してください。流動性が低い場合、希望する価格で売却できないリスクがあります。
- チームのデューデリジェンス:プロジェクトのホワイトペーパーを読み、開発チームの背景やロードマップを確認しましょう。
- 少額からの投資:新規プロジェクト、特にミームコインに投資する際は、失っても生活に影響のない範囲の少額から始めることを強く推奨します。
「PUMP」トークンの上場や、それに続くミームコインブームは、Hypurr.funがミームコイン発行のデファクトスタンダードとなりつつあることを示していますが、同時に、これらのトークンが持つ高いボラティリティとリスクも示唆しています。ユーザーは、Hypurr.funで取引する際にも、常に慎重な姿勢を保つことが重要です。
- 詐欺的プロジェクトの主な兆候:
- 異常に高いAPYの提示。
- 不透明なチーム情報、匿名性。
- 誇大広告やFOMO(Fear Of Missing Out)の煽り。
- コードの未公開または監査不備。
- 突然の流動性削除(ラグプル)。
- Hypurr.funでの取引における注意点:
- HIP-1基準を満たしているか確認しましょう。
- 取引するトークンの流動性を確認してください。
- プロジェクトのチーム背景やロードマップを調査しましょう。
- 少額からの投資を心がけましょう。
- ミームコインのリスク:
- 高いボラティリティと、ラグプルのリスクが存在します。
- 投資は自己責任で行い、リスクを十分に理解した上で参加しましょう。
日本語サポートの現状と情報収集の方法
BasedAppを日本で利用するにあたり、日本語でのサポート体制や情報収集の方法は、初心者ユーザーにとって特に重要なポイントとなります。このセクションでは、現在の日本語サポートの状況と、ユーザーが正確な情報を得るための方法について解説します。
日本語サポートの現状
2025年8月時点での情報によると、BasedAppの日本語サポートはまだ発展途上にあります。Oktoアプリの日本語UIは2025年9月に80%完成予定であり、それまでは一部英語表記が残る可能性があります。また、公式のカスタマーサポートも、英語が中心となっている場合が多く、日本語での迅速な対応が難しい場面も想定されます。X(旧Twitter)などのSNS上では、「英語のみで使いにくい」「サポート対応が遅い」といった日本人ユーザーからの不満の声も散見されます。
しかし、BasedAppは日本市場の重要性を認識しており、改善に向けた取り組みを進めています。2025年9月には、日本語FAQが公開される予定であり、これにより多くの基本的な疑問は解消されることが期待されます。また、公式Discordサーバーには日本語チャンネルが既に開設されており、1,000人を超えるコミュニティメンバーが活発に情報交換を行っています。このコミュニティ内では、ユーザー同士で日本語による質問や回答が行われており、非公式ながらも充実したサポートが得られる可能性があります。
情報収集の方法
BasedAppに関する最新かつ正確な情報を得るためには、いくつかの情報源を組み合わせることが重要です。
- 公式ウェブサイトとアプリ:BasedAppの公式ウェブサイト(based.app)やOktoアプリは、最も信頼性の高い情報源です。アップデート情報、機能の追加、利用規約の変更などは、まずここで確認しましょう。
- 公式Xアカウント:BasedAppの公式Xアカウント(@BasedAppHQ, @HyperliquidXなど)は、最新のニュースやアナウンス、キャンペーン情報などをリアルタイムで発信しています。特に、シーズン2エアドロップに関する情報や、日本市場向け施策の進展などは、Xでいち早く発表されることが多いです。
- 公式Discordコミュニティ:Discordの日本語チャンネルは、ユーザー同士の情報交換や質問をするのに最適な場所です。運営チームからのアナウンスも行われるため、積極的に参加してみましょう。
- 日本語KOL(Key Opinion Leader)やメディア:2025年8月には日本の著名KOLとの提携も開始されました。これらのKOLのSNSやブログ、あるいは仮想通貨専門の日本語メディア(例:CoinPost、CoinDesk Japanなど)も、BasedAppに関する情報を得るための有効な手段となります。ただし、個人の見解に基づく情報も含まれるため、複数の情報源を比較検討することが重要です。
- 独自のリサーチ(DYOR: Do Your Own Research):最終的には、ご自身で情報を収集・分析し、BasedAppの利用や投資に関する判断を行うことが重要です。
日本語サポートはまだ完全ではありませんが、コミュニティの活用や公式発表を注視することで、BasedAppをより深く理解し、安全に利用していくことが可能です。
- 日本語サポートの現状:
- Oktoアプリの日本語UIは2025年9月に80%完成予定です。
- 公式カスタマーサポートは英語中心で、日本語対応は限定的です。
- SNS上では「使いにくい」「対応が遅い」といった声も聞かれます。
- 改善に向けた取り組み:
- 2025年9月には日本語FAQの公開が予定されています。
- 公式Discordに日本語チャンネルが開設され、1,000人以上のコミュニティが活発です。
- 情報収集の推奨ルート:
- 公式情報:公式サイト、Oktoアプリ、公式Xアカウント、公式Discord(日本語チャンネル)。
- 日本語KOL・メディア:著名KOLのSNS、仮想通貨専門メディア。
- 継続的なリサーチ:DYOR(Do Your Own Research)の精神で、複数の情報源を比較検討しましょう。
BasedApp 使い方 日本語:初心者向けFAQ
BasedAppを日本で利用したいけれど、何から始めれば良いか分からない。そんな疑問をお持ちではありませんか?BasedAppはHyperliquid L1ブロックチェーンを活用した革新的なDEXで、取引から資産管理、決済まで、仮想通貨に関する様々な体験を提供しています。しかし、その多機能性ゆえに、初心者の方には難しく感じる部分もあるかもしれません。このFAQコンテンツでは、「BasedApp 使い方 日本語」というキーワードで検索されている読者の皆様が抱える疑問に、一つ一つ丁寧にお答えしていきます。BasedAppの基本操作から、Hyperliquidエコシステム、取引方法、リスク管理、そして日本語での利用に関する注意点まで、網羅的に解説します。この記事を通じて、BasedAppを理解し、自信を持って利用できるようになることを目指します。
BasedAppの基本操作とHyperliquidエコシステムに関するFAQ
このFAQセクションでは、BasedAppを初めて利用される方や、Hyperliquidエコシステムについて詳しく知りたい方向けの質問にお答えします。BasedAppがどのような取引所なのか、その基盤となるHyperliquid L1ブロックチェーンや$HYPEトークンがどのような役割を果たしているのか、といった基本的な疑問から、実際にBasedAppを利用するために必要なウォレットの準備や入金方法といった、具体的な操作に関する質問まで、幅広くカバーします。BasedAppの全体像を理解し、スムーズに利用を開始するための第一歩となる情報を提供します。
BasedAppとは何か?に関するFAQ
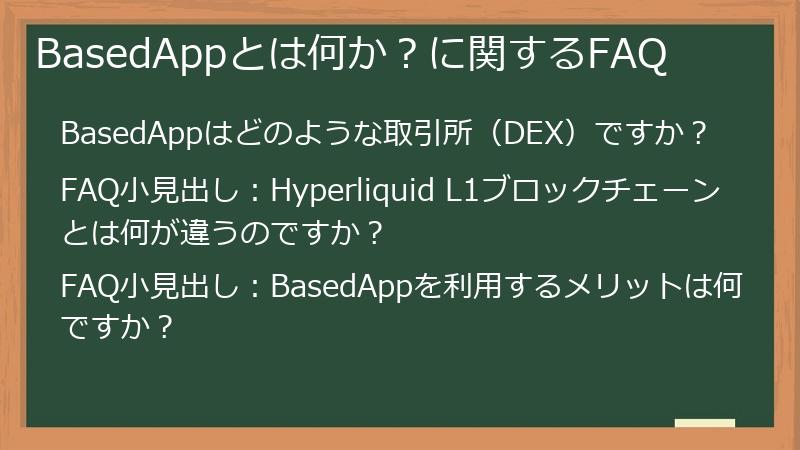
このFAQセクションでは、BasedAppというプラットフォームそのものに関する基本的な疑問に焦点を当てます。BasedAppがどのような種類の取引所(DEX)なのか、その特徴やメリット、そして基盤となるHyperliquid L1ブロックチェーンとの関係性について解説します。また、$HYPEトークンがBasedAppの利用においてどのような役割を果たし、ステーキングなどの機能を通じてどのように収益を得られるのか、といった点についても詳しく説明します。BasedAppの全体像を把握し、その利用価値を理解するための基礎知識を提供します。
BasedAppはどのような取引所(DEX)ですか?
BasedAppは、Hyperliquid L1ブロックチェーンを基盤とした、次世代の分散型取引所(DEX)アプリケーションです。このプラットフォームは、仮想通貨のトレード、資産管理、さらにはVisaカードを通じた実世界での決済までを統合した、包括的な金融サービスを提供することを目指しています。Hyperliquid L1の持つ、ブロック生成時間0.2秒という驚異的な速さと、秒間最大200,000トランザクション(TPS)という高い処理能力、そして何よりもガス手数料が無料であるという特徴を最大限に活用しています。これにより、ユーザーは中央集権型取引所(CEX)に匹敵するスピード感と、DEXならではの透明性・非中央集権性を両立した取引環境を享受できます。
BasedAppの主な特徴としては、以下の点が挙げられます。
- 高速かつ低コストな取引:Hyperliquid L1の技術により、CEX並みの約定スピードと、ガス手数料無料という低コストを実現しています。これにより、ユーザーは頻繁な取引や少額取引も気軽に行えます。
- 統合型ウォレット機能:BasedAppはウォレット機能を内蔵しており、MetaMaskなどの外部ウォレット接続に加え、プラットフォーム内で資産管理や決済までをシームレスに行うことができます。
- 高度な取引ツール:トレーリングストップロス、リミットチェイス、リバースポジションといった、プロトレーダー向けの高度な注文機能を提供し、カスタマイズ性の高い取引環境を実現しています。
- Visaカード決済:$HYPEトークンを基盤としたVisaカード決済機能により、仮想通貨を現実世界でのショッピングやサービス利用に活用できます。
- ポイントプログラムとエアドロップ:取引量やプラットフォームへの貢献に応じてポイントが付与され、将来的なエアドロップに繋がる可能性があります。
- オンチェーンオーダーブック:全ての取引データがブロックチェーン上に記録されるため、透明性の高い取引環境が提供されます。
BasedAppは、CEXの利便性とDEXの安全性を兼ね備えたプラットフォームとして、仮想通貨取引の新たなスタンダードを築こうとしています。
FAQ小見出し:Hyperliquid L1ブロックチェーンとは何が違うのですか?
BasedAppは、Hyperliquid L1ブロックチェーンという、独自のレイヤー1ブロックチェーン技術を基盤としています。Hyperliquid L1は、他の一般的なブロックチェーン、例えばイーサリアム(Ethereum)などとは異なる、いくつかの重要な技術的特徴を持っています。BasedAppの利用を理解する上で、このHyperliquid L1の優位性を把握することは非常に重要です。
Hyperliquid L1の最大の特長は、その**卓越したパフォーマンス**にあります。
- 高速なブロック生成とトランザクション処理:
- Hyperliquid L1は、Tendermintコンセンサスアルゴリズムをベースにした独自のHyperBFTコンセンサスプロトコルを採用しています。
- これにより、ブロック生成時間がわずか0.2秒という、他の主要ブロックチェーンと比較して圧倒的に速い速度を実現しています。
- 秒間最大200,000トランザクション(TPS)という処理能力は、イーサリアムの約6,667倍にも相当します。
- ガス手数料無料:
- Hyperliquid L1上での取引や操作には、原則としてガス手数料がかかりません。
- これは、イーサリアムなどのブロックチェーンで発生するガス代の高騰リスクを回避できる、ユーザーにとって非常に大きなメリットです。
- BasedApp内での取引は、このガス代無料の恩恵を直接受けることができます。
- オンチェーンオーダーブック:
- BasedAppは、中央集権型取引所(CEX)と同様のオンチェーンオーダーブックを採用しています。
- これにより、取引の透明性が確保され、全ての取引履歴がブロックチェーン上に記録されます。
- DEXでありながら、CEXのようなスムーズな取引体験を提供します。
イーサリアムなどのブロックチェーンは、その分散性とセキュリティの高さから広く利用されていますが、ブロック生成時間の遅さやガス代の高騰といったスケーラビリティの問題を抱えています。Hyperliquid L1は、これらの問題を解決するために開発されたブロックチェーンであり、BasedAppは、そのHyperliquid L1の技術的優位性を活かすことで、ユーザーに高速で低コスト、かつ透明性の高い取引環境を提供しています。BasedAppが提供する取引体験の快適さは、このHyperliquid L1ブロックチェーンの技術力に支えられているのです。
FAQ小見出し:BasedAppを利用するメリットは何ですか?
BasedAppを利用する最大のメリットは、Hyperliquid L1ブロックチェーンが提供する、高速で低コスト、そして透明性の高い取引環境を享受できる点にあります。具体的には、以下の点が挙げられます。
- CEX並みの取引スピードと低手数料:
- BasedAppは、Hyperliquid L1の0.2秒というブロック生成時間と、秒間200,000トランザクション(TPS)という高い処理能力により、CEX(中央集権型取引所)に匹敵する、あるいはそれを超える取引スピードを実現しています。
- さらに、BasedApp内での取引にはガス手数料がかからないため、頻繁な取引や少額取引でもコストを気にすることなく行うことができます。
- DEXならではの透明性と自己保管:
- BasedAppはDEXであるため、ユーザーは自身のウォレットの秘密鍵を自身で管理し、資産を自己保管することができます。これにより、CEXのようなハッキングリスクや取引所の閉鎖リスクを低減できます。
- オンチェーンオーダーブックを採用しているため、全ての取引履歴はブロックチェーン上に記録され、高い透明性が確保されています。
- 統合された金融サービス:
- BasedAppは、単なる取引プラットフォームにとどまらず、資産管理機能や、Visaカードを通じた実世界での決済機能も提供しています。
- これにより、仮想通貨の保有者は、複数のプラットフォームを使い分けることなく、一つのアプリケーション内で多様な金融活動を行うことが可能です。
- AIを活用した高度な機能:
- HyperAIボットを利用することで、AIによる自動取引戦略を実行できます。
- HyperVault 2.0では、AIが市場を分析し、リスクを管理しながら流動性提供による収益獲得を目指せます。
- ポイントプログラムとエアドロップの機会:
- BasedAppでの取引や機能利用に応じてポイントが付与され、将来的なエアドロップに繋がる可能性があります。
- シーズン2のポイントプログラムでは、取引量が少ないユーザーでも参加しやすくなっています。
これらのメリットにより、BasedAppは、取引の効率性、資産の安全性、そして仮想通貨の実用性を重視するユーザーにとって、非常に魅力的なプラットフォームと言えるでしょう。
Hyperliquidエコシステムと$HYPEトークンに関するFAQ
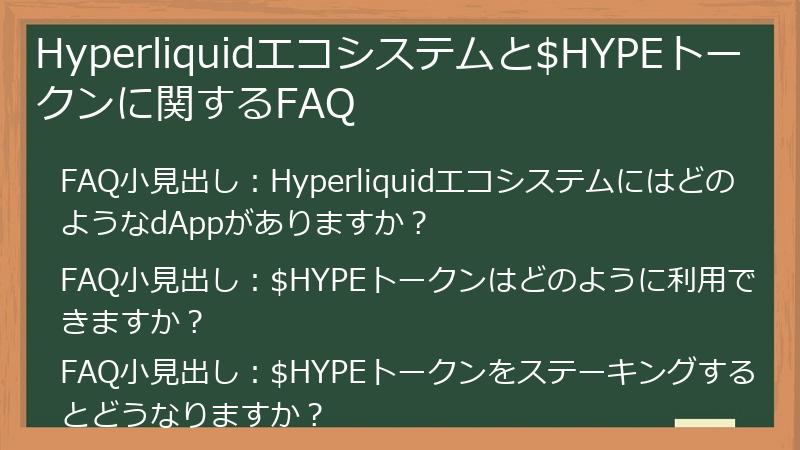
このFAQセクションでは、BasedAppを支えるHyperliquidエコシステム全体と、その中核をなす$HYPEトークンに関する疑問に焦点を当てます。Hyperliquidエコシステムは、BasedApp以外にも様々な分散型アプリケーション(dApp)が含まれており、その全体像を理解することは、BasedAppのポテンシャルをより深く理解する上で重要です。ここでは、HyperEVM上で展開されるdAppの種類や、それらがエコシステムにどのように貢献しているのかを解説します。また、BasedAppの利用や投資において中心的な役割を果たす$HYPEトークンについて、その具体的な用途、トークンエコノミクス、そしてステーキングによる収益獲得の可能性など、ユーザーが知っておくべき情報を網羅的に提供します。
- HyperliquidエコシステムとdAppに関するFAQ:
- $HYPEトークンの利用方法と効用に関するFAQ:
- $HYPEトークンのステーキングに関するFAQ:
FAQ小見出し:HyperliquidエコシステムにはどのようなdAppがありますか?
Hyperliquidエコシステムは、BasedAppというフラッグシップDEXアプリケーションを中核としながらも、その可能性は多岐にわたります。HyperEVMというEVM互換環境の導入により、多様な分散型アプリケーション(dApp)の開発と展開が加速しています。2025年2月のHyperEVMメインネット稼働開始以降、多くのプロジェクトがHyperliquid上で開発を進めており、BasedAppとの連携や相互運用も進んでいます。
現在、Hyperliquidエコシステム内で開発が進んでいる、または既に展開されている主なdAppには、以下のようなものがあります。
- BasedApp:
- Hyperliquid L1を基盤とする、高速・低コスト・高機能なDEXアプリケーションです。
- 現物取引、無期限先物取引、AIトレーディングボット、資産管理、Visaカード決済などを統合しています。
- HyperEVM上でスマートコントラクトを活用し、高度な取引機能や流動性提供機能を提供しています。
- Felix Protocol:
- HyperEVM上で開発されているレンディングプロトコルです。
- $HYPEトークンを担保に、独自の安定コインであるfeUSDを発行することができます。
- これにより、ユーザーは$HYPEを保有しながら流動性を確保し、さらなる投資機会を追求できます。
- Thunderhead:
- MEV(マイナー抽出可能価値)に対応したステーキングハブです。
- $stHYPEというラップドトークンを提供し、エコシステム内の流動性を高める役割を担っています。
- ユーザーは$stHYPEをステーキングすることで、追加の報酬を得ることが可能です。
- Hypurr.fun:
- Hyperliquidエコシステムにおけるミームコインのランチパッド(発行プラットフォーム)です。
- 新しいミームコインがオークション形式で上場され、取引されています。
- BasedAppとも連携しており、Telegramボット経由でのミントや取引も可能です。
- HyperAIボット:
- BasedAppに統合されているAI駆動のトレーディングボットです。
- 市場データをリアルタイム分析し、ユーザー設定に基づいた自動取引をサポートします。
- スキャルピング、トレンドフォローなど、様々な取引戦略を自動化できます。
- HyperVault 2.0:
- AI最適化された市場メイキング戦略により、流動性提供者に追加収益をもたらす次世代流動性プールです。
- 従来のHLP Vaultよりもリスク分散が強化され、清算リスクが低減されています。
- 年利40%超の収益を目指すことができます。
これらのdAppは、Hyperliquidエコシステム全体の成長を促進し、ユーザーに多様な金融サービスへのアクセスを提供しています。BasedAppを利用するユーザーは、これらのdAppとも連携することで、より幅広い投資機会や収益機会を得ることが可能です。Hyperliquidエコシステムは、今後も新しいdAppの登場により、さらに拡大していくことが期待されています。
FAQ小見出し:$HYPEトークンはどのように利用できますか?
$HYPEトークンは、BasedAppおよびHyperliquidエコシステム全体におけるネイティブトークンであり、そのユーティリティは多岐にわたります。BasedAppを最大限に活用し、エコシステムへの貢献を通じてメリットを享受するためには、$HYPEトークンの利用方法を理解することが不可欠です。
$HYPEトークンの主な利用方法と効用は以下の通りです。
- 取引手数料の支払い:
- BasedAppでの取引手数料の支払いに$HYPEトークンを使用することができます。
- これにより、取引コストを削減できる場合があります(具体的な割引率は、プラットフォームの利用規約やアップデートにより変動する可能性があります)。
- ガバナンスへの参加:
- $HYPEトークンを保有するユーザーは、Hyperliquidエコシステムのガバナンスに参加する権利を持ちます。
- プラットフォームの将来的な開発方針、手数料構造の変更、新しい資産の上場基準などに関する提案に投票することができます。
- このガバナンス参加により、ユーザーはプラットフォームの意思決定プロセスに直接関与し、エコシステムの発展に貢献できます。
- ステーキングによる報酬獲得:
- $HYPEトークンをステーキングすることで、受動的な報酬を得ることができます。
- Hyperliquidエコシステムでは、HLP Vaultなどを通じて$HYPEをステーキングすることが可能で、年利24%以上のリターンが期待できます。
- ステーキングは、トークン保有者へのインセンティブ提供だけでなく、エコシステムの流動性やセキュリティ強化にも寄与します。
- Visaカード決済での利用:
- BasedAppと連携するVisaカードでは、$HYPEトークンを基盤とした決済が可能です。
- これにより、保有している$HYPEトークンを、現実世界でのショッピングやサービス利用に直接活用できます。
- ポイントプログラムへの貢献:
- BasedAppでの取引やプラットフォームへの貢献を通じて$HYPEトークンを獲得したり、利用したりすることで、ポイントプログラムの対象となる場合があります。
- これらのポイントは、将来的なエアドロップやその他の報酬に繋がる可能性があります。
- HYPEアシスタンスファンド:
- プラットフォームの収益の一部は、$HYPEトークンの買い戻しに充てられ、HYPEアシスタンスファンドとして運用されています。
- これにより、トークン価格の安定化と流動性の向上に寄与し、投資家保護の側面も持ち合わせています。
- 受動的な収益の獲得:
- ステーキングすることで、保有している$HYPEトークンがさらに増加します。
- これは、長期的に資産を増やしたいユーザーにとって、非常に魅力的なインセンティブとなります。
- エコシステムのセキュリティ強化への貢献:
- $HYPEトークンをステーキングするユーザーは、ネットワークのバリデーターとして間接的に貢献することになります。
- これにより、Hyperliquid L1ブロックチェーンのセキュリティと安定性が向上します。
- ガバナンスへの影響力向上:
- 一部のステーキングプログラムでは、$HYPEの保有量だけでなく、ステーキング量に応じてガバナンス投票の際の重みが増す場合があります。
- これにより、プラットフォームの意思決定プロセスにおいて、より大きな影響力を持つことができます。
- インセンティブプログラムへの参加:
- BasedAppは、ステーキング参加者に対して、追加のポイント付与や、将来的なエアドロップの対象となるようなインセンティブプログラムを提供することがあります。
- 2025年8月に発表されたシーズン2エアドロップでは、取引量だけでなく、DAO提案参加やステーキングもポイント対象に含まれることで、参加を奨励しています。
- BasedAppを利用するために必要なものは何ですか?:
- MetaMaskウォレットの準備方法を教えてください。:
- ETH(イーサリアム)はなぜ必要ですか?:
- 仮想通貨ウォレット:
- BasedAppは、Hyperliquid L1ブロックチェーン上で動作し、資産の管理や取引にはウォレットが必要です。
- 特に、MetaMaskやRabbyといった、Arbitrumネットワークに対応したブラウザ拡張機能またはモバイルアプリのウォレットが推奨されます。
- ウォレットでは、秘密鍵(シードフレーズ)を自身で厳重に管理する必要があります。
- 仮想通貨(USDCとETH):
- USDC(USD Coin):BasedAppでの取引の証拠金として使用されます。
- ETH(イーサリアム):BasedAppへの資産入金(Arbitrumネットワーク経由)の際に、ネットワーク手数料(ガス代)として必要となります。
- これらの仮想通貨は、国内の仮想通貨取引所などで日本円で購入し、自身のウォレットに送金する必要があります。
- インターネット接続環境:
- BasedAppはウェブサイトまたはモバイルアプリを通じて利用するため、安定したインターネット接続環境が必要です。
- PCまたはスマートフォンがあれば、場所を選ばずに利用できます。
- (推奨)日本語での情報収集手段:
- BasedAppの日本語サポートは発展途上ですが、公式Discordの日本語チャンネルや、日本のKOL(Key Opinion Leader)による情報発信などを活用することで、よりスムーズに利用できます。
- 最新のアップデート情報や利用方法に関するFAQ(よくある質問)などを確認できる環境があると便利です。
- ブラウザ拡張機能の場合:
- MetaMaskの公式サイト( metamask.io )にアクセスします。
- お使いのブラウザの拡張機能ストア(Chromeウェブストアなど)へのリンクが表示されるので、そこから「MetaMask」を検索してインストールしてください。
- インストール後、ブラウザのツールバーにMetaMaskのアイコンが表示されます。
- スマートフォンアプリの場合:
- App Store(iOS)またはGoogle Play Store(Android)で「MetaMask」を検索し、公式アプリをダウンロードしてインストールしてください。
- シードフレーズの重要性:
- シードフレーズは、ウォレットの秘密鍵に相当するものであり、これがあれば誰でもあなたのウォレットにアクセスできます。
- このフレーズを紛失したり、他人に知られたりすると、ウォレット内の資産をすべて失うことになります。
- 絶対にデジタルデータ(PC、スマホ、クラウドなど)で保存せず、紙に書き留め、オフラインで安全な場所(金庫など)に保管してください。
- パスワードの設定:
- ウォレットへのアクセスを容易にするために、安全なパスワードを設定します。
- このパスワードは、シードフレーズとは異なり、ウォレットへのログイン時に必要となります。
- ネットワーク追加手順:
- MetaMaskを開き、画面上部にあるネットワーク表示(通常は「Ethereum Mainnet」)をクリックします。
- 「ネットワークの追加」を選択し、「カスタムネットワーク」タブに以下の情報を手動で入力します。
- ネットワーク名:Arbitrum One
- 新しいRPC URL:
https://arb1.arbitrum.io/rpc - チェーンID:
42161 - 通貨記号:ETH
- ブロックエクスプローラーURL:
https://arbiscan.io/ - 入力後、「保存」をクリックすると、Arbitrum OneネットワークがMetaMaskに追加されます。
- ネットワークの切り替え:
- BasedAppを利用する際は、必ずMetaMaskのネットワークを「Arbitrum One」に切り替えてください。
- これにより、Arbitrumネットワーク上のトランザクションを正しく処理できるようになります。
- BasedAppへのUSDCなどの入金時:
- BasedAppへ資産を入金する際、通常はArbitrumネットワークを経由して行われます。
- Arbitrumネットワーク上でのトランザクションを承認・実行するためには、ネットワーク手数料としてETHが必要となります。
- このETHは、ウォレットに保有しておくことで、入金トランザクションをスムーズに完了させるために使用されます。
- ウォレット間での仮想通貨送金時:
- 仮想通貨取引所から自身のウォレットへ送金する際にも、取引所によってはETHをガス代として使用することがあります。
- また、自身のウォレット間で仮想通貨を送金する際にも、Arbitrumネットワーク上でのトランザクションにはETHのガス代が必要となります。
- スマートコントラクトとのインタラクション時:
- BasedAppと連携する他のdApp(分散型アプリケーション)を利用する際、例えばHyperVault 2.0への流動性提供や、Social Vaultへの参加など、スマートコントラクトとのやり取りが発生する場合には、Arbitrumネットワーク上でのガス代としてETHが必要となることがあります。
$HYPEトークンは、単なる投機対象としてだけでなく、BasedAppおよびHyperliquidエコシステム全体の成長と利用を促進するための重要な役割を担っています。エコシステムへの参加や貢献を通じて、$HYPEトークンの価値をさらに高めていくことが期待されます。
FAQ小見出し:$HYPEトークンをステーキングするとどうなりますか?
$HYPEトークンをステーキングすることは、BasedAppおよびHyperliquidエコシステムへの参加を深め、受動的な収益を得るための有効な手段です。ステーキングの仕組みと、それによって得られるメリットについて詳しく解説します。
$HYPEトークンのステーキングは、主にHyperliquidエコシステム内で提供されている流動性プールや、専用のステーキングプラットフォームを通じて行われます。2025年末時点では、HLP Vaultなどを通じたステーキングで、年利24%以上のリターンが期待できるとされています。ただし、このAPY(年換算利回り)は市場の状況やエコシステムの活動量によって変動する可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
$HYPEトークンをステーキングする主なメリットは以下の通りです。
BasedAppでは、$HYPEトークンの保有量に応じて、ステーキング報酬率が変動する「ステーキングTierシステム」も導入されています。Tier1(10万HYPE以上保有)ではAPY35%が提供される一方、Tier3(1,000HYPE以下)ではAPY15%となります。このTierシステムは、$HYPEトークンの保有を奨励し、エコシステムへの長期的なコミットメントを促すことを目的としています。
$HYPEトークンのステーキングは、受動的な収益源としてだけでなく、エコシステムへの貢献やガバナンス参加といった多角的なメリットをもたらします。BasedAppを長期的に利用したいと考えているユーザーにとっては、積極的に検討すべき選択肢と言えるでしょう。ステーキングを行う際は、利用するプラットフォームの規約をよく確認し、リスクを理解した上で実行してください。
BasedAppの利用環境と準備に関するFAQ

BasedAppをスムーズに利用開始するためには、事前の準備が不可欠です。このFAQセクションでは、BasedAppを利用する上で必要となる環境や、取引を開始するための準備について解説します。BasedAppを利用するために、具体的にどのようなウォレットが必要なのか、また、取引の際に不可欠となるETH(イーサリアム)の準備とその重要性について、初心者の方にも分かりやすく説明します。これらの準備を万全に行うことで、BasedAppでの取引をストレスなく開始し、そのメリットを最大限に享受できるようになります。
FAQ小見出し:BasedAppを利用するために必要なものは何ですか?
BasedAppをスムーズに利用開始するためには、いくつか事前に準備しておくべきものがあります。これらを事前に確認しておくことで、AfterAppでの取引や機能の利用を円滑に進めることができます。
BasedAppを利用するために最低限必要なものは、以下の通りです。
これらの準備を事前に完了しておくことで、BasedAppへのウォレット接続から入金、そして取引開始までのプロセスをスムーズに進めることができます。特に、ウォレットのセキュリティ管理と、ETHの十分な準備は、AfterAppの利用を安全かつ快適に行う上で非常に重要です。
FAQ小見出し:MetaMaskウォレットの準備方法を教えてください。
BasedAppを利用するためには、まずMetaMaskウォレットを準備する必要があります。MetaMaskは、ブラウザ拡張機能またはスマートフォンアプリとして利用できる、最もポピュラーな仮想通貨ウォレットの一つです。ここでは、MetaMaskの準備手順を、初心者の方でも理解できるように、順を追って解説します。
MetaMaskのインストール
まず、お使いのブラウザ(Chrome, Firefox, Braveなど)またはスマートフォン(iOS, Android)にMetaMaskをインストールします。
ウォレットの新規作成とシードフレーズの管理
MetaMaskを起動したら、「ウォレットの作成」を選択します。この際、**非常に重要なステップ**として、12個の英単語で構成される「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)」が生成されます。
シードフレーズの確認とパスワードの設定が完了すれば、MetaMaskウォレットの準備は完了です。
Arbitrumネットワークの設定
BasedAppはHyperliquid L1上で動作しますが、資産の入出金にはArbitrumネットワークを経由します。そのため、MetaMaskにArbitrum Oneネットワークを追加する必要があります。
これで、BasedAppとの連携に必要なMetaMaskウォレットの準備はすべて完了しました。次に、このウォレットにUSDCとETHを入金するステップに進みます。
FAQ小見出し:ETH(イーサリアム)はなぜ必要ですか?
BasedAppを利用するにあたり、ETH(イーサリアム)が必要となる理由は、主に**Arbitrumネットワーク上でのガス代(ネットワーク手数料)の支払い**にあります。BasedApp自体はHyperliquid L1ブロックチェーン上で動作しており、プラットフォーム内での取引や操作には原則としてガス代はかかりません。しかし、BasedAppへの資産の入出金プロセスや、BasedAppが連携するArbitrumネットワーク上でのトランザクション(取引)を実行する際には、イーサリアムのブロックチェーンインフラを利用するため、ETHによるガス代の支払いが不可欠となります。
具体的には、以下の場面でETHが必要となります。
ETHは、イーサリアムブロックチェーンおよびそれと互換性のあるネットワーク(Arbitrumなど)における、ネットワーク手数料の標準的な支払い手段です。BasedAppを利用する上で、このETHのガス代の必要性を理解し、常にウォレットに一定量のETHを準備しておくことが、取引の遅延や失敗を防ぐために不可欠です。
ETHは、国内の仮想通貨取引所で購入し、自身のMetaMaskやRabbyウォレットに送金することで準備できます。必要なETHの量は、ネットワークの混雑状況によって変動するため、常に余裕を持った量を用意しておくことが推奨されます。例えば、0.01ETH~0.05ETH程度あれば、多くの場合、一度のトランザクションを完了させることができますが、ネットワークの混雑時にはさらに多くのETHが必要になることもあります。
BasedApp内での取引自体にはガス代がかかりませんが、Arbitrumネットワークへの入出金や、関連するスマートコントラクトとのやり取りでETHが必要となることを念頭に置いて、準備を進めてください。
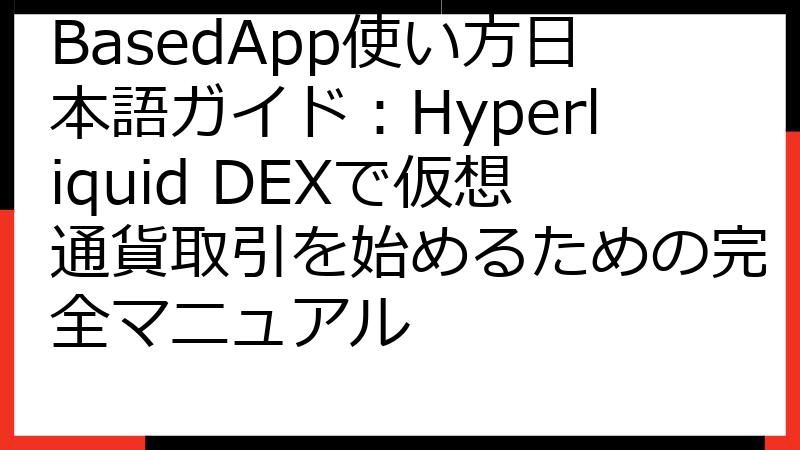
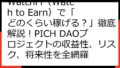
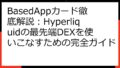
コメント