【中学生必見!】税の作文、これで完璧!書き方からテーマ選び、構成まで徹底解説
税の作文の書き方に悩んでいませんか?。この記事では、中学生の皆さんが税の作文を効果的に書くための方法を、テーマ選びから構成、具体的な書き方まで、分かりやすく解説します。。自信を持って作文を完成させるためのヒントが満載です。。
税の作文とは?基本を理解して差をつける
税の作文を書く上で、まず何よりも大切なのは「税の作文」そのものがどのようなものなのか、その目的や重要性を正確に理解することです。中学生という立場だからこそ、税金について学ぶことには大きな意義があり、作文を通してどのような視点や表現力が求められているのかを知ることで、他の人とは一味違う、説得力のある作文を書くことができるでしょう。
税の作文の目的と重要性
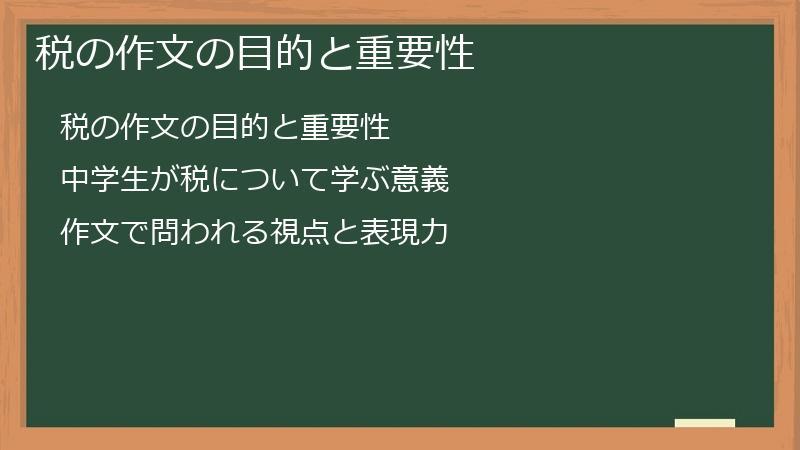
税の作文を始めるにあたり、まず「なぜ税の作文を書く必要があるのか?」という目的と、それがなぜ重要なのかを理解しておきましょう。作文を通して、普段あまり意識しない税金が、私たちの社会や生活にどれほど深く関わっているのかを改めて認識する機会となります。また、この作文は、単に税金について知っているかを試すだけでなく、それを自分なりにどう考え、どう表現できるかという、思考力や表現力も問われる場なのです。
税の作文の目的と重要性
税の作文の目的
- 税金が社会でどのように役立っているのかを理解し、その重要性を認識すること。
- 税金に関する知識を深め、社会の一員としての自覚を育むこと。
- 税金について自分の考えをまとめ、それを文章で表現する能力を養うこと。
- 社会の仕組みや公共サービスについて、税金との関連で考察する力をつけること。
税の作文の重要性
- 税金は、道路の整備、教育、医療、治安維持など、私たちの生活を支える様々な公共サービスに不可欠です。
- 作文を通して、これらのサービスが税金によって成り立っていることを実感し、税金の大切さを学びます。
- 税金がなければ、現代社会が維持できないことを理解することは、社会の一員としての責任感を育む上で重要です。
- 作文は、税金に対する関心を高め、将来的に税金について主体的に考え、判断する力を養うための第一歩となります。
作文で問われる視点と表現力
- 税金というテーマに対して、一方的な知識の披露ではなく、自分自身の経験や考えを交えて論じることが求められます。
- 身近な例(例えば、お菓子やゲームを買うときに支払う消費税など)から税金について考え、それを具体的に記述する力が重要です。
- 論理的な文章構成、分かりやすい言葉遣い、そして自分の意見を明確に伝える表現力が、作文の評価において重視されます。
中学生が税について学ぶ意義
社会への関心を高める
- 税金は、私たちの社会がどのように成り立っているのかを理解する上で、非常に重要な要素です。
- 中学校で税について学ぶことは、政治や経済といった社会の仕組みへの関心を深めるきっかけとなります。
- 税金が使われている公共サービス(例えば、学校の施設、図書館、公園、警察、消防など)を知ることで、社会との繋がりを実感できます。
- これらの学びを通して、自分たちが暮らす社会をより良くしていくために、税金がどのように貢献しているのかを理解することができます。
社会の一員としての自覚
- 税金は、国民が国の運営のために負担するものであり、社会の一員としての責任を果たす行為の一つです。
- 税金について学ぶことで、自分が社会の構成員であることを意識し、社会への貢献のあり方を考えるようになります。
- 将来、納税者となるという視点を持つことで、税金に対する理解が深まり、社会への参画意識が高まります。
- 税金は、世代を超えて社会を維持していくための仕組みであり、その一端を担うことの重要性を認識することが大切です。
将来の生活への準備
- 大人になると、私たちは様々な形で税金と関わることになります。例えば、給料から所得税が天引きされたり、買い物の際には消費税を支払ったりします。
- 学校で税金について学ぶことは、将来、自身がお金の管理をしたり、社会の出来事を理解したりする上で、確かな土台となります。
- 税金の種類やその使われ方を知っておくことは、将来のライフプランを考える上でも役立ちます。
- 税金に関する知識は、社会人としての経済的なリテラシーを高めるために不可欠です。
作文で問われる視点と表現力
税金に対する「自分ごと」としての視点
- 税の作文では、単に税金の種類や仕組みを説明するだけでなく、それらが自分自身の生活や社会にどのように影響しているのかを考える視点が重要です。
- 例えば、地域の公園や図書館が税金で運営されていることを知り、そこで自分がどのように恩恵を受けているのかを具体的に記述することが考えられます。
- また、将来どのような社会になってほしいか、そのために税金がどのように使われるべきかといった、未来への視点を持つことも評価されます。
- 「なぜ税金が必要なのか」「税金があることで何が可能になるのか」といった問いに対する自分なりの答えを探求することが、作文の深みを増します。
具体例を盛り込む表現力
- 抽象的な説明だけでなく、具体的なエピソードや例を挙げることで、文章に説得力が増します。
- 例えば、家族がお金について話している様子、買い物の際にレシートを見て消費税を確認した経験などを描写すると、読者も税金が身近なものであることを感じやすくなります。
- 社会の出来事(例えば、震災復興や新しい公共施設の建設など)と税金を結びつけて説明するのも効果的です。
- 「~と思います」といった断定的な表現だけでなく、「~だと感じました」「~という可能性もあるのではないでしょうか」といった、多様な表現を使い分けることも大切です。
論理的で分かりやすい構成
- 作文は、読者が内容をスムーズに理解できるよう、論理的に構成されている必要があります。
- まず、自分が何について書きたいのか(テーマ)を明確にし、そのテーマについてどのようなことを伝えたいのか(主張)をはっきりとさせることが大切です。
- 導入で読者の関心を引きつけ、本文で具体的な理由や例を挙げて主張を裏付け、結論で改めて主張をまとめたり、今後の展望を示したりする構成が一般的です。
- 各段落で伝えたいことが明確になるように、接続詞などを効果的に使用し、話の流れをスムーズにすることも、表現力の一つと言えます。
テーマ選びのコツ:身近な税金から発想する
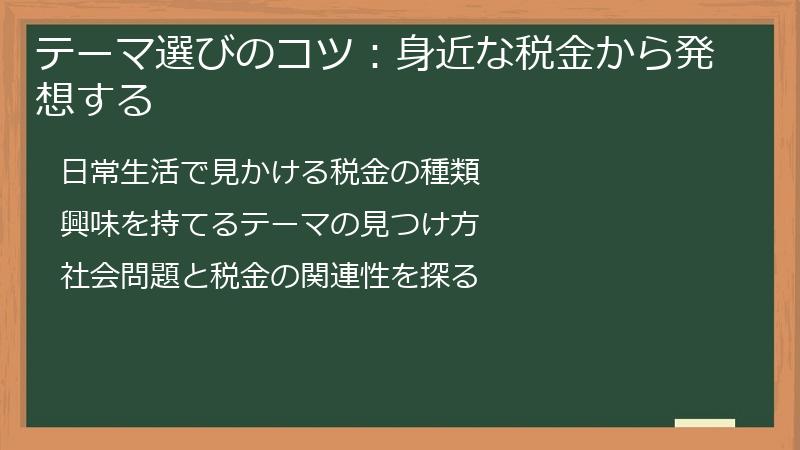
税の作文で最も悩むのが「どんなテーマで書けばいいのだろう?」ということかもしれません。しかし、税金は決して難しいものではなく、私たちの日常生活の至るところに存在しています。まずは、身近なところから税金に目を向けてみましょう。普段何気なく見ているもの、利用しているサービスの中に、税金との繋がりが隠されています。そうした身近な税金に焦点を当てることで、自分ならではの視点を見つけやすくなり、オリジナリティのある作文を書くためのヒントが得られるはずです。
日常生活で見かける税金の種類
身近な消費税
- 消費税は、商品やサービスを購入する際に、その価格に上乗せして支払う税金です。
- 例えば、コンビニでお菓子を買ったり、本屋で漫画を買ったり、美容院で髪を切ったりする時など、ほとんどの買い物で消費税を支払っています。
- 「税抜き価格」と「税込み価格」の表示を見て、自分がいくら消費税を払っているのかを意識してみましょう。
- 日々の買い物を記録してみると、一年間でかなりの額の消費税を納めていることに気づくはずです。
地域と結びつく固定資産税・都市計画税
- 固定資産税や都市計画税は、土地や家屋といった不動産を所有している人が、その資産がある市町村に納める税金です。
- これらの税金は、道路や学校、図書館、公園、上下水道など、地域社会のインフラ整備や公共サービスのために使われています。
- 自分の家や、学校の周りの施設などが、これらの税金によってどのように整備・維持されているのかを想像してみると、税金の存在をより身近に感じられます。
- 自治体が発行する広報誌などには、税金の使い道について書かれていることもありますので、参考にしてみると良いでしょう。
働くこととお金、そして税金(所得税・住民税)
- 所得税や住民税は、働いて得た収入(所得)に対してかかる税金です。
- 親御さんが会社から給料をもらう際、そこから所得税や住民税が差し引かれていることがあります。
- これは、国や地方自治体が、社会保障や教育、福祉などに税金を使っているためです。
- 「働くこと」と「税金を納めること」がどのように繋がっているのかを理解することは、社会の仕組みを知る上で重要です。
興味を持てるテーマの見つけ方
身近な体験から税金を探る
- 「なぜ?」と疑問に思ったことから、税金への関心が生まれることがあります。
- 例えば、お菓子を買った時のレシートに書かれている消費税額を見て、その金額の多さに驚いた経験はありませんか?
- また、家族が「税金が高い」と言っていたり、ニュースで税金に関する話題を聞いたりしたことも、テーマを見つけるきっかけになります。
- 普段の生活の中で、「これは税金で賄われているのかな?」と疑問に思ったことをメモしておくと、作文のテーマが見つかりやすくなります。
学校生活や地域との繋がり
- 学校の施設(体育館、図書館、コンピュータ室など)や、学校で使われている備品、あるいは学校行事(修学旅行など)にかかる費用も、間接的に税金と関係している場合があります。
- 住んでいる地域の公園、図書館、病院、道路、橋、消防署、警察署なども、税金によって整備・運営されています。
- これらの公共施設やサービスを実際に利用した経験を振り返り、「もし税金がなかったらどうなるだろう?」と考えてみるのも良いでしょう。
- 地域で最近行われたイベントやお祭りが、どのようにして開催されているのか、その裏側にも税金が関わっていることがあります。
ニュースや社会問題からヒントを得る
- テレビやインターネットのニュースで、税金に関する話題が取り上げられることがあります。
- 例えば、新しい法律で税金が変わるというニュースや、税金の使い道に関する議論などがそれにあたります。
- 環境問題、少子高齢化、福祉、教育など、社会が抱える様々な問題と税金がどのように関連しているのかを調べてみるのも、興味深いテーマとなるでしょう。
- 「なぜこの問題が起こっているのか?」「税金はどのように役立てば、この問題を解決できるのか?」といった問いを立ててみることで、より深いテーマ設定が可能になります。
社会問題と税金の関連性を探る
環境問題と税金
- 近年、環境問題への関心が高まる中で、環境税という考え方が注目されています。
- これは、環境に負荷を与える製品や活動に対して課税することで、環境保護を促すための税金です。
- 例えば、ガソリン税は、自動車の利用が環境に与える影響を考慮して課税されている側面があります。
- また、ゴミの削減やリサイクルの推進を目的とした税金や、再生可能エネルギーの普及を支援するための税制なども存在します。
- 「地球温暖化を食い止めるために、税金はどう活用されるべきか」といった視点で作文を書くことも可能です。
少子高齢化社会と税金
- 日本は、世界でも有数の少子高齢化社会であり、この問題と税金は深く関わっています。
- 高齢者が増加し、医療費や年金といった社会保障費が増大する一方で、働く世代の人口が減少していくという状況があります。
- こうした中で、社会保障制度を維持するために、税金がどのように使われているのか、あるいは今後どのように使われるべきなのかを考えることは、非常に重要なテーマです。
- 子供たちが将来安心して暮らせる社会を作るために、今の世代がどのような税負担を負うべきか、といった視点も考えられます。
国際社会における税の役割
- 税金は、国内だけでなく、国際社会においても重要な役割を果たしています。
- 例えば、国連などの国際機関への分担金や、開発途上国への援助資金なども、税金から支出されていることがあります。
- また、国境を越える経済活動(例えば、多国籍企業の活動など)に対する課税ルールも、国際的な協調によって定められています。
- 「世界平和のために、あるいは国際協力のために、税金はどのように役立っているのか」といった視点や、「グローバル化が進む現代において、税金はどのような役割を担うべきか」といった考察も、作文のテーマとして深みを与えます。
作文の構成:基本の型をマスターする
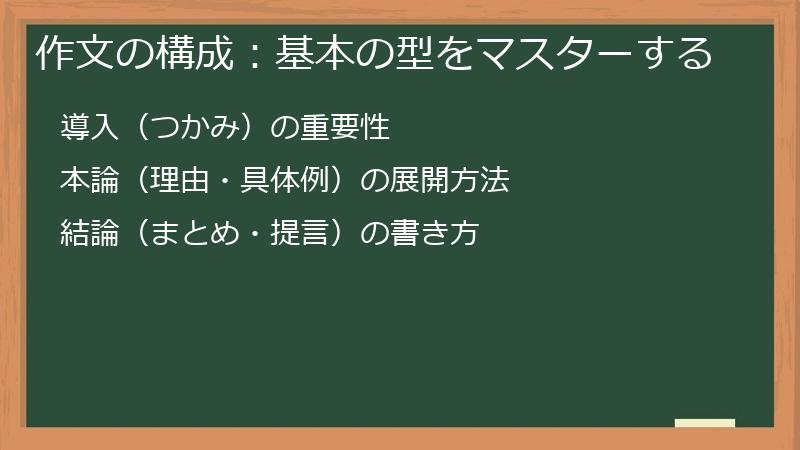
作文を書く上で、どんなに素晴らしいアイデアや知識があっても、それを効果的に伝えるための「構成」がしっかりしていなければ、読者に伝わりにくくなってしまいます。税の作文も例外ではありません。ここでは、読者を引きつけ、内容をスムーズに理解してもらうための、基本的な作文の構成方法について解説します。この基本の型をマスターすることで、あなたの作文は格段に分かりやすく、説得力のあるものになるでしょう。
導入(つかみ)の重要性
読者の興味を引く「つかみ」とは
- 作文の導入部分は、読者が「この先を読みたい」と思わせるための、いわば「顔」となる部分です。
- ここで読者の興味を引くことができれば、その後の文章も読んでもらいやすくなります。
- 税金というテーマは、少し堅苦しいと感じる人もいるかもしれませんが、導入で工夫を凝らすことで、親しみやすく、面白そうだと感じてもらうことが可能です。
効果的な導入の書き方
- 身近な体験談から始める:例えば、「先日、お菓子を買った時にレシートを見て、消費税って結構高いな、と思ったのがきっかけです。」のように、自身の体験を語ることで、読者は共感しやすくなります。
- 問いかけで始める:「もし、この世の中から税金がなくなったら、私たちの生活はどうなるでしょうか?」といった問いかけは、読者に「自分ならどう答えるだろう?」と考えさせ、興味を引きます。
- 驚くべき事実やデータを示す:「日本には、約○○種類もの税金があることを知っていますか?」のように、意外な事実や統計データを示すことで、読者の好奇心を刺激します。
- 比喩や例えを用いる:税金が社会を支える「血液」のようなものである、といった比喩を使うことで、抽象的な税金のイメージを具体的に伝えやすくなります。
導入で避けるべきこと
- いきなり専門用語を並べたり、教科書的な説明から始めたりするのは避けましょう。読者が内容に入る前に疲れてしまう可能性があります。
- 長すぎる導入も、読者の集中力を削ぐ原因となります。簡潔に、しかしインパクトのある言葉を選ぶことが重要です。
- 作文のテーマから逸れた内容にならないよう、導入で示す方向性を明確にしておく必要があります。
本論(理由・具体例)の展開方法
主張を支える根拠の提示
- 作文の本論は、導入で提示したテーマや主張に対して、その理由や根拠を具体的に述べる部分です。
- なぜそのように考えるのか、どのような事実やデータに基づいているのかを、読者に分かりやすく説明する必要があります。
- 税の作文であれば、税金が社会でどのように役立っているのか、あるいは税金についてどのように考えるべきなのか、といった自分の意見の根拠を明確に示します。
具体例で説得力を高める
- 身近な具体例:例えば、消費税が身近な商品にどのようにかかっているか、お小遣いの範囲で税金がどれだけ影響しているかなどを具体的に書くことが有効です。
- 公共サービスとの関連:学校の図書館で借りた本、通学路の整備された道路、地域の消防署の活動など、税金によって実現している公共サービスを例に挙げ、その恩恵について触れることで、税金の重要性を伝えることができます。
- データや統計の活用:もし可能であれば、税金の使われ方に関するデータや、特定の税金が社会に与える影響を示す統計などを引用することで、文章に客観性と説得力を持たせることができます。ただし、中学校の作文では、そこまで厳密なデータ引用は求められない場合が多いので、正確な情報源に基づいて、分かりやすく伝えることを意識しましょう。
- 体験談の挿入:家族との会話や、ニュースを見て感じたこと、地域での出来事などを具体的に描写することで、読者はより共感しやすくなります。
論理的な文章の流れ
- 本論は、いくつかの段落に分けることが一般的です。
- 各段落で一つのテーマや論点を扱い、その段落内で理由や具体例を説明するように構成すると、読者は内容を追いやすくなります。
- 「なぜなら~」「例えば~」「また~」「さらに~」といった接続詞を適切に使うことで、段落間のつながりがスムーズになり、文章全体の論理性が高まります。
結論(まとめ・提言)の書き方
作文の締めくくりとしての結論
- 作文の結論は、本文で述べた内容を簡潔にまとめ、読者に最終的なメッセージを伝えるための重要な部分です。
- ここで、導入で提示したテーマや主張を再確認し、作文全体を通して伝えたいことを明確に示します。
- 単に内容を繰り返すだけでなく、読者に「なるほど」と思わせるような、まとめ方や、今後の行動を促すような言葉を加えることが大切です。
効果的な結論の書き方
- 要点の再確認:本文で述べた最も重要なポイントや、自分の主張を改めて簡潔に述べます。「このように、税金は私たちの生活の様々な場面で役立っており、社会を支える大切なものであることが分かりました。」といった形です。
- 未来への提言:税金について学んだことを踏まえ、自分が今後どのように税金と関わっていきたいか、あるいは社会をより良くするために税金がどのように活用されるべきか、といった未来への希望や提言を述べます。「将来、私も社会の一員として、税金の大切さを理解し、責任ある行動をしていきたいです。」や「より公平で、効果的な税金の使われ方について、これからも関心を持っていきたいです。」といった表現が考えられます。
- 読者への呼びかけ:読者に対しても、税金について考えることの重要性を伝え、行動を促すような言葉を加えることも効果的です。「皆さんも、身近な税金について、ぜひ一度考えてみてください。」といった呼びかけが考えられます。
- 感謝の言葉(必要に応じて):もし、作文を書くにあたって、家族や先生からアドバイスをもらった場合などは、最後に感謝の言葉を添えることも良いでしょう。
結論で注意すべき点
- 結論で、本文で述べていない新しい情報や意見を付け加えるのは避けましょう。
- 長すぎる結論は、せっかくのまとまりを損ねてしまう可能性があります。簡潔に、しかし力強く締めくくることを意識しましょう。
- 抽象的な表現だけでなく、具体的な言葉で締めくくることで、読者の心に響きやすくなります。
税の作文の具体的な書き方:ステップバイステップ
テーマが決まり、構成の基本も理解したら、いよいよ具体的な執筆段階です。ここでは、税の作文をより完成度の高いものにするための、ステップごとの書き方と、文章をより説得力のあるものにするためのテクニックを詳しく解説します。また、書き終えた後に、さらに質を高めるための「推敲」についても触れていきます。このステップを丁寧に踏むことで、あなたの税の作文は、より伝わるものになるはずです。
題材の決定と情報収集
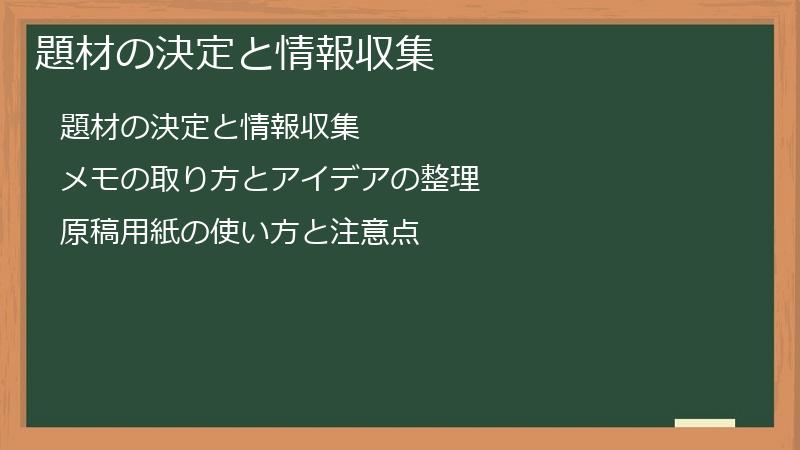
作文を書く上で、まず最初に取り組むべきは、どのようなテーマで、どのような内容を書くかを具体的に決めることです。そして、そのテーマについて、より詳しく、正確な情報を集めることが重要になります。情報収集の方法は様々ですが、信頼できる情報源から、作文に活かせるエピソードや事実を見つけ出すことが、説得力のある作文への第一歩となります。
題材の決定と情報収集
テーマを絞り込む
- 興味のある税金を選ぶ:消費税、所得税、地方税など、自分が一番関心を持った税金について深く掘り下げてみましょう。
- 身近な体験と結びつける:普段の買い物、家族の仕事、地域の施設利用など、自分の体験を基にテーマを設定すると、書きやすくなります。例えば、「お菓子を買うときに支払う消費税について、その使われ方を知りたい」といったテーマ設定です。
- 社会課題と関連付ける:環境問題、高齢化社会、地域活性化など、自分が関心のある社会問題と税金との関連を探るのも、深みのあるテーマになります。
- 「なぜ?」を深掘りする:「なぜ税金が必要なのか」「この税金はどのように使われているのか」といった疑問を掘り下げていくことで、作文の核となる視点が見えてきます。
情報収集の方法
- 教科書や副教材を確認する:学校で配布された資料や教科書には、税金に関する基本的な情報がまとめられています。まずはここから確認しましょう。
- 国税庁のウェブサイトを活用する:国税庁のウェブサイトは、税金に関する最新情報や、税金の仕組みについて分かりやすく解説されている資料が豊富にあります。特に「税の学習コーナー」などは中学生にも理解しやすい内容です。
- 税務署に問い合わせる(可能であれば):お近くの税務署に問い合わせて、パンフレットをもらったり、簡単な質問をしたりすることも、生きた情報を得る良い機会になります。
- 図鑑や児童書、専門書を読む:税金に関する入門書や、歴史的な背景を解説した書籍なども、理解を深めるのに役立ちます。
- 家族や先生に聞く:身近な大人に、税金についてどのように考えているか、あるいは税金に関する疑問などを質問してみるのも良いでしょう。
収集した情報の整理
- 集めた情報は、作文の構成に合わせて整理することが大切です。
- テーマに関連する事実、自分の意見、具体的なエピソードなどを、それぞれ書き出してみましょう。
- ノートに書き出したり、付箋にメモしたり、パソコンでまとめたりと、自分に合った方法で整理してください。
- 「どの情報が作文のどの部分で使えるか」を考えながら整理すると、執筆がスムーズに進みます。
メモの取り方とアイデアの整理
効果的なメモの取り方
- キーワードを書き出す:情報収集中に見つけた重要なキーワードや、自分の考えを連想させる言葉を書き留めましょう。
- 「なぜ?」を記録する:疑問に思ったことや、さらに調べてみたいと思った点は、その理由と共にメモしておくと、後で深掘りする際に役立ちます。
- 短い文章で要点をまとめる:長い文章で書き留めるよりも、要点を短くまとめておく方が、後で見返したときに理解しやすくなります。
- 引用元を明記する:参考にした資料やウェブサイトの名前などをメモしておくと、後で作文に活かす際や、より詳しい情報を確認したいときに便利です。
- 自分の言葉で書き換える:資料の内容をそのまま書き写すのではなく、一度自分の言葉で理解し直してからメモすることで、記憶に定着しやすくなります。
アイデアを整理する
- マインドマップを作成する:中心となるテーマから、関連するキーワードやアイデアを放射状に広げていくマインドマップは、発想を広げ、整理するのに効果的です。
- 箇条書きでリスト化する:作文で展開したい内容や、盛り込みたいエピソードを箇条書きにしていくことで、構成を考える上での全体像を掴むことができます。
- KJ法を活用する:集めた情報やアイデアを付箋などに書き出し、類似したものをグルーピングし、さらにそれらに名前をつけていくKJ法は、複雑な情報でも整理しやすくなります。
- 文章の骨子を作る:導入、本論(複数のパートに分ける)、結論といった骨子を決め、それぞれのパートでどのような内容を盛り込むかを簡単に書き出しておくと、執筆がスムーズに進みます。
アイデアの整理と作文の構成
- メモや整理したアイデアを元に、作文の構成案を作成します。
- 導入で読者の興味を引き、本論で具体的な説明や自分の考えを述べ、結論でまとめや提言を行う、という流れを意識しましょう。
- どのアイデアをどの部分に配置すれば、最も効果的に伝わるかを考えながら、構成を練り上げることが大切です。
原稿用紙の使い方と注意点
原稿用紙の正しい使い方
- 1マスに1文字:原則として、原稿用紙の1マスに1文字ずつ書きます。
- 句読点、記号の扱い:句点(。)や読点(、)も、1マスに1文字として書きます。ただし、文頭に句読点や閉じ括弧が来る場合は、前のマスが空く場合でも、そのマスに記入します。
- 改行のルール:段落の始まりは、1マス空けて書き始めます。
- 会話文の表記:「」などの会話符も1マスに1文字として扱います。会話文が長くなる場合、改行して次の行の文頭も1マス空けます。
- 「〃」などの符号:繰り返し記号(「〃」など)は、特殊な場合を除き、使用しない方が無難です。
作文で注意すべき点
- 文字数制限の確認:作文には文字数制限がある場合が多いので、事前に確認し、それに沿って書くようにしましょう。
- 誤字脱字のチェック:作文を書き終えたら、必ず誤字脱字がないかを確認します。
- 表現の重複を避ける:同じ言葉や表現を繰り返すと、単調な文章になってしまいます。類義語を使ったり、表現方法を変えたりする工夫をしましょう。
- 丁寧な言葉遣いを心がける:作文では、丁寧で品のある言葉遣いを心がけることが大切です。
- 脅迫的な言葉や不快な言葉は避ける:読者に不快感を与えるような言葉遣いは避け、建設的な意見を述べるようにしましょう。
作文をより良くするための工夫
- 漢字とひらがなのバランス:漢字を使いすぎると読みにくくなり、ひらがなが多すぎると幼稚な印象を与えることがあります。漢字とひらがなのバランスを意識しましょう。
- 文の長さを調整する:短い文と長い文を組み合わせることで、文章にリズムが生まれます。
- 比喩や例えを効果的に使う:税金のような抽象的なテーマを分かりやすく伝えるために、比喩や例えを適切に用いることは有効です。
説得力のある文章にするためのテクニック
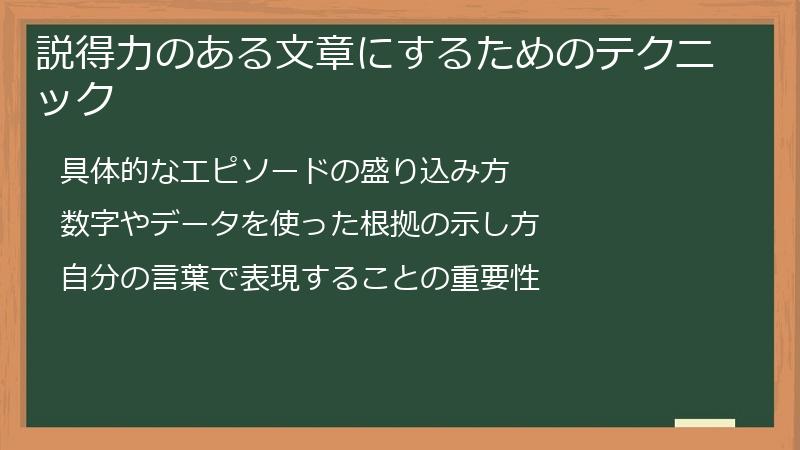
税の作文は、単に事実を並べるだけでは、読者の心に響きません。ここでは、あなたの意見や考えをより説得力を持って伝えるための具体的なテクニックをご紹介します。具体的なエピソードを盛り込んだり、数字やデータを用いて根拠を示したりすることで、あなたの作文は格段に深みを増し、読者を引きつける力を持つでしょう。自分の言葉で表現することの重要性も併せて解説します。
具体的なエピソードの盛り込み方
エピソードが作文に与える力
- 読者の共感を引き出す:具体的な体験談は、読者が「自分にも似たような経験がある」「そうかもしれない」と感じやすく、共感を呼びます。
- 税金への親近感を持たせる:抽象的な税金の話が、具体的なエピソードを介することで、より身近で理解しやすいものになります。
- 作文にリアリティを与える:個人的な体験談を交えることで、作文に厚みと信憑性が増し、単なる知識の披露に終わらない、あなた自身の考えが伝わる文章になります。
- 記憶に残りやすくなる:感情や情景が伴うエピソードは、読者の記憶に残りやすく、作文全体の印象を強くします。
どのようなエピソードを選ぶか
- 身近な消費体験:例えば、お母さんと一緒に買い物に行った際に、レジで渡されたレシートに消費税の金額が明記されていたのを見て、税金について考えた経験などを書くことができます。
- 家族との会話:家族が仕事の話をする中で、税金がどのように関係しているのかを聞いたことや、家計と税金について話していたことなどを描写するのも良いでしょう。
- 公共施設を利用した経験:図書館で本を借りたときの静かな環境、公園で友達と遊んだ楽しい時間、自転車で安全な道路を走れたことなど、身近な公共サービスを利用した際の体験を、税金と結びつけて語ることができます。
- ニュースや社会の出来事への反応:ニュースで見た社会問題(例えば、子供たちのための施設整備や、災害時の復興支援など)と税金がどう関係しているかを知り、自分が感じたことや考えたことを書くこともできます。
エピソードを効果的に書くコツ
- 状況を具体的に描写する:いつ、どこで、誰と、何をしたのか。その時の天気や、どんな気持ちだったのかなど、情景が目に浮かぶように具体的に描写しましょう。
- 自分の「なぜ?」を明確にする:なぜそのエピソードを書こうと思ったのか、その経験から何を感じ、何を考えたのかを、はっきりと述べることが重要です。
- 税金との関連性を明確にする:そのエピソードが、どのように税金と結びついているのかを、読者に分かりやすく説明しましょう。
- 感情を込めて書く:体験した時の驚き、感動、疑問、感謝など、自分の素直な感情を表現することで、読者にもその気持ちが伝わりやすくなります。
数字やデータを使った根拠の示し方
数字やデータが文章に与える信頼性
- 客観的な事実として提示できる:数字やデータは、個人の主観ではなく、客観的な事実に基づいた情報として、読者に信頼感を与えます。
- 具体性が増す:「たくさん」や「たくさん」といった曖昧な表現ではなく、「約〇〇円」「〇〇%」のように具体的な数値を示すことで、読者は内容をより正確に理解できます。
- 説得力が高まる:特に、自分の主張を裏付けるために数字やデータを示すことで、その主張の正当性や重要性を効果的に伝えることができます。
- 比較や変化が分かりやすくなる:税金の使われ方の推移や、他の国との比較など、数字を用いることで、変化や違いが明確になります。
作文で使える数字やデータの例
- 消費税の金額:例えば、「普段買っているお菓子1つには、〇〇円の消費税が含まれている。」といった身近な例。
- 公共サービスの維持費:地域の図書館の年間運営費や、学校の施設改修にかかる費用など、もし調べることができれば、税金がいかに多くの場面で使われているかを示すことができます。
- 税金の種類と割合:国税と地方税の種類や、それぞれの税収の割合などを調べてみるのも良いでしょう。
- 国際比較:他の国の税率や、税金の使われ方と比較してみることで、日本の税制の特徴や課題が見えてくることもあります。
数字やデータを効果的に使うための注意点
- 正確な情報源に基づくこと:インターネットの情報でも、国税庁や総務省などの公的機関のウェブサイトや、信頼できる報道機関の情報を参照するようにしましょう。
- 出典を明記する(可能であれば):もし、作文の指示で出典の明記が求められている場合は、忘れずに行いましょう。そうでない場合でも、どこでその数字を知ったのかを記憶しておくと、話の根拠として役立ちます。
- 分かりやすく説明すること:数字やデータを提示するだけでなく、それが何を意味するのか、どのように税金と関連しているのかを、自分の言葉で分かりやすく説明することが重要です。
- 過度な使用は避ける:数字やデータを羅列しすぎると、かえって読みにくくなってしまうこともあります。作文のテーマに沿って、最も効果的な数字を厳選して使いましょう。
自分の言葉で表現することの重要性
「自分の言葉」で書くことの意味
- オリジナリティの創出:「自分の言葉」で書くということは、教科書やインターネットで集めた情報をそのまま書き写すのではなく、一度自分の中で消化し、理解した上で、自分の考えや感じたことを付け加えて表現することです。
- 思考力の証明:自分の言葉で表現できているということは、そのテーマについて深く考え、自分なりの意見を持っていることの証になります。
- 共感を生む力:機械的な文章ではなく、自分の言葉で語られる文章には、書き手の熱意や人間性が宿り、読者はより共感しやすくなります。
- 評価に繋がる:作文の評価においては、知識の量だけでなく、いかに自分の頭で考え、それを表現できているかが重視されます。
「自分の言葉」で書くためのヒント
- 「なぜそう思うのか」を問い続ける:集めた情報や体験について、「なぜそうなるのだろう?」「なぜ自分はそう感じたのだろう?」と自問自答を繰り返すことで、表面的な事柄から一歩踏み込んだ考えにたどり着けます。
- 比喩や例えを自分で考える:難しい概念を説明する際に、自分なりに分かりやすい例えや比喩を考えることで、オリジナリティのある表現が生まれます。
- 感情や感想を素直に表現する:税金について「すごい」「不思議だ」「大切だ」など、自分が感じた素直な気持ちを言葉にしてみましょう。
- 文章の構成を工夫する:集めた情報を、ただ順序通りに並べるのではなく、自分が伝えたいメッセージが最も効果的に伝わるように、構成を工夫することも、「自分の言葉」で表現することに繋がります。
- 声に出して読んでみる:書いた文章を声に出して読んでみると、不自然な言い回しや、もっと良い表現がないかなどに気づきやすくなります。
「丸写し」の危険性
- インターネットや書籍から文章をそのまま書き写す行為は、オリジナリティを失うだけでなく、場合によっては「剽窃(ひょうせつ)」とみなされる可能性もあります。
- たとえ引用するとしても、必ず出典を明記し、自分の言葉で説明を加えることが重要です。
- 作文の目的は、知識の伝達だけではなく、あなた自身の思考力と表現力を養うことにあることを忘れないでください。
推敲(すいこう)で完成度を高める
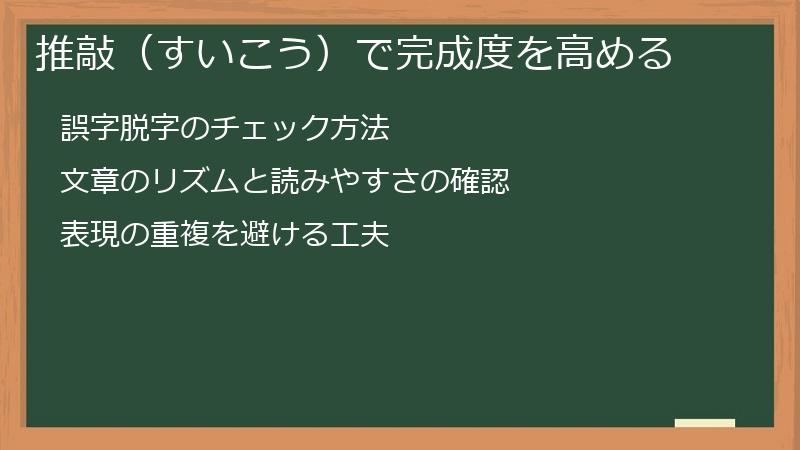
作文を書き終えたら、それで終わりではありません。より良い作文にするためには、「推敲」という作業が不可欠です。推敲とは、書いた文章を読み返し、誤字脱字がないか、表現が適切か、論理的なつながりはどうかなどをチェックし、修正していく作業のことです。この推敲を丁寧に行うことで、あなたの作文は、さらに洗練され、読者に正確に意図が伝わる、完成度の高いものへと生まれ変わります。
誤字脱字のチェック方法
なぜ誤字脱字チェックが重要なのか
- 文章の信頼性を損なう:誤字脱字が多いと、読者に「きちんと書けていない」「注意力がない」という印象を与え、文章全体の信頼性を低下させてしまいます。
- 意味が変わってしまう可能性:些細な誤字脱字でも、文意を大きく変えてしまうことがあります。例えば、「税金」を「税巾」と間違えただけで、全く意味が通じなくなってしまいます。
- 評価に影響する:作文の採点においては、誤字脱字の数も評価の対象となることがあります。
- 読みにくさの原因となる:誤字脱字が多いと、読者は内容を理解するのに余計な労力を要し、ストレスを感じてしまう可能性があります。
効果的な誤字脱字チェックのコツ
- 声に出して読んでみる:文章を声に出して読むことで、普段は気づかない不自然な言い回しや、単語の誤りに気づきやすくなります。
- 時間を置いてから読み返す:書き終えた直後ではなく、少し時間を置いてから冷静な目で読み返すと、客観的に誤りを見つけやすくなります。
- 印刷して確認する:パソコンの画面で確認するだけでなく、一度印刷して、紙の上で確認すると、見落としがちな誤字脱字に気づきやすくなります。
- 反対から読んでみる:文章を単語や文節ごとに、後ろから前に向かって読んでいくと、文脈に引っ張られず、個々の単語の誤りに気づきやすくなります。
- チェックリストを作成する:よく間違えやすい漢字や、頻繁に起こる誤字脱字のパターンをリスト化し、それらを重点的にチェックするようにすると効果的です。
- 他の人に読んでもらう:可能であれば、家族や友人、先生などに読んでもらい、客観的な視点からのチェックをしてもらうのが最も確実な方法です。
具体的なチェックポイント
- 漢字の誤り:似ている漢字や、常用漢字外の漢字を使っていないか。
- ひらがな・カタカナの誤り:単語の区切り方や、促音・長音の使い間違いなど。
- 助詞の誤り:「は」と「わ」、「が」と「か」などの使い分け。
- 句読点の位置:文の区切りが適切か、句読点が漏れていないか。
- 用語の統一:同じ意味の言葉を、文中で不統一に使っていないか(例:「税金」「公課」など)。
文章のリズムと読みやすさの確認
なぜ文章のリズムと読みやすさが重要なのか
- 読者の集中力を維持する:リズム感のある、読みやすい文章は、読者の注意を引きつけ、最後まで飽きさせません。
- 内容の理解を助ける:文章の流れがスムーズであれば、読者は書かれている内容をより深く、正確に理解することができます。
- 印象が良くなる:丁寧で読みやすい文章は、書き手に対する好印象を与え、作文全体の評価にも繋がることがあります。
- メッセージが伝わりやすくなる:読みやすさは、あなたが伝えたいメッセージを、より効果的に、より多くの人に届けるための重要な要素です。
文章のリズムを良くする工夫
- 文の長さを変化させる:短い文と長い文を組み合わせることで、単調さを避け、文章にメリハリが生まれます。
- 接続詞を効果的に使う:「そして」「しかし」「また」「だから」といった接続詞を適切に使うことで、文と文のつながりが明確になり、スムーズな流れを作ることができます。
- 体言止めを活用する:文末を名詞で終える「体言止め」を効果的に使うと、文章にアクセントがつき、読者に強い印象を与えることができます。ただし、使いすぎると逆効果になることもあるので注意が必要です。
- 繰り返しを避ける:同じ言葉や表現を繰り返し使うと、単調でくどい印象を与えます。類義語を使ったり、表現方法を変えたりして、言葉のバリエーションを豊かにしましょう。
読みやすさを高めるためのチェックポイント
- 句読点の適切さ:句読点が適切に打たれているか、読みにくい箇所がないかを確認します。
- 一文が長すぎないか:一文が長すぎると、読者は途中で意味を理解するのが難しくなります。必要であれば、文を短く区切るなどの工夫をしましょう。
- 漢字とひらがなのバランス:漢字が多すぎると読みにくく、ひらがなが多すぎると幼稚な印象になることがあります。バランスを意識して、読みやすい表記を選びましょう。
- 専門用語や難しい言葉の解説:もし専門用語や難しい言葉を使う場合は、それが読者(同じ中学生)に理解できるか、必要であれば簡単な説明を加えるなどの配慮が必要です。
- 第三者の視点での確認:可能であれば、他の人に読んでもらい、どこが読みにくいか、どこが分かりにくいかを尋ねてみましょう。自分では気づきにくい改善点が見つかることがあります。
表現の重複を避ける工夫
なぜ表現の重複が良くないのか
- 単調な印象を与える:同じ言葉や言い回しを繰り返すと、文章が単調になり、読者の集中力を低下させてしまいます。
- 文章の深みがなくなる:表現に変化がないと、書き手の思考や感情が十分に伝わらず、文章の深みが損なわれてしまいます。
- 稚拙な印象を与える:表現の幅が狭いと、読者によっては「言葉を知らない」「語彙力が乏しい」といった印象を受ける可能性があります。
- 読みにくさの原因になる:特に、接続詞や指示語の使い方が偏っていると、文と文のつながりが悪くなり、読みにくくなります。
表現の重複を避けるための具体的な方法
- 類義語辞典や類語検索を活用する:同じ意味でも、異なる言葉で表現できないか調べてみましょう。「大切」を「重要」、「必要」、「不可欠」などに言い換えたり、「行う」を「実施する」「実行する」「実施する」などに変えたりすることが考えられます。
- 表現方法を変える:同じ内容を伝える場合でも、一度直接的に表現した後に、比喩や例えを用いて説明するなど、表現方法を変化させることで、単調さを避けることができます。
- 指示語を効果的に使う:「これ」「それ」「その」などの指示語は便利ですが、使いすぎると、何を指しているのか分かりにくくなることがあります。必要に応じて、名詞で具体的に示すようにしましょう。
- 文の構造を変える:同じような文の構造が続くと、単調になりがちです。主語を変えたり、修飾語の位置を変えたりすることで、文章に変化をつけましょう。
- 接続詞を工夫する:毎回「そして」で繋ぐのではなく、「また」「さらに」「それに加えて」「一方で」「しかし」など、文脈に合った様々な接続詞を使い分けることで、文章の流れを豊かにすることができます。
推敲時のチェックポイント
- 同じ言葉の連続使用:同じ単語やフレーズが、一つの段落内や、近い箇所で繰り返されていないかを確認します。
- 決まり文句の多用:「〜と思います」「〜だと感じます」といった表現が、結論部分以外で過度に多用されていないか確認します。
- 文末表現の偏り:「〜です」「〜ます」といった文末表現が、不自然なほど同じパターンで繰り返されていないか確認します。
- 接続詞の使い方の偏り:特定の接続詞に頼りすぎていないか、文脈に合った適切な接続詞が使われているかを確認します。
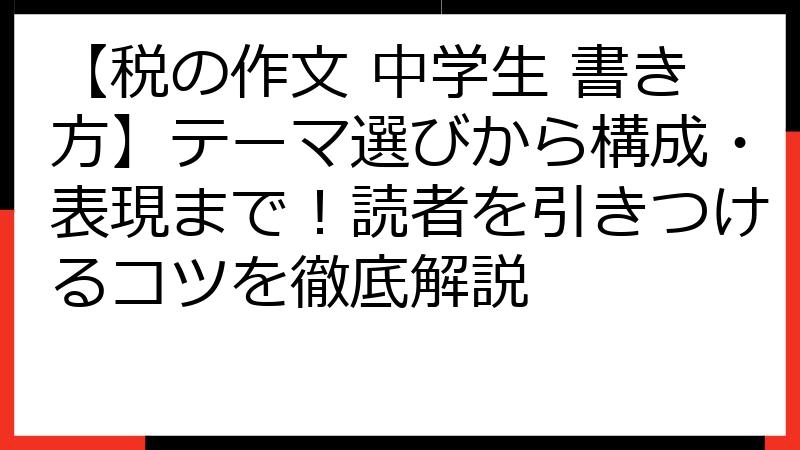
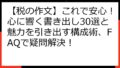

コメント