【中学生向け】税の作文で心を掴む!プロが教える書き出し完全攻略ガイド
税の作文、何を書けばいいのか、書き出しはどうすればいいのか、悩んでいませんか?
この記事では、中学生の皆さんが税の作文で高評価を得るための、書き出しに特化したテクニックを徹底解説します。
書き出しは、作文の第一印象を決める重要な部分です。
魅力的な書き出しは、読者の興味を引きつけ、最後まで読んでもらうための鍵となります。
この記事を読めば、税の作文の書き出しに対する不安を解消し、自信を持って書き始めることができるでしょう。
具体的なアイデアやテクニックを駆使して、オリジナリティあふれる、素晴らしい税の作文を完成させましょう!
税の作文、最初の第一歩を成功させる!書き出しの重要性と基本
税の作文で良い評価を得るためには、最初の書き出しが非常に重要です。
このセクションでは、なぜ書き出しが重要なのか、読者の心を掴むための基本的なポイント、そして税の作文特有の書き出しの考え方を詳しく解説します。
魅力的な書き出しで、審査員の興味を引きつけ、高評価へとつなげましょう。
書き出しの重要性を理解し、効果的なテクニックを身につけることで、自信を持って作文に取り組めるようになります。
なぜ書き出しが重要なのか?読者の心をつかむための3つのポイント
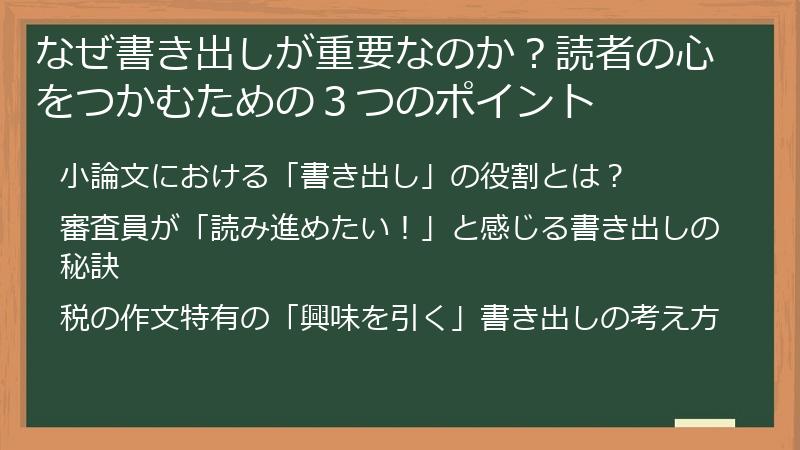
税の作文において、なぜ書き出しが重要なのでしょうか?
このセクションでは、読者(特に審査員)の興味を引きつけ、最後まで読んでもらうために、書き出しが果たす役割を明確に解説します。
魅力的な書き出しを作成するための3つの重要なポイントを理解することで、あなたの作文は一気にレベルアップするでしょう。
書き出しの重要性を認識し、効果的なアプローチを学ぶことで、自信を持って読み手を引き込む作文を書けるようになります。
小論文における「書き出し」の役割とは?
小論文、ひいては税の作文における書き出しは、単なる導入部分ではありません。
それは、読者、特に評価者の心をつかみ、読み進めてもらうための最初の、そして最も重要なチャンスなのです。
書き出しは、以下の3つの重要な役割を担っています。
-
読者の興味を引く:
書き出しは、読者に「この作文を読んでみよう」と思わせるための最初のきっかけです。
退屈で平凡な書き出しでは、読者はすぐに興味を失い、読み進めてくれない可能性があります。
魅力的な書き出しは、読者の好奇心を刺激し、内容への期待感を高めます。 -
テーマを明確にする:
書き出しは、作文のテーマを明確に提示する役割も担っています。
読者は書き出しを読むことで、これから何について書かれるのかを理解し、読み進める準備をすることができます。
曖昧な書き出しでは、読者はテーマを理解できず、混乱してしまう可能性があります。 -
自分の主張を印象付ける:
書き出しは、自分の主張を最初に印象付けるための重要な機会です。
読者は書き出しを読むことで、筆者の視点や立場を理解し、その後の展開に興味を持つことができます。
効果的な書き出しは、読者の記憶に残りやすく、作文全体の印象を大きく左右します。
税の作文においては、これらの役割がさらに重要になります。
なぜなら、税金というテーマは、一見すると中学生にとって身近ではないと感じられる可能性があるからです。
だからこそ、書き出しで読者の興味を惹きつけ、税金が自分たちの生活にどのように関わっているのかを理解してもらう必要があるのです。
例えば、以下のようなアプローチが考えられます。
-
具体的な事例を用いる:
税金がどのように使われているかを具体的な事例を用いて示すことで、読者の関心を引くことができます。
例えば、「学校の教科書や体育館の建設費は、私たちの払った税金で賄われています」といった具体的な記述は、読者に税金の重要性を実感させます。 -
問題提起をする:
税金に関する疑問や課題を提起することで、読者の思考を刺激し、作文への興味を高めることができます。
例えば、「もし税金がなかったら、私たちの生活はどうなるでしょうか?」といった問いかけは、読者に税金について深く考えるきっかけを与えます。 -
意外な事実を提示する:
税金に関する意外な事実を提示することで、読者の興味を引くことができます。
例えば、「私たちが普段使っているスマートフォンの開発にも、税金が使われています」といった事実は、読者に税金の意外な側面を認識させます。
このように、書き出しは単なる導入部分ではなく、読者の興味を引きつけ、テーマを明確にし、自分の主張を印象付けるための重要なツールです。
効果的な書き出しを心がけることで、あなたの税の作文は、他の作文とは一線を画す、魅力的な作品となるでしょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 税金の種類と仕組みを理解しよう
- 身の回りの税金が使われている場所を探してみよう
- 税金に関するニュースや記事を読んでみよう
審査員が「読み進めたい!」と感じる書き出しの秘訣
税の作文の審査員は、多くの作品に目を通す必要があります。
その中で、あなたの作文が「読み進めたい!」と思ってもらえるかどうかは、書き出しにかかっています。
審査員の心に響く書き出しには、いくつかの共通点があります。
-
独自性:
他の作文とは異なる、オリジナルの視点や表現を取り入れましょう。
一般的な意見や教科書的な内容だけでなく、あなた自身の経験や考えを織り交ぜることで、個性を際立たせることができます。
例えば、「私は普段、税金について深く考えることはありませんでしたが…」という書き出しは、正直な気持ちを表現しつつ、読者の共感を呼ぶことができます。 -
具体性:
抽象的な表現を避け、具体的な事例やデータを用いることで、説得力を高めましょう。
例えば、「もし税金が10%上がったら…」といった仮定の話をするだけでなく、「消費税が10%に上がった時、○○という商品を買うのをためらった」という具体的な体験談を交えることで、読者はより深く共感することができます。 -
簡潔さ:
長すぎる文章や複雑な言い回しは避け、簡潔で分かりやすい文章を心がけましょう。
冗長な書き出しは、読者の集中力を削ぎ、読む気を失わせてしまう可能性があります。
短く、力強い言葉で、読者の心に響く書き出しを目指しましょう。
税の作文の審査員は、単に税金に関する知識を評価するだけでなく、あなたの思考力や表現力も評価しています。
審査員が「読み進めたい!」と感じる書き出しは、これらの要素をバランス良く兼ね備えている必要があります。
さらに、以下の点にも注意すると、より効果的な書き出しを作成することができます。
-
読者層を意識する:
審査員がどのような知識レベルを持っているのか、どのような視点を重視しているのかを考慮して、書き出しの内容を調整しましょう。 -
目的を明確にする:
書き出しで何を伝えたいのか、どのような効果を期待するのかを明確にしてから、書き始めましょう。 -
推敲を重ねる:
書き出しは、何度も読み返し、修正を重ねることで、より洗練されたものにすることができます。
これらの秘訣を参考に、審査員の心に響く、魅力的な書き出しを作成し、あなたの税の作文を成功に導きましょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 過去の税の作文の入賞作品を参考にしよう
- 先生や家族に書き出しを見てもらい、意見を聞いてみよう
- 色々な種類の文章を読み、表現力を磨こう
税の作文特有の「興味を引く」書き出しの考え方
税の作文は、他の作文とは異なり、テーマがやや堅苦しく、中学生にとって身近に感じにくい場合があります。
そのため、書き出しで読者の興味を惹きつけるためには、税の作文特有の考え方を取り入れる必要があります。
-
身近な視点から入る:
税金というテーマを、日常生活と結びつけて考えましょう。
例えば、普段利用している公共サービス(学校、図書館、公園など)が税金で支えられていることを具体的に示すことで、読者は税金をより身近に感じることができます。
「毎日利用している学校の給食は、税金で安く提供されています」といった書き出しは、読者の共感を呼びやすいでしょう。 -
疑問や問題意識を提起する:
税金に関する疑問や課題を提示することで、読者の思考を刺激し、作文への興味を高めましょう。
例えば、「なぜ税金は必要なのか?」、「税金の使い道は本当に適切なのか?」といった問いかけは、読者に税金について深く考えるきっかけを与えます。
ただし、批判的な視点だけでなく、建設的な提案も盛り込むことが重要です。 -
未来への展望を示す:
税金が未来の社会にどのように貢献できるかを語ることで、読者の希望を抱かせ、前向きな気持ちにさせましょう。
例えば、「税金は、未来の地球環境を守るためにどのように活用できるのか?」、「税金は、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためにどのように役立つのか?」といったテーマは、読者の関心を引くでしょう。
具体的なアイデアや提案を示すことが大切です。
税の作文で「興味を引く」書き出しを作成するためには、以下の点も考慮しましょう。
-
読者の年齢層を意識する:
審査員だけでなく、同じ中学生の読者にも分かりやすい言葉遣いや表現を心がけましょう。 -
ユーモアを取り入れる:
硬いテーマだからこそ、適度なユーモアを取り入れることで、読者の緊張をほぐし、親しみやすさを演出しましょう。
ただし、不謹慎な表現や税金を揶揄するような内容は避けましょう。 -
ストーリー性を持たせる:
自分の体験談や架空の物語を交えることで、読者の感情に訴えかけ、共感を呼び起こしましょう。
例えば、「もし私が税務署長になったら…」といった設定で、税金に関する政策を提案するのも面白いでしょう。
これらの考え方を取り入れることで、あなたの税の作文は、単なる知識の羅列ではなく、読者の心に響く、魅力的な作品となるでしょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 税金に関するアンケートを実施し、同級生の意見を聞いてみよう
- 税金に関するクイズを作成し、友達と楽しんでみよう
- 税金に関するマンガやアニメを見て、興味を深めよう
タイプ別!税の作文に使える書き出しの3つのパターン
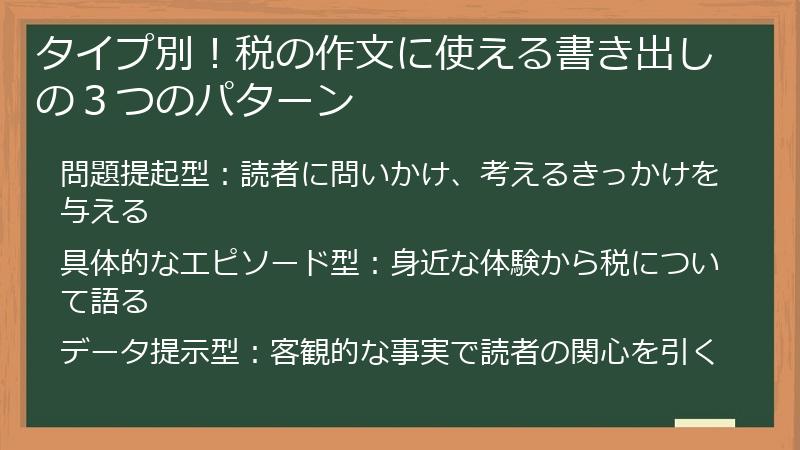
効果的な税の作文の書き出しには、いくつかのパターンがあります。
このセクションでは、特によく使われる3つのパターンを紹介し、それぞれの特徴と具体的な例を解説します。
これらのパターンを理解することで、あなたの作文のテーマや目的に合った、最適な書き出しを選ぶことができるようになります。
問題提起型、具体的なエピソード型、データ提示型、それぞれの書き出しのメリットとデメリットを把握し、効果的に活用しましょう。
問題提起型:読者に問いかけ、考えるきっかけを与える
問題提起型の書き出しは、読者に問いかけ、税金について深く考えるきっかけを与える効果的な手法です。
このタイプの書き出しは、読者の関心を引きつけ、作文の内容への興味を高めることができます。
問題提起型の書き出しを作成する際には、以下の点に注意しましょう。
-
具体的な問いかけ:
抽象的な問いかけではなく、具体的な疑問を投げかけることで、読者の思考を刺激しましょう。
例えば、「なぜ税金は必要なのか?」という問いかけよりも、「もし税金がなかったら、私たちの学校はどうなるだろうか?」といった具体的な問いかけの方が、読者の関心を惹きつけやすくなります。 -
身近な問題との関連付け:
税金というテーマを、読者の日常生活と関連付けることで、問題意識を高めましょう。
例えば、「私たちが毎日使っているスマートフォンには、消費税が含まれています。この消費税は、どのように使われているのでしょうか?」といった書き出しは、読者に税金を身近な問題として捉えさせることができます。 -
多角的な視点の提示:
問題提起をするだけでなく、その問題に対する様々な視点を提示することで、読者の思考を深めましょう。
例えば、「税金は国民全員で負担するものですが、その負担割合は本当に公平でしょうか?高所得者と低所得者では、税金の負担感は異なるのではないでしょうか?」といった書き出しは、読者に多角的な視点から税金について考えるきっかけを与えます。
問題提起型の書き出しの例:
- 「もし、明日から税金がなくなったら、私たちの生活はどう変わるでしょうか?」
- 「なぜ、私たちは税金を払わなければならないのでしょうか?その理由は、本当に納得できるものなのでしょうか?」
- 「税金の使い道は、誰が決めているのでしょうか?そして、その決定は、本当に国民の意見を反映したものなのでしょうか?」
問題提起型の書き出しは、読者に考えるきっかけを与え、税金に対する関心を高める効果的な手法です。
ただし、単に問題を提起するだけでなく、その問題に対する自分自身の考えや意見を明確にすることが重要です。
作文の本文では、提起した問題に対する考察を深め、具体的な解決策や提案を示すように心がけましょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 税金に関するニュースや記事を読み、問題点や課題を見つけよう
- 家族や先生と税金について話し合い、様々な意見を聞いてみよう
- 税金に関するアンケートを実施し、同級生の意見を調べてみよう
具体的なエピソード型:身近な体験から税について語る
具体的なエピソード型の書き出しは、あなた自身の体験や身近な出来事を基に、税金について語る方法です。
このタイプの書き出しは、読者に共感を与えやすく、親近感を持って作文を読んでもらうことができます。
具体的なエピソード型の書き出しを作成する際には、以下の点に注意しましょう。
-
具体的な描写:
体験したことや見たことを、五感を使い、具体的に描写しましょう。
例えば、「先日、家族と旅行に行った際、お土産を買う時に消費税を払いました。その時、消費税がどのように使われているのか疑問に思いました。」というように、具体的な状況を説明することで、読者はあなたの体験をよりリアルに感じることができます。 -
感情を表現する:
その体験を通して感じたことや考えたことを、素直に表現しましょう。
例えば、「消費税を払った時、少し高いなと感じましたが、税金が公共サービスに使われていることを考えると、必要なことだと思いました。」というように、自分の感情を言葉にすることで、読者はあなたに共感しやすくなります。 -
税金との関連付け:
エピソードの中に、必ず税金に関する要素を盛り込み、その体験が税金について考えるきっかけになったことを示しましょう。
例えば、「旅行中に訪れた観光地は、税金で整備されていることを知りました。その時、税金が私たちの生活を豊かにするために役立っていることを実感しました。」というように、税金と体験を結びつけることで、作文のテーマを明確にすることができます。
具体的なエピソード型の書き出しの例:
- 「小学生の頃、運動会の練習中に怪我をして、保健室で手当てを受けました。その時、保健室の先生が、税金で運営されていることを知りました。」
- 「先日、コンビニでお菓子を買った時、レジの画面に消費税が表示されました。その時、消費税がどのような仕組みで、どこに使われているのか疑問に思いました。」
- 「私の住んでいる地域では、高齢者向けの福祉サービスが充実しています。これらのサービスは、税金で支えられていることを知りました。」
具体的なエピソード型の書き出しは、読者に共感を与えやすく、親近感を持って作文を読んでもらうことができる効果的な手法です。
ただし、単に体験談を語るだけでなく、その体験を通して税金について考えたことや学んだことを明確にすることが重要です。
作文の本文では、エピソードから得られた学びを深め、税金に対する自分自身の考えや意見を展開するように心がけましょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 日常生活の中で税金に関わる出来事を意識してみよう
- 家族や友達と税金に関する体験談を共有してみよう
- 税金に関するニュースや記事を読み、自分の体験と関連付けて考えてみよう
データ提示型:客観的な事実で読者の関心を引く
データ提示型の書き出しは、客観的なデータや統計情報を提示することで、読者の関心を惹きつけ、説得力を高める方法です。
このタイプの書き出しは、税金というテーマを客観的に捉え、論理的な思考を展開するのに適しています。
データ提示型の書き出しを作成する際には、以下の点に注意しましょう。
-
信頼できる情報源:
提示するデータや統計情報は、政府機関や信頼できる調査機関など、信頼性の高い情報源から引用しましょう。
例えば、財務省のホームページや総務省統計局のデータなどを参考にすると良いでしょう。
情報の出所を明記することで、読者は提示されたデータを安心して受け入れることができます。 -
分かりやすい表現:
難しい専門用語や複雑な数式は避け、読者が理解しやすい言葉で表現しましょう。
グラフや図表などを用いて、データを視覚的に表現するのも効果的です。
例えば、「日本の税収は年間約○○兆円です」というように、具体的な金額を示すことで、読者は税金の規模を実感することができます。 -
税金との関連付け:
提示するデータが、税金とどのように関連しているのかを明確に示しましょう。
例えば、「日本の高齢化率は世界で最も高く、税金による社会保障費の負担が増加しています」というように、データと税金の関連性を説明することで、作文のテーマを明確にすることができます。
データ提示型の書き出しの例:
- 「日本の税収は年間約○○兆円です。これは、全国民が1年間で○○円ずつ税金を払っている計算になります。」
- 「日本の高齢化率は世界で最も高く、税金による社会保障費の負担が増加しています。この問題を解決するために、私たちはどのような対策を講じるべきでしょうか?」
- 「消費税は、日本の税収の約○○%を占めています。この消費税は、私たちの生活にどのような影響を与えているのでしょうか?」
データ提示型の書き出しは、客観的な事実に基づいて読者の関心を惹きつけ、説得力を高める効果的な手法です。
ただし、単にデータを提示するだけでなく、そのデータが意味することや、税金との関連性を明確にすることが重要です。
作文の本文では、提示したデータに基づいて論理的な思考を展開し、具体的な解決策や提案を示すように心がけましょう。
さらに深く掘り下げるために:
- 政府機関や調査機関のホームページで税金に関するデータを調べてみよう
- 新聞やニュースで税金に関する記事を読み、データがどのように使われているか分析してみよう
- グラフや図表を使って、税金に関するデータを分かりやすく表現してみよう
書き出しを魅力的にするための3つのテクニック
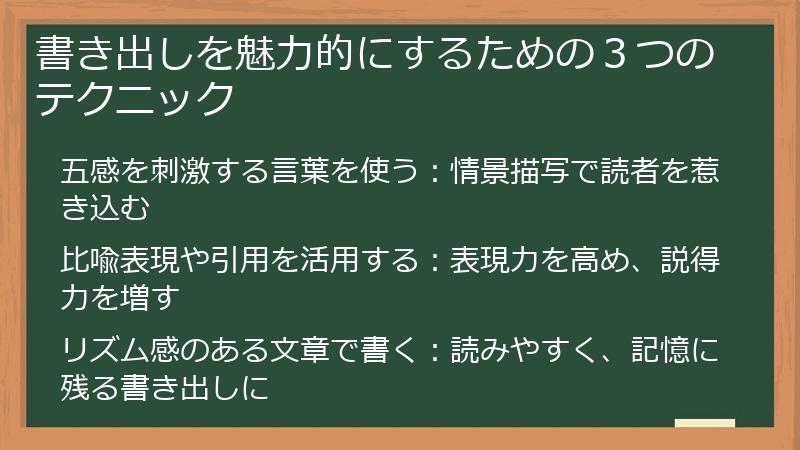
書き出しの種類を理解した上で、さらに読者の心を掴むためには、文章表現のテクニックが重要になります。
このセクションでは、五感を刺激する言葉の使い方、比喩表現や引用の活用法、リズム感のある文章の書き方という3つのテクニックを紹介します。
これらのテクニックを習得することで、あなたの作文の書き出しは、より魅力的で印象的なものになるでしょう。
読者を惹きつけ、最後まで読んでもらえるような、効果的な文章表現を身につけましょう。
五感を刺激する言葉を使う:情景描写で読者を惹き込む
税の作文の書き出しで、読者の心を掴むためには、五感を刺激する言葉を効果的に使うことが重要です。
五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚のことです。
これらの感覚を刺激する言葉を使うことで、読者は作文の内容をよりリアルに感じ、感情移入しやすくなります。
-
視覚に訴える:
色や形、光などを表現する言葉を使って、読者の目に鮮やかな情景を思い描かせましょう。
例えば、「夕焼け空のようなオレンジ色の街灯が、税金のありがたさを静かに照らしている」といった表現は、読者の視覚を刺激し、情景を想像させます。 -
聴覚に訴える:
音や声、音楽などを表現する言葉を使って、読者の耳に心地よい響きを届けましょう。
例えば、「税金の音は、未来への希望を奏でるオーケストラのようだ」といった表現は、読者の聴覚を刺激し、税金に対するイメージを豊かにします。 -
嗅覚に訴える:
香りや匂いを表現する言葉を使って、読者の記憶を呼び起こし、感情を揺さぶりましょう。
例えば、「税金は、故郷の田んぼの匂いのように、私たちの生活を支える力強い存在だ」といった表現は、読者の嗅覚を刺激し、郷愁を誘います。 -
味覚に訴える:
味や食感などを表現する言葉を使って、読者の食欲を刺激し、共感を呼び起こしましょう。
例えば、「税金は、毎日食べるお米のように、私たちの生活に欠かせないものだ」といった表現は、読者の味覚を刺激し、税金の重要性を伝えます。 -
触覚に訴える:
感触や温度などを表現する言葉を使って、読者の肌に直接触れるような感覚を与えましょう。
例えば、「税金は、冬の寒さをしのぐ暖房のように、私たちの生活を温かく守ってくれる」といった表現は、読者の触覚を刺激し、安心感を与えます。
五感を刺激する言葉を使った書き出しの例:
- 「夕焼け空のようなオレンジ色の街灯が、税金のありがたさを静かに照らしている。その光は、私たちの未来を明るく照らしてくれる希望の光だ。」(視覚)
- 「税金の音は、未来への希望を奏でるオーケストラのようだ。それぞれの楽器が、それぞれの役割を果たし、社会全体を豊かにしていく。」(聴覚)
- 「税金は、故郷の田んぼの匂いのように、私たちの生活を支える力強い存在だ。その匂いを嗅ぐと、感謝の気持ちが湧き上がってくる。」(嗅覚)
- 「税金は、毎日食べるお米のように、私たちの生活に欠かせないものだ。その味は、安心と安定を与えてくれる。」(味覚)
-
「税金は、冬の寒さを
比喩表現や引用を活用する:表現力を高め、説得力を増す
税の作文の書き出しで、表現力を高め、読者に強い印象を与えるためには、比喩表現や引用を効果的に活用することが重要です。
比喩表現とは、ある物事を別の物事に例えて表現することで、読者の想像力を刺激し、理解を深める効果があります。
引用とは、有名な言葉や文章を引用することで、自分の主張に説得力を持たせ、読者の共感を呼ぶ効果があります。-
比喩表現の種類:
比喩表現には、直喩、隠喩、擬人化など、様々な種類があります。
直喩は、「~のようだ」というように、直接的に例える表現です。
隠喩は、「~は~だ」というように、間接的に例える表現です。
擬人化は、人間以外のものを人間に例える表現です。
これらの比喩表現を使い分けることで、より豊かな表現力を身につけることができます。 -
効果的な比喩表現:
効果的な比喩表現は、読者の共感を呼び、印象に残る言葉を選ぶことが重要です。
例えば、「税金は、社会を支える血液のようだ」という比喩表現は、税金が社会にとって不可欠な存在であることを分かりやすく伝えます。
また、「税金は、未来への投資だ」という比喩表現は、税金が将来の社会を豊かにするために使われることを示唆します。 -
適切な引用:
引用は、自分の主張を裏付けるために、適切な言葉を選ぶことが重要です。
例えば、有名な政治家や経済学者の言葉を引用することで、自分の主張に説得力を持たせることができます。
また、古典や文学作品の一節を引用することで、作文に深みと品格を与えることができます。
ただし、引用する際には、必ず出典を明記し、著作権に配慮しましょう。
比喩表現や引用を活用した書き出しの例:
- 「税金は、社会を支える血液のようだ。血液が全身を巡り、生命を維持するように、税金は社会全体を支え、発展させていく。」(比喩表現)
- 「税金は、未来への投資だ。私たちが今払う税金は、未来の子供たちが安心して暮らせる社会を作るために使われる。」(比喩表現)
- 「『国は国民のために存在し、国民は国のために存在するのではない』。これは、有名な政治家の言葉だ。税金は、国民が国を支えるための大切な手段であると同時に、国が国民の生活を豊かにするための資源でもある。」(引用)
比喩表現や引用を効果的に活用することで、税の作文の書き出しは、より魅力的で印象的なものになります。
ただし、比喩表現や引用は、あくまでも自分の主張をサポートするための手段であることを忘れずに、適切リズム感のある文章で書く:読みやすく、記憶に残る書き出しに
税の作文の書き出しで、読者の心を掴むためには、リズム感のある文章で書くことが非常に効果的です。
リズム感のある文章は、読みやすく、記憶に残りやすく、読者の心を自然と惹きつけます。
税の作文は、ともすると堅苦しい印象を与えがちですが、リズム感のある文章で書くことで、親しみやすさを演出し、読者の興味を惹きつけることができます。-
句読点の効果的な使い方:
句読点は、文章のリズムを作る上で非常に重要な役割を果たします。
句点(。)は、文の終わりを示すだけでなく、読者に一息つかせる効果があります。
読点は(、)は、文中で意味の区切りを示すだけでなく、文章に流れを作る効果があります。
句読点を適切に使うことで、文章に自然なリズムを生み出すことができます。 -
短い文と長い文の組み合わせ:
短い文は、テンポが良く、力強い印象を与えます。
長い文は、情報を詳しく伝え、深みのある印象を与えます。
短い文と長い文をバランス良く組み合わせることで、文章に変化とリズムを生み出すことができます。
例えば、「税金は大切だ。なぜなら、私たちの生活を支えているからだ。」というように、短い文と長い文を組み合わせることで、文章にリズムが生まれます。 -
同じ表現の繰り返し:
同じ表現を繰り返すことで、文章にリズムと強調効果を与えることができます。
例えば、「税金は、私たちの未来を照らす光。税金は、私たちの生活を豊かにする力。税金は、私たちの社会を支える基盤。」というように、同じ構造の文を繰り返すことで、税金の重要性を強調し、読者の記憶に残る文章にすることができます。
ただし、同じ表現を繰り返す際には、単調にならないように、少しずつ変化を加えることが大切です。
リズム感のある文章を使った書き出しの例:
- 「税金は、私たちの未来を照らす光。だから、私たちは税金についてもっと知る必要がある。」
- 「税金は大切だ。なぜなら、私たちの生活を支えているからだ。税金がなければ、学校も病院も道路も、何もかもが成り立たない。」
- 「税金は、社会を支える力。税金は、未来を築く希望。税金は、私たち一人ひとりの生活を豊かにする源。」
リズム感のある文章で書くことは、税の作文
実践!税の作文、テーマ別・書き出しアイデア集
理論だけでは作文は書けません。
ここでは、実際に税の作文でよく取り上げられるテーマ別に、具体的な書き出しのアイデアを提供します。
消費税、所得税、税金と社会貢献という3つのテーマについて、すぐに使える書き出し例を多数紹介します。
これらのアイデアを参考に、あなたの作文に最適な書き出しを見つけ、オリジナリティあふれる作品を完成させましょう。消費税をテーマにした書き出し3選:身近な買い物から考える
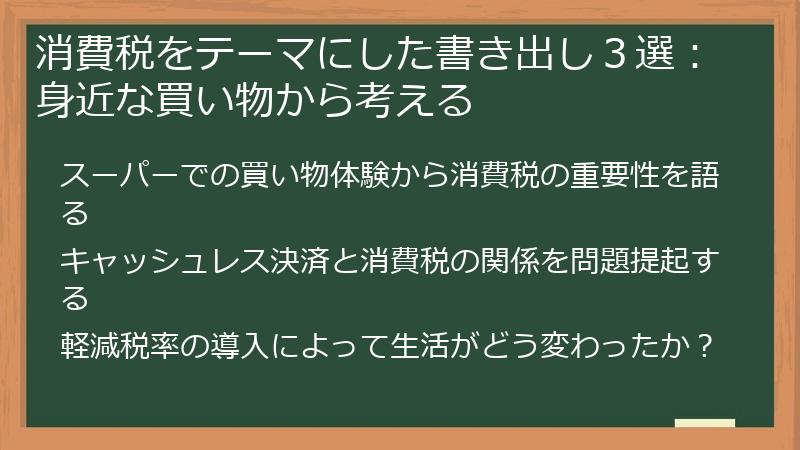
消費税は、私たちの日常生活に最も身近な税金の一つです。
ここでは、スーパーでの買い物体験、キャッシュレス決済、軽減税率といった、消費税に関わる具体的な場面をテーマにした、3つの書き出しアイデアを紹介します。
これらのアイデアを参考に、消費税に対するあなたの視点や考えを、魅力的な書き出しで表現しましょう。スーパーでの買い物体験から消費税の重要性を語る
スーパーマーケットは、私たちの食生活を支える場所であり、日常的に消費税を意識する場所でもあります。
スーパーでの買い物体験をテーマにした書き出しは、読者に親近感を与え、消費税に対する関心を高める効果があります。
このタイプの書き出しでは、具体的な商品の値段や消費税額を提示し、消費税が私たちの生活に与える影響を具体的に示すことが重要です。
書き出しの例:- 「先日、スーパーでジュースを買った時、150円のジュースに15円の消費税がかかることを知りました。15円という金額は小さいけれど、毎日ジュースを買う人がいれば、消費税は大きな金額になるのではないかと思いました。」
- 「母と一緒にスーパーに行った時、野菜や果物には消費税がかかるのに、お米には消費税がかからないことを知りました。なぜ、同じ食べ物なのに、消費税がかかるものとかからないものがあるのでしょうか?」
- 「スーパーのレジで、消費税込みの金額が表示されるのを見て、消費税は私たちの生活に深く関わっていることを改めて感じました。もし、消費税がなかったら、スーパーの商品はもっと安くなるのでしょうか?」
これらの書き出しは、具体的な買い物体験を基に、消費税に対する疑問や関心を提示しています。
作文の本文では、これらの疑問や関心を深掘りし、消費税の仕組みや役割について詳しく解説することが重要です。
例えば、消費税がどのように使われているのか、消費税が社会保障や公共サービスにどのように貢献しているのかなどを具体的に示すことで、読者の理解を深めることができます。
また、消費税のメリットとデメリットを比較検討し、消費税のあり方について自分自身の考えを述べることも重要です。
さらに、スーパーでの買い物体験をより効果的に活用するためには、以下の点に注意しましょう。-
具体的な商品の名前を挙げる:
「ジュース」や「野菜」といった一般的な言葉だけでなく、「○○ジュース」や「△△トマト」といった具体的な商品の名前を挙げることで、読者はよりリアルな情景を思い描くことができます。 -
消費税額を意識する:
レジで表示される消費税額を意識しキャッシュレス決済と消費税の関係を問題提起する
キャッシュレス決済の普及は、私たちの消費行動を大きく変えつつあります。
クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、様々なキャッシュレス決済手段が登場し、消費税の支払い方も多様化しています。
キャッシュレス決済と消費税の関係をテーマにした書き出しは、読者に新しい視点を提供し、消費税に対する関心を深める効果があります。
書き出しの例:- 「最近、キャッシュレス決済を使うことが増えましたが、レシートを見ると、消費税がしっかりと引かれていることに気づきます。キャッシュレス決済でも、消費税は変わらずに払わなければならないのでしょうか?」
- 「キャッシュレス決済でポイントが貯まるのは嬉しいですが、そのポイントで買い物をする時にも消費税はかかるのでしょうか?ポイントを使っても、消費税は必ず払わなければならないのでしょうか?」
- 「キャッシュレス決済は便利ですが、お店によっては消費税を上乗せするところもあります。これは、本当に正しいのでしょうか?キャッシュレス決済の場合、消費税の扱いが異なるのでしょうか?」
これらの書き出しは、キャッシュレス決済の普及に伴い、消費税の支払い方や扱いに対する疑問を提示しています。
作文の本文では、これらの疑問を深掘りし、キャッシュレス決済と消費税の関係について詳しく解説することが重要です。
例えば、キャッシュレス決済の種類によって消費税の扱いが異なるのか、キャッシュレス決済の普及が消費税収にどのような影響を与えているのかなどを具体的に示すことで、読者の理解を深めることができます。
また、キャッシュレス決済のメリットとデメリットを比較検討し、キャッシュレス決済時代の消費税のあり方について自分自身の考えを述べることも重要です。
さらに、キャッシュレス決済と消費税の関係をより効果的に活用するためには、以下の点に注意しましょう。-
具体的なキャッシュレス決済手段を挙げる:
「キャッシュレス決済」という一般的な言葉だけでなく、「クレジットカード」「PayPay」「Suica」といった具体的な決済手段を挙げることで、読者はより身近に感じることができます。 -
ポイントや割引との関係を意識する:
キャッシュレス決済で得られるポイントや割引が、消費税にどのように影響するのかを考察軽減税率の導入によって生活がどう変わったか?
軽減税率は、特定の品目に対して消費税率を低く設定する制度です。
日本では、2019年10月に食料品や新聞などに対して軽減税率が導入されました。
軽減税率の導入は、私たちの生活に様々な影響を与えています。
軽減税率の導入によって生活がどう変わったかをテーマにした書き出しは、読者に身近な問題として消費税を捉えさせ、関心を高める効果があります。
書き出しの例:- 「軽減税率が導入されてから、スーパーで食料品を買う時に、レジの表示が少し複雑になったように感じます。軽減税率の対象となるものとならないものを、どのように見分ければ良いのでしょうか?」
- 「軽減税率が導入されたことで、新聞の購読を続けることにしました。でも、電子版の新聞は軽減税率の対象にならないと聞きました。なぜ、同じ新聞なのに、紙と電子版で税率が違うのでしょうか?」
- 「軽減税率が導入されたことで、外食を控えて、家で食事をする機会が増えました。軽減税率は、私たちの食生活にどのような影響を与えているのでしょうか?」
これらの書き出しは、軽減税率の導入によって生じた疑問や変化を提示しています。
作文の本文では、これらの疑問や変化を深掘りし、軽減税率の目的や効果、課題について詳しく解説することが重要です。
例えば、軽減税率が低所得者の負担軽減にどのように貢献しているのか、軽減税率の対象品目の選定基準は妥当なのか、軽減税率の導入によって税収がどのように変化したのかなどを具体的に示すことで、読者の理解を深めることができます。
また、軽減税率のメリットとデメリットを比較検討し、軽減税率のあり方について自分自身の考えを述べることも重要です。
さらに、軽減税率の導入によって生活がどう変わったかをより効果的に活用するためには、以下の点に注意しましょう。-
具体的な商品やサービスを挙げる:
「食料品」や「新聞」といった一般的な言葉だけでなく、「○○パン」「△△新聞」といった具体的な商品やサービスを挙げることで、読者は所得税をテーマにした書き出し3選:税金の役割を理解する
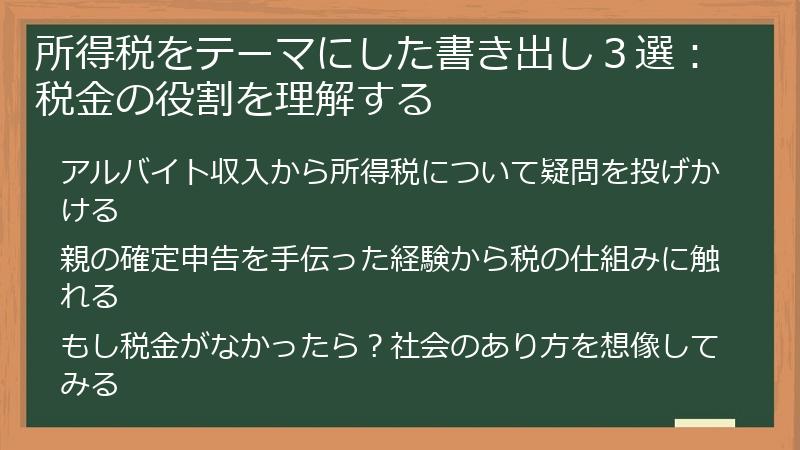
所得税は、私たちの収入に応じて課税される税金であり、税金の役割を理解する上で重要なテーマです。
ここでは、アルバイト収入、親の確定申告、もし税金がなかったらという仮定という、所得税に関わる3つのテーマについて、すぐに使える書き出しアイデアを紹介します。
これらのアイデアを参考に、所得税に対するあなたの考えを深め、オリジナリティあふれる書き出しを作成しましょう。アルバイト収入から所得税について疑問を投げかける
中学生の皆さんの中には、アルバイトをしている人もいるでしょう。
アルバイトで得た収入には、所得税がかかる場合があります。
アルバイト収入をテーマにした書き出しは、読者に身近な問題として所得税を捉えさせ、関心を高める効果があります。
書き出しの例:- 「初めてアルバイトをした時、給料明細を見て、所得税が引かれていることに気づきました。なぜ、アルバイトで稼いだお金にも税金がかかるのでしょうか?」
- 「アルバイトで貯めたお金で、欲しかったゲームを買おうと思っていましたが、所得税が引かれた分、少し足りなくなってしまいました。所得税は、私たち学生の生活にどのような影響を与えているのでしょうか?」
- 「アルバイトをしている友達から、所得税を払いすぎると、後で還付されると聞きました。所得税の還付とは、どのような仕組みなのでしょうか?」
これらの書き出しは、アルバイト収入から生じる所得税への疑問を提示しています。
作文の本文では、これらの疑問を深掘りし、所得税の仕組みや役割について詳しく解説することが重要です。
例えば、所得税はどのような場合に課税されるのか、所得税率はどのように決まるのか、所得税がどのように使われているのかなどを具体的に示すことで、読者の理解を深めることができます。
また、アルバイト収入を得る学生にとって、所得税はどのような意味を持つのか、所得税を 납부することで、社会にどのように貢献できるのかなどについて考察することも重要です。
さらに、アルバイト収入をテーマにした書き出しをより効果的に活用するためには、以下の点に注意しましょう。-
具体的なアルバイトの種類を挙げる:
「アルバイト」という一般的な言葉だけでなく、「コンビニエンスストアの店員」「レストランのウェイトレス」「塾講師」といった具体的なアルバイトの種類を挙げることで、読者はより身近に感じることができます。 -
具体的な金額を提示する:
「給料明細」や「所得税」といった言葉だけでなく、具体的な金額を提示することで、読者は所得税の影響をより実感することができます。
例えば、「時給○○円のアルバイトで、月○○円稼ぎ、所得税が○○円引かれた」といったように、具体的な金額を提示親の確定申告を手伝った経験から税の仕組みに触れる
確定申告は、所得税を納めるために、1年間の所得を計算して税務署に申告する手続きです。
中学生の皆さんの中には、親の確定申告を手伝った経験がある人もいるかもしれません。
親の確定申告を手伝った経験をテーマにした書き出しは、読者に税の仕組みをより身近に感じさせ、関心を高める効果があります。
書き出しの例:- 「先日、親の確定申告を手伝った時、たくさんの書類が必要で、計算も複雑で大変でした。確定申告は、なぜこんなに難しいのでしょうか?」
- 「親の確定申告を手伝った時、医療費控除という制度があることを知りました。医療費控除を受けると、税金が安くなるのでしょうか?」
- 「親の確定申告を手伝った時、税務署の人が親切に教えてくれました。税務署は、どのような役割を果たしているのでしょうか?」
これらの書き出しは、親の確定申告を手伝った経験から生じる税の仕組みへの疑問を提示しています。
作文の本文では、これらの疑問を深掘りし、確定申告の仕組みや所得税の控除制度、税務署の役割について詳しく解説することが重要です。
例えば、確定申告はなぜ必要なのか、確定申告の手続きはどのように行うのか、医療費控除や扶養控除などの控除制度はどのようなものがあるのか、税務署は国民の税金をどのように管理しもし税金がなかったら?社会のあり方を想像してみる
税金は、私たちの社会を支えるために不可欠なものです。
もし税金がなかったら、私たちの社会はどのような姿になるのでしょうか?
「もし税金がなかったら?」という仮定をテーマにした書き出しは、読者に税金の重要性を改めて認識させ、関心を高める効果があります。
書き出しの例:- 「もし、税金がなかったら、学校はどうなるでしょうか?授業料は高くなり、教科書も自分で買わなければならなくなるかもしれません。」
- 「もし、税金がなかったら、病院はどうなるでしょうか?病気になっても、十分な治療を受けられなくなるかもしれません。」
- 「もし、税金がなかったら、道路はどうなるでしょうか?道路は整備されなくなり、安全に通行できなくなるかもしれません。」
これらの書き出しは、「もし税金がなかったら?」という仮定を基に、社会の様々な側面への影響を提示しています。
作文の本文では、これらの影響を具体的に考察し、税金が社会においてどのような役割を果たしているのかを詳しく解説することが重要です。
例えば、税金が教育、医療、福祉、公共サービスなどにどのように使われているのか、税金が社会全体の安定と発展にどのように貢献しているのかなどを具体的に示すことで、読者の理解を深めることができます。
また、もし税金がなかった場合に税金と社会貢献をテーマにした書き出し3選:未来を考える
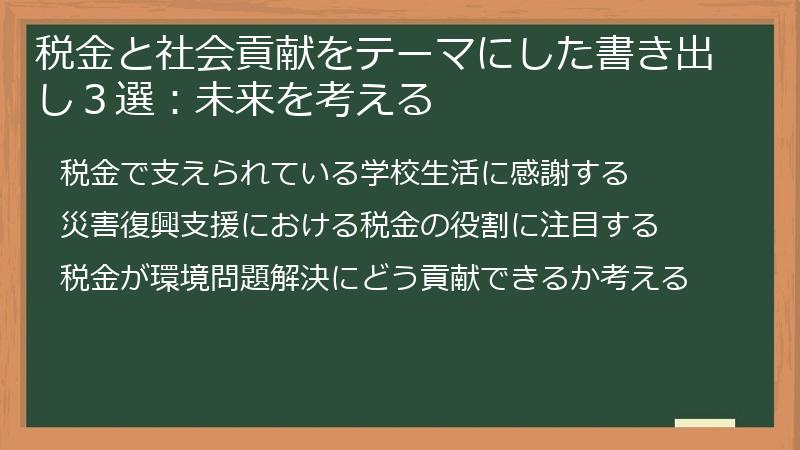
税金は、社会を支えるだけでなく、未来を創造するためにも重要な役割を果たします。
ここでは、学校生活、災害復興支援、環境問題解決という3つのテーマについて、税金が社会貢献にどのように繋がっているのかを考察し、未来への希望を抱かせる書き出しアイデアを紹介します。
これらのアイデアを参考に、税金と社会貢献に対するあなたの熱意を、オリジナリティあふれる書き出しで表現しましょう。税金で支えられている学校生活に感謝する
私たちは、毎日学校に通い、勉強したり、友達と遊んだり、部活動に励んだり、様々な経験をしています。
しかし、その学校生活が、税金によって支えられていることを意識することは少ないかもしれません。
税金で支えられている学校生活に感謝する気持ちを表現する書き出しは、読者に税金の恩恵を再認識させ、社会貢献への意識を高める効果があります。
書き出しの例:- 「毎日通っている学校の校舎や体育館は、税金で建てられていることを知りました。もし税金がなかったら、私たちは快適な環境で勉強することができなかったかもしれません。」
-
「学校で使っている教科書や机、椅子は、税金で無償
災害復興支援における税金の役割に注目する
日本は、地震や台風などの自然災害が多い国です。
災害が発生すると、被災地の復興には莫大な費用がかかります。
その費用は、税金によって賄われています。
災害復興支援における税金の役割に注目する書き出しは、読者に税金の重要性を改めて認識させ、助け合いの精神を育む効果があります。
書き出しの例:- 「〇〇年に発生した△△地震で、私の住む地域も大きな被害を受けました。復興には多額の税金が使われ、私たちの生活は少しずつ元の姿を取り戻しています。税金は、災害から立ち直るための希望の光だと思いました。」
- 「テレビで、災害で家を失った人たちが、税金で建てられた仮設住宅で生活しているのを見ました。税金は、困っている人を助けるために使われているのだと実感しました。」
-
「災害復興には、様々な支援が必要です。税金だけでなく、ボランティア活動や寄付も大切な役割を果たします。私たち中学生
税金が環境問題解決にどう貢献できるか考える
地球温暖化、海洋プラスチック問題、森林破壊など、環境問題は深刻化しており、私たちの未来を脅かしています。
これらの問題を解決するためには、税金を有効活用することが重要です。
税金が環境問題解決にどう貢献できるかを考える書き出しは、読者に未来への希望を抱かせ、主体的な行動を促す効果があります。
書き出しの例:- 「地球温暖化の影響で、異常気象が頻繁に発生するようになりました。税金を活用して、再生可能エネルギーを普及させることで、温暖化を抑制することができるのではないでしょうか?」
- 「海洋プラスチック問題は深刻で、多くの海洋生物が苦しんでいます。税金を使って、プラスチックごみを減らすための技術開発や啓発活動を推進すべきだと思います。」
- 「森林破壊は、地球の生態系に大きな影響を与えています。税金を使って、植林活動を支援したり、違法伐採を取り締まったりすることで、森林を守ることができるのではないでしょうか
-
比喩表現の種類:
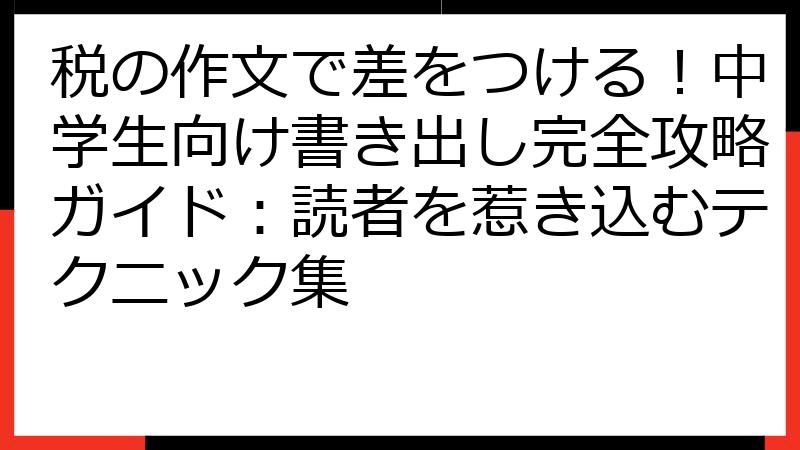
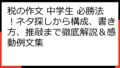
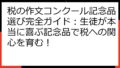
コメント