【不登校 相談】子どもの変化にどう向き合う?親が知っておくべき専門家の活用法
お子さんが学校に行きたがらない、
あるいは、学校での様子が以前と違うと感じていませんか。
「不登校 相談」というキーワードで情報を探されているということは、
お子さんのことで悩みを抱えている、
あるいは、これからどうすれば良いか不安を感じている、
そんな親御さんの切実な思いが伝わってきます。
この記事では、不登校に悩むお子さんとそのご家族が、
専門家のサポートを効果的に活用し、
一歩ずつ前へ進むための道標となる情報を提供します。
お子さんの変化に戸惑い、一人で抱え込んでしまわないよう、
知っておくべきこと、やるべきことを、
段階を追ってわかりやすく解説していきます。
不登校の兆候と親の初期対応
お子さんが学校に行き渋る、あるいは休むようになった時、
親御さんはどのように対応すれば良いのでしょうか。
このセクションでは、不登校の初期段階で見られるお子さんの変化のサインに気づき、
冷静かつ適切に対応するための基本をお伝えします。
早期の理解と適切な初期対応は、問題の深刻化を防ぎ、
お子さんの安心感に繋がります。
子どもの行動変化に気づくサイン
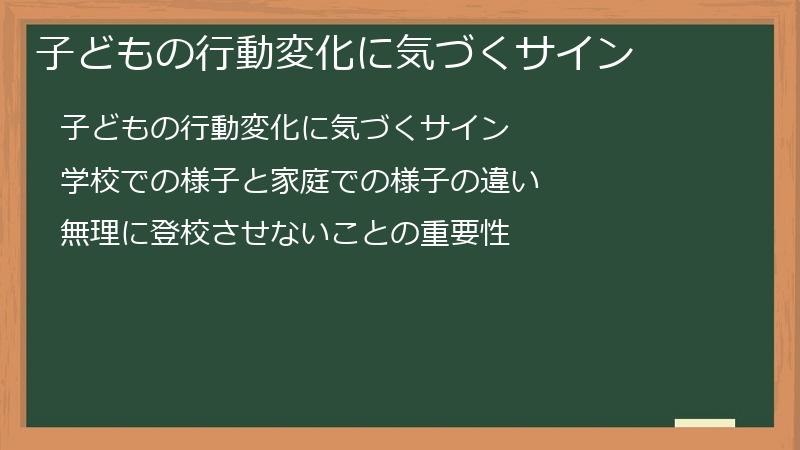
不登校の兆候は、突然現れるものではありません。
日頃からお子さんの様子を注意深く観察し、
普段との違いに気づくことが大切です。
ここでは、不登校につながる可能性のある、
お子さんの行動や心境の変化のサインを具体的に解説します。
これらのサインに早く気づくことで、
親御さんは適切なサポートの準備を始めることができます。
子どもの行動変化に気づくサイン
身体的な変化
-
- 原因不明の頭痛や腹痛が続く。
- 食欲不振や過食、睡眠不足や過眠など、生活リズムの乱れが見られる。
- 顔色がすぐれない、元気がない様子が目立つ。
- 以前よりも落ち着きがなく、イライラしていることがある。
感情や態度の変化
-
- 些細なことで泣いたり、怒ったりするなど、感情の起伏が激しくなる。
- 何事にも興味を示さなくなり、無気力な状態になる。
- 親や家族に対して、過度に攻撃的になったり、逆に過度に甘えたりする。
- 自分の殻に閉じこもり、他人との関わりを避けるようになる。
- 以前は楽しんでいたこと(趣味や友人との交流)に、関心を示さなくなる。
行動の変化
-
- 朝、学校に行く準備をしない、または準備に時間がかかるようになる。
- 学校に行くことに抵抗を示す、または欠席が増える。
- 家で過ごす時間が増え、ゲームやスマホばかりしているようになる。
- 外出を嫌がるようになり、部屋にこもりがちになる。
- 服装や身だしなみに無頓着になる、または逆に過度に気にするようになる。
- 約束の時間に遅れる、または約束を破ることが増える。
学校での様子と家庭での様子の違い
学校での変化
-
- 授業への集中力が低下し、ぼーっとしていることが増える。
- 友人とのコミュニケーションが減り、一人でいることが多くなる。
- 先生からの質問に答えなくなったり、授業態度が悪くなったりする。
- 以前は熱心に取り組んでいた部活動や係の仕事に、意欲を示さなくなる。
- 提出物を出さなくなったり、宿題をしなくなったりする。
- 学校での出来事について、話したがらなくなる、または話しても上の空になる。
家庭での変化
-
- 朝なかなか起きられず、学校への出発時間に間に合わないことが増える。
- 学校に行きたくない、という言葉を口にするようになる。
- 学校で嫌なことがあった、と話すが、具体的に何があったかは明かさない。
- 親からの干渉を嫌がり、部屋に閉じこもるようになる。
- 以前は楽しそうに話していた家族との会話が減り、無関心な態度をとる。
- 食欲がなくなったり、逆に過食になったりするなど、食生活に変化が見られる。
親が知っておくべきこと
-
- お子さんが学校で抱えている問題が、家庭での様子と結びついている場合がある。
- 学校での様子は、お子さんの置かれている状況を把握する重要な手がかりとなる。
- 家庭での様子は、お子さんが抱えるストレスや不安が表れている可能性がある。
- 両親で学校での様子と家庭での様子を共有し、一貫した対応をすることが重要。
- 学校からの連絡を待つだけでなく、積極的に学校に連絡を取り、情報交換をすることが望ましい。
- 学校での出来事について、無理に聞き出そうとせず、お子さんが話したい時に話せる雰囲気作りを心がける。
無理に登校させないことの重要性
なぜ無理に登校させないことが大切なのか
-
- お子さんが学校に行きたくないと感じている背景には、何らかの理由があると考えられます。
- 無理に登校させると、お子さんはさらに追い詰められ、心身に大きな負担をかけてしまう可能性があります。
- 「行かなければならない」というプレッシャーは、お子さんの自己肯定感を低下させ、自信を失わせることにつながります。
- お子さんの「行きたくない」という気持ちを否定せず、まずは受け止めることが、信頼関係を築く第一歩となります。
- お子さんが安心できる場所(家庭)で、心身を休ませ、回復させる時間が必要です。
「行きたくない」という気持ちへの対応
-
- お子さんが「学校に行きたくない」と言ったときは、まずその気持ちを否定せずに受け止めましょう。
- 「そうなんだね」「つらいんだね」といった共感の言葉を伝えることで、お子さんの気持ちに寄り添う姿勢を示します。
- 無理に理由を聞き出そうとせず、お子さんが話したい時に話せるような雰囲気を作ることが大切です。
- 「学校に行かないといけない」というプレッシャーを与えるような言葉は避けましょう。
- お子さんのペースで、まずは休息することに専念させることが重要です。
- 「学校に行かない」という選択が、決して悪いことではない、というメッセージを伝えることも大切です。
初期段階での親の役割
-
- お子さんの変化に気づいたら、まずは冷静に状況を把握することに努めましょう。
- お子さんの気持ちに寄り添い、安心感を与えることが最優先です。
- 学校への欠席連絡は、正直に理由を伝え、状況を共有することが大切です。
- 一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に相談することも視野に入れましょう。
- お子さんの様子を注意深く観察し、変化があった場合は記録しておくと、後に相談する際に役立ちます。
- お子さんが休息できる環境を整え、安心できる時間を提供しましょう。
専門機関への相談タイミングと種類
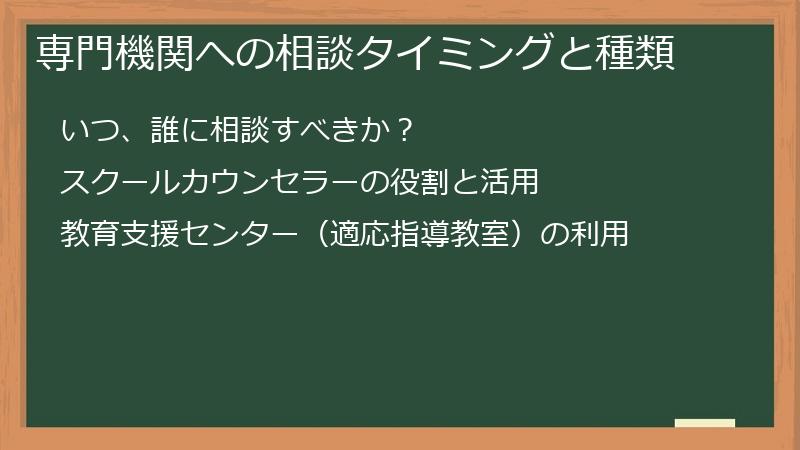
不登校の状況が長引いたり、お子さんの状態が悪化する前に、
専門機関へ相談することは非常に重要です。
しかし、「いつ」「誰に」相談すれば良いのか、
また、どのような機関があるのか、迷われる方もいらっしゃるでしょう。
このセクションでは、不登校に関する相談を専門とする機関の種類と、
それぞれの機関がどのようなサポートを提供してくれるのかを詳しく解説します。
適切なタイミングで、適切な機関に相談することで、
問題解決への道が大きく開かれます。
いつ、誰に相談すべきか?
相談を検討すべきタイミング
-
- お子さんが学校に行くことを強く拒否するようになった。
- お子さんの心身の不調が、数週間以上続いている。
- お子さんの行動や言動に、以前とは明らかに異なる、気になる変化が見られる。
- 親御さん自身が、どう対応して良いか分からず、精神的に疲弊してきた。
- 学校との連携がうまくいかず、孤立感を感じている。
- お子さんの不登校が長引き、学業の遅れが心配になってきた。
相談できる専門家・機関
-
- 学校の先生・スクールカウンセラー:まず身近な存在として、お子さんの学校での様子を把握しているため、相談しやすい相手です。
- 教育支援センター(適応指導教室):不登校の児童生徒の学習支援や心のケアを行う公的な施設です。
- 教育委員会・教育相談室:各自治体の教育委員会が設置している相談窓口で、専門的なアドバイスを受けることができます。
- 民間のフリースクール・フリースペース:学校とは異なる教育環境を提供し、お子さんの居場所づくりや社会性の育成を支援します。
- 児童精神科医・心療内科医:お子さんの心の不調が深刻な場合や、発達上の特性が疑われる場合に、専門的な診断や治療を受けることができます。
- 臨床心理士・公認心理師(民間のカウンセリングルーム):専門的な知識と技術を持ったカウンセラーが、お子さんの心理的な問題や、親御さんの悩みに対して個別に対応してくれます。
相談する際の心構え
-
- お子さんの状態や、親御さん自身の悩みを具体的に伝える準備をしておきましょう。
- 「なぜ学校に行けないのか」という原因追及よりも、「どうすればお子さんが安心できるか」という視点を大切にしましょう。
- 相談先によっては、予約が必要な場合や、相談内容に制限がある場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
- 一つの相談機関の意見だけでなく、複数の意見を聞くことも有効です。
- 相談は、お子さんの状態を改善するための一つの手段であり、お子さんを責めるためのものではありません。
- 相談したからといって、すぐに問題が解決するわけではありません。焦らず、根気強く向き合う姿勢が大切です。
スクールカウンセラーの役割と活用
スクールカウンセラーとは
-
- スクールカウンセラーは、学校に勤務する臨床心理士や公認心理師などの専門家です。
- お子さんの心の悩みや、学校生活での困りごとについて、専門的な立場から相談に乗ってくれます。
- また、保護者の方からの相談にも応じ、お子さんへの接し方や、問題解決に向けたアドバイスを行います。
- 必要に応じて、学校の先生や保護者と連携し、お子さんにとってより良い支援体制を築く役割も担います。
スクールカウンセラーに相談できること
-
- お子さんの不登校に関する悩みや不安について相談する。
- お子さんの情緒面や行動面での変化について、専門的な視点からのアドバイスをもらう。
- 学校での友人関係や学習面での悩みについて、相談し、解決策を探る。
- 保護者自身が抱える、お子さんへの接し方や子育てに関する悩みについて相談する。
- お子さんの状況を学校側と共有し、担任の先生との連携について相談する。
- 具体的な支援策(例えば、別室登校の検討など)について、専門家の意見を聞く。
スクールカウンセラーを効果的に活用するために
-
- 積極的に声をかける:お子さんが学校にいる間に、勇気を出して声をかけてみましょう。
- 予約を活用する:学校によっては、事前に予約が必要な場合があります。掲示などを確認しましょう。
- 具体的な状況を伝える:お子さんの最近の様子や、親御さんが感じている心配事を具体的に伝えましょう。
- 保護者面談を依頼する:お子さんの様子を詳しく知るために、保護者面談を依頼することも有効です。
- 継続的に関わる:一度の相談で終わらせず、必要に応じて何度か相談することで、より深い理解と支援を得られます。
- 先生との連携を密にする:スクールカウンセラーの助言を先生と共有し、学校全体でサポートできる体制を整えましょう。
教育支援センター(適応指導教室)の利用
教育支援センター(適応指導教室)とは
-
- 教育支援センターは、文部科学省が推進する「不登校児童生徒への支援」の一環として、各教育委員会が設置している公的な施設です。
- 「適応指導教室」とも呼ばれ、学校に登校できない児童生徒が、安心して過ごせる場所を提供します。
- 学習支援だけでなく、体験活動や集団活動を通して、社会性や協調性を育むことを目的としています。
- 専門の指導員や心理士が配置されており、お子さんの状況に合わせたきめ細やかな支援を受けることができます。
教育支援センターで受けられる支援
-
- 学習支援:学校の授業に遅れないよう、個々のレベルに合わせた学習指導を行います。
- 生活リズムの回復:規則正しい生活習慣を身につけるためのサポートを行います。
- 心理的なケア:専門家によるカウンセリングや、心のケアを受けることができます。
- 体験活動:料理、園芸、工場見学、自然体験など、様々な体験活動を通して、お子さんの興味関心を広げます。
- 集団活動・交流:同じような悩みを抱える仲間との交流を通して、コミュニケーション能力や協調性を育みます。
- 進路相談・学習相談:今後の進路や学習について、専門家と一緒に考える機会を提供します。
教育支援センターを利用するメリット
-
- 安心できる居場所の提供:学校とは異なる、リラックスして過ごせる環境があります。
- 個別に対応した支援:お子さんのペースや興味関心に合わせたプログラムを受けることができます。
- 仲間との出会い:同じような経験を持つ仲間との交流は、お子さんの孤立感を和らげ、安心感を与えます。
- 学習の遅れを取り戻す機会:学習支援により、学力維持・向上を目指すことができます。
- 社会性の向上:集団活動や体験活動を通して、多様な人との関わり方を学びます。
- 親御さんへのサポート:教育支援センターのスタッフがお子さんの状況を共有し、親御さんへのアドバイスや支援も行います。
信頼できる相談先の見極め方
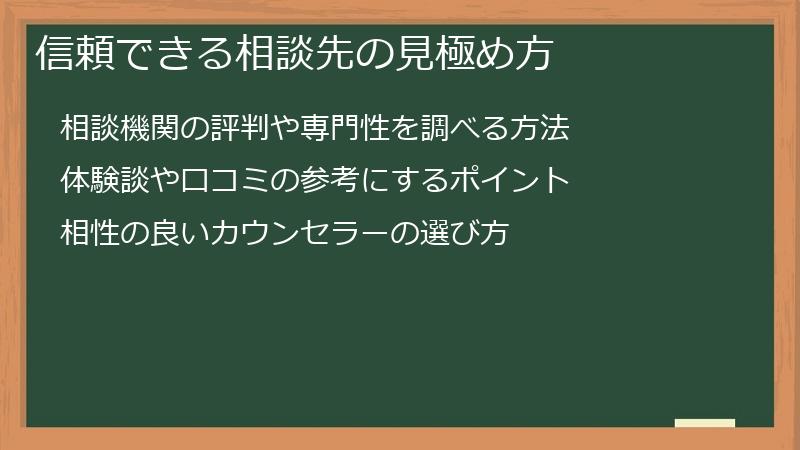
不登校の相談窓口は数多く存在しますが、
「どこに相談すれば良いのか」「自分たちに合った場所はどこなのか」
と迷うことは少なくありません。
信頼できる相談先を見つけることは、お子さんの回復への第一歩です。
このセクションでは、相談機関の選び方や、
どのような点に注意して見極めるべきかを具体的に解説します。
お子さんとご家族にとって、最善のサポートが得られる場所を見つけるためにお役立てください。
相談機関の評判や専門性を調べる方法
情報収集の重要性
-
- 相談機関を選ぶ際には、事前の情報収集が非常に重要です。
- お子さんやご家族の状況に合った専門性を持っているか、評判はどうかなどを把握することで、より効果的なサポートを受けられる可能性が高まります。
- インターネット検索だけでなく、実際に利用した方の声なども参考にすると良いでしょう。
評判や専門性を調べるための具体的な方法
-
- インターネット検索:相談機関名で検索し、公式サイトや紹介ページを確認します。
- 口コミサイトやSNSの活用:実際に利用した保護者や当事者の口コミや体験談を探します。ただし、個人の感想であるため、参考程度に留め、鵜呑みにしないように注意が必要です。
- 第三者機関の評価を確認:NPO法人や専門家団体などが、相談機関の質を評価・公表している場合があります。
- 専門家への相談:学校の先生や、以前に相談経験のある専門家(医師やカウンセラーなど)に、おすすめの相談機関がないか尋ねてみるのも良い方法です。
- 行政の紹介:教育委員会や自治体の相談窓口では、提携している相談機関や、専門性のある機関を紹介してもらえることがあります。
- 初回相談時の質問:気になる機関が見つかったら、まずは電話やメールで問い合わせ、提供しているサービス内容や、どのような専門家が在籍しているかなどを質問してみましょう。
確認すべきポイント
-
- 専門性:不登校や児童心理に詳しい専門家(臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士など)が在籍しているか。
- 対象年齢:お子さんの年齢に合ったプログラムや対応が可能なのか。
- 支援内容:学習支援、心理カウンセリング、家族支援など、どのような支援を提供しているのか。
- 所在地・アクセス:通いやすい場所にあるか、オンライン相談に対応しているか。
- 料金体系:公的機関か民間かによって、料金設定は大きく異なります。事前に確認しておきましょう。
- 相談者のプライバシー保護:個人情報の取り扱いや守秘義務について、どのように対応しているか。
体験談や口コミの参考にするポイント
体験談・口コミの活用方法
-
- 体験談や口コミは、相談機関の実際の雰囲気や、どのようなサポートが受けられるのかを具体的に知るための貴重な情報源です。
- しかし、個人の感想であるため、そのまま鵜呑みにするのではなく、客観的な視点を持って参考にすることが大切です。
- 複数の体験談や口コミを比較検討することで、より多角的な情報を得ることができます。
体験談・口コミを読む際の注意点
-
- 主観的な意見であることの理解:個人の経験や感じ方によって、評価は大きく異なります。
- 情報の新しさ:相談機関の体制やサービス内容は変化する可能性があります。できるだけ新しい情報を参考にしましょう。
- 特定の状況への偏り:体験談は、その方の特定の状況下での感想です。ご自身の状況と合致するかどうかを慎重に判断しましょう。
- ネガティブな情報への向き合い方:悪い口コミがあった場合でも、それが全ての利用者に当てはまるわけではありません。
- ポジティブな情報への過信:良い口コミばかりでも、過信せず、他の情報源も確認しましょう。
- 情報源の信頼性:匿名掲示板やSNSなど、情報源の信頼性を吟味することも重要です。
参考にするべき具体的な内容
-
- 相談員の対応:親切丁寧か、親身になって話を聞いてくれるか、専門的な知識を持っているか。
- お子さんへの関わり方:お子さんが安心できるような対応か、お子さんの気持ちを尊重しているか。
- 施設・環境:清潔か、落ち着いた雰囲気か、お子さんが過ごしやすい環境か。
- 効果・変化:相談を利用したことで、お子さんの状態にどのような変化があったか。
- 予約の取りやすさ:希望する日時で予約が取れるか、待ち時間はどれくらいか。
- 料金とのバランス:提供されるサービス内容に対して、料金は妥当か。
相性の良いカウンセラーの選び方
カウンセリングにおける「相性」の重要性
-
- カウンセリングは、カウンセラーとクライアント(お子さんや保護者)との信頼関係が基盤となります。
- 相性が良いと感じるカウンセラーとは、安心して本音を話しやすく、より深いレベルでのサポートを受けることができます。
- 相性は、カウンセラーの専門性だけでなく、人柄や話し方、価値観なども影響します。
- 「この人になら話せる」と思えることが、解決への大きな一歩となります。
相性の良いカウンセラーを見つけるためのポイント
-
- 第一印象を大切にする:初回相談の際に、カウンセラーの話し方、表情、雰囲気などを感じ取ってみましょう。
- 安心感を得られるか:話をしていて、自分がリラックスできているか、否定されずに受け入れられていると感じるか。
- 信頼できると感じるか:専門的な知識を持ちつつも、威圧的でなく、誠実な対応をしてくれるか。
- 共感してくれるか:自分の気持ちを理解しようとしてくれている、共感を示してくれるか。
- 質問への丁寧な応答:疑問や不安に対して、分かりやすく丁寧に答えてくれるか。
- 価値観の押し付けがないか:自分の考え方や価値観を押し付けるのではなく、あくまでサポートに徹してくれるか。
- お子さんとの相性も考慮する:お子さんがカウンセラーに対して、どのような印象を持っているかも重要です。
相性が合わないと感じた時の対応
-
- 無理をしない:もし、どうしても相性が合わないと感じた場合は、無理に通い続ける必要はありません。
- 率直に伝える:可能であれば、カウンセラーにその旨を正直に伝えることで、相手も理解し、他の選択肢を提案してくれることもあります。
- 別のカウンセラーを試す:相談機関によっては、複数のカウンセラーがいる場合があります。他のカウンセラーに相談することも検討しましょう。
- 相談機関を変える:どうしてもその機関で合うカウンセラーが見つからない場合は、別の相談機関を探すことも一つの方法です。
- 家族で話し合う:お子さんや他の家族とも相談し、どのようなカウンセラーが良いか、意見を交換しましょう。
不登校の原因と子どもの心理状態
「なぜうちの子は学校に行きたがらないのだろう?」
不登校の原因は、お子さん一人ひとりによって異なります。
学校での人間関係、学習への不安、家庭環境の変化など、
様々な要因が複雑に絡み合っている場合も少なくありません。
このセクションでは、不登校の背景にあるお子さんの心理状態や、
原因として考えられる要因を掘り下げていきます。
お子さんの心に寄り添い、理解を深めることが、
問題解決への第一歩となります。
学校生活への不安やストレス要因
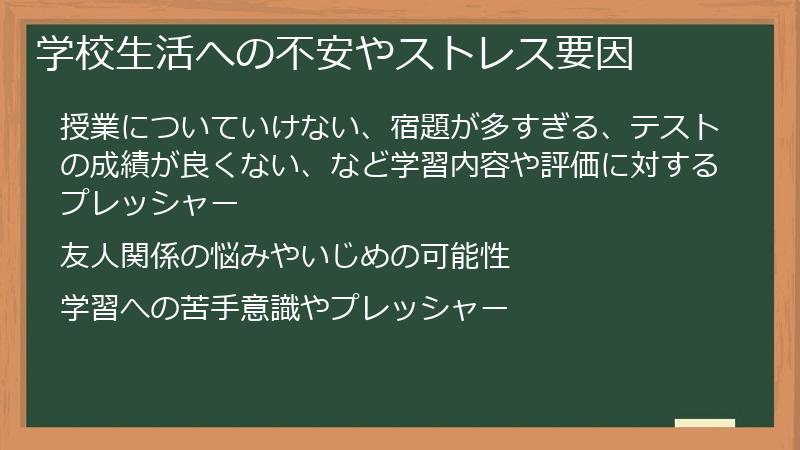
-
- 学校生活は、お子さんにとって多くの刺激や人間関係が存在する場所です。
- そのため、様々な不安やストレスを感じやすい環境とも言えます。
- これらの要因が積み重なることで、学校への行き渋りや、不登校につながることがあります。
- お子さんの様子を注意深く観察し、どのような点に不安を感じているのかを理解することが大切です。
具体的な不安やストレス要因
-
- 学習面での不安:授業についていけない、宿題が多すぎる、テストの成績が良くない、など学習内容や評価に対するプレッシャー。
- 友人関係の悩み:友人とのトラブル、いじめ、仲間外れ、孤立感、グループに入れない、うまくコミュニケーションが取れない。
- 教師との関係:先生との相性が悪い、叱責が多い、先生に相談しにくい、先生からの期待に応えられないと感じる。
- 学校の雰囲気やルール:校風が合わない、校則が厳しい、学校の雰囲気に馴染めない、集団行動が苦手。
- 部活動や学校行事:部活動での人間関係や練習の厳しさ、学校行事(修学旅行、運動会など)への参加が負担になる。
- 進路や将来への不安:将来何をしたいか分からない、受験へのプレッシャー、進路選択への迷い。
- 通学方法や時間:通学に時間がかかる、通学路で嫌なことがある、満員電車が苦手。
- 些細な出来事の積み重ね:直接的な大きな問題でなくても、日々の小さなストレスや嫌な出来事が積み重なること。
親が理解しておくべきこと
-
- お子さんが感じている不安やストレスは、大人から見ると些細なことでも、お子さんにとっては非常に大きなものである場合があります。
- 「気のせい」「大げさだ」と片付けず、お子さんの訴えに真剣に耳を傾ける姿勢が大切です。
- お子さんが抱える不安やストレスは、一つだけではなく、複数の要因が複合的に影響していることも少なくありません。
- これらの要因に早期に気づき、適切に対応することで、不登校の予防や改善につながる可能性があります。
授業についていけない、宿題が多すぎる、テストの成績が良くない、など学習内容や評価に対するプレッシャー
学習面での不安と不登校
-
- 学習内容の理解が追いつかない、授業についていけないといった不安は、お子さんが学校を避ける大きな要因となることがあります。
- 宿題の量が多くてこなせない、テストの点数が振るわないといった経験が積み重なると、学習に対する苦手意識や無力感を抱くようになります。
- 「頑張ってもできない」「努力しても無駄だ」と感じてしまうと、学校に行くこと自体が苦痛になってしまうのです。
- このような学習面でのプレッシャーは、お子さんの自己肯定感を著しく低下させ、自信を失わせる原因にもなり得ます。
親ができるサポート
-
- お子さんのペースを尊重する:無理に成績を上げさせようとしたり、他の子と比較したりせず、お子さんのペースに合わせて学習を進められるようにサポートしましょう。
- 「できた」経験を積ませる:難しい問題に挑戦させるよりも、まずは「できた」という達成感を味わえるような、少し易しめの課題から始めるのが効果的です。
- 学習習慣の見直し:宿題の量が多い場合は、学校の先生と相談して、負担を軽減してもらえないか検討しましょう。
- 苦手分野の克服支援:苦手な科目は、塾や家庭教師、学習支援教室などを活用して、専門的なサポートを受けることも有効です。
- 学習以外の得意なことを見つける:勉強だけでなく、お子さんが得意なことや興味のあることを見つけ、それを伸ばすことも大切です。
- 「結果」ではなく「過程」を褒める:たとえ結果が出なくても、努力した過程を認め、褒めることで、お子さんのモチベーションを維持させることができます。
- 過度な期待をしない:親の過度な期待は、お子さんにとって大きなプレッシャーになります。お子さんのありのままを受け入れることが重要です。
学校との連携
-
- お子さんが学習面で困難を感じている場合は、担任の先生や教科担当の先生に相談し、状況を共有することが大切です。
- 授業の進め方や宿題の量について、先生と相談し、お子さんに合った対応を検討してもらいましょう。
- 必要であれば、個別指導や、学習支援員によるサポートについても相談してみると良いでしょう。
- お子さんが安心して学習に取り組める環境を、学校と家庭で協力して作っていくことが重要です。
友人関係の悩みやいじめの可能性
人間関係における苦悩
-
- 学校生活において、友人関係は非常に大きなウェイトを占めます。
- 友人との良好な関係は、学校生活を楽しく、充実したものにする一方で、
- 友人関係のトラブルやいじめは、お子さんにとって耐えがたい苦痛となり、
- 不登校の直接的な原因となることも少なくありません。
友人関係の悩み
-
- 仲間外れや孤立:グループに入れなかったり、意図的に無視されたりすることで、孤立感を感じる。
- 悪口や陰口:陰で悪口を言われたり、噂を流されたりすることに傷つく。
- 意見の衝突や価値観の違い:友人との意見の食い違いや、価値観の違いから、関係が悪化する。
- SNSでのトラブル:SNS上での誹謗中傷、仲間外れ、個人情報の漏洩など。
- 恋愛関係のもつれ:友人間での恋愛関係のトラブルに巻き込まれる。
- コミュニケーションの苦手意識:うまく話しかけられない、会話が続かない、相手の気持ちを理解するのが難しい。
いじめの可能性
-
- 身体的ないじめ:叩く、蹴る、物を隠す、乱暴な言葉をかけるなど。
- 言葉によるいじめ:悪口、陰口、無視、脅し、からかい、侮辱など。
- ネットいじめ(サイバーいじめ):SNSやインターネットを使った誹謗中傷、個人情報の暴露、仲間外れなど。
- その他のいじめ:金銭の要求(恐喝)、物の隠匿、嫌がらせ行為など。
- 「いじめ」という認識のずれ:お子さん自身がいじめだと認識していない場合もあるため、大人が慎重に判断する必要があります。
親ができること
-
- お子さんの話を丁寧に聞く:お子さんが話したいと思ったときに、じっくりと耳を傾け、感情を受け止めることが大切です。
- 「いじめかも?」と感じたら、すぐに学校へ連絡・相談する:「気のせい」「大げさだ」と判断せず、担任の先生やスクールカウンセラーに相談しましょう。
- お子さんのSOSを見逃さない:普段と違う様子に気づいたら、積極的に声をかけ、お子さんの心に寄り添いましょう。
- お子さんを責めない・否定しない:いじめられた原因をお子さんのせいにするような言動は絶対に避けましょう。
- 学校との連携を密にする:学校側と情報共有を密に行い、いじめの早期発見・早期解決に努めましょう。
- お子さんの味方であることを伝える:どんな状況でも、親はあなたの一番の味方であるというメッセージを伝え、安心感を与えましょう。
- 専門機関の活用:いじめが深刻な場合は、スクールカウンセラーや専門の相談機関に相談することも検討しましょう。
学習への苦手意識やプレッシャー
学習への苦手意識の背景
-
- お子さんが特定の科目や学習内容に対して苦手意識を持っている場合、
- それが学校に行くことへの億劫さや、自己肯定感の低下につながることがあります。
- 苦手意識は、単に「できるようにならない」ということだけでなく、
- 「頑張っても無駄だ」「自分にはできない」といった諦めの感情や、
- 失敗への過度な恐れを生み出すこともあります。
苦手意識が生まれる要因
-
- 理解不足の積み重ね:授業のペースについていけず、基礎的な内容の理解が不十分なまま進んでしまう。
- 苦手な指導法:先生の教え方が合わない、説明が分かりにくい、一方的な講義形式で退屈に感じる。
- 過去の失敗体験:テストで低い点数を取った、発表で失敗した、といった経験がトラウマとなり、その科目や学習全般を避けるようになる。
- 「できない」という自己暗示:一度苦手意識を持つと、「自分はできない」と思い込み、努力する意欲を失ってしまう。
- 保護者や周囲の期待とのギャップ:親や周囲からの期待が高く、それにプレッシャーを感じてしまう。
- 発達上の特性:集中力の持続が難しい、特定の感覚過敏がある、といった発達上の特性が学習に影響している可能性。
学習へのプレッシャー
-
- 成績への執着:常に良い成績を取ることを求められ、結果が出せないと自分を責めてしまう。
- 進路への不安:希望する進路に進むためには、特定の科目の成績が必須であるというプレッシャー。
- 競争社会:クラス内や学校全体での成績競争に疲れてしまう。
- 「勉強しなさい」という言葉の重み:親からの「勉強しなさい」という言葉が、プレッシャーや義務感となってしまう。
親ができること
-
- 「なぜ」ではなく「どうすれば」を考える:苦手意識の原因を探るだけでなく、「どうすれば少しでも楽になるか」「どうすれば興味を持てるか」を一緒に考えましょう。
- 小さな成功体験を大切にする:「できた!」という経験を積み重ねることが、苦手意識の克服につながります。
- 学習方法の多様化:教科書や問題集だけでなく、図鑑、ドキュメンタリー、体験学習など、様々なアプローチを試してみましょう。
- 「結果」より「努力」を認める:たとえ結果が悪くても、頑張った過程や努力したことを具体的に褒め、お子さんの自信を育みましょう。
- 親自身の学習への向き合い方を見せる:親が楽しそうに学んでいる姿を見せることも、お子さんの学習意欲に良い影響を与えることがあります。
- 休息や気分転換を促す:学習に疲れたときは、無理せず休憩させ、気分転換できる時間を与えることも大切です。
- 専門家への相談:苦手意識が強い場合や、発達上の特性が疑われる場合は、スクールカウンセラーや専門機関に相談しましょう。
子どもの気持ちに寄り添うコミュニケーション
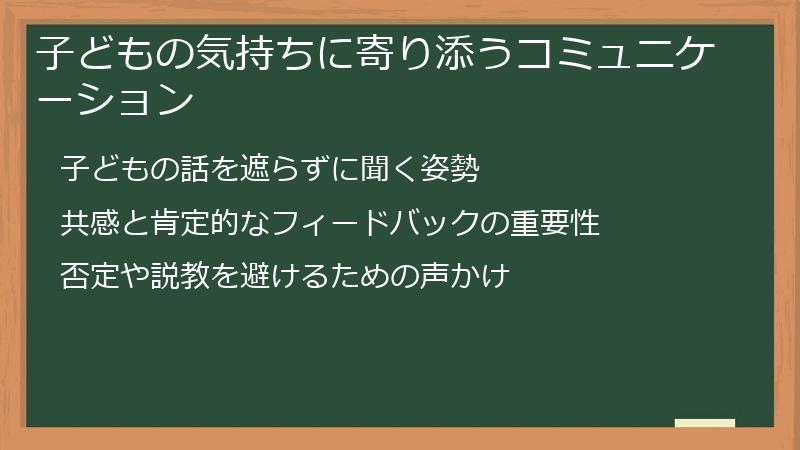
-
- 不登校のお子さんとの関わりで最も大切なのは、「お子さんの気持ちに寄り添う」ことです。
- お子さんが抱える不安や辛さを理解し、安心できる言葉がけや態度を示すことで、
- お子さんは「自分は一人ではない」「大切にされている」と感じることができます。
- このセクションでは、お子さんの心に響くコミュニケーションの取り方について、
- 具体的な声かけや傾聴の技術を解説します。
お子さんの気持ちに寄り添うとは
-
- 理解しようと努める姿勢:お子さんが感じているであろう感情や状況を、親の価値観で判断せず、まずは理解しようと努めることです。
- 共感を示す:「つらいね」「大変だったね」など、お子さんの感情をそのまま受け止め、共感する言葉を伝えることです。
- 非審判的な態度:お子さんの言動を「良い」「悪い」と評価せず、どのような状況であっても、ありのままを受け入れることです。
- 安心できる雰囲気作り:お子さんが安心して本音を話せるような、温かく、穏やかな雰囲気を作ることです。
具体的なコミュニケーションのポイント
-
- 傾聴(アクティブリスニング):
-
- 相手の目を見て聞く:相槌を打ちながら、相手の言葉に注意を払う。
- 話を遮らない:お子さんの話が終わるまで、最後まで聞く。
- 感情を言葉にする:「〜と感じているんだね」と、お子さんの感情を代弁する。
- 要約して確認する:「つまり、〜ということだね」と、理解した内容をまとめて伝える。
- 質問は確認のために:「〜ということ?」「〜だったの?」など、相手を追い詰めるような質問は避ける。
- 肯定的な言葉がけ:
-
- 「〜しなさい」ではなく「〜してみる?」:命令形ではなく、提案するような形で伝える。
- 「〜してえらいね」ではなく「〜できたね」:結果だけでなく、努力や行動そのものを褒める。
- 感謝の気持ちを伝える:「ありがとう」という言葉を大切にする。
- 励ましの言葉:「大丈夫だよ」「応援しているよ」といった、安心感を与える言葉をかける。
- 沈黙を恐れない:無理に会話を続けようとせず、沈黙を共有することも、安心感につながることがあります。
避けるべき対応
-
- 一方的な説教やアドバイス:お子さんが話している途中で、親の意見やアドバイスを一方的に押し付ける。
- 原因追及や人格否定:「なんで学校に行けないの!」「あなたのせいよ!」など、お子さんを責めるような言葉。
- 他の子との比較:「〇〇ちゃんはちゃんと学校に行ってるのに」「もっと頑張りなさい」といった比較。
- 安易な励ましや励ますつもりでの否定:「元気出しなさい」「そんなことで悩むな」といった、お子さんの気持ちを否定するような言葉。
- 無理強いや過度な期待:お子さんの状況を無視して、登校を強要したり、過度な期待をかけたりすること。
子どもの話を遮らずに聞く姿勢
傾聴の重要性
-
- お子さんが抱える悩みや辛さを理解し、共感するためには、「聞く」という行為が何よりも大切です。
- 特に、不登校のお子さんは、自分の気持ちをうまく言葉にできなかったり、
- 親に心配をかけたくないという思いから、本音を隠してしまうこともあります。
- そのような状況だからこそ、親が「遮らずに聞く」という姿勢を示すことが、
- お子さんの心を開き、信頼関係を築く上で非常に重要になります。
「遮らずに聞く」ための具体的な技術
-
- 話を最後まで聞く:お子さんが話し始めたら、途中で口を挟まず、最後まで聞きましょう。
- 評価や批判をしない:お子さんの話の内容について、「それは間違っている」「そんなことで悩むな」といった評価や批判は一切しないことが大切です。
- 相槌を打つ:「うんうん」「そうなんだね」といった相槌は、相手が話を聞いてもらえているという安心感を与えます。
- アイコンタクトを保つ:無理のない範囲で、お子さんの目を見て話を聞くことで、真剣に聞いている姿勢を伝えられます。
- 共感の言葉を添える:「つらかったね」「大変だったね」といった共感の言葉は、お子さんの気持ちに寄り添い、理解していることを伝えます。
- 沈黙を恐れない:お子さんが言葉に詰まったり、沈黙したりしても、無理に会話を続けようとせず、待つことも大切です。
- 非言語的なサインに注意を払う:お子さんの表情や声のトーン、体の動きなど、言葉以外のサインにも注意を払い、心情を察しようと努めましょう。
話を聞く際の親の心構え
-
- 「聞く」こと自体が目的であると意識する:すぐに解決策を見つけようとしたり、アドバイスをしようとしたりするのではなく、まずは「聞く」ことに集中します。
- お子さんのペースに合わせる:お子さんが話したいペースで、話したいことを話せるように、焦らず見守ります。
- 自分の感情をコントロールする:お子さんの話を聞いて、親自身が動揺したり、怒りを感じたりすることがあっても、それを表に出さないように努めましょう。
- 「聞く」ことの訓練と捉える:最初からうまくできなくても当然です。練習を重ねることで、より上手にお子さんの話を聞けるようになります。
共感と肯定的なフィードバックの重要性
共感の力
-
- お子さんが抱える辛さや不安に対して、共感を示すことは、
- お子さんの心を安心させ、親への信頼感を深める上で非常に効果的です。
- 共感とは、単に同情することではなく、お子さんが感じている感情を理解し、
- 「あなただけではないよ」「つらい気持ちもわかるよ」というメッセージを伝えることです。
共感の伝え方
-
- 感情を言葉で受け止める:「〜なんだね」「〜と感じているんだね」というように、お子さんの感情をそのまま言葉にして返します。
- 「もし私があなただったら」という視点:もし自分が同じ状況だったらどう感じるか、という想像力を働かせ、その気持ちを共有します。
- 非言語的なサインに注意する:お子さんの表情や声のトーンから感情を読み取り、それに寄り添うような態度を示します。
- 「わかるよ」という言葉:たとえ完全に理解できなくても、「わかるよ」という言葉は、お子さんに安心感を与えます。
肯定的なフィードバックとは
-
- 「できた」という経験を肯定する:たとえ小さなことでも、お子さんが「できた」と感じたことを具体的に褒めることです。
- 努力や過程を認める:結果だけでなく、そこに至るまでの努力や頑張りを認め、褒めることで、お子さんの自己肯定感を育みます。
- 長所や得意なことを伝える:お子さんの良いところや、得意なことを具体的に伝え、お子さん自身が自分の価値を認識できるように促します。
- 「ありがとう」を伝える:お子さんがしてくれたことに対して、感謝の気持ちを伝えることで、お子さんの自己有用感を高めます。
肯定的なフィードバックの効果
-
- 自己肯定感の向上:自分はできる、自分は価値がある、と感じられるようになります。
- モチベーションの維持・向上:褒められることで、さらに頑張ろうという意欲が湧きます。
- 安心感の獲得:親に認められている、という感覚は、お子さんに安心感を与えます。
- 前向きな姿勢の育成:失敗しても、「また頑張ろう」と思えるようになります。
注意点
-
- 過剰な褒めすぎは逆効果:事実と異なる過剰な褒め方は、お子さんの信頼を失う可能性があります。
- 結果のみを褒めない:結果だけでなく、努力や過程を褒めることが重要です。
- 「〜しなさい」を促すための褒め言葉にならないようにする:あくまでお子さん自身の行動や内面を肯定する言葉を選びましょう。
否定や説教を避けるための声かけ
なぜ否定や説教が避けられるべきか
-
- 不登校のお子さんに対して、親がついやってしまいがちなのが、否定的な言葉や説教です。
- しかし、これらの言葉は、お子さんの心をさらに閉ざさせ、
- 親への不信感を増幅させる可能性があります。
- 「行かなければならない理由」を一方的に伝えるのではなく、
- お子さんの気持ちに寄り添った声かけを心がけることが大切です。
否定的な言葉・説教の具体例とその影響
-
- 「〜しなさい」という命令形:お子さんを追い詰め、反発心を招く可能性があります。
- 「〜すべき」という価値観の押し付け:親の価値観を押し付けることで、お子さんは「自分は間違っている」と感じてしまうかもしれません。
- 「〜してえらいね」ではなく「〜できて当然」という見方:結果が出なかった場合、「なぜできないのか」と責めることにつながります。
- 他の子との比較:「〇〇ちゃんはできているのに」といった言葉は、お子さんの劣等感を刺激します。
- 原因追及や人格否定:「あなたのせいよ」「怠けているだけ」といった言葉は、お子さんの自己肯定感を著しく傷つけます。
- 感情的な叱責:親の感情的な怒りは、お子さんを委縮させ、本音を話すことを妨げます。
否定や説教を避けるための声かけの工夫
-
- 「〜できてすごいね」といった肯定的な言葉を使う:結果ではなく、お子さんの行動や努力を具体的に褒めることで、前向きな気持ちを育みます。
- 「〜しなさい」ではなく「〜してみる?」と提案する:お子さんの意思を尊重し、自分で選択する機会を与えます。
- お子さんの感情を受け止める:「つらいんだね」「不安なんだね」と、お子さんの気持ちに共感する言葉を伝えます。
- 「どうしたらいいかな?」と問いかける:親が一方的に解決策を示すのではなく、お子さん自身に考えさせることで、主体性や問題解決能力を育みます。
- 「大丈夫だよ」「応援しているよ」といった安心感を与える言葉をかける:親が味方であることを伝え、お子さんが安心して過ごせるように促します。
- 沈黙を恐れず、待つ姿勢:お子さんが言葉に詰まったときも、無理に話させようとせず、待つことで、お子さんのペースを尊重します。
- 「まず休もう」と提案する:お子さんが疲れている様子であれば、無理に何かをさせようとせず、「まずはゆっくり休もう」と提案することも大切です。
親自身の感情のコントロール
-
- お子さんの言動にイライラしたり、不安になったりすることは自然なことです。
- しかし、その感情をそのままぶつけてしまうと、お子さんを傷つけてしまいます。
- 親自身が、自分の感情を認識し、落ち着いて対応できるよう、
- 深呼吸をしたり、一度その場を離れたりするなど、感情のコントロールを意識しましょう。
- 必要であれば、親自身もカウンセリングなどを利用して、心のケアをすることも有効です。
子どもの自己肯定感を育む接し方
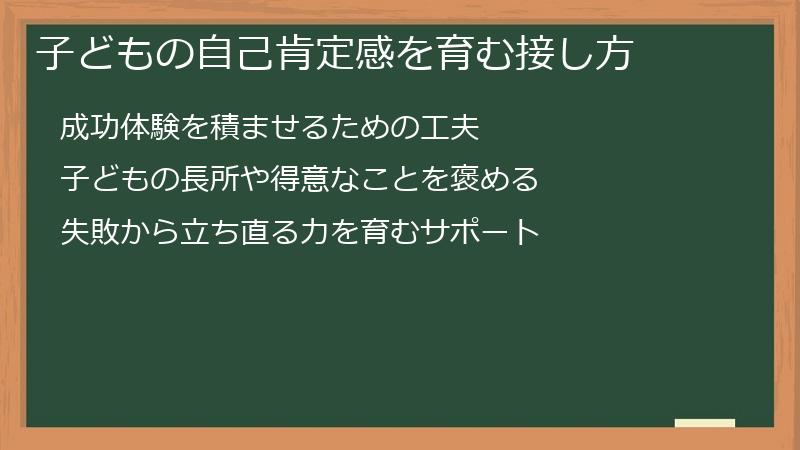
-
- 不登校のお子さんは、学校での経験や、日々の葛藤から、
- 自己肯定感が低下している場合が多く見られます。
- 自己肯定感とは、「自分には価値がある」「自分はできる」と思える感覚のことです。
- この感覚が育つことで、お子さんは困難に立ち向かう勇気や、
- 新しいことに挑戦する意欲を持つことができます。
- ここでは、お子さんの自己肯定感を育むための、具体的な接し方や考え方をお伝えします。
自己肯定感とは
-
- 自分を肯定的に捉える感覚:自分の長所も短所も含めて、ありのままの自分を認め、大切にできる感覚です。
- 「自分はやればできる」という感覚:困難な状況に直面しても、努力すれば乗り越えられる、という自信を持つことです。
- 他者との比較ではなく、自分自身の成長に目を向ける:他者との比較ではなく、過去の自分と比べて成長できた点に目を向けることができます。
- 自己肯定感が高いと、どのようなメリットがあるか:
-
- 困難な状況でも諦めずに挑戦できる。
- 他者との健全な関係を築きやすい。
- ストレスへの対処能力が高い。
- 精神的な安定を保ちやすい。
- 失敗から学び、成長することができる。
自己肯定感を育むための具体的な接し方
-
- お子さんの「できた」を共有し、褒める:
-
- 「今日は朝ごはんをちゃんと食べたね、えらいね。」
- 「お母さんの言ったことを思い出して、自分で片付けができたね。」
- 「苦手な勉強に少しだけ取り組めたね、すごいね。」
- お子さんの長所や得意なことを具体的に伝える:
-
- 「〇〇君は絵を描くのが上手だね。この色使い、とってもいいね。」
- 「△△ちゃんは、いつも人の気持ちを考えることができる優しい子だね。」
- 「□□君は、物事を最後までやり遂げる力があるね。」
- お子さんの選択を尊重し、応援する:
-
- 「〇〇君がやりたいなら、やってみればいいよ。お母さんは応援しているよ。」
- 「自分で決めたことだから、まずはやってみよう。」
- 失敗しても責めずに、次に繋げる声かけをする:
-
- 「うまくいかなかったね。でも、頑張ったことは無駄じゃないよ。」
- 「次はどうしたらうまくいくか、一緒に考えてみようか。」
- 「失敗から学ぶことはたくさんあるよ。」
- 家庭を安心できる「聖域」にする:
-
- 家では、学校での出来事や成績のプレッシャーから解放され、リラックスして過ごせるようにします。
- お子さんが安心して自分を表現できる場所であることを、言葉や態度で示します。
- 親自身が自分を大切にする姿を見せる:
-
- 親が自分自身を大切にし、ポジティブな言動を心がけることは、お子さんにとっての良いお手本となります。
避けるべきこと
-
- 過度な干渉や心配:お子さんが自分でできることを、先回りしてやってしまう。
- 期待を押し付ける:親の価値観や理想をお子さんに押し付ける。
- 他の子との比較:お子さんの個性やペースを無視して、他人と比較する。
- 否定的な言葉や批判:お子さんの行動や言動を一方的に否定したり、批判したりする。
- 「〜しなさい」という命令口調:お子さんの自律性を尊重せず、強制するような言い方。
成功体験を積ませるための工夫
「成功体験」とは
-
- 成功体験とは、お子さんが「自分はできた」「自分はやればできる」と感じられる経験のことです。
- この経験は、お子さんの自己肯定感を高め、自信を育む上で非常に重要です。
- 不登校のお子さんは、学校での経験から「自分はできない」という無力感を抱えがちですが、
- 家庭での小さな成功体験を積み重ねることで、その感覚を塗り替えていくことができます。
成功体験を積ませるための工夫
-
- スモールステップを設ける:
-
- 目標を細かく分解し、達成可能な小さなステップを設定します。
- 例えば、「部屋を片付ける」という目標なら、「まず机の上だけ片付ける」「服をタンスにしまう」など、段階を踏みます。
- 一つ一つのステップをクリアするたびに、お子さんを褒めることで、達成感を感じさせます。
- お子さんの「できた」を具体的に褒める:
-
- 「宿題を1ページできたね、すごいね。」
- 「朝、自分で起きることができたね、えらいね。」
- 「お母さんにお茶を運んでくれてありがとう。」
- 完璧を求めない:
-
- 少しくらいできなくても、その努力や過程を認め、褒めることが大切です。
- 「完璧でなくても大丈夫だよ」というメッセージを伝えることで、お子さんは失敗を恐れずに挑戦できるようになります。
- お子さんの興味関心に沿った活動を取り入れる:
-
- お子さんが好きなこと、得意なことに関わる活動は、成功体験を得やすい機会です。
- 例えば、絵を描くのが好きなら、作品を褒めたり、展示したりする機会を作る。
- ゲームが得意なら、ゲームでレベルアップしたことを一緒に喜ぶ。
- 失敗しても責めない:
-
- 失敗は成長の糧です。「失敗しても大丈夫」「次はこうしてみよう」と、前向きな声かけを心がけます。
- 失敗から何を学んだのかを一緒に考えることで、お子さんの問題解決能力も育まれます。
- 親も一緒に楽しむ姿勢を見せる:
-
- お子さんが何か新しいことに挑戦するとき、親も一緒に楽しむ姿勢を見せることで、お子さんは安心感を得て、さらに意欲的に取り組むことができます。
成功体験を促す上での注意点
-
- 過度な期待をしない:親の期待が大きすぎると、お子さんにとってプレッシャーとなり、逆効果になることがあります。
- 無理強いをしない:お子さんが乗り気でないことを無理強いしても、成功体験にはつながりません。お子さんの意思を尊重しましょう。
- 結果だけでなく過程を重視する:目標達成だけでなく、そこに至るまでの努力や工夫も褒めることが大切です。
子どもの長所や得意なことを褒める
「長所・得意なこと」を褒めることの意義
-
- 不登校のお子さんは、学校での経験から、自分の短所やできないことにばかり目が向きがちです。
- その結果、自己肯定感が低下し、「自分には価値がない」と感じてしまうこともあります。
- お子さんの長所や得意なことを意識的に見つけ、それを具体的に褒めることは、
- お子さんが自分自身を肯定的に捉えるための、非常に効果的な手段となります。
長所・得意なことを見つけるための視点
-
- 観察を習慣にする:お子さんの普段の行動や言動を注意深く観察し、どのような点に優れているのか、どのようなことに興味を持っているのかを見つけます。
- 「できないこと」ではなく「できること」に焦点を当てる:勉強や学校生活でうまくいかないことがあっても、それ以外の場面で発揮されているお子さんの良いところに目を向けます。
- お子さん自身の言葉に耳を傾ける:お子さんが「これが好き」「これが得意」と話すことは、お子さん自身が大切にしている価値観や能力の表れです。
- 親以外の他者の意見も参考にする:学校の先生や、お子さんと関わる機会のある親戚、友人などから、お子さんの良いところを聞いてみるのも良いでしょう。
長所・得意なことを具体的に褒める方法
-
- 具体的な行動や結果に言及する:
-
- 「〇〇君は、この絵を最後まで丁寧に描いたね。色の使い方がとても上手だよ。」
- 「△△さんは、いつも弟に優しく話しかけているね。その優しさは本当に素晴らしいと思うよ。」
- 「□□君は、ゲームの攻略法を考えるのが得意だね。その集中力はすごいよ。」
- 「〜なところがいいね」「〜なところが素敵だね」と伝える:お子さんの人間性や内面的な良さを褒める言葉も効果的です。
- 「ありがとう」を添える:例えば、お手伝いをしてくれたときなど、「ありがとう。助かったよ。」と感謝の気持ちを伝えることで、お子さんの自己有用感が高まります。
- 無理に褒めすぎない:事実に基づいた、誠実な褒め方を心がけましょう。過剰な褒め方は、かえってお子さんを不安にさせることもあります。
- 「長所」として言葉にする:お子さんの得意なことを、「あなたの〇〇なところは、本当に長所だと思うよ」と、長所であることを伝えることで、お子さんは自分の強みを認識しやすくなります。
褒めることで期待できる効果
-
- 自己肯定感の向上:自分は認められている、自分には価値がある、と感じるようになります。
- 自信の育成:得意なことや長所を認識することで、自信を持って行動できるようになります。
- モチベーションの向上:得意なことへの取り組みがさらに積極的になり、新たな挑戦への意欲も湧きます。
- 他者への肯定的な関わり:自分を肯定的に捉えられるようになると、他者に対しても寛容になり、良好な人間関係を築きやすくなります。
失敗から立ち直る力を育むサポート
「失敗」と「立ち直る力」
-
- お子さんが不登校になる背景には、失敗体験や、失敗への恐れが隠れていることが少なくありません。
- 「どうせやってもできない」「失敗したら恥ずかしい」といった思いは、
- お子さんの挑戦意欲を削ぎ、自己肯定感を低下させる原因となります。
- しかし、人生において失敗はつきものです。
- 失敗から学び、そこから立ち直っていく力(レジリエンス)を育むことは、
- お子さんの将来にとって非常に大切なことです。
失敗から立ち直る力を育むためのサポート
-
- 失敗は学びの機会と捉える:
-
- 「失敗したね。でも、ここから何を学べるかな?」と、失敗を責めるのではなく、前向きな声かけをします。
- お子さんと一緒に、失敗の原因や、次にどうすれば良いかを話し合います。
- 「完璧」を求めない姿勢を示す:
-
- 「失敗しても大丈夫」「完璧でなくてもいいんだよ」というメッセージを伝えることで、お子さんは失敗を恐れずに挑戦できるようになります。
- 親自身も、完璧ではない姿を見せることで、お子さんにとって安心感を与えます。
- 共感と励まし:
-
- 失敗して落ち込んでいるお子さんの気持ちに寄り添い、「つらかったね」と共感を示します。
- その後、「でも、君ならきっと乗り越えられるよ」といった励ましの言葉をかけ、お子さんの力を信じていることを伝えます。
- 小さな成功体験を積み重ねる:
-
- 前述したように、小さな目標を設定し、それを達成する経験を積ませることで、お子さんの自信と「自分はやればできる」という感覚を育みます。
- この自信が、失敗から立ち直るための土台となります。
- 問題解決能力を育む:
-
- お子さんが困っているとき、すぐに親が解決策を示すのではなく、「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、お子さん自身に考えさせる機会を与えます。
- お子さんが自分で考え、行動し、その結果から学ぶプロセスをサポートします。
- 親自身が失敗から立ち直る姿を見せる:
-
- 親自身も、失敗を経験し、そこから学び、乗り越えていく姿を見せることは、お子さんにとって何よりの学びとなります。
- 「お母さんも昔、こういう失敗をして、こうやって乗り越えたんだよ」といった経験談も有効です。
避けるべきこと
-
- 失敗を過度に叱責する:お子さんの失敗を一方的に責めたり、過剰に叱ったりすることは、お子さんの挑戦意欲を奪います。
- 「だから言ったのに」という言葉:後から否定するような言葉は、お子さんの心を傷つけます。
- 失敗を隠蔽させる:失敗を隠すように促したり、親が代わりに処理したりすることは、お子さんの学びの機会を奪います。
- 過保護になりすぎる:失敗を恐れるあまり、何でも先回りしてやってしまうと、お子さん自身が困難に立ち向かう力を育む機会を失います。
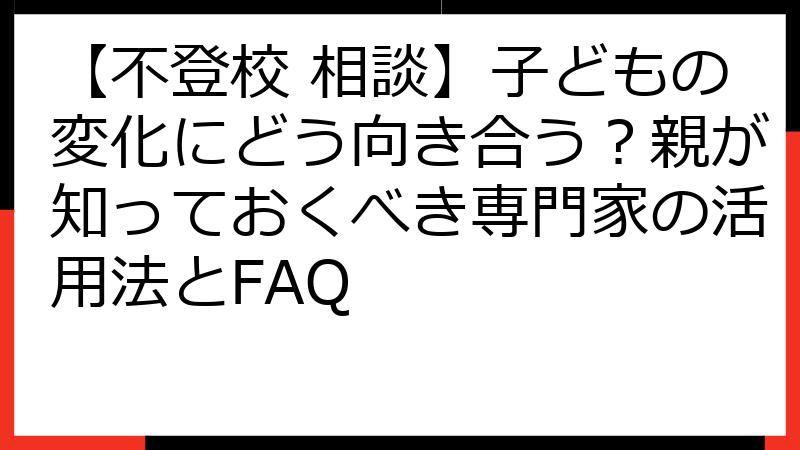
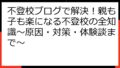
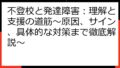
コメント