- 読書感想文 小学生 入賞作品の秘密!書けないを「書けた!」に変える攻略ガイド
- 読書感想文の基本:「なぜ書くのか?」から「何を書くのか?」まで
- テーマ別!「読書感想文」で入賞を狙うためのポイント
読書感想文 小学生 入賞作品の秘密!書けないを「書けた!」に変える攻略ガイド
このブログ記事では、小学生の読書感想文で「入賞」を狙うための具体的な方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
「何から書き始めればいいか分からない…」
「どうすれば評価される文章になるの?」
そんな悩みを抱える皆さんへ、入賞作品に共通する書き方の秘訣をお伝えします。
読むだけでなく、書く力がぐんと伸びるヒントが満載です。
さあ、あなたも読書感想文の達人を目指しましょう!
読書感想文の基本:「なぜ書くのか?」から「何を書くのか?」まで
読書感想文を書く目的を理解し、魅力的なテーマと構成の基礎を築くためのガイドです。
入賞作品に共通する「心に響く」テーマの見つけ方から、読書体験を物語に変える構成のコツ、そして差がつく表現力アップの秘訣までを網羅します。
読書感想文の基本をしっかりと押さえることで、あなたの文章は大きく変わるはずです。
入賞作品に共通する「心に響く」テーマの見つけ方
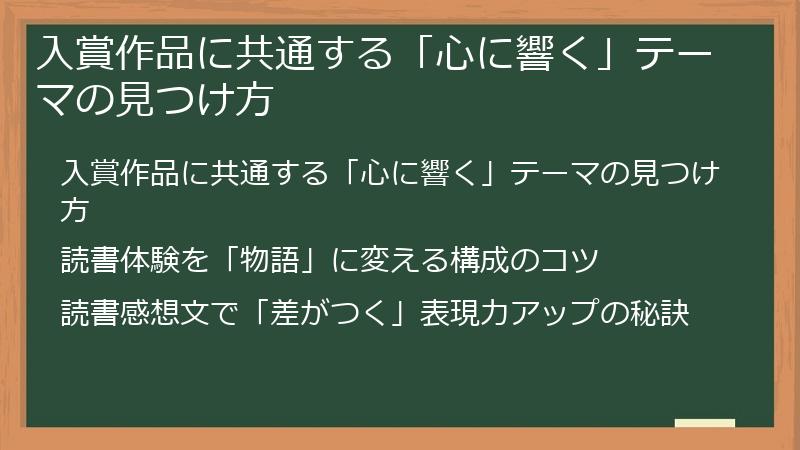
読書感想文で読者の心を掴み、評価を得るためには、まず「どのようなテーマで書くか」が重要です。
ここでは、数多くの入賞作品に見られる、共感を呼び、感動を与えるテーマ設定の秘訣を解き明かします。
あなたが読んだ本の中から、宝物のようなテーマを見つけ出すための具体的なヒントを提供します。
入賞作品に共通する「心に響く」テーマの見つけ方
読書感想文で入賞を果たすためには、読んだ本の内容をただまとめるだけでなく、作者が伝えたいメッセージや、作品を通して読者が何を感じ、何を学んだのかを深く掘り下げることが大切です。入賞作品の多くは、読んだ人の心に強く訴えかける「テーマ」を持っています。
-
テーマ設定の重要性
読書感想文の評価は、内容の面白さだけでなく、書き手の「視点」や「考え方」がどれだけ深まっているかによって大きく左右されます。そのため、読んだ本の中から、自分自身の体験や感情と結びつく、「なぜその本を読んだのか」「なぜそれが心に残ったのか」という問いに深く答えられるテーマを見つけることが、入賞への第一歩となります。
-
心に響くテーマを見つけるための具体的なステップ
まずは、読書中に特に感動した場面や、考えさせられた言葉、共感した登場人物の言動などをメモしておきましょう。
-
感情のアンテナを張る
本を読んでいる最中に、思わず「すごい!」と思ったり、「自分も同じような経験をしたことがある」と感じたりした箇所に印をつけてみてください。
-
疑問や発見を書き出す
「なぜこの登場人物はこんな行動をとったのだろう?」といった疑問や、「この言葉で今まで知らなかったことが分かった」といった発見も、テーマを見つけるための重要な手がかりとなります。
-
本を読み終えて
読後すぐに、本を読んで感じたこと、考えたことを自由に書き出してみましょう。その中で、特に繰り返し思い浮かぶことや、人にも伝えたいと思ったことが、あなたのテーマになる可能性が高いです。
-
-
入賞作品に見られるテーマの傾向
入賞作品では、以下のようなテーマがよく見られます。
-
登場人物への共感
主人公や特定の登場人物の心情に深く共感し、その成長や葛藤について自分の言葉で語ることで、読者も感情移入しやすくなります。
-
読書で得た学びや気づき
本を通して、新しい知識を得たり、自分の考え方が変わったりした経験を具体的に書くことで、読書体験の価値を伝えることができます。
-
本と自分自身の経験の関連性
本の内容を、自分自身の過去の経験や、身の回りで起こっている出来事と結びつけて考察することで、文章に深みとオリジナリティが生まれます。
-
読書体験を「物語」に変える構成のコツ
読書感想文は、単に読んだ本のあらすじを紹介するものではありません。読んだ本を通して自分がどのように感じ、考え、何を発見したのかを、読者に伝わるように「物語」として再構築することが大切です。ここでは、入賞作品に学ぶ、読書体験を魅力的な「物語」に変えるための構成のコツを詳しく解説します。
-
読書感想文の基本的な構成
ほとんどの読書感想文は、以下の3つの要素で構成されています。
-
導入(書き出し)
読者の興味を引きつけ、「この本を読んだらどうなるのだろう?」と思わせるような書き出しが重要です。本の魅力や、自分がこの本に興味を持ったきっかけなどを簡潔に伝えます。
-
本文(内容の紹介と感想)
本のあらすじを簡潔に紹介しつつ、自分が特に感動した場面や、心に残った言葉、登場人物の行動などを具体的に掘り下げて感想を述べます。ここが読書感想文の最も重要な部分であり、あなたの「考え」を伝える場です。
-
結論(まとめ)
読書を通して得た学びや、自分の成長、今後どうしていきたいかなどをまとめて締めくくります。本を読む前と読んだ後で、自分がどう変わったのかを明確に伝えられると、より説得力のある文章になります。
-
-
魅力的な「物語」にするための構成テクニック
読書体験を単なる感想文で終わらせず、「物語」として読者に届けるための具体的な構成テクニックを紹介します。
-
読書前の「期待感」を演出
「この本はどんな物語なんだろう?」という読者の好奇心を刺激するような書き出しを工夫しましょう。本のタイトルや表紙から感じたこと、あるいは、この本を選んだ理由などを共有するのも効果的です。
-
「起承転結」を意識した展開
読んだ本の内容を、単なる時系列で追うのではなく、「起承転結」のような物語の展開を意識して構成すると、読者が内容を理解しやすくなります。特に、物語の「転」にあたる部分、つまり、何かしらの変化や事件が起こる場面に焦点を当てて、そこでの登場人物の心情を深く掘り下げてみましょう。
-
「共感」を生むエピソードの選び方
自分が物語の登場人物になったつもりで、その行動や心情を追体験し、共感した部分を具体的に描写することで、読者もその感情を共有しやすくなります。たとえば、「主人公の○○が、△△に悩んでいた時、私も同じように苦しい気持ちになった」といったように、自分自身の感情と結びつけて書くことが重要です。
-
-
構成を考える上での注意点
入賞作品に近づくためには、構成を考える上でいくつか注意すべき点があります。
-
あらすじの「要約」と「感想」のバランス
本のあらすじを説明する部分が長すぎると、単なる紹介文になってしまいます。あらすじは簡潔にまとめ、それに対する自分の「感想」や「考え」をしっかりと書くように心がけましょう。
-
「なぜ」を深掘りする
「面白かった」という感想だけでなく、「なぜ面白かったのか」「なぜ感動したのか」という「なぜ」を掘り下げて理由を説明することで、文章に深みが増します。
-
読後感の「発展」
本を読んだことで、自分がどのように成長できたのか、あるいは、これからどのように行動したいのかといった「発展」を示すことで、読書感想文がより価値あるものになります。
-
読書感想文で「差がつく」表現力アップの秘訣
読書感想文で入賞を目指すためには、内容の充実だけでなく、表現力も非常に重要になります。読んだ本の感動や考えたことを、読者にしっかりと伝えるための表現力を磨くことで、あなたの文章は格段に魅力的になります。ここでは、読書感想文で「差がつく」表現力をアップさせるための具体的な秘訣を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
言葉の「選び方」で感情を豊かに表現
同じ出来事でも、使う言葉によって伝わる感情は大きく変わります。
-
感情を的確に表す言葉
「嬉しい」「悲しい」だけでなく、「わくわくする」「胸がいっぱいになる」「ほっとする」「切なくなる」など、より具体的な感情を表す言葉を使い分けることで、読者はあなたの心情をより深く理解できます。
-
情景を描写する言葉
本の場面を読者に「見せる」ように描写するためには、五感を刺激する言葉が効果的です。たとえば、「太陽がキラキラと輝いていた」「風がそっと頬をなでた」といった表現は、情景を鮮やかに浮かび上がらせます。
-
比喩や擬人化の活用
「まるで宝石のような瞳」「星が優しく微笑んでいる」のように、比喩や擬人化を用いることで、文章に彩りが加わり、読者の想像力を掻き立てることができます。
-
-
具体的なエピソードで「説得力」を高める
抽象的な感想だけでなく、具体的なエピソードを交えることで、あなたの感想に説得力を持たせることができます。
-
「なぜそう思ったか」を具体的に
「この登場人物の気持ちがよく分かった」と書くだけでなく、「主人公が友達に謝る場面で、私も過去に同じような経験をして、相手を傷つけてしまったことを思い出し、胸が痛みました」のように、具体的な経験や感情を付け加えることで、読者はあなたの言葉をより信じやすくなります。
-
読書体験と実体験を結びつける
本で読んだ出来事や登場人物の心情を、自分の日常生活や過去の経験と結びつけて書くことで、文章にリアリティが生まれます。「この本を読んで、今まで怖かったことに挑戦する勇気をもらいました。それは、学校で発表する時にも役立ちました。」といったように、具体的な行動の変化を示すと良いでしょう。
-
読書から得た「発見」を明確に
「この本で新しいことを学んだ」というだけでなく、「この本を読むまで、〇〇だと思っていましたが、作者の△△という言葉で、全く違う視点があることに気づかされました」のように、具体的な発見を伝えることで、読書体験の価値を効果的に示すことができます。
-
-
「驚き」や「感動」を伝える言葉選び
読書で味わった「驚き」や「感動」を読者に伝えるためには、感情をストレートに表現する言葉を選ぶことが大切です。
-
感情をストレートに表現する
「すごく感動した」「びっくりした」といったシンプルな言葉でも、それが心からの言葉であれば、読者にもその感情は伝わります。さらに、「涙が止まらなかった」「鳥肌が立った」といった、より具体的な身体的な反応を表現すると、感動がより伝わりやすくなります。
-
読書体験がもたらした「変化」を伝える
本を読む前と後で、自分の気持ちや考え方がどう変わったのかを具体的に描写することで、感動の度合いを伝えることができます。「この本を読む前は、〇〇ということに苦手意識がありましたが、読後、△△という気持ちになり、前向きに考えることができるようになりました。」のように、変化を伝えることが重要です。
-
読者への「問いかけ」
文章の最後に、「皆さんはどう思いましたか?」といった読者への問いかけを入れることで、読書感想文が一方的な情報伝達で終わらず、読者とのコミュニケーションを生み出すことができます。
-
構成要素をマスター!「読書感想文」の骨子を掴む
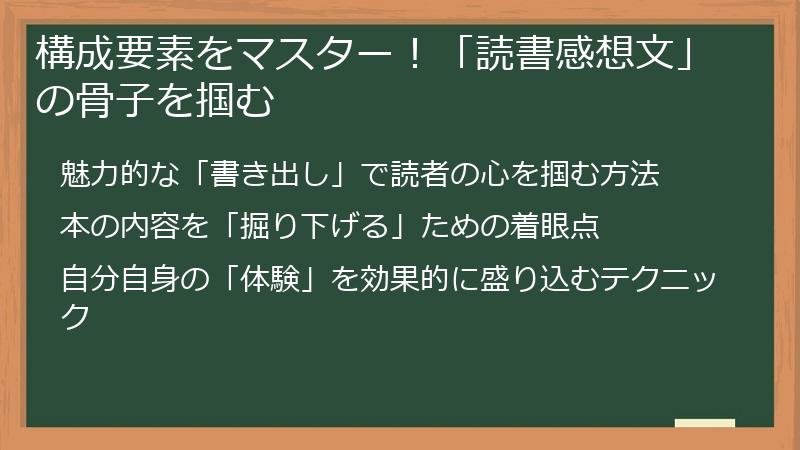
読書感想文の評価を大きく左右するのは、その「構成」です。読んだ本の魅力を最大限に引き出し、自分の考えを効果的に伝えるためには、しっかりとした骨子を掴むことが不可欠です。ここでは、入賞作品に学ぶ、読書感想文の構成要素をマスターするための秘訣を、具体的なステップと共に解説します。
魅力的な「書き出し」で読者の心を掴む方法
読書感想文の「書き出し」は、読者(先生や審査員)に「この感想文を最後まで読みたい」と思わせるための、まさに「顔」となる部分です。ここで読者の興味を引くことができれば、その後の文章もより魅力的に読んでもらえます。ここでは、入賞作品に学ぶ、読者の心を掴む魅力的な書き出しのテクニックを、具体例を交えながら詳しく解説します。
-
読書感想文における「書き出し」の役割
書き出しは、単に本の紹介を始める場所ではありません。
-
読者の興味を惹きつける
「この本にはどんな秘密が隠されているのだろう?」
「この感想文を読んだら、どんなことが分かるのだろう?」
といった読者の好奇心を刺激し、本文を読み進めたいと思わせるフックとなります。 -
感想文全体のトーンを設定する
書き出しの雰囲気は、そのまま感想文全体のトーン(真面目、感動的、ユーモラスなど)を決定づけます。
-
作者の意図や本の魅力を暗示する
本のテーマや、作者が伝えたいメッセージ、あるいは本が持つ独特の雰囲気を、書き出しでさりげなく暗示することができます。
-
-
読者の心を掴む「書き出し」の具体的なパターン
様々なアプローチがありますが、ここでは特に効果的な書き出しのパターンをいくつかご紹介します。
-
「問いかけ」から始める
読者自身に考えさせるような問いかけから入ることで、読者を引き込みやすくなります。例えば、「もしあなたが主人公の〇〇だったら、どんな選択をしますか?」といった問いかけは、読者の関心を一気に引きつけます。
-
「驚きの発見」や「意外な事実」を提示する
本を読んで驚いたことや、読後で初めて気づいた意外な事実などを提示することで、読者の「へぇ!」を引き出すことができます。「この物語には、こんなに驚くべき結末が待っていました。」といったように、期待感を持たせることも有効です。
-
「共感」を誘うエピソードを語る
本を読んだきっかけや、本の内容に触れて自分が感じた個人的な体験談から始めることで、読者は親近感を覚えやすくなります。「私がこの本を手に取ったのは、ちょうど△△という悩みを抱えていた時でした。」といった個人的なエピソードは、読者の共感を呼びやすくなります。
-
印象的な「一文」を引用する
本の中で特に心に残った一文を引用し、そこから自分の感想へと繋げていく方法も、読者の注意を惹きつけるのに効果的です。引用する一文は、感想文のテーマと関連性の高いものを選びましょう。
-
-
「書き出し」で避けるべきこと
効果的な書き出しがある一方で、避けるべき表現も存在します。
-
定型的な挨拶
「この本を読んで、私は〇〇と思いました」といった、あまりにも定型的で当たり障りのない書き出しは、読者の興味を引くことが難しい場合があります。
-
長すぎるあらすじの紹介
書き出しから本のあらすじを延々と説明してしまうと、読者は飽きてしまい、感想文の本体を読む前に疲れてしまう可能性があります。あらすじは本文で簡潔に触れるようにしましょう。
-
曖昧すぎる表現
「この本は面白かったです」といった、具体性のない曖昧な表現は、読者に何も伝わりません。何が、どのように面白かったのかを具体的に示すことが重要です。
-
本の内容を「掘り下げる」ための着眼点
読書感想文で差をつけるためには、単に「面白かった」「感動した」で終わるのではなく、読んだ本の内容を深く掘り下げ、自分なりの視点や考えを盛り込むことが重要です。ここでは、入賞作品に学ぶ、本の内容を掘り下げるための具体的な着眼点を、小学生にも理解できるように詳しく解説します。
-
読書感想文における「内容の掘り下げ」の意義
内容を掘り下げることで、読書体験がより深まり、自分自身の成長や学びにも繋がります。
-
作者の意図を読み解く
作者がこの本を通して、読者に何を伝えたかったのか、どんなメッセージを込めたのかを想像することで、文章に深みが増します。
-
自分自身の考えを深める
本に書かれている出来事や登場人物の言動を通して、自分ならどうするか、なぜそう考えるのかを深く掘り下げることで、読書感想文にオリジナリティが生まれます。
-
読書体験をより豊かなものにする
単に本を「読む」だけでなく、「なぜ?」「どうして?」と問いかけながら読むことで、読書体験そのものがより面白く、価値あるものになります。
-
-
内容を掘り下げるための「着眼点」
本の内容を多角的に捉え、自分なりの視点を見つけるための着眼点を紹介します。
-
登場人物の「行動」と「心理」
登場人物がなぜそのような行動をとったのか、その時の心情はどうだったのかを深く考えてみましょう。特に、主人公だけでなく、脇役の行動や心情にも注目すると、物語の深層が見えてくることがあります。
-
物語の「伏線」や「象徴」
物語の中に隠された伏線や、特定の物や言葉が象徴している意味などを読み解くことで、作者が込めたメッセージに気づくことができます。
-
本が描く「世界観」
物語の舞台となっている時代や場所、社会背景などを理解することで、物語の理解が深まります。その世界観が、登場人物の行動や物語の展開にどのように影響しているのかを考察してみましょう。
-
読書を通して得た「新しい視点」
本を読む前は知らなかったこと、気づかなかったこと、あるいは考え方が変わったことなどを意識的に探してみましょう。それが、あなたの読書感想文における独自の視点となります。
-
-
「掘り下げ」の具体例
例えば、ある物語で主人公が困難に立ち向かう場面があったとします。
-
表面的な理解
「主人公は勇気があってすごいと思った。」
-
掘り下げた理解
「主人公が困難に立ち向かうことができたのは、単に勇敢だからではなく、友達に助けられた経験があったからだと思った。その経験が、彼に諦めない心を植え付けたのではないか。」
のように、「なぜ」そう言えるのか、その背景にある理由や経験を考えることが「掘り下げる」ということです。 -
さらに掘り下げる
「主人公が友達に助けられた時、どんな言葉をかけられたのだろうか?その言葉が主人公の心にどう響いたのだろうか?」のように、さらに細部まで想像を巡らせることで、より深い洞察が得られます。
-
自分自身の「体験」を効果的に盛り込むテクニック
読書感想文は、本の内容に触れるだけでなく、読んだ人の「体験」や「感情」を盛り込むことで、よりパーソナルで共感を呼ぶ文章になります。ここでは、入賞作品にも見られる、自分自身の体験を効果的に盛り込むためのテクニックを、小学生でも実践しやすいように詳しく解説します。
-
読書感想文における「体験」の重要性
自分自身の体験を交えることで、文章にリアリティと深みが増し、読者との共感を生み出しやすくなります。
-
読者との共感を生む
読んだ本の内容と、自分の過去の経験や感情を結びつけて語ることで、読者は「自分もそう感じたことがある」「自分も同じような経験をしたことがある」と感じ、あなたの文章に引き込まれます。
-
感想に説得力を持たせる
具体的な体験談は、あなたの感想に信憑性を持たせます。「感動した」というだけでなく、「なぜ感動したのか」を体験を通して説明することで、読者はその感動の理由を理解しやすくなります。
-
オリジナリティを出す
一人ひとりが持つ体験はユニークです。自分の体験を盛り込むことで、他の人とは違う、あなただけのオリジナルの読書感想文を作成することができます。
-
-
「体験」を効果的に盛り込むためのステップ
読書体験と自分自身の体験をうまく繋げるための具体的なステップをご紹介します。
-
読書中に「関連する体験」を思い出す
本を読んでいる時、登場人物の言動や物語の展開で、過去の自分の経験や感情がふと蘇ってくることがあります。その瞬間に、「これは自分のあの時の経験と似ているな」と感じたことをメモしておきましょう。
-
「感情」で結びつける
物語の登場人物が感じている感情と、自分が過去に感じた同じような感情を繋げてみてください。「主人公が目標を達成できずに悔しがっているのを見て、私も部活でレギュラーになれなかった時の悔しい気持ちを思い出しました。」のように、感情を軸に繋げると自然な文章になります。
-
「行動」や「考え方」の変化に焦点を当てる
本を読んで、自分の行動や考え方に変化があった場合、それを具体的に描写することで、読書体験の成果を伝えることができます。「この本で〇〇という考え方を知り、それ以来、友達との接し方が変わりました。」のように、変化を具体的に示すことが大切です。
-
-
「体験」を盛り込む際の注意点
体験談は効果的ですが、いくつか注意すべき点があります。
-
体験談が「主役」にならないように
あくまで主役は「読んだ本」とその内容に対する感想です。体験談は、その感想を深めるための「スパイス」として活用しましょう。体験談が長すぎると、本の紹介がおろそかになってしまいます。
-
「普遍性」を意識する
自分の体験談を書く際には、読者も共感しやすいように、ある程度普遍的な感情や出来事を題材にすると良いでしょう。あまりにも個人的すぎる体験談は、読者に伝わりにくくなる可能性があります。
-
「誠実さ」を大切にする
体験談は、正直に、そして誠実に書きましょう。無理に話を大きくしたり、事実と異なることを書いたりする必要はありません。
-
入賞作品に学ぶ!「読書感想文」の表現力を極める
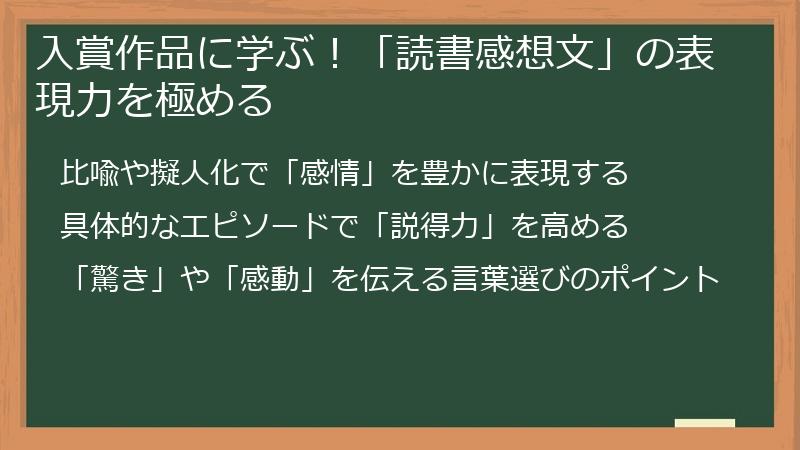
読書感想文で入賞を目指すためには、内容の充実だけでなく、読んだ本の感動や考えたことを、読者にしっかりと伝えるための「表現力」が不可欠です。ここでは、入賞作品に見られる、表現力を豊かにするための具体的なテクニックを、小学生にも分かりやすく解説します。
比喩や擬人化で「感情」を豊かに表現する
読書感想文で読者に感動や共感を与えるためには、登場人物の気持ちや、物語の情景を、より鮮やかに、そして豊かに表現することが大切です。ここでは、比喩や擬人化といった表現技法を使い、読書感想文の「感情表現」を格段に豊かにするための具体的な方法を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
比喩・擬人化の基本的な意味と効果
比喩や擬人化は、文章に彩りを加え、読者の想像力を掻き立てるための強力なツールです。
-
比喩(たとえ)
「~のような」「~みたいだ」といった言葉を使い、あるものを別のものに例えて表現する方法です。これにより、抽象的な物事を具体的に、あるいは詩的に表現することができます。
-
擬人化
人間ではないもの(動物、植物、物、自然現象など)が、人間のように考えたり、行動したり、話したりするように表現する方法です。これにより、無機質なものに生命感を与えることができます。
-
-
読書感想文で使える「比喩」の具体例
本の内容や、自分の感情を表現する際に、比喩を効果的に使うための例を見てみましょう。
-
感情を表現する比喩
「喜びが泉のように湧き上がってきた。」
「悲しみは鉛のように重く、心に沈んだ。」
このように、抽象的な感情を、具体的なイメージに例えることで、読者はその感情の強さをよりリアルに感じ取ることができます。 -
情景を描写する比喩
「夜空にはダイヤモンドのような星が輝いていた。」
「朝露は小さな真珠のように葉の上で光っていた。」
といった表現は、情景をより美しく、幻想的に描写します。 -
登場人物の様子を描写する比喩
「彼女の笑顔は太陽のように明るかった。」
「彼の声はベルベットのように滑らかだった。」
このように、人物の様子を比喩で表現することで、その人物の印象を読者に強く印象づけることができます。
-
-
読書感想文で使える「擬人化」の具体例
擬人化は、物語の世界をより生き生きとさせるのに役立ちます。
-
自然現象を擬人化する
「風が優しく頬を撫でていった。」
「雨粒が窓を叩くように、激しく降っていた。」
自然がまるで意思を持っているかのように描写することで、情景に感情が宿ります。 -
物を擬人化する
「古い時計が時を刻むように、静かに息をしていた。」
「本棚の古い本が、何かを語りかけるようにじっとこちらを見ていた。」
inanimate objects seem to have a life of their own. -
物語の「テーマ」を擬人化する
「勇気は、私を励ますようにそっと背中を押してくれた。」
「希望は、暗闇の中で灯る小さな光のように、道を示してくれた。」
物語の抽象的なテーマを擬人化することで、読者はそのテーマが自分にとってどのような意味を持つのかをより深く理解できます。
-
具体的なエピソードで「説得力」を高める
読書感想文は、単なる感想の羅列ではなく、読んだ本に対するあなたの「考え」や「感じ方」を、読者に納得してもらえるように伝えることが重要です。そのためには、抽象的な感想だけでなく、具体的なエピソードを交えることが「説得力」を高める鍵となります。ここでは、入賞作品に学ぶ、具体的なエピソードで説得力を高めるための方法を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
説得力のある読書感想文とは
説得力のある読書感想文とは、読んだ人に「なるほど、そういう考え方もあるのか」「確かに、そのように感じるのも無理はない」と思わせる文章のことです。
-
読者の共感を得る
あなたの体験や感想が、読者自身の経験や感情と重なる部分があると、共感が生まれ、説得力が増します。
-
論理的な説明
「なぜそう思ったのか」「なぜ感動したのか」といった理由を、具体的な根拠(エピソードや本の描写)とともに説明することで、あなたの意見に信憑性が生まれます。
-
感情と論理のバランス
感動したという感情だけでなく、その感情に至った理由を論理的に説明することで、より深みのある文章になります。
-
-
「説得力」を高めるためのエピソードの選び方
どのようなエピソードを選ぶかが、説得力を大きく左右します。
-
本の内容に「直接」関連するエピソード
物語の特定の場面、登場人物の行動、あるいは心に残った一文など、本の内容と密接に関連するエピソードを中心に選びましょう。例えば、主人公が困難に立ち向かう場面を読んで、自分が過去に似たような困難を乗り越えた経験を話す、といった具合です。
-
「自分の感情」が動いた瞬間
「この場面を読んで、すごく嬉しかった」「この言葉にハッとさせられた」といった、自分の感情が大きく動いた瞬間をエピソードとして語ると、読者はその感情を共有しやすくなります。
-
「具体的な描写」を伴うエピソード
「楽しかった」というだけでなく、「友達と笑いながら、〇〇を食べて、△△という話で盛り上がった」のように、具体的な情景や行動を描写することで、読者はそのエピソードを鮮明にイメージできます。
-
-
「説得力」のあるエピソードの伝え方
選んだエピソードを効果的に伝えるための方法です。
-
「なぜ」そのエピソードを選んだのかを明確にする
単にエピソードを話すだけでなく、「このエピソードを選んだのは、主人公の〇〇という気持ちが、当時の私自身の気持ちと重なったからです。」のように、なぜそのエピソードが重要なのか、その理由を説明しましょう。
-
エピソードから「学び」や「気づき」を導き出す
エピソードを語った後で、そこから自分が何を学び、どのような気づきを得たのかを明確に示します。「この経験を通して、諦めないことの大切さを学びました。」のように、エピソードと学びを結びつけることが重要です。
-
物語の「テーマ」とエピソードを結びつける
選んだエピソードが、本の中心的なテーマやメッセージとどのように関連しているのかを説明することで、文章全体のまとまりが良くなり、説得力が増します。
-
「驚き」や「感動」を伝える言葉選びのポイント
読書感想文で読者を引きつけ、心に残る文章にするためには、自分が感じた「驚き」や「感動」を、読者にも「追体験」してもらえるような言葉を選ぶことが重要です。ここでは、入賞作品に学ぶ、驚きや感動を効果的に伝えるための言葉選びのポイントを、小学生にも分かりやすく解説します。
-
「感動」を伝える言葉の力
感動を伝える言葉は、読者との感情の共有を可能にします。
-
感情の「解像度」を上げる
「感動した」という一言だけでなく、「胸が熱くなった」「涙が止まらなかった」「心が震えた」といった、より具体的な感情を表す言葉を使うことで、感動の度合いを読者に正確に伝えることができます。
-
読書体験の「深さ」を示す
感動したという事実だけでなく、なぜ感動したのか、その感動が自分にどのような影響を与えたのかを説明することで、読書体験の深さを示すことができます。
-
読後感の「余韻」を大切にする
読書を終えた後も、心に残った感動や考えが、すぐには消えない「余韻」があります。その余韻を言葉にすることで、感動がより長続きし、読者にも伝わります。
-
-
「驚き」を伝えるための言葉選び
予期せぬ展開や、新しい発見に対する「驚き」は、読者の興味を強く引きます。
-
意外性や「まさか」の感情を表現する
「まさか、そんな結末が待っているとは思いませんでした。」
「この登場人物が、実は〇〇だったなんて、驚きました。」
といった表現は、読者に驚きを共有させます。 -
発見の「新鮮さ」を伝える
「この本を読むまで、〇〇ということを全く知りませんでした。」
「作者の〇〇という言葉に、目から鱗が落ちるような思いでした。」
のように、新しい発見の新鮮さや、それによって得られた知識の価値を伝えることが大切です。 -
比喩や擬人化の活用
「驚きで、まるで体が石になったかのように動けなかった。」
「心臓がドキドキと、太鼓のように鳴り響いた。」
といった比喩表現は、驚きの大きさを視覚的・聴覚的に伝えるのに効果的です。
-
-
「感動」を伝えるための言葉選び
感動は、登場人物への共感や、物語のメッセージに触れた時に生まれます。
-
登場人物への「共感」を表現する
「主人公の〇〇が、どんなに辛い状況でも諦めずに努力する姿を見て、私も勇気をもらいました。」
「△△という言葉が、まるで私自身に語りかけているように感じて、胸がいっぱいになりました。」
のように、登場人物の心情に寄り添い、自分の感情と重ねて表現することで、感動が伝わります。 -
物語の「メッセージ」に触れる
「この本を通して、友達を大切にすることの重要性を学びました。」
「〇〇という言葉は、これからの人生で大切にしたい、私の宝物になりました。」
のように、物語が伝えるメッセージが、自分にどのような影響を与えたかを具体的に示すことが、感動を伝える鍵となります。 -
「五感」で感じたことを言葉にする
感動した場面の情景や、登場人物の表情、声の調子などを五感を通して描写することで、読者はその感動をよりリアルに感じることができます。「主人公の泣き顔を見て、私も思わず涙ぐんでしまった。」といった描写は、読者の感情を揺さぶります。
-
テーマ別!「読書感想文」で入賞を狙うためのポイント
読書感想文のテーマ設定は、作品の評価に大きく影響します。ここでは、入賞作品でよく見られる、特定のテーマに焦点を当てた書き方や、ジャンル別の表現のコツを解説します。あなたの読書体験を、より魅力的な読書感想文に仕上げるための具体的なヒントを提供します。
物語の「主人公」に共感!「人物」に焦点を当てる書き方
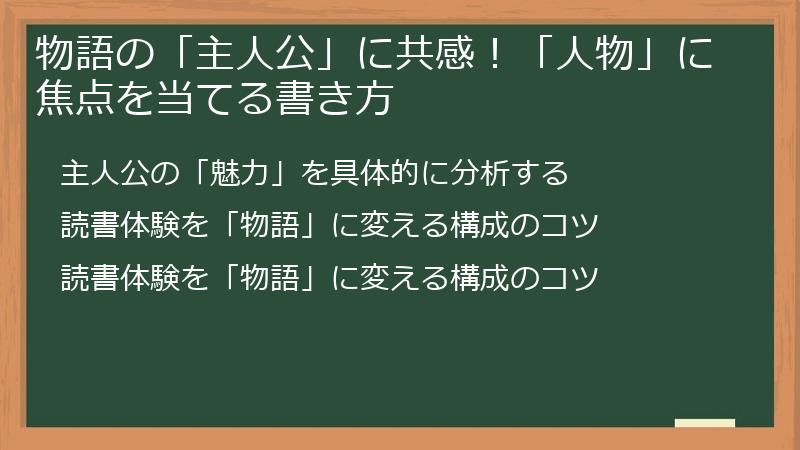
読書感想文で入賞を目指す上で、物語の「主人公」に焦点を当てて書くことは、読者からの共感を得やすく、高い評価に繋がりやすい方法の一つです。ここでは、主人公の魅力や、その成長、葛藤に深く迫り、読書感想文で「人物」に焦点を当てる書き方のコツを、具体的にお伝えします。
主人公の「魅力」を具体的に分析する
物語の主人公に焦点を当てる読書感想文では、その主人公がなぜ魅力的なのか、読者の心に響くのはどのような点なのかを具体的に分析することが重要です。ここでは、主人公の隠された魅力や、読者が共感するポイントを深く掘り下げるための分析方法を解説します。
-
主人公の「人間味」に注目する
完璧すぎる主人公よりも、時には失敗したり、悩んだりする「人間味」のある主人公の方が、読者の共感を呼びやすい傾向があります。
-
弱さや葛藤を理解する
主人公が抱える弱さや、乗り越えようとする葛藤は、読者自身の経験と重なる部分が多く、共感を生む強力な要素となります。主人公がどのような状況で、どんな悩みを抱えているのかを深く理解しましょう。
-
失敗から学ぶ姿勢
失敗から落ち込むだけでなく、そこから学び、成長しようとする主人公の姿勢は、読者に勇気や希望を与えます。主人公の失敗とその後の行動を丁寧に追ってみましょう。
-
-
主人公の「行動」の裏にある「心理」を探る
主人公がどのような行動をとったのか、そしてその行動の裏にはどのような心理が働いていたのかを考察することで、主人公への理解が深まります。
-
「なぜ」その行動をとったのか
物語の中で主人公がとった印象的な行動について、「なぜ主人公はあのような行動をとったのだろうか?」と問いかけてみましょう。その行動の背景にある主人公の考えや、置かれている状況を推測することが大切です。
-
登場人物との「関わり」から見える心理
他の登場人物との会話や関わりを通して、主人公の隠された一面や、本音が見えてくることがあります。特に、主人公が信頼する人物とのやり取りに注目してみましょう。
-
-
読者が「共感」するポイント
読者が主人公に共感するポイントは、多様ですが、一般的には以下のような点が多く見られます。
-
自分と似た境遇や感情
主人公の抱える悩みや、感じている感情が、自分自身の経験や感情と重なる時、読者は強く共感します。
-
主人公の「成長」
物語を通して主人公が困難を乗り越え、人間的に成長していく姿は、読者に感動と勇気を与え、共感を呼びます。
-
主人公の「信念」や「価値観」
主人公が大切にしている信念や、譲れない価値観は、読者に強い印象を与え、共感の対象となることがあります。
-
読書体験を「物語」に変える構成のコツ
読書感想文は、単に読んだ本のあらすじを紹介するものではありません。読んだ本を通して自分がどのように感じ、考え、何を発見したのかを、読者に伝わるように「物語」として再構築することが大切です。ここでは、入賞作品に学ぶ、読書体験を魅力的な「物語」に変えるための構成のコツを、具体的なステップと共に解説します。
-
読書感想文の基本的な構成
ほとんどの読書感想文は、以下の3つの要素で構成されています。
-
導入(書き出し)
読者の興味を引きつけ、「この本を読んだらどうなるのだろう?」と思わせるような書き出しが重要です。本の魅力や、自分がこの本に興味を持ったきっかけなどを簡潔に伝えます。
-
本文(内容の紹介と感想)
本のあらすじを簡潔に紹介しつつ、自分が特に感動した場面や、心に残った言葉、登場人物の行動などを具体的に掘り下げて感想を述べます。ここが読書感想文の最も重要な部分であり、あなたの「考え」を伝える場です。
-
結論(まとめ)
読書を通して得た学びや、自分の成長、今後どうしていきたいかなどをまとめて締めくくります。本を読む前と読んだ後で、自分がどう変わったのかを明確に伝えられると、より説得力のある文章になります。
-
-
魅力的な「物語」にするための構成テクニック
読書体験を単なる感想文で終わらせず、「物語」として読者に届けるための具体的な構成テクニックを紹介します。
-
読書前の「期待感」を演出
「この本はどんな物語なんだろう?」という読者の好奇心を刺激するような書き出しを工夫しましょう。本のタイトルや表紙から感じたこと、あるいは、この本を選んだ理由などを共有するのも効果的です。
-
「起承転結」を意識した展開
読んだ本の内容を、単なる時系列で追うのではなく、「起承転結」のような物語の展開を意識して構成すると、読者が内容を理解しやすくなります。特に、物語の「転」にあたる部分、つまり、何かしらの変化や事件が起こる場面に焦点を当てて、そこでの登場人物の心情を深く掘り下げてみましょう。
-
「共感」を生むエピソードの選び方
自分が物語の登場人物になったつもりで、その行動や心情を追体験し、共感した部分を具体的に描写することで、読者もその感情を共有しやすくなります。たとえば、「主人公の○○が、△△に悩んでいた時、私も同じように苦しい気持ちになった」といったように、自分自身の感情と結びつけて書くことが重要です。
-
-
構成を考える上での注意点
入賞作品に近づくためには、構成を考える上でいくつか注意すべき点があります。
-
あらすじの「要約」と「感想」のバランス
本のあらすじを説明する部分が長すぎると、単なる紹介文になってしまいます。あらすじは簡潔にまとめ、それに対する自分の「感想」や「考え」をしっかりと書くように心がけましょう。
-
「なぜ」を深掘りする
「面白かった」という感想だけでなく、「なぜ面白かったのか」「なぜ感動したのか」という「なぜ」を掘り下げて理由を説明することで、文章に深みが増します。
-
読後感の「発展」
本を読んだことで、自分がどのように成長できたのか、あるいは、これからどのように行動したいのかといった「発展」を示すことで、読書感想文がより価値あるものになります。
-
読書体験を「物語」に変える構成のコツ
読書感想文は、単に読んだ本のあらすじを紹介するものではありません。読んだ本を通して自分がどのように感じ、考え、何を発見したのかを、読者に伝わるように「物語」として再構築することが大切です。ここでは、入賞作品に学ぶ、読書体験を魅力的な「物語」に変えるための構成のコツを、具体的なステップと共に解説します。
-
読書感想文の基本的な構成
ほとんどの読書感想文は、以下の3つの要素で構成されています。
-
導入(書き出し)
読者の興味を引きつけ、「この本を読んだらどうなるのだろう?」と思わせるような書き出しが重要です。本の魅力や、自分がこの本に興味を持ったきっかけなどを簡潔に伝えます。
-
本文(内容の紹介と感想)
本のあらすじを簡潔に紹介しつつ、自分が特に感動した場面や、心に残った言葉、登場人物の行動などを具体的に掘り下げて感想を述べます。ここが読書感想文の最も重要な部分であり、あなたの「考え」を伝える場です。
-
結論(まとめ)
読書を通して得た学びや、自分の成長、今後どうしていきたいかなどをまとめて締めくくります。本を読む前と読んだ後で、自分がどう変わったのかを明確に伝えられると、より説得力のある文章になります。
-
-
魅力的な「物語」にするための構成テクニック
読書体験を単なる感想文で終わらせず、「物語」として読者に届けるための具体的な構成テクニックを紹介します。
-
読書前の「期待感」を演出
「この本はどんな物語なんだろう?」という読者の好奇心を刺激するような書き出しを工夫しましょう。本のタイトルや表紙から感じたこと、あるいは、この本を選んだ理由などを共有するのも効果的です。
-
「起承転結」を意識した展開
読んだ本の内容を、単なる時系列で追うのではなく、「起承転結」のような物語の展開を意識して構成すると、読者が内容を理解しやすくなります。特に、物語の「転」にあたる部分、つまり、何かしらの変化や事件が起こる場面に焦点を当てて、そこでの登場人物の心情を深く掘り下げてみましょう。
-
「共感」を生むエピソードの選び方
自分が物語の登場人物になったつもりで、その行動や心情を追体験し、共感した部分を具体的に描写することで、読者もその感情を共有しやすくなります。たとえば、「主人公の○○が、△△に悩んでいた時、私も同じように苦しい気持ちになった」といったように、自分自身の感情と結びつけて書くことが重要です。
-
-
構成を考える上での注意点
入賞作品に近づくためには、構成を考える上でいくつか注意すべき点があります。
-
あらすじの「要約」と「感想」のバランス
本のあらすじを説明する部分が長すぎると、単なる紹介文になってしまいます。あらすじは簡潔にまとめ、それに対する自分の「感想」や「考え」をしっかりと書くように心がけましょう。
-
「なぜ」を深掘りする
「面白かった」という感想だけでなく、「なぜ面白かったのか」「なぜ感動したのか」という「なぜ」を掘り下げて理由を説明することで、文章に深みが増します。
-
読後感の「発展」
本を読んだことで、自分がどのように成長できたのか、あるいは、これからどのように行動したいのかといった「発展」を示すことで、読書感想文がより価値あるものになります。
-
ジャンル別「読書感想文」の書き方:初心者でも安心
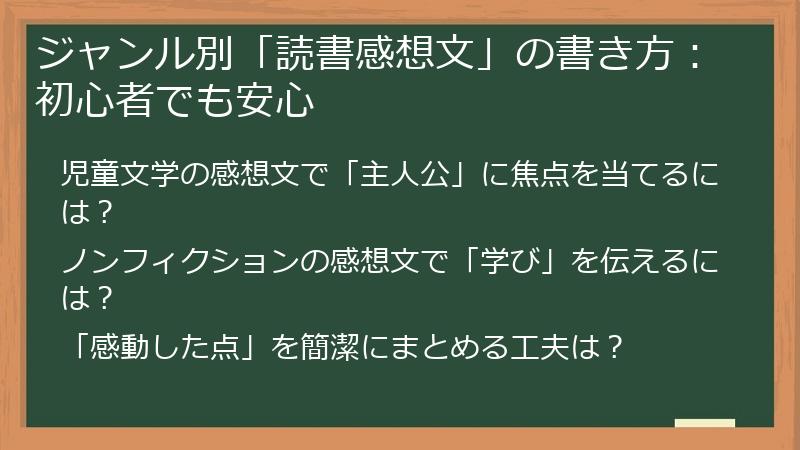
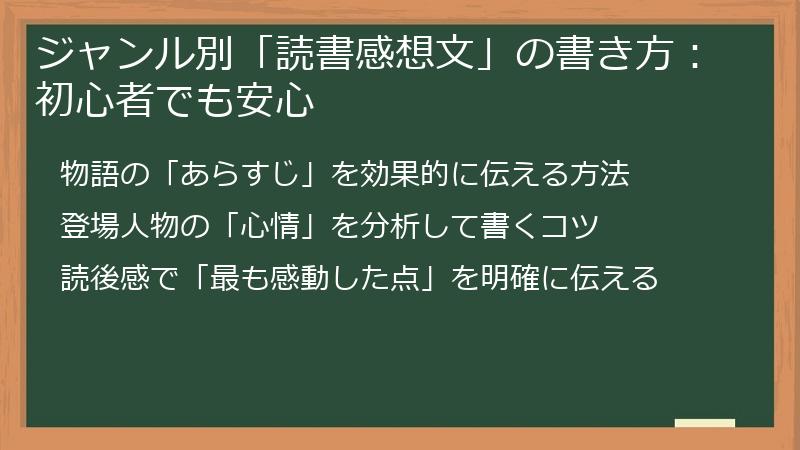
読書感想文の書き方は、読む本のジャンルによって、焦点を当てるべきポイントや表現方法が異なります。ここでは、児童書から物語、ノンフィクションまで、様々なジャンルの本に対応できる、初心者でも安心の書き方のコツを、具体的なアドバイスと共に紹介します。
物語の「あらすじ」を効果的に伝える方法
読書感想文において、物語のあらすじを伝えることは、読者があなたの感想を理解するための基礎となります。しかし、あらすじの紹介が長すぎたり、単調になったりすると、読者の興味を失わせてしまう可能性があります。ここでは、物語のあらすじを効果的に伝え、読者の関心を惹きつけ続けるための方法を、具体例を交えながら解説します。
-
あらすじ紹介の「目的」を理解する
読書感想文におけるあらすじ紹介の目的は、本の内容を「説明」することだけではありません。
-
読者に「興味」を持たせる
あらすじを紹介する際は、物語の最も魅力的な部分や、読者の興味を引くであろう要素を盛り込むことで、読者に「もっと読みたい」と思わせることが大切です。
-
自分の「感想」への導入とする
あらすじの紹介は、その後に続く自分の感想や意見への自然な橋渡しとなります。どの部分に焦点を当てて、なぜそれを紹介するのかを意識しましょう。
-
物語の「要点」を明確にする
物語の核となる出来事や、主人公の置かれている状況などを簡潔に伝えることで、読者はあなたの感想をより深く理解できます。
-
-
効果的な「あらすじ」の伝え方
あらすじを単に紹介するのではなく、読者の心に残るように伝えるためのコツを紹介します。
-
「核心」となる部分に絞る
物語の全てを網羅する必要はありません。主人公が置かれている状況、物語の始まりとなる出来事、あるいは、主人公が抱える最も大きな葛藤など、「この物語の要はここだ」という部分に焦点を絞って紹介しましょう。
-
「読者の感情」を揺さぶる言葉を選ぶ
あらすじを紹介する際にも、感情に訴えかける言葉を選ぶことで、読者の興味を惹きつけることができます。「主人公は、ある日突然、驚くべき出来事に巻き込まれます。」といった表現は、読者の好奇心を掻き立てます。
-
「誰が」「いつ」「どこで」「何をした」を明確に
物語の基本的な要素(誰が、いつ、どこで、何をした)を明確に伝えることで、読者は物語の状況をスムーズに理解できます。
-
「伏線」を意識させる
物語の結末に繋がるような伏線や、謎めいた出来事を匂わせるように紹介することで、読者の「先が気になる」という気持ちを掻き立てることができます。
-
-
「あらすじ」紹介の長さとタイミング
あらすじの紹介は、長すぎず、短すぎず、適切な長さにすることが重要です。
-
「短く、簡潔に」を心がける
一般的に、読書感想文のあらすじ紹介は、全体の1/4~1/3程度に収めるのが目安です。読者の集中力が途切れないように、簡潔にまとめることを意識しましょう。
-
「本文」で具体的に触れる
あらすじで触れた内容の、特に印象に残った場面や、自分の感想に繋がる部分については、本文でさらに詳しく掘り下げて描写すると、より効果的です。
-
「書き出し」で簡潔に紹介し、「本文」で深掘りする
書き出しで物語の導入部分を簡潔に紹介し、本文でその部分に触れて自分の感想を述べる、という流れは、読者を引き込みやすい構成です。
-
登場人物の「心情」を分析して書くコツ
読書感想文で読者の心を掴むためには、登場人物の行動だけでなく、その「心情」を深く分析し、自分の言葉で表現することが不可欠です。ここでは、入賞作品にも見られる、登場人物の心情を分析し、読書感想文に効果的に盛り込むためのコツを、小学生にも分かりやすく解説します。
-
「心情分析」の重要性
登場人物の心情を理解し、それを文章にすることで、読書体験がより豊かになります。
-
物語への「没入感」を高める
登場人物の喜びや悲しみ、怒りなどを共有することで、読者は物語の世界に深く没入することができます。
-
読者との「共感」を生む
登場人物の抱える悩みや葛藤が、自分自身の経験と重なる時、読者は強く共感し、物語をより自分事として捉えることができます。
-
物語の「テーマ」への理解を深める
登場人物の心情の変化は、物語のテーマや作者のメッセージを理解するための重要な手がかりとなります。
-
-
「心情」を分析するための着眼点
登場人物の心情を理解するために、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。
-
「行動」の裏にある「感情」
主人公がどのような行動をとっているかだけでなく、「なぜその行動をとったのか」という動機や、その時の感情を想像することが大切です。例えば、勇気を出して一歩踏み出す行動の裏には、恐怖心と戦う心情があるかもしれません。
-
「言葉」に表れない「本音」
登場人物が口にする言葉だけでなく、表情や仕草、あるいは沈黙などに隠された本音や感情に注目してみましょう。作者が描写する細かな部分に、心情のヒントが隠されています。
-
「他の登場人物」との関わり
他の登場人物との会話や関係性を通して、主人公の心情がどのように影響を受けているのかを観察することも重要です。誰かと話すことで、本音を打ち明けたり、逆に隠したりすることがあります。
-
「状況の変化」による心情の変化
物語が進むにつれて、登場人物の置かれている状況が変化します。その変化が、登場人物の心情にどのような影響を与えているのかを追うことで、キャラクターの深みが増します。
-
-
「心情」を文章で表現するコツ
分析した登場人物の心情を、読者に効果的に伝えるための表現方法です。
-
「感情を表す言葉」を具体的に使う
「悲しい」だけでなく、「胸が締め付けられるようだった」「心が折れそうになった」など、より具体的で感情の深さを表す言葉を選びましょう。
-
「比喩」や「擬人化」を活用する
登場人物の心情を、比喩や擬人化を用いて表現することで、読者はその感情をより鮮明にイメージすることができます。「彼の心は、嵐に巻き込まれた小舟のようだった。」といった表現は、心情の激しさを伝えます。
-
「自分の体験」と結びつけて語る
登場人物の心情を、自分自身の過去の経験や感情と結びつけて語ることで、読者は共感しやすくなります。「主人公の孤独感は、私が転校して友達がいなかった時の気持ちと重なりました。」といった表現は、説得力があります。
-
「なぜそう思ったのか」を説明する
単に「主人公の〇〇という気持ちが分かった」と書くだけでなく、「主人公が△△という状況で、どうしてそのような気持ちになったのか」という理由を具体的に説明することで、あなたの分析の深さを示すことができます。
-
読後感で「最も感動した点」を明確に伝える
読書感想文の締めくくりである「読後感」は、読んだ本全体を通して、あなたが最も強く感じたこと、心に残ったことを伝えるための重要な部分です。ここでは、入賞作品に学ぶ、読後感で「最も感動した点」を明確に伝え、読者に強い印象を与えるための方法を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
「読後感」で伝えるべきこと
読後感は、読書体験の集大成です。
-
最も心に残った「テーマ」や「メッセージ」
本全体を通して、あなたが最も重要だと感じたテーマや、作者が伝えようとしたメッセージを改めて強調します。
-
読書による「自分自身の変化」
本を読む前と読んだ後で、自分の考え方や感じ方がどのように変わったのか、あるいは、どのような学びを得たのかを具体的に示します。
-
「感動」や「共感」の核心
あなたが物語のどの部分に、どのように感動し、共感したのか、その核心を改めて伝えることで、読者もその感動を共有しやすくなります。
-
-
「最も感動した点」を明確にするためのステップ
読後感で最も感動した点を明確に伝えるための具体的なステップです。
-
読書中に「感動した箇所」を特定する
読書中に、特に心に響いた場面、登場人物の言葉、あるいは物語の結末などをマークしておきましょう。それが、あなたが最も感動した点を見つけるための手がかりとなります。
-
「なぜ」それが感動したのかを掘り下げる
特定した箇所について、「なぜそれが自分にとって感動的だったのか?」という理由を深く考えてみましょう。それは、登場人物の心情への共感なのか、物語のメッセージなのか、あるいは自分自身の経験との関連なのか、その理由を明確にすることが大切です。
-
感動を「具体的な言葉」で表現する
「感動した」というだけでなく、「その場面を読んだ時、自分の心も温かくなるような気持ちになった。」「主人公の〇〇という言葉は、まるで私自身に語りかけているようで、勇気をもらった。」のように、具体的な言葉で感動の質や、それが自分に与えた影響を表現しましょう。
-
-
「感動した点」を効果的に伝えるための表現方法
感動した点を、読者にしっかりと伝えるための表現の工夫です。
-
「導入」で提示したテーマと結びつける
もし感想文の導入で特定のテーマに触れていた場合、結論ではそのテーマと、自分が最も感動した点がどのように結びついているのかを説明すると、文章全体にまとまりが出ます。
-
「体験談」と絡めて共感を呼ぶ
感動した点を、自分自身の体験談と結びつけて語ることで、読者はその感動をより身近に感じることができます。「この本を読んで、〇〇という大切さを改めて感じました。それは、私が以前△△という経験をした時にも強く思ったことだからです。」のように、体験を交えることで説得力が増します。
-
「未来への影響」を示す
その感動が、今後の自分の生活や考え方にどのような影響を与えてくれるのかを示すことで、読書体験の価値をさらに高めることができます。「この感動を胸に、私も〇〇のようなことに挑戦してみたいと思いました。」といった前向きな言葉で締めくくると、読後感に希望が生まれます。
-
書けないを「書けた!」に!「読書感想文」の悩み解決法
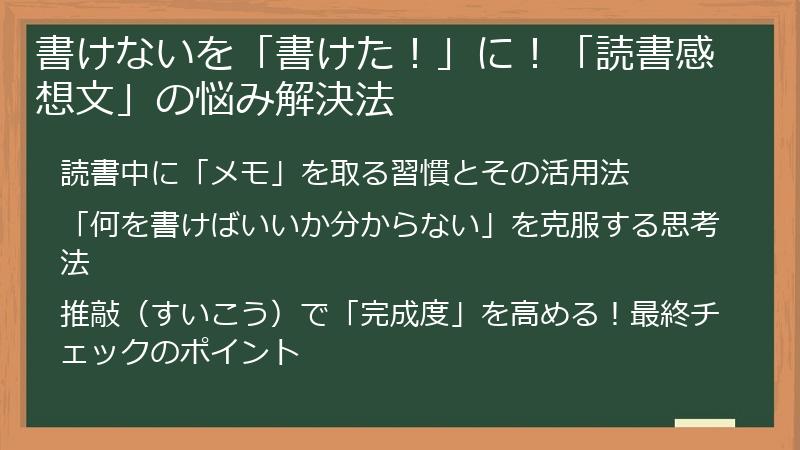
読書感想文を書く上で、「何を書けばいいか分からない」「どう書いたら評価されるのか不安」といった悩みを抱える人は少なくありません。ここでは、そんな「書けない」という悩みを「書けた!」という自信に変えるための、具体的な解決策と、書くためのコツを、小学生の皆さんに分かりやすく解説します。
読書中に「メモ」を取る習慣とその活用法
読書感想文を書く際に、読書中の「メモ」は非常に強力な武器となります。印象に残った箇所、疑問に思ったこと、自分の考えなどを記録しておくことで、後で感想文を書く際に、内容を思い出しやすく、また、より深く掘り下げるための材料となります。ここでは、読書中にメモを取る習慣の重要性と、その効果的な活用法を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
読書中の「メモ」の重要性
読書中のメモは、読書体験をより有意義にするための様々な効果があります。
-
内容の「定着」を助ける
本を読んでいる最中にメモを取ることで、物語の細部や登場人物の名前、印象的なセリフなどを記憶に定着させやすくなります。
-
「思考」を整理する
読んでいる最中に湧き上がる疑問や、自分の考え、感想などを書き出すことで、思考を整理し、論理的な文章構成の基礎を作ることができます。
-
「感想文の材料」を蓄積する
メモは、感想文を書く際に「何を書けばいいか分からない」という状況を打破する、貴重な材料の宝庫となります。
-
読書への「集中力」を高める
メモを取るという能動的な行為は、受動的に読むだけよりも、読書への集中力を高める効果があります。
-
-
効果的な「メモ」の取り方
どのようなメモを取るのが効果的なのでしょうか。
-
「気になった言葉」や「印象的なセリフ」
「この言葉、心に残ったな」「こんなセリフ、自分も言ってみたいな」と思った言葉やセリフは、そのまま書き留めておきましょう。後で感想文の引用にも使えます。
-
「登場人物の心情」や「行動」
主人公や他の登場人物が、どのような気持ちで、なぜそのような行動をとったのかを考えたことは、メモしておくと良いでしょう。特に、自分の感情と重なった部分は重要です。
-
「疑問」や「不思議に思ったこと」
「なぜだろう?」「これはどういう意味だろう?」と疑問に思ったことは、そのまま書き留めておきましょう。感想文で、その疑問を掘り下げて書くことができます。
-
「自分の考え」や「感想」
「これは自分も経験あるな」「こんな時、自分だったらこうするかも」といった、読書を通して自分の頭に浮かんだ考えや感想も、積極的にメモしましょう。
-
「印象的な場面」の描写
情景が目に浮かぶような印象的な場面があれば、その場面の描写を簡単にメモしておくと、後で文章に活かしやすくなります。
-
-
「メモ」を感想文に活用する方法
取ったメモを、どのように読書感想文に活かせば良いでしょうか。
-
「書き出し」や「本文」の材料にする
メモしておいた印象的なセリフや、疑問に思ったこと、自分の考えなどは、感想文の書き出しや本文の材料として活用できます。
-
「感動した点」を具体的に説明する
メモに書き留めた「なぜ感動したのか」という理由を、感想文で具体的に説明することで、感動の深さを読者に伝えることができます。
-
「構成」を考えるヒントにする
メモを見返しながら、どのような順番で書けば、自分の考えが伝わりやすいかを考えることができます。特に、疑問点から入って、その答えや自分の考えを述べる構成は効果的です。
-
「推敲」の際に役立てる
書き終えた感想文を読み返す際に、メモと照らし合わせることで、書き漏らしている点や、もっと掘り下げられる点がないかを確認することができます。
-
「何を書けばいいか分からない」を克服する思考法
読書感想文で最も多くの小学生が悩むのが、「何を書けばいいか分からない」という問題です。本を読んだのに、いざ書こうとすると言葉が出てこない…。そんな悩みを克服し、書くための材料を見つけるための思考法を、ここでは具体的に解説します。
-
「何を書けばいいか分からない」状態の原因
この状態になる原因は、いくつか考えられます。
-
「感想」と「あらすじ」の混同
本の内容をそのまま書き写そうとしてしまい、自分自身の「感想」や「考え」をどう盛り込めば良いか分からなくなってしまうケースです。
-
「感動」や「学び」を言語化できない
本を読んで何かを感じていても、それを的確な言葉で表現する方法が分からず、頭の中だけで終わってしまうことがあります。
-
「完璧」を求めすぎる
「入賞できるような素晴らしい文章を書かなければ」というプレッシャーから、最初の一歩が踏み出せないことがあります。
-
「読書」と「書く」ことの結びつきが弱い
読書体験を、感想文を書くための「材料集め」として捉える視点が不足している場合も、何を書けば良いか分からなくなる原因となります。
-
-
「書けない」を克服する思考法
これらの悩みを解決するための、具体的な思考法をご紹介します。
-
「読書ノート」を「感想文の設計図」にする
読書中に取ったメモを、単なる記録ではなく、「感想文の設計図」として捉え直しましょう。メモの中から、感想文の「導入」になりそうなこと、「本文」で詳しく書きたいこと、「結論」に繋がる考えなどを整理していきます。
-
「問いかけ」から始める
「この本で一番心に残ったことは何?」「主人公の〇〇が△△だった時、自分はどう感じた?」といった、自分自身への簡単な問いかけから始めると、思考が整理されやすくなります。
-
「感情」を言葉にする練習
「嬉しい」「楽しい」だけでなく、「わくわくした」「ホッとした」「ドキドキした」「切なくなった」など、具体的な感情を表す言葉を意識して使ってみましょう。辞書などを活用するのも良い方法です。
-
「誰かに話す」つもりで書く
「この本について、友達や家族に説明するならどう話すかな?」と想像しながら書くと、自然な言葉で、分かりやすく書くことができます。
-
「完璧」を目指さず、「まず書く」ことを重視する
最初から完璧な文章を書こうとせず、まずは思いつくままに書き出してみることが大切です。後で修正すれば良いのです。
-
-
「感想文のネタ」を見つけるためのヒント
「何を書けばいいか分からない」という状況を打開するための、具体的なネタの見つけ方です。
-
「一番〇〇だったこと」を探す
「一番心に残った登場人物は?」「一番面白かった場面は?」「一番驚いたのは?」など、「一番」に焦点を当てることで、感想文の核となる部分が見えてきます。
-
「読書前と読後」の変化を比べる
本を読む前はどんなことを思っていたか、そして読んだ後に何を感じ、どう考えが変わったかを比べることで、自分自身の変化を感想文のテーマにできます。
-
「本と自分」の共通点・相違点を見つける
登場人物の行動や考え方と、自分自身の経験や考え方を比較し、共通点や相違点を見つけることで、深い考察が生まれます。
-
「疑問」を「発見」に変える
読書中に生じた疑問をそのままにせず、「この疑問について、自分なりに考えてみよう」「もしかしたら、こういう意味なのかもしれない」と掘り下げることで、感想文のオリジナリティに繋がります。
-
推敲(すいこう)で「完成度」を高める!最終チェックのポイント
読書感想文を書き終えたら、それで終わりではありません。入賞を目指すためには、文章の「完成度」を高めるための「推敲(すいこう)」作業が欠かせません。ここでは、書き終えた読書感想文をより良くするための、最終チェックのポイントと、推敲の具体的な方法を、小学生にも分かりやすく解説します。
-
「推敲」の重要性
推敲は、読書感想文の質を格段に向上させるための、非常に重要なプロセスです。
-
誤字脱字や文法ミスの修正
文章の正確さを保ち、読者(先生や審査員)に不快感を与えないために、誤字脱字や文法の間違いをチェックします。
-
「分かりやすさ」の向上
自分の考えが読者に正確に伝わるように、表現が曖昧な箇所や、言葉足らずな部分を修正し、より明確で分かりやすい文章にします。
-
「構成」の改善
文章の流れがスムーズか、論理的な矛盾がないかなどを確認し、より説得力のある構成に修正します。
-
「表現力」の向上
より効果的な言葉遣いや、比喩表現などを加えることで、文章の魅力を高めることができます。
-
-
「最終チェック」の具体的なポイント
推敲の際に、特に注意して確認すべきポイントをリストアップしました。
-
「誤字脱字」のチェック
漢字の誤り、ひらがなの誤り、送り仮名の誤り、句読点の使い方などに注意して、丁寧に読み返しましょう。声に出して読むと、間違いに気づきやすくなります。
-
「文法」や「表現」の確認
主語と述語が対応しているか、文のつながりは自然か、不自然な言い回しはないかなどを確認します。
-
「内容」の確認
読んだ本のテーマや、自分が伝えたいメッセージが明確になっているか、感想に説得力があるかなどを確認します。
-
「構成」の確認
導入、本文、結論の流れがスムーズか、各部分のつながりは自然かを確認します。
-
「表現」の確認
より効果的な言葉遣いができないか、比喩や擬人化などを活用できないかなどを検討します。
-
-
「推敲」を効果的に行うためのコツ
推敲作業をより効率的かつ効果的に進めるためのコツです。
-
「時間を置いて」読み返す
書き終えた直後ではなく、少し時間を置いてから読み返すことで、客観的に自分の文章を評価しやすくなります。
-
「声に出して」読む
声に出して読むことで、文章のリズムや、不自然な表現、誤字脱字に気づきやすくなります。
-
「第三者」に読んでもらう
家族や友達に読んでもらい、感想やアドバイスをもらうと、自分では気づけなかった改善点が見つかることがあります。
-
「チェックリスト」を活用する
上記のようなチェックポイントをまとめたリストを作り、それに沿って確認していくと、見落としを防ぐことができます。
-
「修正」は具体的に
「ここを直したい」と思った箇所は、具体的にどのように修正すれば良いかを考え、実行しましょう。
-
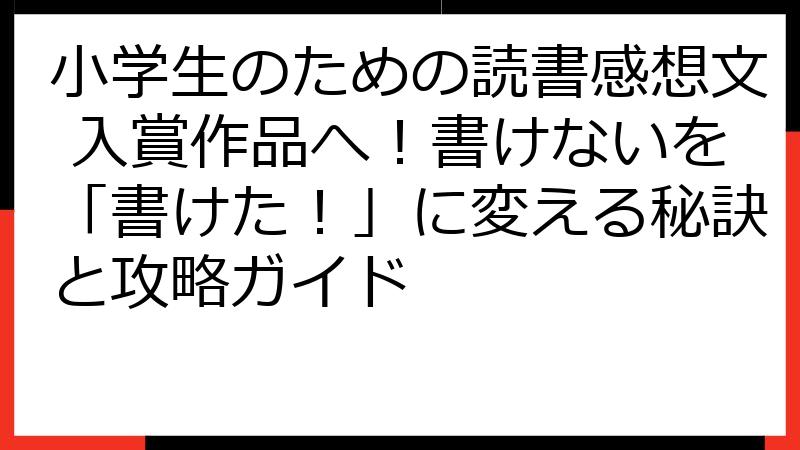
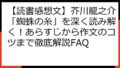
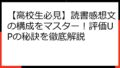
コメント