中学生必見!読書感想文5枚を完璧に書き上げるための完全攻略ガイド
読書感想文5枚…それは、中学生にとって一つの大きな壁かもしれません。
「何を書けばいいのかわからない」「どうすれば5枚も埋められるのか不安」そんな悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、読書感想文5枚を無理なく、そして確実に書き上げるための、具体的な方法を徹底解説します。
本の選び方から、テーマの見つけ方、構成の作り方、表現のコツ、そして推敲のポイントまで、ステップバイステップで詳しく説明していきますので、安心してください。
この記事を読めば、読書感想文が単なる苦行ではなく、読書体験を深め、表現力を磨く、貴重な機会へと変わるはずです。
さあ、読書感想文5枚攻略の旅に出ましょう!
読書感想文5枚攻略の第一歩:読書体験を深掘りする
読書感想文を書き始める前に、最も重要なのは、読書体験を深く掘り下げることです。
単に本の内容を要約するのではなく、「何が心に響いたのか」「何を感じ、何を考えたのか」を明確にすることが、5枚の読書感想文を充実させるための第一歩となります。
この章では、テーマ設定から読書ノートの活用、構成設計まで、読書体験を深掘りし、読書感想文の土台を作るための具体的な方法を解説します。
読書体験を深掘りすることで、自分ならではの視点や考察が生まれ、読書感想文にオリジナリティと深みを与えることができるでしょう。
読書感想文のテーマ設定:読書体験を言語化する出発点
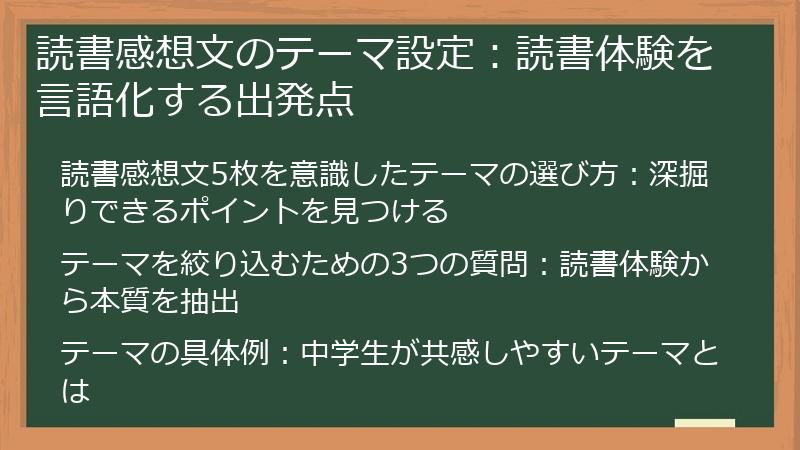
読書感想文のテーマ設定は、読書体験を自分自身の言葉で表現するための最初のステップです。
単に「面白かった」「感動した」という感想だけではなく、なぜそう感じたのか、何が心に残ったのかを深く掘り下げ、読書体験を具体的なテーマとして言語化することが重要です。
このセクションでは、5枚の読書感想文を書き上げるために、深掘りできるテーマの選び方、テーマを絞り込むための質問、そして中学生が共感しやすいテーマの具体例を紹介します。
読書体験を言語化することで、読書感想文に自分自身の個性を反映させ、読者の心に響く、オリジナリティあふれる作品を作り上げることができるでしょう。
読書感想文5枚を意識したテーマの選び方:深掘りできるポイントを見つける
読書感想文を5枚というボリュームで書き上げるためには、深掘りできるテーマを選ぶことが非常に重要です。
表面的な感想だけでは、すぐに書くことがなくなってしまい、文字数を埋めることに苦労することになるでしょう。
そこで、読書体験の中から、より深く考察できるポイントを見つけ出す必要があります。
深掘りできるテーマを選ぶためのポイントはいくつかあります。
- 個人的な経験との関連性:自分の過去の経験や現在の状況と、本のテーマや登場人物の心情がどのように結びついているかを考えてみましょう。個人的な経験と結びつけることで、より感情豊かで、オリジナリティあふれる文章を書くことができます。
- 社会問題との関連性:本の中で描かれている出来事や問題が、現代社会における問題とどのように関連しているかを考察してみましょう。社会的な視点を取り入れることで、読書感想文に深みと社会性を加えることができます。
- 普遍的なテーマ:愛、友情、正義、差別など、時代を超えて普遍的なテーマに着目してみましょう。普遍的なテーマについて考察することで、読書感想文に哲学的な深みを与えることができます。
例えば、戦争を題材にした小説を読んだ場合、単に「戦争は悲惨だ」と書くだけではなく、以下の様な点を深掘りすることができます。
- 戦争によって失われたもの(家族、友人、故郷など)
- 戦争が人々の心にもたらす傷跡
- 平和の尊さ
- 現代社会における紛争との類似点
これらのポイントを意識しながら、読書体験を振り返り、自分にとって本当に心に響いた点、深く考察したいと思った点を見つけ出すことが、読書感想文5枚を成功させるための鍵となります。
テーマを絞り込むための3つの質問:読書体験から本質を抽出
読書体験の中からテーマを見つけたとしても、そのままでは広すぎる場合があります。
5枚の読書感想文を深掘りするためには、テーマを絞り込み、焦点を当てる必要があります。
そこで、テーマを絞り込むための3つの質問を自分自身に問いかけてみましょう。
- 「なぜ、この部分が特に心に残ったのか?」:物語の中で特に印象に残った場面、登場人物の言葉、あるいは作品全体から受けた印象について、その理由を深く掘り下げて考えてみましょう。単に「感動した」「面白かった」という感情だけでなく、なぜそう感じたのか、具体的な理由を明確にすることで、テーマを絞り込むことができます。例えば、登場人物の勇気に感動したのなら、「なぜその勇気に感動したのか?」「自分にとって勇気とは何か?」といった問いを深掘りすることで、読書体験の本質に迫ることができます。
- 「この作品は、自分にとってどのような意味を持つのか?」:読書体験を通して、自分が何を学び、何を感じたのかを具体的に考えてみましょう。作品の内容が、自分の過去の経験や現在の状況とどのように関連しているかを考察することで、テーマを絞り込むことができます。例えば、友情をテーマにした作品を読んだ場合、「自分にとって友情とは何か?」「これまでの友情経験を振り返って、この作品と共通する点や異なる点は何か?」といった問いを深掘りすることで、読書体験を自分自身の人生と結びつけ、よりパーソナルな読書感想文を書くことができます。
- 「この作品から、どのようなメッセージを受け取ったのか?」:作品全体を通して、作者が伝えたいメッセージは何なのか、そして、そのメッセージを自分自身がどのように解釈したのかを考えてみましょう。作者の意図を理解し、自分なりの解釈を加えることで、テーマを絞り込むことができます。例えば、環境問題をテーマにした作品を読んだ場合、「作者は環境問題についてどのようなメッセージを伝えたいのか?」「自分は環境問題についてどのように考えているのか?」「自分自身ができることは何か?」といった問いを深掘りすることで、読書体験を通して得られた気づきや行動の変化を読書感想文に反映させることができます。
これらの質問に答えることで、読書体験の中から最も重要な要素を抽出し、5枚の読書感想文を深掘りするためのテーマを絞り込むことができるでしょう。
テーマの具体例:中学生が共感しやすいテーマとは
中学生が読書感想文のテーマを選ぶ際、共感しやすいテーマを選ぶことは、書きやすさ、深掘りやすさの点で非常に重要です。
共感しやすいテーマとは、中学生自身の日常や関心事、悩みなどに寄り添ったテーマであり、自分自身の言葉で語りやすく、感情を込めやすいテーマと言えるでしょう。
以下に、中学生が共感しやすいテーマの具体例をいくつかご紹介します。
- 友情:友達との関係、友情の喜びや葛藤、裏切り、友情の大切さなど、中学生にとって身近で重要なテーマです。
- 例:いじめられている友達を助けることの難しさ、友達とのケンカとその後の関係修復、転校生との出会いと友情など
- 家族:家族との関係、親との意見の衝突、兄弟姉妹との関係、家族の温かさなど、中学生にとって最も身近な人間関係のテーマです。
- 例:親の期待に応えられないことへの葛藤、反抗期における親との衝突、家族旅行を通して感じた絆など
- 夢・目標:将来の夢、目標達成への努力、挫折、夢を諦めることなど、将来に対する希望や不安を描くテーマです。
- 例:憧れの職業を目指すための努力、部活動での目標達成、進路選択の悩みなど
- 自分らしさ:個性の尊重、他人との違い、自分を受け入れることなど、自己肯定感や自己理解を深めるテーマです。
- 例:周りの人と違うことへの不安、自分の短所を受け入れること、個性を活かすことなど
- 社会問題:環境問題、貧困、差別、人権など、社会に対する関心を高めるテーマです。
- 例:環境破壊の現状と未来への影響、貧困問題の解決策、人種差別問題など
これらのテーマはあくまで一例であり、自分自身の読書体験を通して、本当に心に響いたテーマを選ぶことが重要です。
また、これらのテーマを組み合わせることで、よりオリジナリティあふれる読書感想文を書くことができます。
例えば、「友情」と「夢」を組み合わせ、「友達との友情を支えに夢を追いかける」といったテーマを設定することも可能です。
自分自身の言葉で語りやすく、感情を込めやすいテーマを選び、5枚の読書感想文を充実させましょう。
読書ノート術:記憶と感情を鮮明に残すテクニック
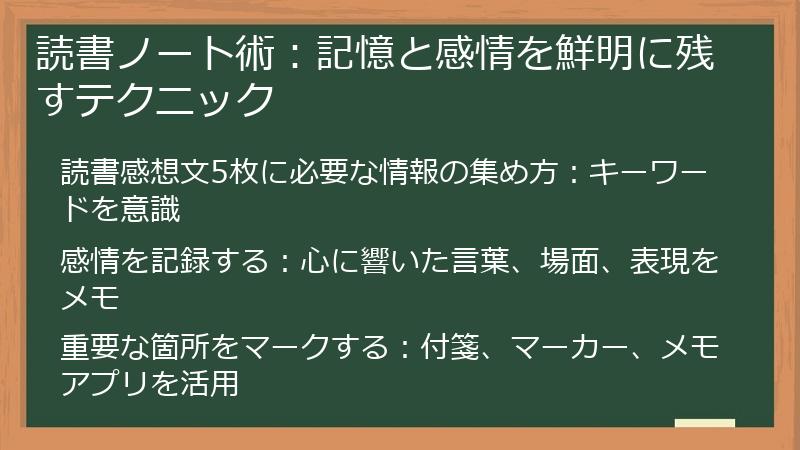
読書体験を深掘りし、5枚の読書感想文を豊かにするためには、読書ノートの活用が不可欠です。
読書ノートは、単に本の要約を書き留めるだけでなく、読書中に感じた感情や考えたこと、心に響いた言葉などを記録することで、記憶を鮮明にし、読書体験をより深く理解するためのツールとなります。
このセクションでは、5枚の読書感想文に必要な情報を効率的に集める方法、感情を記録するコツ、そして重要な箇所をマークするための具体的なテクニックを紹介します。
読書ノートを効果的に活用することで、読書体験を鮮明に記録し、読書感想文の執筆をスムーズに進めることができるでしょう。
読書感想文5枚に必要な情報の集め方:キーワードを意識
5枚の読書感想文を書き上げるためには、計画的に情報を収集することが重要です。
闇雲に読書をするのではなく、あらかじめテーマを意識し、読書感想文に必要な情報を効率的に集めることで、スムーズに執筆を進めることができます。
情報を集める際に意識すべきキーワードは、以下の通りです。
- テーマに関連する箇所:読書感想文のテーマとして選んだ箇所を中心に、物語の展開、登場人物の心情、背景描写などを注意深く読み込みましょう。特に、テーマを深掘りするための根拠となる部分を重点的にメモしておくと、執筆時に役立ちます。
- 印象的な言葉・表現:心に響いた言葉、美しい表現、作者独自の言い回しなどを記録しておきましょう。これらの言葉は、読書感想文に深みと彩りを与え、読者の心に響く文章を書くためのヒントとなります。
- 疑問点・考察点:読んでいて疑問に思ったこと、深く考察したいと思ったことなどをメモしておきましょう。これらの疑問点や考察点は、自分自身の考えを深め、オリジナルの読書感想文を書くための出発点となります。
- 他の作品との関連性:もし、読んだ本と似たテーマを扱った作品や、関連する情報があれば、それらもメモしておきましょう。他の作品との比較や関連情報を加えることで、読書感想文に深みと広がりを持たせることができます。
情報収集の方法としては、以下の様なものが考えられます。
- ノートに手書きでメモする:紙のノートに手書きでメモを取ることで、記憶に残りやすく、自由な発想を促す効果があります。
- 読書メモアプリを活用する:スマートフォンやタブレットの読書メモアプリを活用することで、場所を選ばずにメモを取ることができ、情報を整理・検索するのも容易です。
- 本の余白に直接書き込む:古本や自分の所有している本であれば、余白に直接書き込むことで、読書体験とメモが一体化し、より深い理解につながります。
これらのキーワードを意識し、自分に合った情報収集の方法を見つけることで、5枚の読書感想文に必要な情報を効率的に集め、充実した内容の読書感想文を書くことができるでしょう。
感情を記録する:心に響いた言葉、場面、表現をメモ
読書体験を深く掘り下げ、5枚の読書感想文を魅力的なものにするためには、読書中に感じた感情を記録することが非常に重要です。
単に物語の内容を要約するだけでなく、どのような場面で、どのような感情が湧き上がったのかを具体的に記録することで、読書体験をより鮮明に思い出すことができ、読書感想文に感情豊かな表現を加えることができます。
感情を記録する際には、以下のポイントを意識しましょう。
- 具体的な場面を特定する:どの場面で、どのような感情が湧き上がったのかを具体的に記録しましょう。「感動した」「悲しかった」という漠然とした感情だけでなく、どの場面でそう感じたのかを特定することで、感情の根源を深く理解することができます。例えば、「主人公が困難を乗り越える場面で、強い感動を覚えた」のように、具体的な場面と感情を結びつけて記録しましょう。
- 感情の種類を特定する:一口に「感動」と言っても、様々な種類の感動があります。例えば、「勇気づけられる感動」「心が温まる感動」「切ない感動」など、感情の種類を具体的に特定することで、読書体験をより細やかに表現することができます。
- 感情の度合いを表現する:感情の強さを表現することで、読書体験の臨場感を高めることができます。「少し悲しかった」「とても感動した」「涙が止まらなかった」など、感情の度合いを具体的に表現することで、読者の共感を呼びやすくなります。
- 五感を使った表現を取り入れる:視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの五感を使った表現を取り入れることで、感情をより鮮やかに表現することができます。「主人公の涙が頬を伝うのを見て、胸が締め付けられるような気持ちになった」「雨の音を聞きながら、主人公の孤独を感じた」のように、五感を使った表現を取り入れることで、読者に追体験を促し、感情を共有することができます。
感情を記録する方法としては、以下の様なものが考えられます。
- 読書ノートに感情を書き出す:読書ノートに、感じた感情を自由に書き出しましょう。箇条書きで感情を羅列するだけでなく、感情が湧き上がった背景や理由なども詳しく記述することで、読書体験をより深く理解することができます。
- 感情表現のボキャブラリーを増やす:感情を表現するための言葉のボキャブラリーを増やすことで、より細やかに感情を表現することができます。類語辞典や感情表現に関する書籍などを参考に、様々な感情表現を学びましょう。
- SNSで読書記録を共有する:TwitterやInstagramなどのSNSで読書記録を共有することで、他の読者との交流を通じて、新たな発見や気づきを得ることができます。
これらのポイントを意識し、感情を記録することで、5枚の読書感想文に深みと感情豊かな表現を加えることができるでしょう。
重要な箇所をマークする:付箋、マーカー、メモアプリを活用
読書体験を深掘りし、5枚の読書感想文を効果的に書き上げるためには、重要な箇所をマークすることが非常に有効です。
重要な箇所をマークすることで、後で読書ノートを見返したり、読書感想文を執筆する際に、必要な情報を効率的に見つけ出すことができます。
重要な箇所をマークする際には、以下のツールを活用しましょう。
- 付箋:手軽に貼ったり剥がしたりできる付箋は、重要な箇所をマークするのに最適なツールです。色分けして使うことで、重要度やテーマごとに分類することもできます。
- 例:ピンクの付箋は感動した場面、青い付箋は疑問に思った箇所、黄色の付箋は重要なキーワードなど
- マーカー:重要な箇所を線で強調するマーカーは、文章を目立たせたい場合に効果的です。ただし、本の紙質によっては裏写りする可能性があるので、注意が必要です。
- 例:重要なキーワード、心に響いた言葉、テーマに関連する箇所など
- メモアプリ:スマートフォンやタブレットのメモアプリを活用すれば、場所を選ばずにメモを取ることができます。読書中に気になったことや考えたことを、その場で記録することができるので、読書体験をより深く理解することができます。
- 例:引用したい箇所、自分自身の考察、他の作品との関連性など
重要な箇所をマークする際には、以下のポイントを意識しましょう。
- 目的を明確にする:何のためにマークするのか、目的を明確にしてからマークしましょう。漠然と「重要だ」と感じた箇所をマークするのではなく、「読書感想文のテーマに関連する箇所」「引用したい箇所」「疑問に思った箇所」など、目的を明確にすることで、後で情報を整理しやすくなります。
- マークする箇所を絞る:あまりにも多くの箇所をマークすると、かえって重要な箇所が埋もれてしまい、情報を見つけ出すのが困難になります。本当に重要な箇所だけを厳選してマークするように心がけましょう。
- マークした理由を書き込む:付箋やメモアプリに、なぜその箇所をマークしたのか、理由を書き込むようにしましょう。理由を書き込むことで、後でマークした箇所を見返した際に、当時の感情や考えを思い出しやすくなります。
これらのツールを活用し、ポイントを意識して重要な箇所をマークすることで、5枚の読書感想文に必要な情報を効率的に集め、スムーズに執筆を進めることができるでしょう。
構成設計:読書感想文5枚を飽きさせない流れを作る
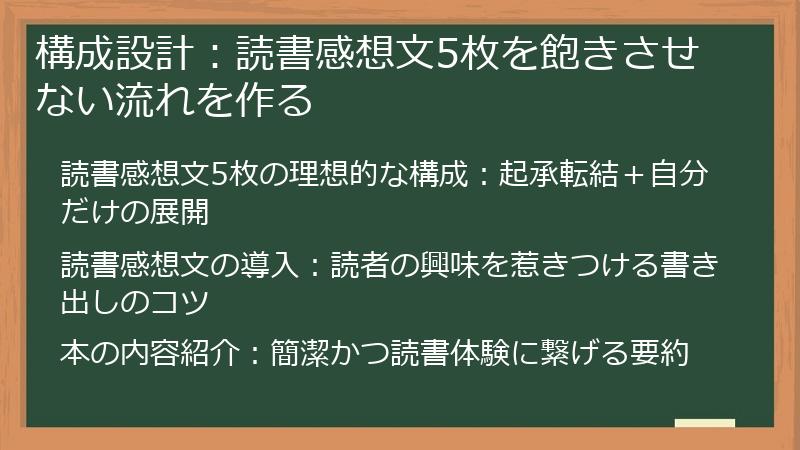
読書感想文5枚という長丁場を、読者を飽きさせることなく、最後まで読ませるためには、しっかりとした構成設計が不可欠です。
構成がしっかりしていれば、自分の考えを論理的に展開することができ、読者にメッセージを効果的に伝えることができます。
このセクションでは、5枚の読書感想文を飽きさせないための理想的な構成、読者の興味を惹きつける導入の書き方、そして読書体験に繋げるための本の要約のコツを紹介します。
構成設計をしっかりと行うことで、5枚の読書感想文をスムーズに書き上げ、読者の心に響く、完成度の高い作品を作り上げることができるでしょう。
読書感想文5枚の理想的な構成:起承転結+自分だけの展開
読書感想文5枚というボリュームで、読者を飽きさせずに最後まで読ませるためには、しっかりとした構成が必要です。
基本となるのは、**起承転結**の構成ですが、それに加えて、自分自身の読書体験や考察を盛り込んだ**自分だけの展開**を加えることで、オリジナリティあふれる、魅力的な読書感想文にすることができます。
以下に、5枚の読書感想文における理想的な構成をご紹介します。
- 起(導入):読者の興味を引きつけ、読書感想文の世界へ誘う部分です。
- 本のタイトル、作者名、簡単なあらすじを紹介する。
- 読んだきっかけや、本に対する第一印象を述べる。
- 読書感想文全体のテーマを提示する。
- 承(本の要約):読者が本のあらすじを知らなくても、読書感想文の内容を理解できるように、本の要約を簡潔にまとめます。
- 物語の主要な登場人物、舞台設定、出来事を説明する。
- 物語の重要なポイントを絞って、簡潔にまとめる。
- 読書感想文のテーマに関わる部分を重点的に説明する。
- 転(自分自身の読書体験・考察):ここが読書感想文の最も重要な部分です。自分自身の読書体験や考察を、自由に、そして深く掘り下げて記述します。
- 心に残った場面、印象的な言葉、考えさせられたことなどを具体的に挙げる。
- なぜそう感じたのか、自分自身の経験や価値観と照らし合わせて考察する。
- 物語のテーマについて、自分自身の意見や考えを述べる。
- 結(結論・まとめ):読書体験を通して得られた学びや気づきをまとめ、読書感想文全体を締めくくります。
- 読書体験を通して、自分自身がどのように変化したかを述べる。
- 読書を通して得られた学びや気づきをまとめる。
- 今後の生活にどのように活かしていきたいかを述べる。
- 自分だけの展開:上記の起承転結に加えて、自分自身の個性を発揮できる部分を盛り込みます。
- 物語の登場人物になりきって手紙を書いてみる。
- 物語の続きを想像して書いてみる。
- 物語のテーマを現代社会の問題と関連付けて考察してみる。
この構成を参考に、自分自身の読書体験や考察を盛り込み、オリジナリティあふれる5枚の読書感想文を書き上げてください。
読書感想文の導入:読者の興味を惹きつける書き出しのコツ
読書感想文の導入は、読者の興味を惹きつけ、最後まで読んでもらうための重要な要素です。
書き出しがつまらないと、読者はすぐに読むのをやめてしまう可能性があります。
読者の心を掴み、読書感想文の世界へ引き込むための、書き出しのコツをいくつかご紹介します。
- 本の印象的な一文を引用する:本の冒頭部分や、特に印象に残った一文を引用することで、読者の興味を惹きつけることができます。
- 例:「『100万回生きたねこ』という絵本の中に、こんな一文があります。『ねこは、100万回死んで、100万回生きた。』この言葉に、私は心を奪われました。」
- 読んだきっかけを語る:なぜその本を読んだのか、読んだきっかけを語ることで、読者に親近感を与えることができます。
- 例:「夏休みの課題図書として、この本を読みました。最初は気が進まなかったのですが、読み進めるうちに、物語の世界に引き込まれていきました。」
- 読書前の自分の状況を語る:本を読む前の自分の状況を語ることで、読者に共感してもらうことができます。
- 例:「私は将来の夢が見つからず、悩んでいました。そんな時、この本に出会い、自分の生き方について深く考えるようになりました。」
- 問いかけで始める:読者に問いかけることで、読者の思考を刺激し、読書感想文への関心を高めることができます。
- 例:「あなたは、自分の人生をどのように生きたいですか?この本は、そんな問いを私たちに投げかけてきます。」
- インパクトのある言葉を使う:読者の心に強く残るような、インパクトのある言葉を使うことで、読書感想文への興味を惹きつけることができます。
- 例:「この本は、私の人生を変えました。それは、まるで暗闇の中に光が差し込んだような体験でした。」
これらの書き出しのコツを参考に、自分自身の言葉で、読者の心を掴む、魅力的な導入を書き上げてください。
大切なことは、読者に「この読書感想文は面白そうだ」「この人の考えをもっと知りたい」と思わせることです。
本の内容紹介:簡潔かつ読書体験に繋げる要約
読書感想文において、本のあらすじを簡潔に要約することは、読者が感想文の内容を理解するために必要不可欠です。
しかし、単にあらすじを説明するだけでなく、自分の読書体験に繋げることを意識することで、より深みのある読書感想文にすることができます。
以下に、本の要約を書く際のポイントをご紹介します。
- 物語の主要な要素を絞り込む:登場人物、舞台、出来事など、物語を構成する要素の中から、特に重要なものを絞り込みましょう。5枚という限られた枚数の中で、すべてを詳細に説明することはできません。読書感想文のテーマに関連する要素を重点的に説明するようにしましょう。
- あらすじを簡潔にまとめる:物語の全体像がわかるように、あらすじを簡潔にまとめましょう。重要な出来事の流れを把握できるように、わかりやすく説明することが大切です。ただし、結末を書いてしまうと、読者の興味を損ねてしまう可能性があるため、結末は伏せておくのが一般的です。
- 自分の読書体験に繋げる:あらすじを説明するだけでなく、自分の読書体験に繋げることを意識しましょう。例えば、特定の場面で感動した理由や、登場人物の心情に共感した理由などを加えることで、読書感想文にオリジナリティを与えることができます。
- 引用を活用する:物語の中で特に印象に残った一文を引用することで、読者の興味を惹きつけ、自分の読書体験をより鮮明に伝えることができます。引用する際は、著作権に配慮し、出典を明記するようにしましょう。
- 客観的な視点を保つ:本の要約は、あくまで客観的な視点で書くように心がけましょう。自分の主観的な意見や感想ばかりを述べるのではなく、物語の内容を正確に伝えることが大切です。
以下に、本の要約の例をご紹介します。
『星の王子さま』は、飛行機が砂漠に不時着した「ぼく」が、様々な星からやってきた王子さまと出会う物語です。王子さまは、自分の星を大切にすること、そして、本当に大切なものは目に見えないことを教えてくれます。私が特に印象に残ったのは、王子さまがキツネと出会う場面です。キツネは王子さまに、「大切なものは、目に見えないんだよ」と教えます。この言葉を聞いた時、私は自分の周りの大切なものについて、改めて考えさせられました。
この例のように、本のあらすじを簡潔にまとめつつ、自分の読書体験に繋げることで、読者の心に響く、深みのある読書感想文を書くことができるでしょう。
読書感想文5枚を彩る表現力:自分らしい言葉で語る
読書感想文5枚を単なる文字の羅列で終わらせず、読者の心を揺さぶる作品にするためには、表現力が不可欠です。
自分自身の感情や考えを、的確かつ魅力的な言葉で表現することで、読書体験をより鮮明に伝え、読者に深い感動を与えることができます。
この章では、感情を言葉に乗せる方法、表現力を高めるための具体的なテクニック、そして引用を効果的に活用するための注意点などを解説します。
自分らしい言葉で語り、読書感想文を彩る表現力を身につけることで、読者の心に深く刻まれる、記憶に残る作品を作り上げることができるでしょう。
心を動かす表現:感情を言葉に乗せる方法
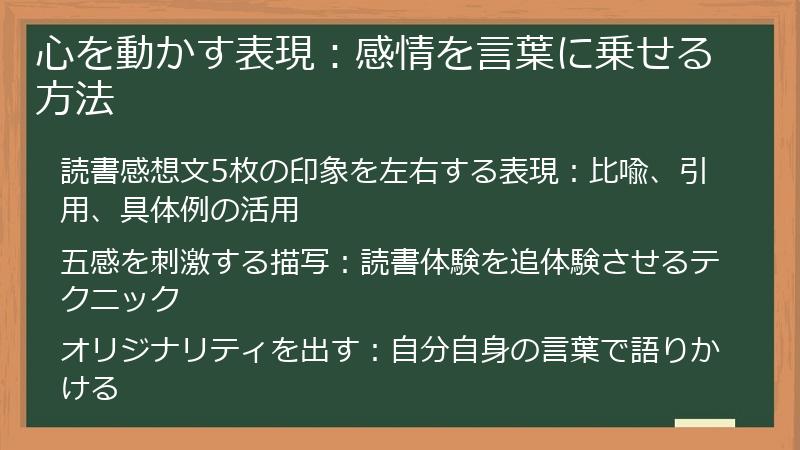
読書感想文において、感情を言葉に乗せることは、読者の共感を呼び、心を動かすために非常に重要です。
単に「面白かった」「感動した」と書くだけでなく、なぜそう感じたのか、どのような感情が湧き上がったのかを具体的に表現することで、読書体験をより鮮明に伝えることができます。
このセクションでは、読書感想文の印象を左右する表現方法、五感を刺激する描写のテクニック、そしてオリジナリティを出すための方法を紹介します。
感情を言葉に乗せることで、読書感想文に深みと感動を与え、読者の心に深く響く作品を作り上げることができるでしょう。
読書感想文5枚の印象を左右する表現:比喩、引用、具体例の活用
読書感想文5枚を魅力的なものにするためには、表現力を磨き、読者の心に響く文章を書くことが重要です。
比喩、引用、具体例は、表現力を高め、読書感想文の印象を大きく左右する、効果的なテクニックです。
- 比喩を活用する:比喩とは、ある物事を別の物事に例えて表現する技法です。比喩を使うことで、抽象的な概念を具体的にイメージさせることができ、読者の理解を深めることができます。
- 例:「悲しみは、まるで底なし沼のように、私を深く沈めていった。」
- 例:「希望は、暗闇の中に光る、一筋の星のように、私を導いてくれた。」
- 引用を活用する:本の印象的な一文や、心に響いた言葉を引用することで、読者に作品の魅力を伝えることができます。引用する際は、著作権に配慮し、出典を明記するようにしましょう。
- 例:「『銀河鉄道の夜』の中に、こんな一文があります。『ほんとうにいいことは、みんな、目に見えないんだよ。』この言葉に、私は心を奪われました。」
- 具体例を活用する:抽象的な概念や感情を説明する際には、具体例を用いることで、読者の理解を深めることができます。
- 例:「友情の大切さを教えてくれたのは、小学校の頃からの親友であるA子です。彼女はいつも私のことを気にかけてくれ、困った時には必ず助けてくれます。」
- 例:「努力することの大切さを学んだのは、部活動での経験です。毎日厳しい練習に耐え、目標を達成するために努力することで、大きな成長を遂げることができました。」
これらのテクニックを効果的に活用することで、読書感想文に深みと彩りを与え、読者の心に強く残る文章を書くことができます。
大切なことは、これらのテクニックを単に形式的に使うのではなく、自分の感情や考えを表現するために、自然に使いこなすことです。
五感を刺激する描写:読書体験を追体験させるテクニック
読書感想文で読者の心を掴むためには、五感を刺激する描写を取り入れることが非常に効果的です。
読者がまるでその場にいるかのように感じられるような描写をすることで、読書体験を追体験させ、より深い感動を与えることができます。
- 視覚:色、形、大きさ、光などを具体的に描写することで、情景を鮮やかに表現します。
- 例:「夕焼け空は、燃えるような赤色と、紫色のグラデーションに染まり、まるで絵画のようだった。」
- 例:「主人公の瞳は、深い海の底のように、吸い込まれそうなほど美しかった。」
- 聴覚:音、声、音楽などを描写することで、臨場感を高めます。
- 例:「雨の音は、まるで子守唄のように、静かに私の心を癒してくれた。」
- 例:「風の音は、木々の葉を揺らし、まるで歌っているかのようだった。」
- 嗅覚:匂いを描写することで、情景をより鮮明にイメージさせることができます。
- 例:「雨上がりの土の匂いは、どこか懐かしく、幼い頃の記憶を呼び覚ましてくれた。」
- 例:「パン屋さんの前を通ると、焼きたてのパンの香ばしい匂いが漂ってきた。」
- 味覚:食べ物や飲み物の味を描写することで、読者に味を想像させることができます。
- 例:「おばあちゃんの作ってくれたおにぎりは、あたたかくて、どこか懐かしい味がした。」
- 例:「レモネードは、甘酸っぱくて、爽やかな味がした。」
- 触覚:肌触り、温度、質感などを描写することで、情景をよりリアルに感じさせることができます。
- 例:「風は、頬を優しく撫で、まるで誰かに抱きしめられているようだった。」
- 例:「砂浜は、あたたかくて、裸足で歩くと心地よかった。」
これらの五感を刺激する描写を効果的に活用することで、読書体験を追体験させ、読者の心に深く残る読書感想文を書くことができます。
大切なことは、五感を意識的に働かせ、感じたことを素直に言葉にすることです。
オリジナリティを出す:自分自身の言葉で語りかける
読書感想文において、オリジナリティを出すことは、他の人と差をつけるために非常に重要です。
自分自身の言葉で語りかけることで、読者に共感を与え、記憶に残る読書感想文を書くことができます。
- 自分自身の経験と結びつける:本の内容と自分自身の経験を結びつけることで、オリジナリティを出すことができます。
- 例:「主人公が困難に立ち向かう姿を見て、私は過去の辛い経験を思い出しました。あの時、私も諦めずに努力したからこそ、今の自分があるのだと改めて感じました。」
- 例:「物語の舞台となっている場所は、私が子供の頃に住んでいた場所に似ています。風景描写を読んでいると、懐かしい思い出が蘇ってきました。」
- 自分自身の視点で考察する:本の内容を自分自身の視点で考察することで、オリジナリティを出すことができます。
- 例:「この物語は、友情の大切さを教えてくれます。しかし、私は友情だけではなく、自分自身を大切にすることの重要性も感じました。」
- 例:「作者は、この物語を通して、何を伝えたかったのでしょうか?私は、作者は私たちに、幸せは身近なところにあることに気づいてほしいのだと思いました。」
- 自分自身の言葉で表現する:難しい言葉や表現を使うのではなく、自分自身の言葉で、わかりやすく表現することが大切です。
- 例:「この本を読んで、私はとても感動しました。」ではなく、「この本を読んで、心が震えるほど感動しました。」のように、より具体的に感情を表現する。
- 例:「この物語は、非常に示唆に富んでいる。」ではなく、「この物語は、色々なことを考えさせてくれる。」のように、難しい言葉を避けて、わかりやすく表現する。
自分自身の言葉で語りかけることで、読者に共感を与え、記憶に残る読書感想文を書くことができます。
大切なことは、自分自身の感情や考えを素直に表現することです。
論理的な文章構成:説得力を高める書き方
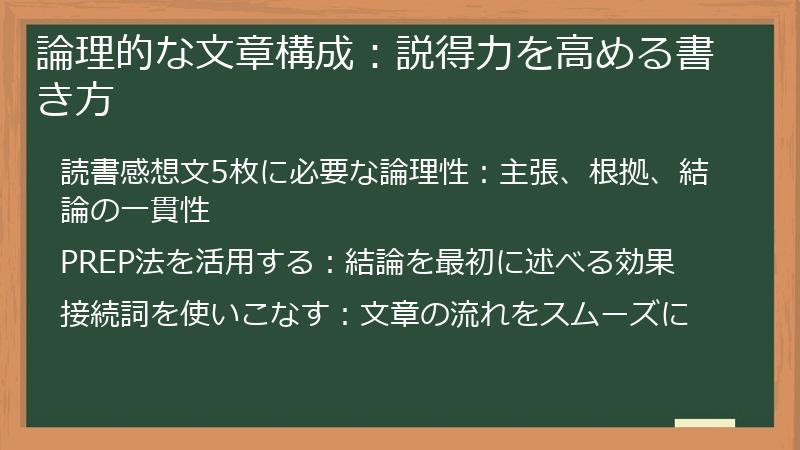
読書感想文5枚を読者の心に響かせるためには、感情的な表現だけでなく、論理的な文章構成も重要です。
論理的な文章構成は、自分の考えを明確に伝え、読者を説得し、納得させる力を持っています。
このセクションでは、5枚の読書感想文に必要な論理性、PREP法を活用した文章構成、そして文章の流れをスムーズにするための接続詞の使い方を紹介します。
論理的な文章構成を身につけることで、読書感想文に説得力を持たせ、読者の心を掴む、完成度の高い作品を作り上げることができるでしょう。
読書感想文5枚に必要な論理性:主張、根拠、結論の一貫性
読書感想文5枚というボリュームの中で、読者を納得させるためには、論理的な文章構成が不可欠です。
論理的な文章とは、主張、根拠、結論が一貫しており、筋道が通っている文章のことです。
主張が曖昧だったり、根拠が不足していたり、結論が飛躍していたりすると、読者は納得してくれません。
論理的な文章を書くためには、以下の点を意識しましょう。
- 明確な主張を立てる:読書感想文を通して、何を伝えたいのか、明確な主張を立てましょう。主張が曖昧だと、文章全体の方向性が定まらず、読者は混乱してしまいます。
- 例:「この本は、友情の大切さを教えてくれる。」
- 例:「この物語は、私たちに夢を持つことの重要性を教えてくれる。」
- 主張を裏付ける根拠を提示する:主張を裏付けるためには、具体的な根拠を提示する必要があります。根拠が不足していると、主張に説得力がなく、読者は納得してくれません。
- 例:「主人公が困難な状況でも、友達を信じて助け合う姿は、友情の大切さを教えてくれる。」
- 例:「主人公が夢を諦めずに努力する姿は、私たちに夢を持つことの重要性を教えてくれる。」
- 主張と根拠を繋げる論理的な展開:主張と根拠を繋げるためには、論理的な展開が必要です。論理的な展開がないと、主張と根拠がバラバラになり、読者は混乱してしまいます。
- 例:「主人公が困難な状況でも、友達を信じて助け合う姿は、友情の大切さを教えてくれる。なぜなら、困難な状況では、友達の存在が心の支えとなり、勇気を与えてくれるからだ。」
- 例:「主人公が夢を諦めずに努力する姿は、私たちに夢を持つことの重要性を教えてくれる。なぜなら、夢を持つことで、目標に向かって努力することができ、人生を充実させることができるからだ。」
- 結論を明確に示す:読書感想文の最後には、結論を明確に示す必要があります。結論は、主張と根拠を踏まえたものでなければなりません。
- 例:「この本は、友情の大切さを教えてくれる。私たちは、主人公のように、友達を大切にし、支え合って生きていくべきだ。」
- 例:「この物語は、私たちに夢を持つことの重要性を教えてくれる。私たちは、主人公のように、夢を諦めずに努力し、自分の人生を切り開いていくべきだ。」
これらの点を意識することで、主張、根拠、結論が一貫した、論理的な読書感想文を書くことができます。
PREP法を活用する:結論を最初に述べる効果
PREP法は、読者に分かりやすく、説得力のある文章を書くための効果的なフレームワークです。
結論を最初に述べることで、読者は文章全体の構成を理解しやすくなり、その後の説明をスムーズに理解することができます。
PREP法は、以下の4つの要素で構成されています。
- Point(結論):最初に、文章で最も伝えたい結論を述べます。結論を最初に述べることで、読者は文章の目的を理解しやすくなり、その後の説明に集中することができます。
- 例:「この本は、私たちに勇気を与える物語だ。」
- Reason(理由):結論を述べた後、その理由を説明します。理由を具体的に説明することで、読者は結論に納得しやすくなります。
- 例:「なぜなら、主人公は困難な状況でも決して諦めず、自分の信念を貫き通すからだ。」
- Example(具体例):理由を説明した後、具体的な事例を挙げます。事例を挙げることで、読者は理由をより具体的にイメージすることができ、理解が深まります。
- 例:「例えば、主人公は、自分の夢を諦めるように説得されても、決して屈することなく、自分の夢を追い続けた。」
- Point(結論):最後に、再び結論を述べます。最初に述べた結論を繰り返すことで、読者に文章のメッセージを強く印象づけることができます。
- 例:「だからこそ、この本は、私たちに勇気を与えてくれるのだ。」
PREP法を活用することで、読者に分かりやすく、説得力のある文章を書くことができます。
読書感想文だけでなく、様々な場面で活用できる、非常に有効なテクニックです。
以下に、PREP法を活用した読書感想文の例文を示します。
Point(結論):この本は、私たちに勇気を与える物語だ。
Reason(理由):なぜなら、主人公は困難な状況でも決して諦めず、自分の信念を貫き通すからだ。
Example(具体例):例えば、主人公は、自分の夢を諦めるように説得されても、決して屈することなく、自分の夢を追い続けた。
Point(結論):だからこそ、この本は、私たちに勇気を与えてくれるのだ。
接続詞を使いこなす:文章の流れをスムーズに
読書感想文5枚を論理的に構成し、読者にスムーズに読んでもらうためには、接続詞を効果的に使うことが重要です。
接続詞は、文と文、段落と段落を繋ぎ、文章全体の流れをスムーズにする役割を果たします。
接続詞には様々な種類があり、それぞれ異なる意味を持っています。接続詞の意味を理解し、適切に使いこなすことで、文章の論理性を高め、読者に分かりやすく情報を伝えることができます。
以下に、読書感想文でよく使う接続詞とその使い方をご紹介します。
- 順接:前の文を受けて、理由や原因、結果などを述べる際に使用します。
- 例:だから、したがって、そのため、なぜなら、というのは
- 例文:主人公は困難に立ち向かい、夢を叶えた。だから、私も諦めずに努力しようと思った。
- 逆接:前の文と反対の内容や、予想外の結果を述べる際に使用します。
- 例:しかし、だが、けれども、ところが、それにもかかわらず
- 例文:主人公は努力を重ねた。しかし、結果は思うようにいかなかった。
- 並列・添加:前の文と同等の内容を付け加えたり、別の視点から説明したりする際に使用します。
- 例:また、さらに、加えて、そして、あるいは
- 例文:主人公は勇気があり、困難に立ち向かった。また、周りの人を思いやる優しさも持ち合わせていた。
- 説明・補足:前の文の内容を詳しく説明したり、補足したりする際に使用します。
- 例:つまり、例えば、具体的には、なぜなら、要するに
- 例文:主人公は、自分の夢を諦めなかった。つまり、どんな困難にも立ち向かう強い意志を持っていたのだ。
- 転換:話題を変えたり、別の視点から議論を始めたりする際に使用します。
- 例:さて、ところで、それでは、次に、一方
- 例文:物語のあらすじは上記の通りである。さて、私がこの本を読んで最も印象に残ったのは、主人公の生き方である。
- 結論:文章全体をまとめたり、結論を述べたりする際に使用します。
- 例:したがって、よって、結局、以上のように、つまり
- 例文:以上のことから、この本は私たちに勇気を与えてくれると言えるだろう。つまり、私たちは主人公のように、困難に立ち向かい、自分の夢を叶えるべきなのだ。
これらの接続詞を適切に使いこなすことで、文章の流れをスムーズにし、読者に分かりやすく情報を伝えることができます。
読書感想文を書く際には、接続詞の種類と意味を理解し、効果的に活用するように心がけましょう。
読書感想文における引用:効果的な使い方と注意点
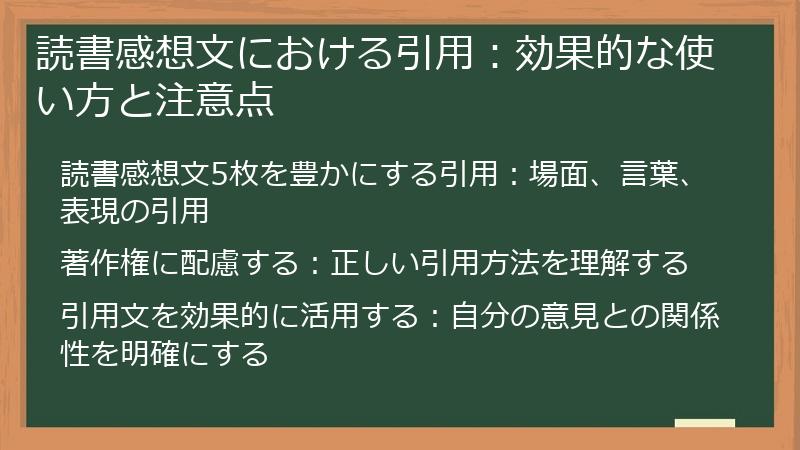
読書感想文において、本の文章を引用することは、自分の意見を裏付けたり、読者に作品の魅力を伝えたりするために有効な手段です。
しかし、引用は適切に行わないと、著作権侵害になる可能性もあります。
このセクションでは、読書感想文5枚を豊かにする引用の使い方、著作権に配慮するための注意点、そして引用文を効果的に活用するための方法を紹介します。
引用を効果的に活用することで、読書感想文に深みと説得力を持たせ、読者の心に響く作品を作り上げることができるでしょう。
読書感想文5枚を豊かにする引用:場面、言葉、表現の引用
読書感想文5枚をより豊かにするためには、本の文章を効果的に引用することが重要です。
引用は、自分の意見を裏付けたり、読者に作品の魅力を伝えたりするために有効な手段となります。
読書感想文で引用する際に、特に効果的なのは、以下の3つの要素です。
- 印象的な場面の引用:物語の中で特に印象に残った場面を引用することで、読者に物語の雰囲気を伝え、共感を呼ぶことができます。
- 例:「主人公が困難に立ち向かう場面を引用し、その場面が自分にどのような感動を与えたかを説明する。」
- 例:「物語のクライマックスシーンを引用し、読者に物語の展開を想像させる。」
- 心に響いた言葉の引用:登場人物の言葉や、作者の言葉で、特に心に響いたものを引用することで、読者に作品のメッセージを伝え、共感を呼ぶことができます。
- 例:「主人公が語った名言を引用し、その言葉が自分にどのような影響を与えたかを説明する。」
- 例:「作者が物語に込めたメッセージを引用し、読者に作品のテーマを伝える。」
- 美しい表現の引用:作者が用いた美しい表現を引用することで、読者に作品の魅力を伝え、文章に彩りを与えることができます。
- 例:「風景描写や心情描写など、特に美しいと感じた表現を引用し、その表現が自分にどのような印象を与えたかを説明する。」
- 例:「比喩や擬人化など、作者が用いた効果的な表現技法を引用し、文章に深みを与える。」
引用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 引用箇所を明確にする:引用符(「」や“”)で囲み、引用箇所を明確に示しましょう。
- 出典を明記する:本のタイトル、作者名、出版社名、ページ数などを明記し、出典を明らかにしましょう。
- 引用文を短くまとめる:引用文は、必要最小限に留め、長すぎる引用は避けましょう。
- 自分の意見と区別する:引用文の後に、自分の意見や感想を述べ、引用文と自分の意見を明確に区別しましょう。
これらのポイントを意識し、効果的に引用を活用することで、読書感想文5枚をより豊かに、そして魅力的にすることができます。
著作権に配慮する:正しい引用方法を理解する
読書感想文で本の文章を引用する際には、著作権に配慮することが非常に重要です。
著作権とは、作者が作品に対して持つ権利であり、作者の許可なく作品を無断で利用することは、著作権侵害にあたります。
読書感想文で引用を行う場合、著作権法で認められている「引用」の範囲内で行う必要があります。
著作権法で認められている引用とは、以下の要件を満たすものです。
- 引用の目的が正当であること:引用は、自分の意見を裏付けたり、作品を批評したりするなど、正当な目的のために行われる必要があります。単に作品をコピーして利用するような場合は、引用とは認められません。
- 引用の必要性があること:引用は、自分の意見を説明するために、どうしても必要な範囲で行われる必要があります。引用せずに自分の言葉で説明できる場合は、引用を避けるべきです。
- 引用部分とそれ以外の部分が明確に区別されていること:引用部分は、引用符(「」や“”)で囲むなどして、自分の文章と明確に区別する必要があります。
- 出典が明記されていること:引用した作品のタイトル、作者名、出版社名、ページ数などを明記し、出典を明らかにします。
- 引用部分が従、自分の文章が主であること:引用部分は、あくまで自分の文章を補足するものであり、引用部分が主、自分の文章が従となるような使い方は、引用とは認められません。
これらの要件を満たさない引用は、著作権侵害にあたる可能性があります。
著作権侵害は、法律で罰せられるだけでなく、作者の名誉を傷つけ、社会的な信用を失うことにも繋がります。
読書感想文を書く際には、著作権に配慮し、正しい引用方法を理解するように心がけましょう。
引用方法に不安がある場合は、学校の先生や図書館の司書に相談することをおすすめします。
引用文を効果的に活用する:自分の意見との関係性を明確にする
読書感想文で引用文を効果的に活用するためには、単に引用文を並べるだけでなく、自分の意見との関係性を明確にすることが重要です。
引用文は、あくまで自分の意見を裏付けたり、補強したりするための手段であり、引用文と自分の意見が有機的に結びついている必要があります。
引用文と自分の意見の関係性を明確にするためには、以下の点に注意しましょう。
- 引用の目的を明確にする:なぜその箇所を引用するのか、目的を明確にしましょう。目的が曖昧だと、引用文が唐突に感じられ、読者は混乱してしまいます。
- 例:「主人公の言葉を引用し、その言葉が自分にどのような影響を与えたかを説明する。」
- 例:「作者の文章を引用し、自分の意見を裏付ける。」
- 引用文の解釈を示す:引用文の意味を、自分自身の言葉で解釈しましょう。引用文をそのまま提示するだけでは、読者に意図が伝わらない可能性があります。
- 例:「主人公の『諦めない』という言葉は、私に大きな勇気を与えてくれた。なぜなら、私も困難な状況に直面した時、諦めそうになったことがあったからだ。」
- 例:「作者は『人間は弱い生き物だ』と述べている。これは、私たち人間は、常に誘惑にさらされており、完璧ではないということを意味している。」
- 引用文と自分の意見を結びつける:引用文と自分の意見を、論理的に結びつけましょう。引用文が、どのように自分の意見を裏付けたり、補強したりするのかを、具体的に説明することで、読者の理解を深めることができます。
- 例:「主人公の『諦めない』という言葉は、私に大きな勇気を与えてくれた。なぜなら、私も困難な状況に直面した時、諦めそうになったことがあったからだ。しかし、主人公の言葉を思い出し、諦めずに努力した結果、目標を達成することができた。」
- 例:「作者は『人間は弱い生き物だ』と述べている。これは、私たち人間は、常に誘惑にさらされており、完璧ではないということを意味している。だからこそ、私たちは、互いに支え合い、助け合って生きていく必要がある。」
これらの点に注意し、引用文を効果的に活用することで、読書感想文5枚に深みと説得力を持たせ、読者の心に響く作品を作り上げることができます。
読書感想文5枚完成に向けて:推敲と最終チェック
読書感想文5枚を書き終えたら、いよいよ完成に向けて、最後の仕上げに取り掛かりましょう。
推敲と最終チェックは、読書感想文の質を大きく左右する、非常に重要なプロセスです。
この章では、読書感想文の完成度を高めるための推敲ポイント、先生を惹きつける読書感想文を書くための秘訣、そして提出前の最終確認事項を解説します。
推敲と最終チェックを丁寧に行うことで、自信を持って提出できる、最高の読書感想文を完成させることができるでしょう。
推敲のポイント:読書感想文の完成度を高める最終チェック
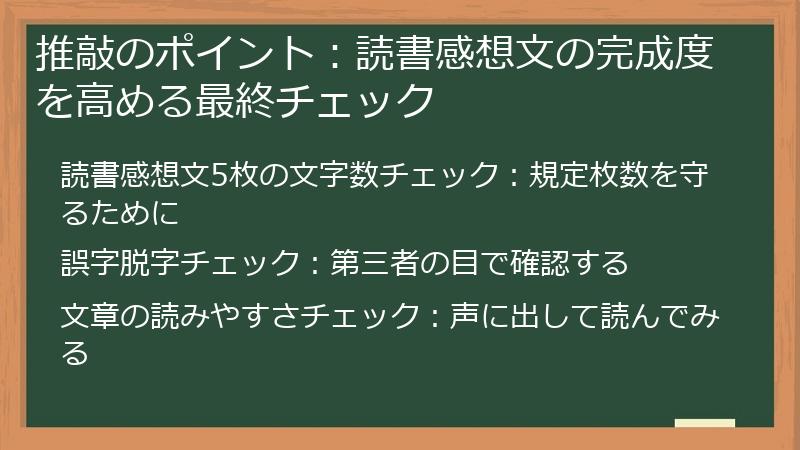
読書感想文を書き終えたら、推敲を行い、文章の完成度を高めましょう。
推敲とは、文章を読み返し、改善点を見つけて修正する作業のことです。
このセクションでは、5枚の読書感想文の文字数チェック、誤字脱字チェック、そして文章の読みやすさチェックのポイントを紹介します。
推敲を丁寧に行うことで、読書感想文の質を向上させ、より完成度の高い作品に仕上げることができます。
読書感想文5枚の文字数チェック:規定枚数を守るために
読書感想文には、通常、文字数や枚数の規定があります。
規定を守らないと、内容がどんなに素晴らしくても、評価が下がってしまう可能性があります。
5枚という規定枚数を守るためには、文字数チェックを必ず行いましょう。
文字数チェックを行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 学校や先生から指示された規定を確認する:学校や先生から、文字数や枚数、書式など、具体的な指示が出ている場合は、必ずそれに従いましょう。指示を無視すると、評価が大きく下がる可能性があります。
- 文字数カウントツールを活用する:WordやPagesなどのワープロソフトには、文字数をカウントする機能が備わっています。また、オンラインで利用できる文字数カウントツールも多数存在します。これらのツールを活用して、正確な文字数を把握しましょう。
- 余白やフォントサイズも考慮する:文字数だけでなく、余白の大きさやフォントサイズも、全体の印象に影響を与えます。規定の余白やフォントサイズを守り、読みやすいレイアウトを心がけましょう。
- 枚数調整のテクニック:
- 文字数を増やす場合:
- 具体的な例やエピソードを付け加える。
- 引用文を効果的に活用する。
- 自分の考えや意見を詳しく説明する。
- 文字数を減らす場合:
- 冗長な表現を削除する。
- 同じ意味の言葉を短い表現に置き換える。
- 文章を簡潔にまとめる。
- 文字数を増やす場合:
文字数チェックを丁寧に行い、規定枚数を守ることは、読書感想文の評価を高めるための第一歩です。
誤字脱字チェック:第三者の目で確認する
誤字脱字は、読書感想文の評価を大きく下げる原因となります。
どんなに内容が素晴らしくても、誤字脱字が多いと、読者に「いい加減な文章だ」という印象を与えてしまいます。
誤字脱字チェックは、必ず行いましょう。
誤字脱字チェックを行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 自分で何度も読み返す:まずは、自分で何度も読み返し、誤字脱字がないか確認しましょう。声に出して読むと、見落としがちな誤字脱字を発見しやすくなります。
- 時間を置いて読み返す:書き終えた直後ではなく、時間を置いてから読み返すことで、客観的に文章を見ることができ、誤字脱字を発見しやすくなります。
- 第三者に読んでもらう:家族や友人、先生など、第三者に読んでもらい、誤字脱字がないか確認してもらいましょう。自分では気づかなかった誤字脱字を、発見してくれる可能性があります。
- 校正ツールを活用する:WordやPagesなどのワープロソフトには、校正機能が備わっています。また、オンラインで利用できる校正ツールも多数存在します。これらのツールを活用して、機械的に誤字脱字をチェックしましょう。ただし、校正ツールは万能ではありません。最終的なチェックは、必ず自分で行いましょう。
- 特に注意すべき誤字脱字:
- 送り仮名の誤り:「〜ください」を「〜下さい」と書くなど、送り仮名の誤りはよくある間違いです。
- 助詞の誤り:「〜は」と「〜が」、「〜に」と「〜へ」など、助詞の使い分けは難しい場合があります。
- 同音異義語の誤り:「感謝」と「感激」、「才能」と「災能」など、同音異義語の使い分けは注意が必要です。
- 変換ミスの誤り:「読書」を「独唱」と変換するなど、変換ミスによる誤りもよくあります。
誤字脱字チェックを徹底的に行い、正確で読みやすい文章を目指しましょう。
文章の読みやすさチェック:声に出して読んでみる
読書感想文の読みやすさは、読者の理解度や印象に大きく影響します。
どんなに内容が充実していても、文章が読みにくいと、読者は内容を理解するのを諦めてしまうかもしれません。
文章の読みやすさチェックは、必ず行いましょう。
文章の読みやすさをチェックする際には、以下の点に注意しましょう。
- 声に出して読んでみる:黙読するだけでなく、声に出して読んでみることで、文章のリズムや言い回しの不自然さに気づきやすくなります。スムーズに読めない箇所は、修正が必要です。
- 一文が長すぎないか:一文が長すぎると、読者は内容を理解するのに苦労します。一文は短く、簡潔にまとめるように心がけましょう。目安としては、40字〜60字程度にすると、読みやすくなります。
- 接続詞が適切に使われているか:接続詞は、文と文、段落と段落を繋ぎ、文章の流れをスムーズにする役割を果たします。接続詞が適切に使われているか確認し、不自然な箇所があれば修正しましょう。
- 同じ言葉が繰り返し使われていないか:同じ言葉が繰り返し使われていると、文章が単調になり、読者は飽きてしまいます。類語や言い換え表現を活用し、文章に変化をつけましょう。
- 抽象的な表現ばかりになっていないか:抽象的な表現ばかりだと、読者は具体的なイメージを持つことができず、文章が理解しにくくなります。具体的な例やエピソードを付け加え、文章を具体的にしましょう。
- 主語と述語が対応しているか:主語と述語が対応していないと、文章の意味が通じなくなります。主語と述語が正しく対応しているか確認し、修正しましょう。
- 段落分けが適切か:段落は、文章の内容を区切り、読者が理解しやすくするためのものです。段落分けが適切に行われているか確認し、不自然な箇所があれば修正しましょう。
これらの点に注意し、文章の読みやすさをチェックすることで、読者
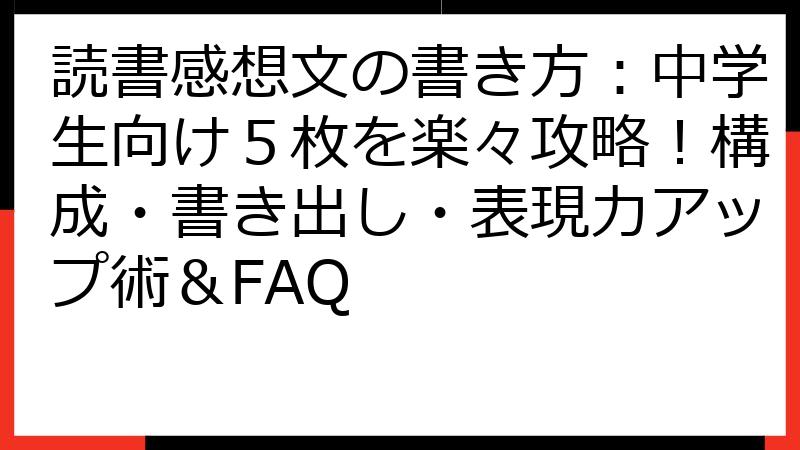
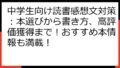
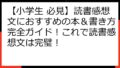
コメント