読書感想文を原稿用紙で完璧に!構成、書き出し、例、注意点まで徹底解説
読書感想文、それは読んだ本の感動や学びを言葉にする、ちょっと特別な宿題。
でも、原稿用紙を前にすると、どう書けばいいか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか?
この記事では、そんなあなたのために、原稿用紙の書き方から構成、書き出しのコツ、そして具体的な例まで、読書感想文を完璧に仕上げるためのすべてを徹底解説します。
減点を防ぐための注意点や、よくある疑問にも答えますので、この記事を読めば、自信を持って読書感想文に取り組めるはずです。
さあ、あなただけのオリジナルな読書感想文を書き上げて、読書の喜びをさらに深めましょう!
読書感想文の原稿用紙マナーと構成の基本
読書感想文を書く上で、まず最初に押さえておきたいのが、原稿用紙の正しい使い方と、文章全体の構成です。
原稿用紙には、書き方のルールがいくつか存在し、これらをきちんと守ることで、読みやすく、整った印象の文章に仕上がります。
また、構成は、読書感想文の骨格となる部分。
序論、本論、結論という基本的な構成を理解し、それぞれにどのような内容を盛り込むべきかを把握することで、スムーズに文章を書き進めることができます。
この大見出しでは、原稿用紙の基本的なルールから、読書感想文の構成要素、そしてオリジナリティ溢れるテーマ選びまで、読書感想文の土台となる知識を丁寧に解説します。
原稿用紙の書き方:基本ルール徹底ガイド
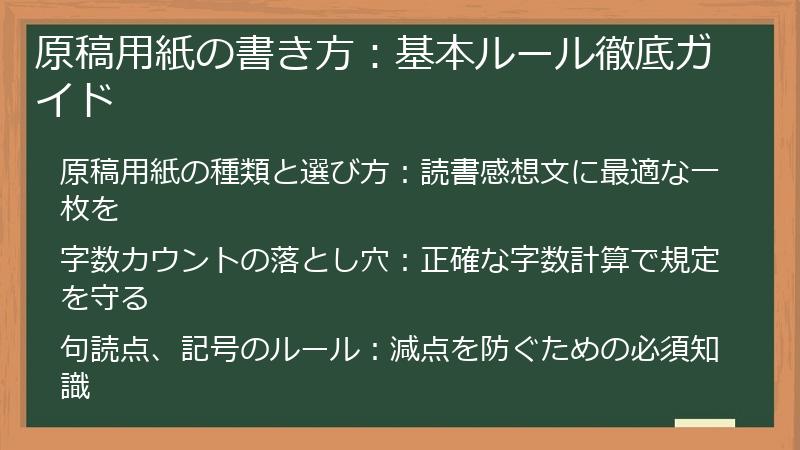
読書感想文を書く上で、原稿用紙の正しい使い方は、意外と重要なポイントです。
誤った使い方をしていると、減点対象になることも。
このセクションでは、原稿用紙の種類から、字数カウントの注意点、句読点や記号のルールまで、原稿用紙の書き方の基本を徹底的に解説します。
これらのルールをしっかりと押さえて、自信を持って読書感想文に取り組みましょう。
原稿用紙の種類と選び方:読書感想文に最適な一枚を
原稿用紙には、様々な種類があることをご存知でしょうか。
実は、読書感想文の内容や目的に合わせて最適な一枚を選ぶことで、書きやすさが格段に向上し、より完成度の高い文章に仕上がるのです。
一般的に、小学校、中学校、高校と、学年が上がるにつれて、原稿用紙のマス目の大きさや行数が変化します。
小学生向けの原稿用紙は、マス目が大きく、行数も少ない傾向にあり、書きやすさを重視した設計になっています。
一方、高校生向けの原稿用紙は、マス目が小さく、行数も多く、より多くの文字数を記述できるようになっています。
また、原稿用紙には、縦書き用と横書き用があります。
読書感想文の提出形式に合わせて、適切な方を選びましょう。
最近では、インターネット上でダウンロードできる無料の原稿用紙テンプレートも豊富に存在します。
これらのテンプレートを利用すれば、自宅で手軽に原稿用紙を印刷することができます。
さらに、罫線の色や紙質など、細部にまでこだわった原稿用紙も販売されています。
例えば、目に優しいクリーム色の紙や、万年筆でも書きやすい滑らかな紙など、様々な種類があります。
読書感想文のテーマや自分の書き方に合わせて、最適な一枚を選んでみてください。
重要なのは、書きやすい原稿用紙を選ぶことです。
書きにくい原稿用紙を選んでしまうと、集中力が途切れてしまい、文章を書くのが億劫になってしまう可能性があります。
- マス目の大きさ
- 行数
- 縦書き用か横書き用か
- 紙質
これらの要素を考慮して、自分にとって最適な一枚を見つけましょう。
適切な原稿用紙を選ぶことは、読書感想文を成功させるための第一歩です。
ぜひ、色々な原稿用紙を試して、自分にとって最高のパートナーを見つけてください。
もちろん、学校から指定された原稿用紙がある場合は、そちらを使用するようにしましょう。
しかし、もし自由に選べる場合は、この記事で紹介したポイントを参考に、最適な一枚を選んでみてください。
字数カウントの落とし穴:正確な字数計算で規定を守る
読書感想文において、意外と重要なのが字数制限です。
指定された字数を守ることは、基本的なルールであり、評価にも影響します。
しかし、原稿用紙での字数カウントは、意外と落とし穴が多いもの。
正確に字数を数え、規定の字数内に収めるための知識を身につけましょう。
まず、注意すべき点は、句読点の扱いです。
句読点は、原則として1文字として数えます。
ただし、学校や先生によっては、句読点を字数に含めない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
また、括弧(「」や()など)も、それぞれ1文字として数えます。
会話文などで括弧を多用する場合は、字数が増えやすいので注意が必要です。
数字やアルファベットは、原則として半角で記述し、2文字で1マスを使用します。
ただし、学校や先生によっては、数字やアルファベットも1文字として数える場合もありますので、こちらも事前に確認しておきましょう。
さらに、改行にも注意が必要です。
段落の始まりや、会話文の後に改行を入れる場合は、改行した行のマス目を空ける必要があります。
この空けたマス目も、字数としてカウントされる場合がありますので、注意が必要です。
最近では、Wordなどのワープロソフトで読書感想文を作成する人も多いでしょう。
ワープロソフトには、字数カウント機能が搭載されていますが、必ずしも正確とは限りません。
原稿用紙に印刷した後、実際に文字を数えて確認することをおすすめします。
字数カウントの落とし穴にハマらないためには、以下の点に注意しましょう。
- 句読点の扱いを確認する
- 括弧の字数を数える
- 数字やアルファベットの扱いを確認する
- 改行によるマス目の空け方を確認する
- ワープロソフトの字数カウント機能を過信しない
これらの点に注意して、正確な字数計算を行い、規定の字数内に収めるようにしましょう。
字数制限を守ることは、読書感想文の評価に大きく影響します。
しっかりと対策を行い、高評価を目指しましょう。
字数が足りない場合は、本の感想や考察を深掘りしたり、具体的なエピソードを付け加えたりすることで、内容を充実させることができます。
字数が多すぎる場合は、冗長な表現を避け、簡潔な文章を心がけるようにしましょう。
字数制限は、表現力を磨くための良い機会と捉え、制限の中で最大限の表現を目指しましょう。
句読点、記号のルール:減点を防ぐための必須知識
読書感想文で減点を避けるためには、句読点や記号の正しい使い方を理解することが不可欠です。
普段何気なく使っている句読点や記号ですが、実は細かいルールが存在し、誤った使い方をすると、読みにくくなるだけでなく、評価を下げる原因にもなりかねません。
ここでは、読書感想文でよく使う句読点や記号のルールを詳しく解説し、減点を防ぐための必須知識を身につけましょう。
まず、句点(。)は、文の終わりに必ず打ちます。
ただし、会話文の終わりに「。」をつけるかどうかは、先生や学校によって指示が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
読点(、)は、文の区切りや意味を明確にするために使用します。
読点を適切に使うことで、文章が読みやすくなり、内容も理解しやすくなります。
ただし、読点の多用は、文章を冗長にする原因にもなりますので、注意が必要です。
疑問符(?)や感嘆符(!)は、それぞれ疑問や感動を表す際に使用します。
ただし、読書感想文では、これらの記号を多用することは避けましょう。
特に感嘆符は、幼稚な印象を与える可能性がありますので、使用は最小限に留めるようにしましょう。
括弧(「」や()など)は、引用や補足説明をする際に使用します。
会話文を引用する場合は、必ず「」で囲みましょう。
また、()は、補足説明や注釈を加える際に使用します。
中黒(・)は、項目を列挙する際に使用します。
箇条書きにする場合は、
- や
- 句点(。)は文末に
- 読点(、)は適切に
- 疑問符(?)感嘆符(!)は控えめに
- 括弧(「」())は正しく使い分け
- 中黒(・)は項目列挙に
- 長音記号(ー)は安易に使わない
- 「私がこの本を手に取ったのは、たまたま立ち寄った本屋でのことでした。その時、私は…」
- 「この本を読み終えた時、私はまるで別世界から帰ってきたような感覚に包まれました。なぜなら…」
- 「主人公の○○は、私とよく似た悩みを抱えていました。だからこそ、私はこの物語に強く引き込まれたのです。」
- 読書体験を鮮やかに表現
- 本の簡単な紹介(ネタバレ注意)
- 読書感想文のテーマ提示
- オリジナリティを重視
- 本の要約(あらすじ、登場人物、重要な出来事)
- 本の考察(感じたこと、考えたこと、学んだこと)
- 具体的な根拠を示す(物語の場面やセリフの引用)
- 自分の体験や知識と関連付ける
- 論理的な思考で文章を展開
- 「この本を読んで、私は○○の大切さを改めて認識しました。今後は、この教訓を活かし、○○のために努力していきたいと思います。」
- 「主人公の○○の生き方に感銘を受け、私も○○のように生きたいと強く思いました。まずは、○○から始めてみようと思います。」
- 「この本を通して、社会問題に対する意識が高まりました。今後は、○○の活動に参加するなど、自分にできることから取り組んでいきたいと思います。」
- 本論の考察を簡潔にまとめる
- 本を通して得た感動や学びを表現
- 未来への展望を示す
- ポジティブな姿勢で締めくくる
- 愛:恋愛、家族愛、友情
- 友情:信頼、裏切り、絆
- 勇気:挑戦、困難、克服
- 希望:夢、目標、未来
- 喪失:別れ、死、悲しみ
- 成長:変化、学び、自己発見
- 過去の出来事や感情を振り返る
- 現在の悩みや葛藤を掘り下げる
- 物語の内容との共通点や相違点を見つける
- 正直な気持ちで向き合う
- 固定観念にとらわれず、自由な発想で考える
- 物語の中に描かれているテーマや出来事を社会問題と結びつける
- 客観的な視点を持つ
- 安易な結論を出さない
- 問題を提起し、読者に考えるきっかけを与える
- 「ページをめくる手が止まらなかった。まるで、ジェットコースターに乗っているかのような、スリリングな展開に、私は息を呑んだ。」
- 「窓の外は雨だった。しとしとと降り続く雨の音を聞きながら、私はこの本の世界に深く没入していった。」
- 「主人公の○○の言葉が、私の胸に突き刺さった。それは、まるで長年抱えていた悩みを言い当てられたかのような、衝撃だった。」
- 具体的な描写を心がける
- 五感を意識した表現を取り入れる
- 比喩表現を活用する
- 最も心に残った場面や感情を鮮やかに表現する
- 普遍的なテーマに関する問いかけを選ぶ
- 読書感想文のテーマと関連付ける
- 比喩的な表現や反語的な表現を使う
- 問いかけに対する自分の考えを提示する
- 読書感想文のテーマと関連性の高い箇所を選ぶ
- 著作権に配慮する
- 出典を明記する
- 必要に応じて引用文を修正する
- 自分の文章と自然に繋がるように配置する
- 直喩:「まるで~のようだ」「~のような」
- 隠喩:「~は~だ」
- 物語の舞台の描写:風景、天気、時間帯
- 登場人物の描写:外見、性格、行動
- 感情の描写:表情、仕草、言葉遣い
- 視覚:「夕焼け空が、まるで燃えるように赤く染まっていた」
- 聴覚:「雨の音が、しとしとと静かに降り注ぎ、心を落ち着かせてくれた」
- 嗅覚:「焼きたてのパンの香ばしい匂いが、食欲をそそった」
- 味覚:「一口食べると、甘酸っぱいイチゴの味が口の中に広がり、幸せな気分になった」
- 触覚:「冷たい風が、肌を刺すように吹きつけ、身が引き締まる思いがした」
- 文章を書き終えた後に行う
- 声に出して読む
- ワープロソフトのスペルチェック機能や文法チェック機能を利用する
- 時間を置いてから再度確認する
- 序論、本論、結論という構成要素が適切に配置されているか
- 各段落がスムーズにつながっているか
- 接続詞が適切に使われているか
- 読者の視点に立って文章を読む
- 第三者に読んでもらい、意見を聞く
- 読書感想文の目的を明確に伝える
- 率直な意見を求める
- 複数の人から意見を聞く
- 文章の構成、内容の理解度、表現の適切さなどを中心に意見を求める
- 難しい言葉を使わず、わかりやすい言葉で書く
- 物語のあらすじを簡単にまとめる
- 心に残った場面や登場人物について、具体的に書く
- 自分の言葉で、素直な気持ちを表現する
- 物語のあらすじを簡単にまとめる
- 登場人物の心情や行動を分析する
- 物語のテーマについて考察する
- 自分自身の考えを深める
- 論理的な構成で文章を組み立てる
- 与えられたテーマを深く掘り下げる
- 独自の視点から分析する
- 社会問題や哲学的な考察を加える
- 自分自身の考えを深める
- 論理的な構成と表現力を意識する
- タグを使用すると、より見やすくなります。
長音記号(ー)は、音を伸ばす際に使用します。
ただし、安易に長音記号を使うことは避けましょう。
例えば、「コンピューター」を「コンピュータ」と表記するなど、できる限り正しい表記を心がけましょう。
その他にも、様々な記号が存在しますが、読書感想文でよく使うのは、上記で紹介したものです。
これらの記号のルールをしっかりと理解し、正しく使うように心がけましょう。
句読点や記号の使い方は、文章の印象を大きく左右します。
正しい使い方を身につけ、読みやすく、美しい文章を目指しましょう。
これらのルールを守ることで、減点を防ぎ、高評価を得られる可能性が高まります。
読書感想文の構成:心に響く文章の組み立て方
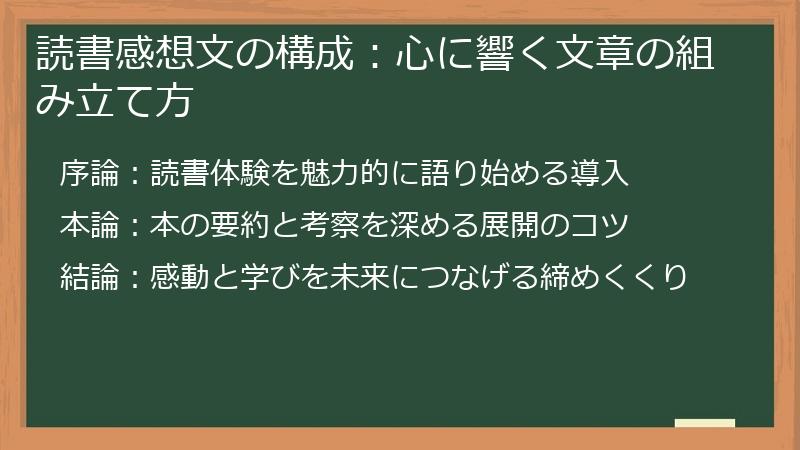
読書感想文は、ただ本の感想を書くだけではありません。
読者の心に響く、感動や学びを伝えるためには、しっかりとした構成が不可欠です。
このセクションでは、読書感想文の基本的な構成要素である序論、本論、結論について、それぞれの役割と書き方のコツを詳しく解説します。
構成を理解することで、自分の考えを整理し、論理的な文章を組み立てることができるようになります。
序論:読書体験を魅力的に語り始める導入
読書感想文の成否は、最初の数行、つまり序論で決まると言っても過言ではありません。
序論は、読者の興味を引きつけ、本文への期待感を高めるための重要な役割を担っています。
魅力的な序論を書くことで、読者はあなたの読書体験に共感し、最後まで読み進めてくれるでしょう。
序論で最も大切なことは、読書体験を鮮やかに表現することです。
本を読んだ時の最初の印象、心を揺さぶられた場面、強く共感した登場人物など、具体的なエピソードを交えながら、読書体験を生き生きと語り始めましょう。
例えば、以下のような書き出しが考えられます。
これらの書き出しは、読者の好奇心を刺激し、本文への期待感を高める効果があります。
また、序論では、本の簡単な紹介をすることも効果的です。
本のタイトル、著者名、簡単なあらすじなどを簡潔に紹介することで、読者は物語の全体像を把握しやすくなります。
ただし、ネタバレには注意が必要です。
まだ本を読んでいない読者のために、核心的な部分には触れないようにしましょう。
さらに、序論では、読書感想文のテーマを提示することも重要です。
この本を通して何を学び、何を感じたのか、どのような視点から感想を述べるのかを明確にすることで、読者はあなたの文章の方向性を理解しやすくなります。
序論を書く上で、最も大切なことは、オリジナリティです。
他の人の文章を参考にすることは大切ですが、決して模倣してはいけません。
自分自身の言葉で、自分自身の読書体験を語ることが、読者の心を掴むための最も効果的な方法です。
魅力的な序論は、読書感想文を成功させるための鍵となります。
読者の心を掴む、オリジナリティ溢れる序論を書き上げましょう。
序論で書くべきこと
これらの要素を意識することで、読者の心に響く、魅力的な序論を書くことができるでしょう。
本論:本の要約と考察を深める展開のコツ
本論は、読書感想文の中心となる部分であり、本の要約と、それに対するあなたの考察を深める役割を担っています。
序論で読者の興味を引いた後、本論で具体的な内容を展開することで、読者はあなたの読書体験をより深く理解し、共感してくれるでしょう。
本論では、まず本の要約を行います。
物語のあらすじ、登場人物、重要な出来事などを簡潔にまとめ、読者に物語の全体像を把握させます。
ただし、単なるあらすじの羅列にならないように注意が必要です。
要約は、あくまであなたの考察を深めるための手段であり、物語の核心に迫るための足掛かりとして活用しましょう。
要約が終わったら、いよいよ考察に入ります。
考察では、本を読んで感じたこと、考えたこと、学んだことなどを、自分の言葉で表現します。
物語のテーマ、登場人物の心情、社会問題との関連など、様々な視点から考察を深めることで、読者はあなたの知的な探求心に感銘を受けるでしょう。
考察を深めるためには、具体的な根拠を示すことが重要です。
物語の具体的な場面を引用したり、登場人物のセリフを引用したりすることで、あなたの考察に説得力が増します。
ただし、引用は必要最小限に留め、引用ばかりにならないように注意しましょう。
また、考察では、自分の体験や知識と関連付けることも効果的です。
自分の過去の経験、現在の状況、将来の展望などを織り交ぜながら、物語との共通点や相違点を見つけることで、読者はあなたの人間性に触れ、共感を覚えるでしょう。
本論を書く上で、最も大切なことは、論理的な思考です。
自分の考えを整理し、根拠を示しながら、論理的に文章を展開することで、読者はあなたの主張を理解しやすくなります。
本論で書くべきこと
これらの要素を意識することで、読者の心に響く、深みのある本論を書くことができるでしょう。
本論は、読書感想文の核となる部分です。
じっくりと時間をかけて、自分の考えを深め、オリジナリティ溢れる本論を書き上げましょう。
結論:感動と学びを未来につなげる締めくくり
結論は、読書感想文の締めくくりとして、あなたの読書体験を総括し、未来への展望を示す重要な役割を担っています。
序論で提示したテーマを再確認し、本論で深めた考察をまとめ、読者に感動と学びを与えるような、印象的な締めくくりを目指しましょう。
結論では、まず本論で述べた考察を簡潔にまとめます。
本のテーマ、登場人物の心情、社会問題との関連など、最も重要なポイントを絞り込み、読者にあなたの主張を再確認させます。
ただし、単なる要約の繰り返しにならないように注意が必要です。
結論は、あくまであなたの読書体験の集大成であり、未来への展望を示すための準備段階として捉えましょう。
次に、本を通して得た感動や学びを、自分の言葉で表現します。
この本を読んで何を感じ、何を考え、何を得たのか、具体的なエピソードを交えながら、読者にあなたの心の変化を伝えます。
読者は、あなたの感動や学びを通して、自分自身の読書体験を振り返り、新たな発見や気づきを得るでしょう。
そして、最も重要なのは、未来への展望を示すことです。
この本を通して学んだことを、今後の人生にどのように活かしていくのか、具体的な目標や行動計画を提示することで、読者はあなたの成長を期待し、応援してくれるでしょう。
例えば、以下のような締めくくりが考えられます。
これらの締めくくりは、読者に感動と学びを与え、未来への希望を抱かせる効果があります。
結論を書く上で、最も大切なことは、ポジティブな姿勢です。
読書体験を通して得た感動や学びを、未来への糧とし、前向きな気持ちで締めくくることで、読者はあなたの成長を祝福し、共感してくれるでしょう。
結論で書くべきこと
これらの要素を意識することで、読者の心に深く刻まれる、感動的な結論を書くことができるでしょう。
結論は、読書感想文の最後のメッセージです。
未来への希望を込めて、力強く締めくくりましょう。
読書感想文のテーマ選び:オリジナリティ溢れる視点を見つける
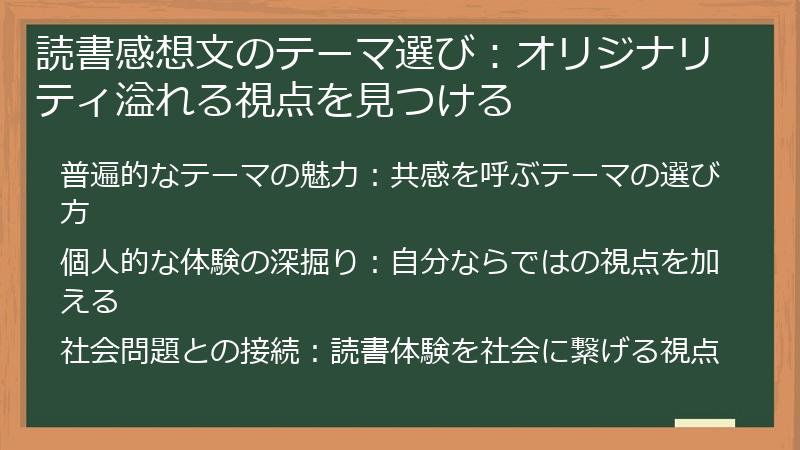
読書感想文のテーマ選びは、単に本の内容をまとめるだけでなく、自分自身の考えや視点を表現する上で非常に重要です。
テーマをしっかりと定めることで、文章全体の方向性が明確になり、より深く、オリジナリティ溢れる読書感想文を書くことができます。
このセクションでは、普遍的なテーマの魅力から、個人的な体験の深掘り、社会問題との接続まで、読書感想文のテーマを見つけるための様々な視点を紹介します。
普遍的なテーマの魅力:共感を呼ぶテーマの選び方
読書感想文のテーマとして、普遍的なテーマを選ぶことは、多くの読者の共感を呼び、心に響く文章を書くための有効な手段です。
普遍的なテーマとは、時代や文化を超えて、多くの人々に共通する感情や経験、価値観を指します。
例えば、愛、友情、勇気、希望、喪失、成長などが挙げられます。
これらのテーマは、誰にとっても身近であり、共感しやすいという特徴があります。
普遍的なテーマを選ぶメリットは、読者が自分の体験や感情と重ね合わせやすく、物語の世界に没入しやすい点にあります。
読者は、あなたの文章を通して、自分自身の人生を振り返り、新たな発見や気づきを得るかもしれません。
例えば、友情をテーマにした読書感想文を書く場合、物語の中の登場人物たちの友情関係を通して、自分自身の友人関係について考察することができます。
友情とは何か、友情を育むために大切なことは何か、友情を失った時の悲しみなど、様々な角度から考察を深めることで、読者は友情の尊さを改めて認識し、感謝の気持ちを抱くでしょう。
また、愛をテーマにした読書感想文を書く場合、物語の中の恋愛関係を通して、自分自身の恋愛観について考察することができます。
愛とは何か、愛を育むために必要なことは何か、失恋の痛みなど、様々な角度から考察を深めることで、読者は愛の深さや複雑さを理解し、恋愛に対する新たな視点を得るでしょう。
普遍的なテーマを選ぶ際には、物語の内容と自分の体験や感情を照らし合わせ、最も心に響くテーマを選ぶことが大切です。
無理にテーマを選ぶのではなく、自然な流れで湧き上がってくる感情や思考を大切にしましょう。
普遍的なテーマは、多くの読者の共感を呼ぶ反面、他の人と似たような内容になりやすいというデメリットもあります。
オリジナリティを出すためには、自分自身の視点や体験を積極的に取り入れ、他の人とは違う、あなただけの読書感想文を書くように心がけましょう。
普遍的なテーマの例
これらのテーマは、多くの人々に共通する感情や経験であり、読者の共感を呼びやすいでしょう。
個人的な体験の深掘り:自分ならではの視点を加える
読書感想文をより魅力的なものにするためには、個人的な体験を深掘りし、自分ならではの視点を加えることが重要です。
本の内容と自分の体験を結びつけることで、読者に共感を与え、印象的な文章を作り上げることができます。
個人的な体験を深掘りするとは、過去の出来事や感情、現在の悩みや葛藤などを掘り下げて考えることです。
読んだ本の内容と、自分の体験との共通点や相違点を見つけ出し、それらを比較検討することで、新たな発見や気づきを得ることができます。
例えば、主人公が困難に立ち向かう物語を読んだ場合、自分自身が過去に困難に立ち向かった経験を振り返り、その時の感情や行動を分析することができます。
そして、主人公の行動と自分の行動を比較し、どのような点が同じで、どのような点が異なっているのかを考察することで、自分自身の成長や課題を見つけることができます。
また、恋愛小説を読んだ場合、自分自身の恋愛経験を振り返り、物語の中の恋愛模様と照らし合わせることができます。
過去の恋愛で感じた喜びや悲しみ、後悔などを思い出し、物語の中の登場人物たちの心情と重ね合わせることで、恋愛に対する新たな視点を得ることができます。
個人的な体験を深掘りする際には、正直な気持ちで向き合うことが大切です。
過去の失敗や恥ずかしい出来事など、目を背けたくなるようなことでも、ありのままに受け止め、考察することで、より深みのある文章を書くことができます。
自分ならではの視点を加えるためには、固定観念にとらわれず、自由な発想で考えることが重要です。
物語の内容を鵜呑みにするのではなく、批判的な視点や疑問を持つことで、新たな解釈や発見が生まれることがあります。
例えば、一般的に良いとされていることでも、本当に良いことなのか、別の視点から見てみるとどうなのか、などを考えてみることで、自分ならではのユニークな視点を見つけることができます。
個人的な体験を深掘りする際のポイント
自分自身の体験を深く掘り下げ、自分ならではの視点を加えることで、読者に感動を与え、記憶に残る読書感想文を書くことができるでしょう。
社会問題との接続:読書体験を社会に繋げる視点
読書感想文を書く際に、社会問題との接続を意識することで、読書体験をより深く、意義のあるものにすることができます。
物語の内容を社会的な視点から捉え、現実世界の問題と関連付けることで、読者に新たな気づきを与え、社会に対する関心を高めることができます。
社会問題との接続とは、物語の中に描かれているテーマや出来事を、現代社会が抱える問題と結び付けて考察することです。
例えば、貧困、差別、環境問題、格差、人権侵害などが挙げられます。
これらの問題は、私たちの社会に深く根付いており、多くの人々の生活に影響を与えています。
物語の中に、貧困に苦しむ人々が登場する場合、現代社会における貧困問題を考察することができます。
貧困の原因、貧困がもたらす影響、貧困を解決するための対策などについて、様々な角度から考察することで、読者は貧困問題に対する理解を深め、解決に向けて行動を起こすきっかけになるかもしれません。
また、物語の中に、人種差別や性差別などの差別が登場する場合、現代社会における差別問題を考察することができます。
差別の原因、差別の影響、差別をなくすための方法などについて、様々な角度から考察することで、読者は差別問題に対する意識を高め、差別のない社会を実現するために貢献できるかもしれません。
社会問題との接続を意識する際には、客観的な視点を持つことが大切です。
自分の意見や感情だけでなく、様々な情報源を参考にしながら、多角的に考察することで、より深い理解を得ることができます。
また、物語の内容を現実世界の社会問題と関連付ける際には、安易な結論を出さないように注意が必要です。
社会問題は複雑であり、一概に解決策を提示することは難しい場合があります。
重要なのは、問題を提起し、読者に考えるきっかけを与えることです。
社会問題との接続におけるポイント
読書体験を社会に繋げる視点を持つことで、読書感想文は単なる個人的な感想文から、社会に対するメッセージを発信する手段へと変わるでしょう。
読書感想文の書き出しから完成まで:表現力UPの秘訣
読書感想文を書き始める際、最初の書き出しに悩む人は少なくありません。
しかし、魅力的な書き出しは、読者の心を掴み、最後まで読んでもらうための重要な要素です。
また、表現力を磨くことで、読書体験をより豊かに、そして効果的に伝えることができます。
この大見出しでは、読者の心を掴む書き出しのテクニックから、表現力を高めるための具体的な方法、そして完成度を高めるための推敲と見直しまで、読書感想文を書き上げるための実践的な秘訣を余すことなく解説します。
読書感想文の書き出し:読者の心を掴む第一印象
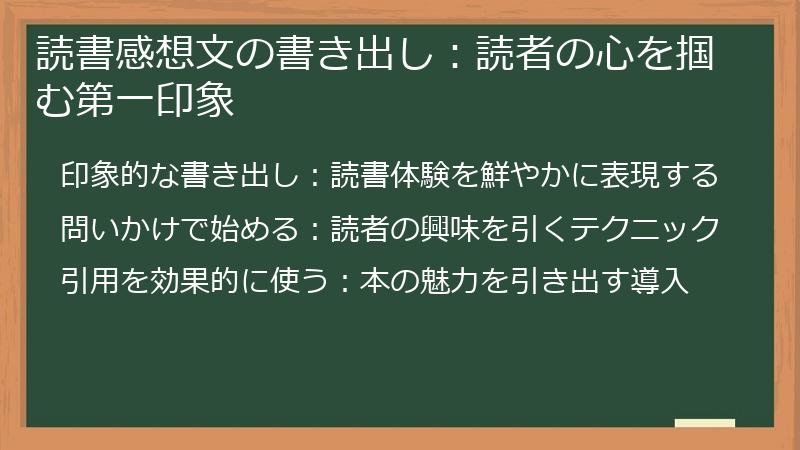
読書感想文において、書き出しは非常に重要な役割を果たします。
最初の数行で読者の興味を引きつけ、本文へとスムーズに誘導することで、読者はあなたの文章に引き込まれ、最後まで読み進めてくれるでしょう。
このセクションでは、印象的な書き出し、問いかけで始めるテクニック、引用を効果的に使う方法など、読者の心を掴むための書き出しの秘訣を伝授します。
印象的な書き出し:読書体験を鮮やかに表現する
読書感想文の書き出しで、読者の心を一瞬で奪うためには、読書体験を鮮やかに表現することが重要です。
まるで映画のオープニングシーンのように、読者の五感を刺激し、物語の世界へと引き込むような、印象的な書き出しを目指しましょう。
印象的な書き出しは、読者の好奇心を刺激し、「この先には何が書かれているのだろう?」という期待感を抱かせます。
読者は、あなたの文章に引き込まれ、最後まで読み進めてくれるでしょう。
読書体験を鮮やかに表現するためには、具体的な描写を心がけることが大切です。
例えば、「面白かった」という一言で済ませるのではなく、「どのような点が面白かったのか」「どのような感情を抱いたのか」を具体的に描写することで、読者はあなたの体験を追体験することができます。
また、五感を意識した表現を取り入れることも効果的です。
例えば、物語の舞台となった場所の風景、登場人物たちの声、物語の中に登場する食べ物の匂いなど、五感を刺激する描写を加えることで、読者は物語の世界をよりリアルに感じることができます。
さらに、比喩表現を活用することもおすすめです。
比喩表現とは、あるものを別のものに例えて表現する技法のことです。
例えば、「この本は、まるで人生の縮図のようだった」というように、比喩表現を使うことで、読者はあなたの読書体験をより深く理解することができます。
印象的な書き出しの例をいくつか紹介します。
これらの書き出しは、読者の五感を刺激し、物語の世界へと引き込む効果があります。
印象的な書き出しを書くためには、読書体験を振り返り、最も心に残った場面や感情を鮮やかに表現することが大切です。
あなたの言葉で、あなただけの読書体験を語り、読者の心を掴みましょう。
印象的な書き出しを書くためのポイント
問いかけで始める:読者の興味を引くテクニック
読書感想文の書き出しで、読者の興味を効果的に引きつけるテクニックの一つが、問いかけで始める方法です。
問いかけは、読者の思考を刺激し、本文への関心を高める効果があります。
読者は、問いかけに対する答えを探しながら、あなたの文章を読み進めてくれるでしょう。
問いかけで始める際には、読者が共感しやすい、普遍的なテーマに関する問いかけを選ぶことが重要です。
例えば、「あなたは、友情とは何だと思いますか?」「あなたは、幸せとは何だと思いますか?」「あなたは、人生で最も大切なものは何だと思いますか?」など、読者自身の価値観や経験と関連付けやすい問いかけは、読者の興味を引きつけやすく、効果的です。
また、問いかけは、読書感想文のテーマと関連付けることも重要です。
例えば、友情をテーマにした読書感想文を書く場合、「この物語を読んで、私は友情について深く考えさせられました。あなたは、友情とは何だと思いますか?」というように、問いかけとテーマを明確に結びつけることで、読者はあなたの文章の方向性を理解しやすくなります。
問いかけの形式は、直接的な質問だけでなく、比喩的な表現や反語的な表現を使うこともできます。
例えば、「この物語は、まるで人生という迷路のようだった。私たちは、その迷路の中で、何を求めて彷徨うのだろうか?」というように、比喩的な表現を使うことで、読者の想像力を刺激し、より深い思考を促すことができます。
問いかけで始める際には、読者に答えを求めるだけでなく、自分自身の考えや意見を提示することも重要です。
例えば、「あなたは、友情とは何だと思いますか?私は、友情とは、お互いを尊重し、支え合う関係だと思います。」というように、問いかけに対する自分の考えを提示することで、読者はあなたの人間性に触れ、共感を覚えるでしょう。
問いかけで始める際のポイント
問いかけで始めることで、読者の知的好奇心を刺激し、読書感想文への興味を効果的に高めることができるでしょう。
引用を効果的に使う:本の魅力を引き出す導入
読書感想文の書き出しで、本の魅力を効果的に引き出すためには、適切な引用を用いることが有効です。
引用は、読者の興味を引きつけ、物語の世界観を伝えるだけでなく、あなたの考察を深めるための足がかりにもなります。
しかし、引用は使い方を間違えると、読書感想文全体の印象を損ねてしまう可能性もあります。
ここでは、引用を効果的に使うためのポイントを解説します。
引用する際には、まず引用箇所を選ぶことが重要です。
物語の中で最も印象に残ったセリフ、物語のテーマを象徴する一文、読者の心を揺さぶる描写など、読書感想文のテーマと関連性の高い箇所を選びましょう。
引用箇所を選ぶ際には、著作権に配慮することも重要です。
引用は、自分の文章を補強するためのものであり、引用部分が文章全体の主にならないように注意しましょう。
引用する際には、出典を明記することが必須です。
本のタイトル、著者名、ページ番号などを正確に記載し、読者が引用箇所を特定できるようにしましょう。
引用文は、そのまま書き写すだけでなく、必要に応じて修正することもできます。
例えば、長すぎる文章を短くしたり、分かりにくい言葉を簡単な言葉に置き換えたりすることで、読者は引用文をより理解しやすくなります。
ただし、引用文を修正する際には、元の意味を変えないように注意が必要です。
引用文は、自分の文章と自然に繋がるように配置することが大切です。
引用文の前後に、自分の考えや意見を加え、引用文が唐突に現れることがないようにしましょう。
引用を効果的に使うためのポイント
引用を効果的に使うことで、読書感想文の説得力が増し、本の魅力をより効果的に伝えることができるでしょう。
読書感想文の書き方:表現力を磨くテクニック
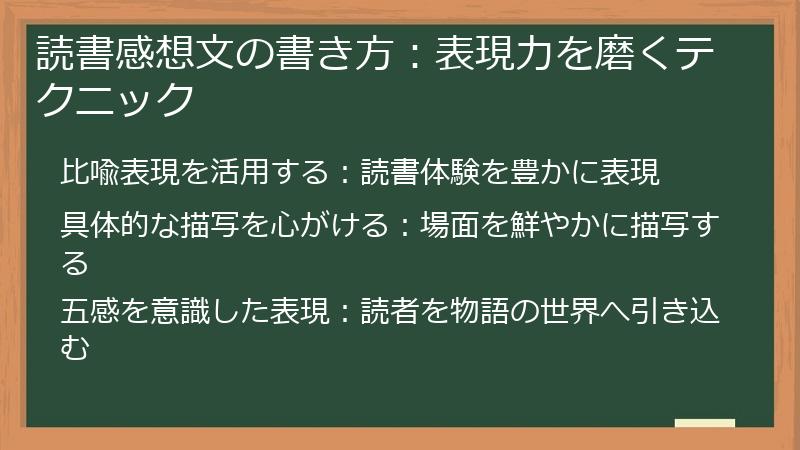
読書感想文は、単に本の感想を述べるだけでなく、自分の考えや感情を表現する場でもあります。
表現力を磨くことで、読者はあなたの文章に引き込まれ、より深く共感してくれるでしょう。
このセクションでは、比喩表現の活用、具体的な描写、五感を意識した表現など、表現力を磨くためのテクニックを伝授します。
比喩表現を活用する:読書体験を豊かに表現
読書感想文の表現力を高めるために、比喩表現は非常に有効な手段です。
比喩表現とは、あるものを別のものに例えて表現する技法のことで、読者の想像力を刺激し、文章に深みと奥行きを与える効果があります。
比喩表現を効果的に使うことで、読者はあなたの読書体験をより豊かに感じ、共感してくれるでしょう。
比喩表現には、主に直喩(ちょくゆ)と隠喩(いんゆ)の2種類があります。
直喩は、「まるで~のようだ」というように、あるものを別のものに直接的に例える表現です。
隠喩は、「~は~だ」というように、あるものを別のものに暗示的に例える表現です。
どちらの比喩表現を使うかは、文章の表現や目的に合わせて選びましょう。
比喩表現を使う際には、読者が理解しやすい、身近なものに例えることが重要です。
例えば、「この物語は、まるで人生の縮図のようだった」というように、人生という誰にとっても身近なものに例えることで、読者は物語の内容をより深く理解することができます。
また、五感を刺激するような比喩表現を使うことも効果的です。
例えば、「主人公の言葉は、まるで鋭いナイフのように、私の心に突き刺さった」というように、五感を刺激する表現を使うことで、読者は主人公の言葉の重みをよりリアルに感じることができます。
比喩表現を使う際には、使いすぎに注意することも重要です。
比喩表現を多用すると、文章が回りくどくなり、読者に伝わりにくくなってしまう可能性があります。
比喩表現は、効果的に使うことで文章に深みを与えることができますが、必要以上に使うことは避けましょう。
比喩表現の例
比喩表現を活用することで、読書体験を豊かに表現し、読者に深い印象を与えることができるでしょう。
具体的な描写を心がける:場面を鮮やかに描写する
読書感想文の表現力を高めるためには、具体的な描写を心がけることが非常に重要です。
具体的な描写とは、物語の場面、登場人物、感情などを、詳細かつ鮮やかに描写することです。
具体的な描写をすることで、読者はあなたの文章を通して、物語の世界をリアルに体験することができます。
具体的な描写をする際には、五感を意識することが大切です。
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚など、五感をフル活用して描写することで、読者は物語の世界をより鮮やかにイメージすることができます。
例えば、物語の舞台が森の中である場合、木々の緑、鳥のさえずり、土の匂い、木漏れ日の暖かさなどを描写することで、読者はまるで森の中にいるかのような感覚を味わうことができます。
また、登場人物の感情を描写する際には、表情、仕草、言葉遣いなどを細かく描写することで、読者は登場人物の感情をより深く理解することができます。
例えば、主人公が悲しんでいる場合、目に涙を浮かべている、肩を震わせている、声が震えているなどを描写することで、読者は主人公の悲しみをよりリアルに感じることができます。
具体的な描写をする際には、客観的な視点と主観的な視点をバランス良く取り入れることが重要です。
客観的な視点とは、物語の状況を第三者の視点から描写することです。
主観的な視点とは、登場人物の視点から物語の状況を描写することです。
客観的な視点と主観的な視点をバランス良く取り入れることで、読者は物語の世界をより多角的に理解することができます。
具体的な描写の例
具体的な描写を心がけることで、読書感想文は単なる感想文から、読者を物語の世界へと誘う、魅力的な文章へと生まれ変わるでしょう。
五感を意識した表現:読者を物語の世界へ引き込む
読書感想文の表現力を飛躍的に向上させるためには、五感を意識した表現を取り入れることが非常に効果的です。
五感を意識した表現とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚といった五感を刺激する言葉を使って、物語の場面や登場人物の感情を鮮やかに描写することです。
五感を意識した表現を取り入れることで、読者はまるで物語の世界にいるかのような感覚を味わい、より深く感情移入することができます。
例えば、視覚を意識した表現としては、「夕焼け空が、まるで燃えるように赤く染まっていた」というように、色や形を具体的に描写することで、読者は鮮やかな光景を思い浮かべることができます。
聴覚を意識した表現としては、「雨の音が、しとしとと静かに降り注ぎ、心を落ち着かせてくれた」というように、音の種類や大きさを具体的に描写することで、読者は静寂な空間を感じることができます。
嗅覚を意識した表現としては、「焼きたてのパンの香ばしい匂いが、食欲をそそった」というように、匂いの種類や強さを具体的に描写することで、読者は食欲を刺激されるでしょう。
味覚を意識した表現としては、「一口食べると、甘酸っぱいイチゴの味が口の中に広がり、幸せな気分になった」というように、味の種類や濃さを具体的に描写することで、読者は幸せな気分を味わうことができます。
触覚を意識した表現としては、「冷たい風が、肌を刺すように吹きつけ、身が引き締まる思いがした」というように、触感の種類や強さを具体的に描写することで、読者は身が引き締まるような感覚を味わうことができます。
五感を意識した表現を使う際には、比喩表現と組み合わせることで、より効果的に読者の五感を刺激することができます。
例えば、「雨の音は、まるで天使の歌声のように、優しく心に響いた」というように、比喩表現を使うことで、雨の音をより美しく、印象的に表現することができます。
五感を意識した表現の例
五感を意識した表現を取り入れることで、読書感想文は、読者を物語の世界へと誘う、臨場感あふれる文章へと進化するでしょう。
読書感想文の完成:推敲と見直しで完成度を高める
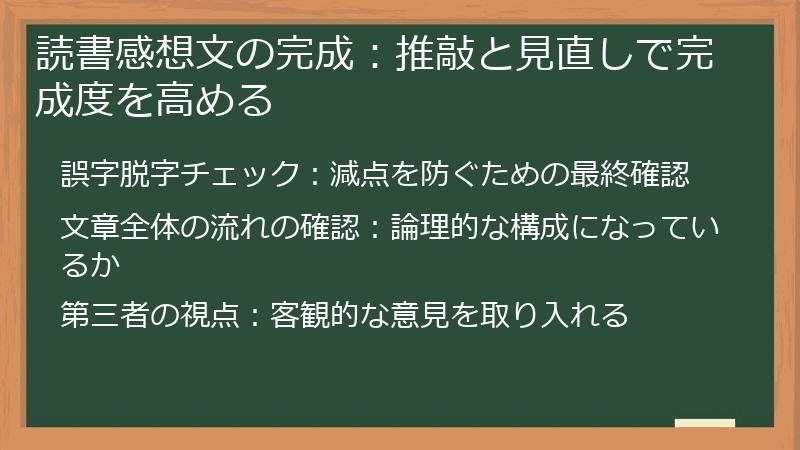
読書感想文を書き終えたら、そこで終わりではありません。
推敲と見直しを行うことで、文章の完成度を格段に高めることができます。
推敲と見直しは、文章の誤字脱字を修正するだけでなく、文章の流れや表現、論理構成などを改善する、重要なプロセスです。
このセクションでは、読書感想文の完成度を高めるための推敲と見直しのポイントを解説します。
誤字脱字チェック:減点を防ぐための最終確認
読書感想文の誤字脱字は、減点対象となるだけでなく、文章全体の印象を損ねてしまう可能性があります。
誤字脱字がないか、入念にチェックすることは、読書感想文を完成させる上で、非常に重要な作業です。
誤字脱字チェックは、必ず文章を書き終えた後に行いましょう。
書いている最中は、内容に集中しているため、誤字脱字を見落としやすいからです。
誤字脱字チェックをする際には、声に出して読むことをおすすめします。
声に出して読むことで、目で見るだけでは気づきにくい誤字脱字や、不自然な表現に気づきやすくなります。
また、音読することで、文章のリズムや流れを確認することもできます。
誤字脱字チェックをする際には、ワープロソフトのスペルチェック機能や文法チェック機能を利用することも有効です。
ただし、これらの機能は完璧ではないため、最終的には自分の目で確認することが重要です。
特に、人名や地名、専門用語などは、スペルチェック機能では誤りを検出できない場合があるため、注意が必要です。
誤字脱字チェックをする際には、時間を置いてから再度確認することも効果的です。
書き終えた直後は、文章に慣れてしまっているため、誤字脱字を見落としやすいからです。
時間を置いてから再度確認することで、客観的な視点で文章を見ることができ、誤字脱字を見つけやすくなります。
誤字脱字チェックのポイント
入念な誤字脱字チェックを行うことで、減点を防ぎ、より完成度の高い読書感想文に仕上げることができるでしょう。
文章全体の流れの確認:論理的な構成になっているか
読書感想文の完成度を高めるためには、文章全体の流れを確認し、論理的な構成になっているかをチェックすることが重要です。
論理的な構成とは、文章が首尾一貫しており、矛盾がなく、読者が理解しやすいように組み立てられていることを意味します。
文章全体の流れを確認する際には、まず序論、本論、結論という基本的な構成要素が、適切に配置されているかをチェックしましょう。
序論では、読者の興味を引きつけ、本文への導入となるような内容が書かれているか、本論では、本の要約や考察が深掘りされており、論理的な根拠に基づいているか、結論では、本論の内容をまとめ、読者にメッセージを伝えるような内容になっているかを確認しましょう。
文章全体の流れを確認する際には、各段落のつながりにも注意が必要です。
各段落がスムーズにつながり、論理的な飛躍がないか、段落間の関係性を明確にするための接続詞(例えば、「しかし」「したがって」「なぜなら」など)が適切に使われているかを確認しましょう。
文章全体の流れを確認する際には、読者の視点に立って文章を読むことが大切です。
読者は、あなたの文章を初めて読む人です。
読者があなたの文章を読んで、内容を理解しやすいか、共感できるか、面白いと感じるかを、客観的に評価しましょう。
文章全体の流れを確認する際には、第三者に読んでもらい、意見を聞くことも有効です。
第三者の意見を聞くことで、自分では気づかなかった文章の欠点や改善点を発見することができます。
文章全体の流れを確認する際のポイント
文章全体の流れを確認し、論理的な構成にすることで、読者にあなたの考えをより効果的に伝え、共感を呼ぶことができるでしょう。
第三者の視点:客観的な意見を取り入れる
読書感想文の完成度をさらに高めるためには、第三者の視点を取り入れ、客観的な意見を参考にすることが非常に有効です。
自分自身で書いた文章は、どうしても主観的な視点になりがちで、客観的な評価が難しくなります。
第三者に読んでもらい、意見を聞くことで、自分では気づかなかった文章の欠点や改善点を発見することができます。
第三者に意見を求める際には、読書感想文の目的を明確に伝えることが重要です。
例えば、「読者に感動を与えたい」「自分の考えを深く伝えたい」「先生に高評価をもらいたい」など、目的を伝えることで、第三者はあなたの目的に沿ったアドバイスをしてくれるでしょう。
第三者に意見を求める際には、遠慮せずに率直な意見を求めることが大切です。
良い点だけでなく、悪い点や改善点も指摘してもらうことで、文章の質を向上させることができます。
第三者からの意見は、必ずしもすべて受け入れる必要はありません。
しかし、複数の人から同じような指摘を受けた場合は、改善を検討する価値があるでしょう。
第三者に意見を求める際には、文章の構成、内容の理解度、表現の適切さなどを中心に意見を求めると効果的です。
例えば、「文章全体の流れはスムーズですか?」「内容を理解しやすいですか?」「表現は適切ですか?」「誤字脱字はありませんか?」など、具体的な質問をすることで、第三者は的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
第三者の視点を取り入れる際のポイント
第三者の視点を取り入れ、客観的な意見を参考にすることで、読書感想文はより洗練され、完成度の高いものへと進化するでしょう。
読書感想文 原稿用紙 書き方:よくある疑問と注意点
読書感想文を書く上で、多くの人が疑問に思うことや、注意すべき点があります。
例を参考にしたいけれど、どうすれば良いのか、ネタバレはどこまでOKなのか、著作権は?
この大見出しでは、読書感想文の書き方に関するよくある疑問に答え、減点を避けるための注意点を解説します。
成功例から学び、注意点を守って、自信を持って読書感想文に取り組みましょう。
読書感想文の例:成功例から学ぶ書き方のヒント
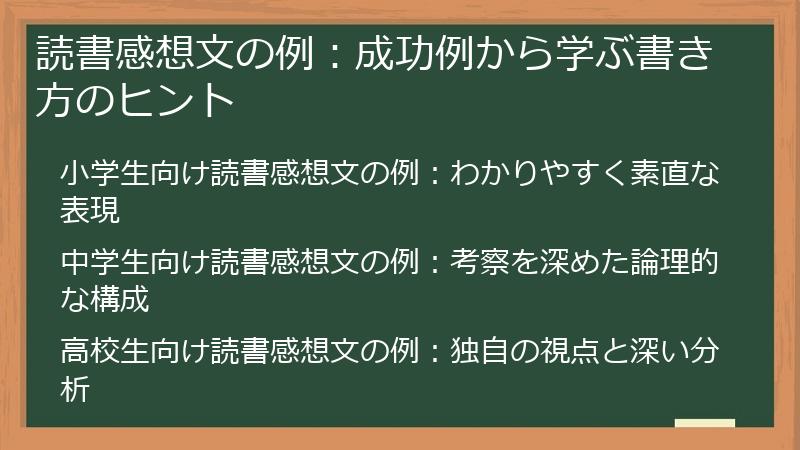
読書感想文の書き方に迷ったときは、成功例を参考にすることが、大きな助けとなります。
成功例は、構成、表現、視点など、読書感想文の書き方のヒントが詰まっています。
ただし、成功例をそのまま真似するのではなく、あくまで参考として、自分自身の読書体験に基づいて、オリジナルの読書感想文を書くように心がけましょう。
このセクションでは、小学生向け、中学生向け、高校生向けの読書感想文の例を紹介し、それぞれのレベルに合わせた書き方のヒントを解説します。
小学生向け読書感想文の例:わかりやすく素直な表現
小学生向けの読書感想文では、難解な表現や難しい言葉を使う必要はありません。
わかりやすく、素直な言葉で、自分の感じたことを表現することが大切です。
物語のあらすじを簡単にまとめ、心に残った場面や登場人物について、具体的なエピソードを交えながら、自分の言葉で語りましょう。
小学生向けの読書感想文の例を以下に示します。
例:『スイミー』を読んで
わたしは、『スイミー』という本を読んで、とても感動しました。
スイミーは、小さな魚でしたが、とてもかしこくて、ゆうかんでした。
スイミーは、大きな魚に食べられてしまった仲間たちの分まで、一生懸命に生きました。
わたしは、スイミーのように、どんなことがあっても、あきらめないで、一生懸命に生きたいと思いました。
特に、スイミーが、大きな魚のふりをして、仲間たちを守った場面が、心に残りました。
スイミーは、自分のことだけでなく、仲間たちのことも考えていて、すごいと思いました。
わたしも、スイミーのように、友達が困っていたら、助けてあげられるような、優しい人になりたいです。
『スイミー』を読んで、勇気をもらいました。
わたしも、スイミーのように、かしこくて、ゆうかんな人になりたいです。
この例では、難しい言葉を使わず、わかりやすく、素直な言葉で、自分の感じたことを表現しています。
また、具体的なエピソードを交えながら、どのように感動したのか、どのように感じたのかを、具体的に説明しています。
小学生向けの読書感想文を書く際には、自分の言葉で、素直な気持ちを表現することを心がけましょう。
小学生向け読書感想文を書く際のポイント
中学生向け読書感想文の例:考察を深めた論理的な構成
中学生向けの読書感想文では、小学生の時よりも、内容を深く掘り下げ、論理的な構成で文章を組み立てることが求められます。
単に物語のあらすじをまとめるだけでなく、登場人物の心情や行動を分析したり、物語のテーマについて考察したりするなど、自分自身の考えを深めることが重要です。
中学生向けの読書感想文の例を以下に示します。
例:『走れメロス』を読んで
太宰治の『走れメロス』は、友情の尊さを描いた不朽の名作として知られています。
物語は、シラクスの暴君ディオニスの暗殺を企てたメロスが、親友セリヌンティウスを人質に残し、妹の結婚式に出席するために故郷へ帰るという展開で始まります。
メロスは、様々な困難に遭遇しながらも、友情を信じて走り続けます。
私は、メロスが、友情のために、自らの命を懸ける覚悟を持っていたことに、深く感動しました。
メロスは、セリヌンティウスを裏切ることは、自分自身の存在意義を否定することだと考えていたのではないでしょうか。
また、セリヌンティウスが、メロスを信じて、自らを人質として差し出したことも、友情の深さを物語っていると思います。
セリヌンティウスは、メロスが必ず帰ってくると信じていたからこそ、そのような行動をとることができたのでしょう。
しかし、現代社会においては、メロスのような友情は、稀有なものとなっているのではないでしょうか。
SNSの発達により、私たちは、多くの人と簡単に繋がることができますが、その一方で、表面的な関係にとどまり、深い信頼関係を築くことが難しくなっています。
私は、メロスとセリヌンティウスのような、心の底から信頼できる友人を持ちたいと思いました。
『走れメロス』は、私に、友情の尊さを改めて教えてくれました。
この例では、物語のあらすじを簡単にまとめ、登場人物の心情や行動を分析し、物語のテーマについて考察しています。
また、現代社会との関連性にも触れ、自分自身の考えを深めています。
中学生向けの読書感想文を書く際には、内容を深く掘り下げ、論理的な構成で文章を組み立てることを心がけましょう。
中学生向け読書感想文を書く際のポイント
高校生向け読書感想文の例:独自の視点と深い分析
高校生向けの読書感想文では、与えられたテーマを深く掘り下げ、独自の視点から分析することが求められます。
単なる感想にとどまらず、社会問題や哲学的な考察を加え、自分自身の考えを深めることが重要です。
また、論理的な構成だけでなく、表現力も求められます。
高校生向けの読書感想文の例を以下に示します。
例:『カラマーゾフの兄弟』を読んで
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は、神、信仰、理性、自由意志といった、人間存在の本質に関わる深遠なテーマを扱った、哲学的な小説です。
物語は、父フョードル・カラマーゾフと、三人の息子、ドミートリー、イワン、アリョーシャを中心に展開されます。
父フョードルは、金銭欲と色欲にまみれた人物であり、息子たちとの関係は、複雑に絡み合っています。
ドミートリーは、情熱的で衝動的な性格であり、父との間で、グルーシェニカという女性を巡って激しい争いを繰り広げます。
イワンは、理性的で懐疑的な性格であり、神の存在を否定し、人間の自由意志を主張します。
アリョーシャは、信仰心の篤い青年であり、人々に愛と希望を与えようとします。
私は、イワンの「神がいなければ、すべてが許される」という言葉に、強い衝撃を受けました。
この言葉は、神の存在を否定し、人間の自由意志を肯定するものであり、現代社会における倫理観の崩壊を象徴しているように感じました。
しかし、アリョーシャの生き方は、イワンの考えとは対照的であり、人々に愛と希望を与えようとする姿は、現代社会において失われつつある、人間の優しさを象徴しているように感じました。
『カラマーゾフの兄弟』は、私に、人間存在の本質について深く考えさせられました。
この例では、物語の概要を説明し、登場人物の性格や思想を分析し、物語のテーマについて深く考察しています。
また、社会問題や哲学的な考察を加え、自分自身の考えを深めています。
高校生向けの読書感想文を書く際には、与えられたテーマを深く掘り下げ、独自の視点から分析することを心がけましょう。
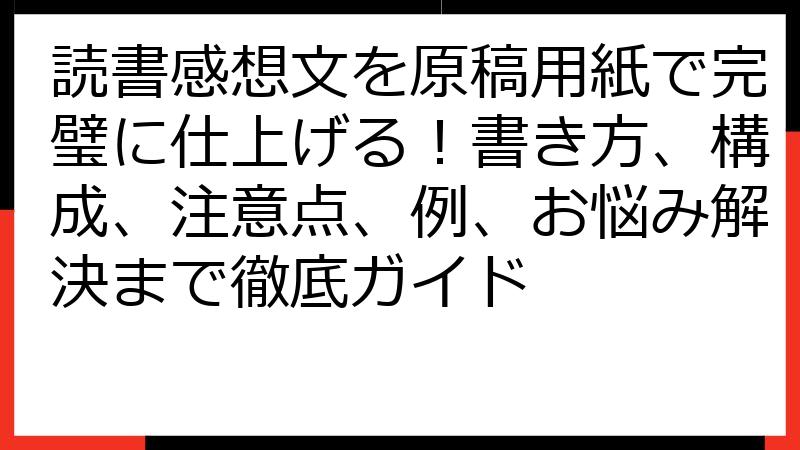
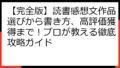
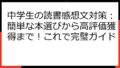
コメント