【高校生必見】読書感想文コンクールで入賞を狙う!基本から応用まで徹底攻略ガイド
高校生向けの読書感想文コンクールで、どうすれば入賞できるのか。
そんな悩みを抱えるあなたへ。
この記事では、数々のコンクールで実績のある専門家が、読書感想文の書き方を基本から応用まで、誰にでもわかるように徹底解説します。
たくさんの本を読んでも、どう文章にすれば良いか分からない。
自分の書いたものが、本当に評価されるのか不安。
そんなあなたのための、コンクール入賞への最短ルートがここにあります。
このガイドを読めば、あなたも自信を持ってコンクールに挑戦できるはずです。
さあ、最高の読書感想文を一緒に作り上げましょう。
読書感想文コンクールで差をつける!「題材選び」と「読解力」の秘密
読書感想文コンクールで入賞するためには、まず何よりも「題材選び」が重要です。
数ある本の中から、自分の心に響き、さらにコンクールのテーマや審査員に響く一冊を見つけることが、勝利への第一歩となります。
しかし、題材選びだけでなく、その本を深く理解し、自分の言葉で表現する「読解力」も不可欠です。
ここでは、コンクールで評価される題材の選び方から、本質を捉える読解力の鍛え方までを、具体的に解説していきます。
あなたの読書体験を、入賞へと繋がる確かな力に変えましょう。
コンクールのテーマに沿った「運命の一冊」の見つけ方
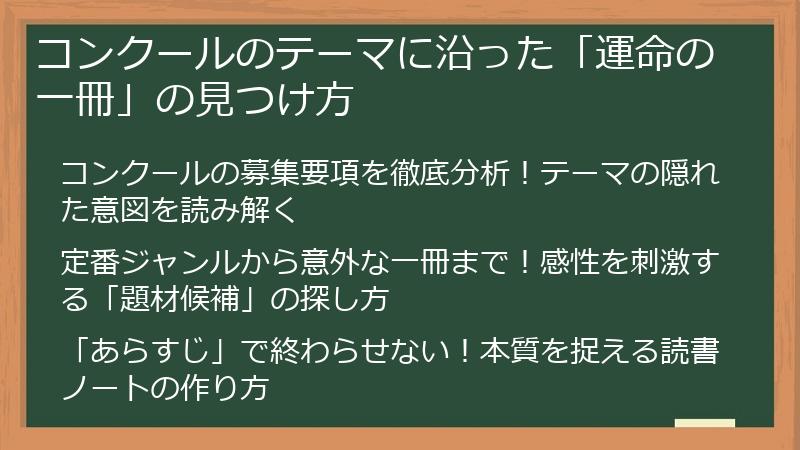
読書感想文コンクールで入賞するための最初の関門は、テーマに合った「運命の一冊」を見つけることです。
数多くの書籍の中から、あなたの個性を輝かせ、審査員の心を掴む本を選ぶための戦略をお伝えします。
単に好きな本を選ぶのではなく、コンクールの趣旨を理解し、そこに合致する作品を効果的に発掘するノウハウを習得しましょう。
このステップをマスターすれば、あなたの読書感想文は、他の作品とは一線を画すものとなるはずです。
コンクールの募集要項を徹底分析!テーマの隠れた意図を読み解く
コンクールの募集要項の読み方
- コンクールの目的と対象者を把握する。
- 過去の受賞作品の傾向を分析する。
- 「指定図書」がある場合は、その選定理由を考察する。
- 「自由図書」の場合は、どのようなテーマやジャンルが求められているかを推測する。
テーマの「キーワード」から本質を探る
- 募集要項に記載されている「キーワード」をリストアップする。
- それぞれのキーワードが持つ意味合いや、関連する概念を深掘りする。
- キーワードを組み合わせることで、コンクールが最も重視しているであろう「テーマの本質」を特定する。
「なぜこのテーマなのか」を考える
- コンクールが設定したテーマの背景にある社会的な課題や、現代に伝えたいメッセージを推測する。
- そのテーマを通して、読者にどのようなことを感じてほしいのか、どのような成長を促したいのかを考える。
- テーマの背後にある「問い」に、自分が読んだ本を通してどのように向き合えるかを検討する。
定番ジャンルから意外な一冊まで!感性を刺激する「題材候補」の探し方
「共感」と「疑問」が生まれる本に出会う
- 主人公の心情や経験に強く共感できる作品を探す。
- 物語の展開や登場人物の言動に対して、「なぜ?」と疑問を抱かせるような作品を選ぶ。
- 自分の日常や将来と結びつけやすいテーマを持つ本に注目する。
「自分だけの視点」を活かせる本を選ぶ
- 一般的な評価に左右されず、自分が純粋に面白いと感じた本を大切にする。
- 普段あまり読まないジャンルや、新進気鋭の作家の作品に触れてみる。
- 古典文学や名作でも、現代的な視点から新しい発見ができるような本を選ぶ。
コンクールで「埋もれない」ための視点
- 多くの人が選びそうな「定番」の作品でも、自分なりの新しい切り口や解釈を見つけられるものを選ぶ。
- 社会問題や多様性、AIなど、現代的なテーマを扱った作品を検討する。
- 絵本や漫画、ノンフィクションなど、ジャンルを問わず、自分の心を動かした一冊を探求する。
「あらすじ」で終わらせない!本質を捉える読書ノートの作り方
読書ノートの基本構成要素
- 本のタイトル、著者名、出版社、発行年月日を正確に記録する。
- 読書を始めた日と、読み終えた日を記録する。
- 簡単なあらすじを自分の言葉でまとめる(100字~200字程度)。
「なぜこの本を選んだか」を言語化する
- コンクールのテーマとの関連性や、自分がその本に惹かれた理由を具体的に記述する。
- 表紙の装丁やタイトルから感じた印象、期待などを書き留める。
- 本屋で平積みされていた、友人におすすめされたなど、出会いのエピソードも重要。
「心に残った箇所」とその理由を掘り下げる
- 印象的なセリフ、情景描写、出来事などを具体的に引用する。
- なぜその箇所が心に響いたのか、どのような感情や考えが生まれたのかを詳細に記述する。
- 引用した箇所が、物語全体のテーマやメッセージとどう繋がっているのかを考察する。
読書感想文の「核」を磨く!作者の意図を読み解く深層読解術
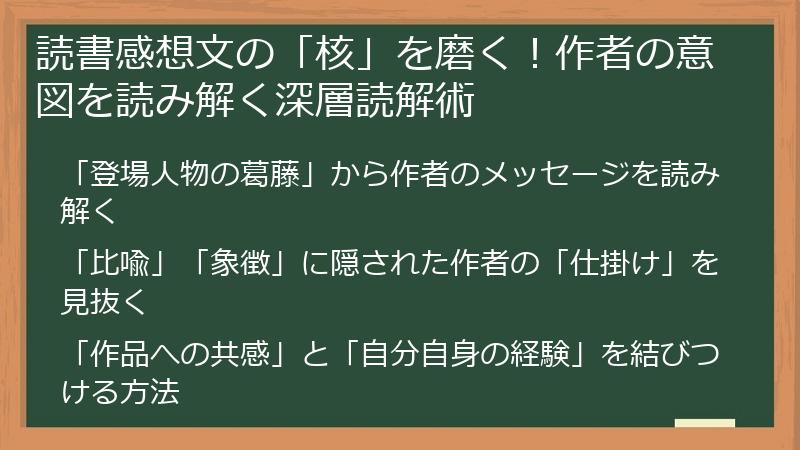
選んだ一冊の魅力を最大限に引き出すためには、作者が込めたメッセージや意図を深く理解することが不可欠です。
表面的なストーリーだけでなく、言葉の裏に隠された作者の想いや、作品が持つ社会的な意味合いまで読み解くことで、あなたの読書感想文は格段に深みを増します。
ここでは、作者の意図を的確に捉え、それを自分の言葉で表現するための実践的な読解術を伝授します。
このテクニックを習得すれば、あなたの感想文は、読後感にとどまらない、作者との対話のような感動を生み出すでしょう。
「登場人物の葛藤」から作者のメッセージを読み解く
登場人物の「行動」と「心理」の矛盾に注目する
- 主人公が、どのような状況で、どのような行動をとるのかを詳細に追う。
- その行動の裏にある、登場人物の複雑な心理や葛藤を推測する。
- 「本当はこうしたいのに、こうせざるを得ない」という状況に注目し、その原因を探る。
「セリフ」に隠された作者の意図を探る
- 登場人物が発する言葉の表面的な意味だけでなく、その言葉が発せられた状況や背景を考慮する。
- 同じ言葉でも、誰が、誰に、どのような感情で言っているのかで意味合いが変わることに注意する。
- 作者が、あえて特定の言葉を強調したり、繰り返し使ったりする意図を考える。
「物語の結末」が示す作者のメッセージを読み解く
- ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのか、あるいは曖昧な結末なのか、その結末が持つ意味を考察する。
- 物語全体を通して、作者が伝えたかった「教訓」や「問いかけ」は何なのかを考える。
- 結末が、登場人物たちの葛藤や成長にどのような影響を与えたのかを分析する。
「比喩」「象徴」に隠された作者の「仕掛け」を見抜く
印象的な「比喩表現」に隠された意味を探る
- 「~のようだ」「~である」といった比喩表現をリストアップする。
- その比喩が、何を何に例えているのか、その共通点や相違点を分析する。
- 作者がその比喩を用いることで、読者に何を伝えたいのか、どのような感情を抱かせたいのかを考察する。
「象徴的なモノ・コト」が持つメッセージを読み解く
- 物語の中に繰り返し登場するモノ(例:花、鳥、時計)や、特定の場面(例:雨、嵐、夜明け)に注目する。
- それらが、登場人物の心情や物語の展開、あるいは作者が伝えたいテーマとどのように関連しているかを考える。
- 例えば、雨が悲しみや絶望を、夜明けが希望や再生を象徴している場合があることを念頭に置く。
「作者の仕掛け」を読み解き、独自の解釈を形成する
- 比喩や象徴が、物語のどの部分で効果的に使われているかを特定する。
- それらの「仕掛け」が、物語のメッセージをどのように補強・強調しているかを分析する。
- 作者の意図を汲み取りつつ、自分自身の経験や価値観に基づいて、独自の解釈や感想を形成する。
「作品への共感」と「自分自身の経験」を結びつける方法
物語の出来事を「自分ごと」として捉え直す
- 主人公が経験した困難や喜びを、もし自分が同じ状況だったらどう感じるか、どう行動するかを想像する。
- 物語の中で描かれる人間関係や社会的な問題について、自分の身の回りで似たような経験がないかを探す。
- 作品に登場する価値観や考え方について、自分自身の考えや経験と照らし合わせてみる。
「感情の共有」を読書感想文の軸にする
- 物語を読んで抱いた、喜び、悲しみ、怒り、感動などの感情を具体的に言葉にする。
- なぜその感情が生まれたのか、その感情が自分自身のどのような経験や価値観に触れたからなのかを説明する。
- 感情の動きを丁寧に描写することで、読者も作品の世界に引き込む。
「学び」と「成長」を、具体的な行動に繋げる
- 作品から得た教訓や気づきを、今後の自分の人生にどのように活かせるかを考える。
- 読書を通して、自分の考え方や行動にどのような変化があったかを具体的に記述する。
- 「この本を読んで、〇〇をしようと思った」というように、具体的な行動目標を示すことで、読書体験の価値を高める。
「伝わる文章」を徹底追求!読者を引き込む構成と表現テクニック
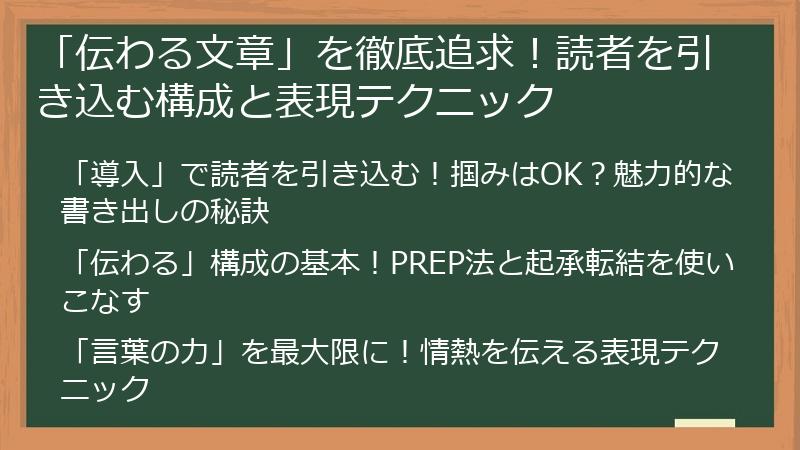
どんなに素晴らしい読書体験や深い洞察も、それを伝える文章が魅力的でなければ、審査員の心に響きません。
ここでは、読者を引き込み、感動を与えるための文章構成の基本から、説得力と共感力を高める具体的な表現テクニックまでを詳細に解説します。
あなたの読書体験を、読者が「もっと読みたい」と思わずにはいられない、魅力的な読書感想文へと昇華させましょう。
この技術をマスターすれば、あなたの感想文は、単なる感想を超え、読者との心の交流を生み出す作品となります。
「導入」で読者を引き込む!掴みはOK?魅力的な書き出しの秘訣
「意外性」や「疑問」で興味を引く
- 読書感想文の冒頭で、読者の予想を裏切るような意外な事実や、問いかけから始める。
- 「この本を読んで、私の世界は180度変わりました」のように、強いインパクトを与える言葉を選ぶ。
- 読者が「この先どうなるんだろう?」と続きを読みたくなるような、魅力的なフックを仕掛ける。
「共感」を呼ぶエピソードを盛り込む
- 物語のテーマや主人公の心情に、自分の経験や感情を重ね合わせて語り始める。
- 読者もきっと経験したことのあるような、普遍的な感情や悩みに触れる。
- 「あの時、私も同じように感じた」と思わせるような、読者の心に寄り添う言葉を選ぶ。
「コンクールのテーマ」との関連性を明確にする
- 冒頭で、選んだ本のテーマが、コンクールの募集テーマとどのように関連しているかを簡潔に示す。
- 「この物語は、〇〇というテーマについて深く考えさせられる作品です」のように、ストレートに伝えることも効果的。
- 読者に「なぜこの本を選んだのか」という理由を、冒頭で理解させることで、その後の内容への期待感を高める。
「伝わる」構成の基本!PREP法と起承転結を使いこなす
PREP法とは?結論から分かりやすく伝える技術
- Point(結論):まず、最も伝えたいこと(感想の核心)を端的に述べる。
- Reason(理由):なぜそう思うのか、その根拠となる本の具体的な箇所や作者の意図を説明する。
- Example(具体例):理由を補強するために、物語の場面や登場人物の行動などを引用・描写する。
- Point(結論の再提示):最後に、改めて結論を述べ、感想を締めくくる。
起承転結で、物語のように読ませる
- 起(導入):本との出会いや、作品の概要、コンクールのテーマとの関連性などを提示し、読者の興味を引く。
- 承(展開):物語のあらすじを簡潔に紹介しつつ、自分が特に心を動かされた場面や、作者の意図について掘り下げる。
- 転(転換):物語の核心となる葛藤や、作者のメッセージ、あるいは自分自身の新たな発見や考え方を提示し、文章に変化をつける。
- 結(結論):作品から学んだこと、今後の自分への影響、そして作者への感謝などを述べ、読後感に深みを与える。
「構成」を意識した推敲の重要性
- 書き終えたら、まず構成のバランスを確認する。導入、展開、結論が明確になっているか。
- PREP法や起承転結のフレームワークに沿って、各パートの内容が過不足なく記述されているかを見直す。
- 論理的なつながりが自然か、読者がスムーズに内容を追えるかを意識して、順番を入れ替えたり、接続詞を工夫したりする。
「言葉の力」を最大限に!情熱を伝える表現テクニック
「感情」を豊かに表現する語彙力を磨く
- 感動、驚き、悲しみ、喜びなど、様々な感情を表す類語辞典や表現集を活用する。
- 抽象的な感情表現だけでなく、「胸が締め付けられた」「心が温かくなった」のように、具体的な身体感覚と結びつけて表現する。
- 比喩や擬人化、感嘆符などを効果的に用い、文章に感情の起伏や色彩を与える。
「具体性」で読者の想像力を掻き立てる
- 情景描写では、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に訴えかける言葉を選ぶ。
- 登場人物の行動や仕草を、細部まで具体的に描写することで、キャラクターに生命を吹き込む。
- 抽象的な概念やメッセージも、具体的なエピソードや例え話を通して説明し、読者の理解を助ける。
「オリジナリティ」あふれる言葉で個性を光らせる
- ありきたりな表現を避け、自分自身の言葉で、独自の視点や感性を表現することを心がける。
- 作品のテーマや作者のメッセージを、自分なりの解釈で再構築し、独自の言葉で語り直す。
- 定型文やテンプレートに頼らず、自身の内面から湧き出る言葉で、読者に語りかけるような文章を目指す。
「自分らしさ」を最大限に!読書感想文で個性を輝かせる方法
読書感想文コンクールで入賞するには、他の応募者との差別化が重要です。
そこで鍵となるのが、「自分らしさ」、つまりあなたの個性や独自の視点をどのように作品に反映させるか、という点です。
ここでは、あなたの内面から湧き出る感性や経験を、作品の魅力として最大限に引き出すための具体的な方法を解説します。
あなたのユニークな読書体験を、審査員に強く印象づけるための戦略を学び、他の誰にも真似できない、あなただけの読書感想文を完成させましょう。
「あなただけの体験」を語る!共感を呼ぶエピソードの選び方
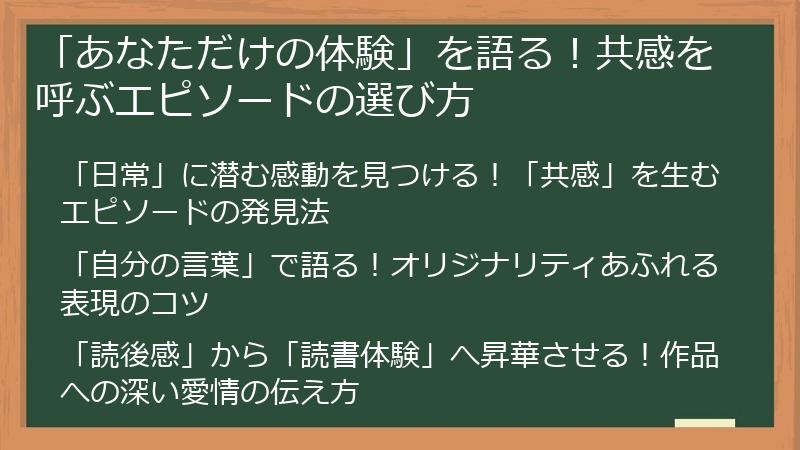
読書感想文は、単なるあらすじの要約や作品の分析だけでは、審査員の心を掴むことはできません。
あなたの個人的な体験や、作品から受けた感銘を、読者が「自分にも起こりうるかもしれない」「自分もそう感じた」と思えるように語ることが、共感を生み、あなたの感想文を特別なものにします。
ここでは、あなた自身のユニークな体験を、読者に響く形で効果的に盛り込むための具体的な方法を解説します。
このテクニックをマスターすれば、あなたの感想文は、作者や登場人物との対話だけでなく、読者との共感の輪を広げる力を持つでしょう。
「日常」に潜む感動を見つける!「共感」を生むエピソードの発見法
「なぜ?」「もしも?」から思考を広げる
- 物語の登場人物の行動や発言に対して、「もし自分が同じ立場だったら、どうするだろう?」と自問自答する。
- 作品で描かれている感情や状況が、自分の過去の経験や、友人・家族の体験とどのように重なるかを考える。
- 物語の展開や結末について、「こうだったらもっと良かったのに」「違う結末もあったのではないか」といった「もしもの世界」を想像する。
「些細な出来事」に隠された普遍的な感情を捉える
- 物語の中で、主人公が経験する何気ない日常の出来事や、ふとした瞬間の感情の揺れ動きに注目する。
- それらの「些細な」出来事が、自分自身の日常で起こったこととどのように結びつくか、共通の感情を見つける。
- 特別な体験だけでなく、喜び、悲しみ、不安、期待といった、誰もが経験する普遍的な感情に焦点を当てる。
「自分自身の変化」に気づく
- 本を読む前と読んだ後で、自分の考え方、感じ方、行動にどのような変化があったかを振り返る。
- 作品を通して、新たな視点や価値観を得た経験、あるいは自分の内面への気づきなどを具体的に書き出す。
- 「この本のおかげで、〇〇について以前より深く理解できるようになった」といった、自己成長に繋がったエピソードを大切にする。
「自分の言葉」で語る!オリジナリティあふれる表現のコツ
「型」にとらわれない自由な発想を大切にする
- 読書感想文のテンプレートや定型文に頼りすぎず、自分の感情や考えを素直に表現することを心がける。
- 「~と思います」「~と感じました」といった、主観的な言葉を効果的に使うことで、あなた自身の声で語っていることを示す。
- 物語の解釈も、一つの正解を求めるのではなく、自分ならではの視点や切り口で語ることで、オリジナリティを出す。
「比喩」や「例え」で、伝わりやすく、印象的に
- 抽象的な感情や概念を、具体的なモノや出来事に例えることで、読者の理解を助け、印象を深める。
- 例えば、「主人公の勇気は、暗闇に灯る一筋の光のようだった」のように、詩的な表現を用いる。
- 物語のテーマやメッセージを、自分自身の日常の出来事に結びつけて説明することで、より親近感を持たせる。
「疑問」や「葛藤」を正直に表現する
- 作品を読んで感じた疑問点や、主人公の行動に対する葛藤などを、正直に、そして丁寧に言葉にする。
- 「この場面の主人公の心情が、どうしても理解できなかった」「作者の意図が、ここでは読み取れなかった」といった率直な感想も、あなたの真摯な読書姿勢を示す。
- 疑問や葛藤を乗り越えて、最終的にどのような結論に至ったのか、その過程を描くことで、読者に発見や共感を与える。
「読後感」から「読書体験」へ昇華させる!作品への深い愛情の伝え方
「なぜこの本が好きなのか」を掘り下げる
- 作品のどの要素(ストーリー、キャラクター、テーマ、文体など)に最も惹かれたのかを具体的に特定する。
- その要素が、あなたの価値観や人生観とどのように結びついているのかを説明する。
- 「この本を読む前は〇〇だと思っていたけれど、この本を読んで考えが変わった」というような、具体的な変化を伝える。
「作者へのリスペクト」を込めて語る
- 作者が作品に込めたであろう想いや、作品を生み出すために費やしたであろう努力に敬意を表する。
- 作者の他の作品にも触れ、その作家の世界観や表現スタイルに対する自身の感想を述べる。
- 作者のメッセージが、現代社会においてどのような意味を持つのか、あるいは将来にどのように繋がっていくのかを考察する。
「感動の共有」を意識した丁寧な言葉遣い
- 読者に感動を伝えることを意識し、熱意のこもった、感情豊かな言葉を選ぶ。
- 専門用語や難しい言葉を多用するのではなく、誰にでも理解できる平易な言葉で、誠実に語りかける。
- 作品の感動を、単に「良かった」で終わらせず、「この作品に出会えて本当に良かった」「この感動を多くの人と共有したい」というような、読後感のその先にある感情を表現する。
「読書体験」を「読書感想文」に落とし込む!表現力を高める3つのポイント
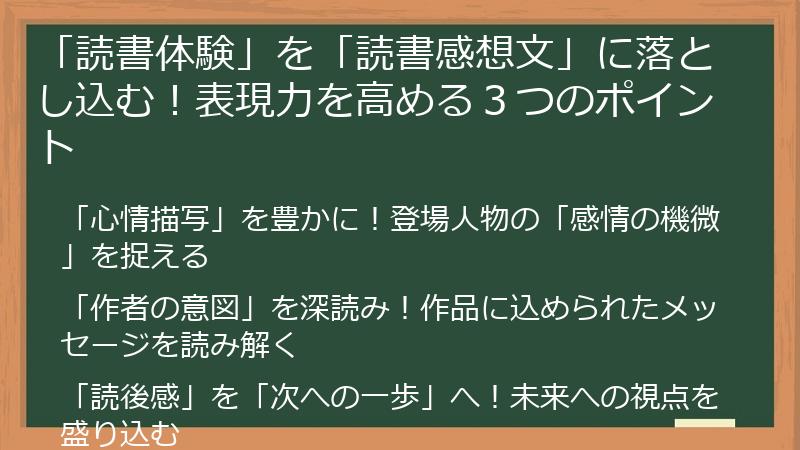
読書体験をどれだけ深くしても、それを魅力的な文章にできなければ、コンクールで評価されることはありません。
ここでは、あなたの読書体験を、審査員の心に響き、共感を呼ぶ「読書感想文」へと効果的に変換するための、具体的な表現力を高める3つのポイントを解説します。
「なんとなく良い」という感想から、「なぜ良いのか」「どう良かったのか」を明確に伝えられるようになるための、実践的なライティングスキルを身につけましょう。
あなたの言葉が、作品の魅力を増幅させ、読者を引きつける力となるはずです。
「心情描写」を豊かに!登場人物の「感情の機微」を捉える
「言葉」の裏にある「感情」を想像する
- 登場人物のセリフの「間」や、声のトーン、表情などを想像し、そこからどのような感情が読み取れるかを考える。
- 言葉そのものの意味だけでなく、その言葉が発せられた状況や、相手との関係性から、隠された感情を推測する。
- 「沈黙」や「ためらい」といった、言葉にならない部分にも、登場人物の心情のヒントが隠されていることに注目する。
「比喩」や「情景描写」と「感情」を結びつける
- 登場人物が置かれている状況や、その時の心情を、具体的な「比喩」や「情景描写」と結びつけて表現する。
- 例えば、「彼女の心は、嵐の前の静けさのように張り詰めていた」のように、外界の様子と内面の感情を重ね合わせる。
- 桜が散る様子を見て切なさを感じたり、雨音を聞いて孤独を感じたりするなど、自然現象と心情の繋がりを描写する。
「共感」を呼ぶ、あなた自身の言葉で
- 登場人物の感情に共感した経験や、その感情に触れて自分自身が感じたことを、率直に表現する。
- 「私も〇〇の時に、同じような気持ちになったことがある」のように、読者も共感しやすい具体的な体験を交える。
- 登場人物の感情の動きを、単に「悲しかった」「嬉しかった」で終わらせず、その感情がどのように自分に影響を与えたのかを掘り下げる。
「作者の意図」を深読み!作品に込められたメッセージを読み解く
「言葉の選択」に隠された作者の意図を探る
- 作者が、特定の場面や登場人物の心情を表すために、どのような言葉を選んでいるかに注目する。
- 類義語の中でも、なぜその言葉が選ばれたのか、その言葉が持つニュアンスや響きを考える。
- 繰り返される言葉や、印象的なフレーズに、作者が特に伝えたいメッセージのヒントが隠されている場合がある。
「物語の構造」から作者のメッセージを読み解く
- 物語の始まり、中間、終わりといった展開の仕方や、伏線の張り方、回収の仕方を分析する。
- 物語の結末が、登場人物の成長や変化にどのような影響を与えたのか、そこから作者が伝えたい教訓は何かを考える。
- 作者が意図的に入れたと思われる「皮肉」や「ユーモア」といった要素も、メッセージを読み解く手がかりになる。
「社会背景」と照らし合わせ、作品の深層を理解する
- 作品が書かれた時代背景や、作者が生きた社会状況を調べることで、作品に込められたメッセージがより鮮明になることがある。
- 作品で描かれている問題が、現代社会にも通じる普遍的なものであるか、あるいは特定の時代に特有のものであるかを考察する。
- 作者が、その時代の社会に対して、どのような問題提起やメッセージを伝えたかったのかを想像する。
「読後感」を「次への一歩」へ!未来への視点を盛り込む
作品から得た「学び」を、自分自身の成長に繋げる
- 物語を通して得た教訓や気づきが、自分の今後の人生や目標にどのように役立つかを具体的に記述する。
- 作品で描かれた価値観や考え方を、自分の日常生活や将来の夢にどう活かせるかを考察する。
- 「この本を読んで、〇〇についてもっと知りたいと思った」「〇〇に挑戦してみようと思った」など、具体的な行動への意欲を示す。
「社会への貢献」や「他者への影響」を考える
- 作品のテーマが、現代社会が抱える課題や、将来の社会にどのような影響を与える可能性があるかを考察する。
- この本を、どのような人に、どのような目的で薦めたいかを具体的に述べる。
- 作品を通して、他者への理解や共感が深まり、より良い人間関係を築くためのヒントを得られたことを伝える。
「未来への希望」を込めた、前向きな締めくくり
- 読書体験を通して得たポジティブな感情や、未来への期待感を、力強く、そして情熱的に表現する。
- 作品のメッセージが、読者自身の未来を切り拓くための「羅針盤」や「灯火」となることを示唆する。
- 読書体験が、自分自身の人生において、どのような「新たな始まり」や「可能性」をもたらしたのかを語る。
「推敲」で完成度を高める!誤字脱字チェックから表現の磨き上げまで
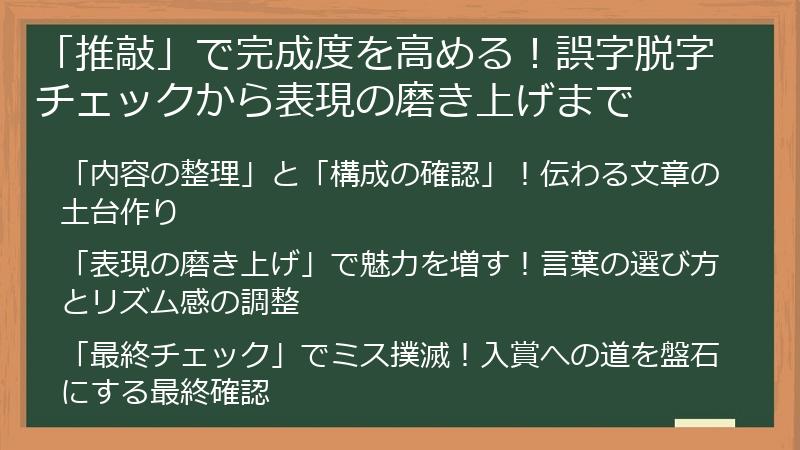
どんなに良い内容の読書感想文も、誤字脱字が多かったり、文章が読みにくかったりすると、その魅力が半減してしまいます。
ここでは、あなたの読書感想文を、より洗練された、完成度の高い作品へと仕上げるための「推敲」のプロセスを、具体的なステップごとに解説します。
内容の整理から、表現のブラッシュアップ、そして最終的なチェックまで、このプロセスを丁寧に行うことで、あなたの感想文は、審査員に「丁寧な仕事」という印象を与えることができるでしょう。
さあ、あなたの感動を、より正確に、より美しく伝えるための最終調整を行いましょう。
「内容の整理」と「構成の確認」!伝わる文章の土台作り
「論旨」が明確か、自己チェック
- 私がこの本を読んで一番伝えたかったことは何だったのか、その「核」となるメッセージを再確認する。
- 感想文全体を通して、そのメッセージが一貫して貫かれているか、論理的な飛躍がないかを確認する。
- 導入で提示したテーマや問いに対して、本文で十分に答えられているか、結論でそれが明確に示されているかをチェックする。
「構成」のバランスと流れを確認する
- 導入、展開、結論といった、感想文全体の構成が、自然な流れになっているかを客観的に見直す。
- 各段落の役割が明確か、話の展開が唐突になっていないか、接続詞の使い方は適切かなどを確認する。
- PREP法や起承転結のフレームワークに沿って、論理的なつながりがスムーズか、読者が迷うことなく内容を追えるかを意識して推敲する。
「冗長な表現」や「重複」を削除・修正する
- 同じような内容が繰り返されている箇所や、なくても意味が通じる「余計な言葉」を削除する。
- より簡潔で分かりやすい表現に置き換えられる箇所がないか、文末表現のバリエーションなどを検討する。
- 「~と思う」「~感じる」といった表現が多すぎないか、あるいは逆に少なすぎないかを確認し、適切なバランスを取る。
「表現の磨き上げ」で魅力を増す!言葉の選び方とリズム感の調整
「一文」の長さを意識し、リズム感を整える
- 長すぎる文は読みにくくなるため、適度なところで区切る。
- 短い文と長い文を組み合わせることで、文章にメリハリとリズムが生まれる。
- 声に出して読んでみて、不自然な箇所や読みにくい部分がないかを確認する。
「類語」や「言い換え」で、表現の幅を広げる
- 同じ言葉の繰り返しを避け、より適切で、感情やニュアンスを的確に表す言葉を探す。
- 「~と思う」といった断定的な表現だけでなく、「~のように感じられた」「~だと推測する」など、表現の幅を広げる。
- 比喩表現や擬人化などを活用し、読者の想像力を刺激するような、より鮮やかな描写を目指す。
「強調したい部分」を際立たせる工夫
- 重要なキーワードや、最も伝えたいメッセージは、文末に配置したり、独立した一文にしたりする。
- 「特に」「最も」「まさに」といった強調の言葉を効果的に使う。
- 読者に強く訴えかけたい箇所では、感情を込めた、より力強い言葉を選ぶ。
「最終チェック」でミス撲滅!入賞への道を盤石にする最終確認
「誤字脱字」は論外!徹底的な校正作業
- 本文の「漢字」「ひらがな」「カタカナ」の変換ミスがないか、一文字ずつ丁寧に確認する。
- 助詞(てにをは)の使い方が適切か、接続詞の誤用はないかなどをチェックする。
- 句読点の打ち方が正しいか、読点(、)の数が多すぎたり少なすぎたりしないかを確認する。
「表記ゆれ」をなくし、統一感を出す
- 同じ単語を異なる表記(例:「コンピューター」と「コンピュータ」)で使っていないかを確認する。
- 「。」と「.」など、句読点の表記に揺れがないか、統一された表記で記述されているかをチェックする。
- 数字の表記(例:「一」「いち」「1」)に統一性があるか、応募要項に沿った表記になっているかを確認する。
「応募要項」の最終確認と「提出形式」の遵守
- 文字数制限、用紙サイズ、フォント指定など、応募要項に定められた形式にすべて従っているかを最終確認する。
- 指定された提出方法(郵送、オンライン提出など)を再度確認し、間違いがないように準備する。
- 万が一、提出書類に不備があった場合、応募が無効になる可能性もあるため、提出前には必ず最終チェックを行う。
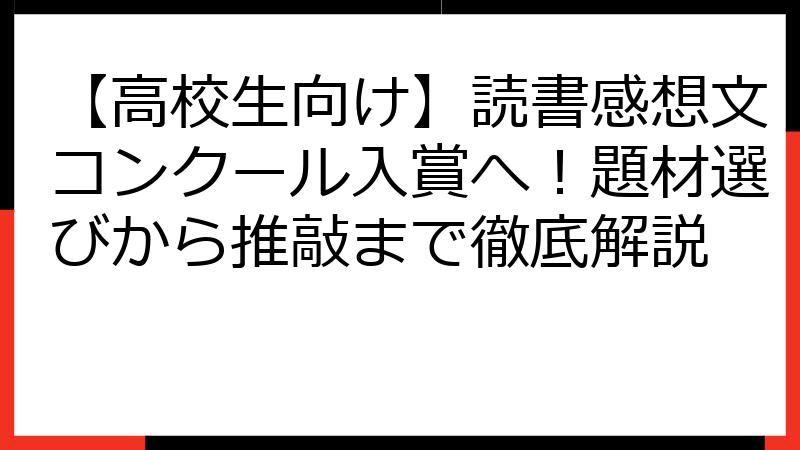


コメント