【小学生向け】読書感想文で高評価!心に響くおすすめ本&書き方完全ガイド
読書感想文、何を書けばいいか迷っていませんか?
小学生の皆さんにとって、読書感想文はちょっと難しい宿題かもしれませんね。
でも大丈夫!この記事では、読書感想文におすすめの心に響く本を厳選してご紹介します。
さらに、読書感想文をスラスラ書けるようになるための、ステップ別の攻略法も詳しく解説。
書き出しのテクニックや、オリジナリティ溢れる表現方法もご紹介するので、周りの友達と差がつく、個性的な読書感想文が書けるようになりますよ。
この記事を読めば、読書感想文が楽しくなり、高評価も夢ではありません!ぜひ最後まで読んで、夏休みの宿題を終わらせましょう!
読書感想文におすすめ!心を揺さぶる厳選書籍3選
読書感想文で何を書けばいいか悩む小学生のために、心を揺さぶるおすすめの本を3つのテーマに分けてご紹介します。
冒険と友情、感動と学び、そしてファンタジーの世界へ。
それぞれのテーマに沿って、読書感想文が書きやすい本、感動的な本、想像力を刺激する本を選びました。
これらの本を読めば、きっと心に残る何かが見つかり、読書感想文を書くのが楽しくなるはずです。
ぜひ、自分にぴったりの一冊を見つけて、読書感想文に挑戦してみてください。
冒険と友情がテーマ!読書感想文が書きやすいおすすめ本
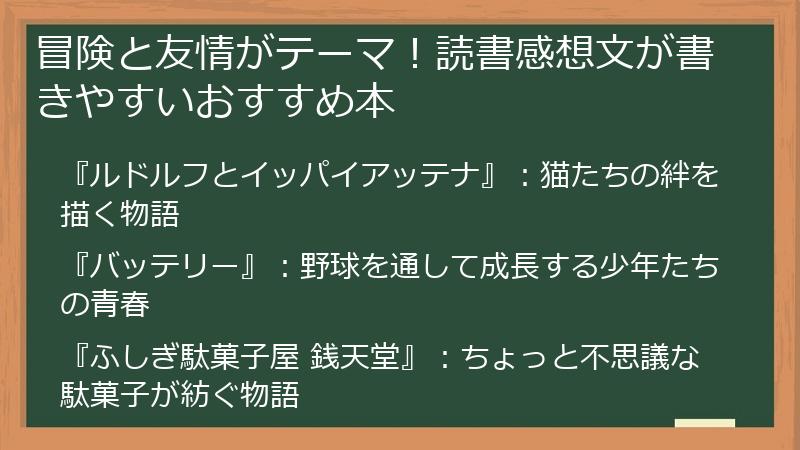
冒険と友情は、読書感想文のテーマとして非常に人気があります。
なぜなら、登場人物たちの困難を乗り越える姿や、友情を通して成長していく様子は、読者の心を強く揺さぶり、共感を生みやすいからです。
ここでは、小学生にも読みやすく、感動的な冒険と友情が描かれたおすすめの本を3冊ご紹介します。
これらの本を読めば、きっと心に残るシーンが見つかり、読書感想文を書く手が止まらなくなるはずです。
『ルドルフとイッパイアッテナ』:猫たちの絆を描く物語
『ルドルフとイッパイアッテナ』は、都会で迷子になった黒猫ルドルフが、さまざまな困難に立ち向かいながら成長していく物語です。
ひょんなことから言葉を話せるボス猫イッパイアッテナと出会い、文字を教わり、友情を深めていきます。
この物語の魅力は、なんといってもルドルフとイッパイアッテナの温かい絆です。
故郷に帰りたいと願いながらも、イッパイアッテナとの生活を通して、ルドルフはたくましさを身につけ、かけがえのない友情を育んでいきます。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- ルドルフが故郷を離れ、都会で生きていく中で、どのような変化があったか。
- イッパイアッテナは、ルドルフにとってどんな存在だったか。
- 物語全体を通して、一番印象に残ったシーンはどこか。
- 自分自身の体験と重ね合わせて、何を感じ、何を学んだか。
この物語は、友情の大切さ、困難に立ち向かう勇気、そして成長することの喜びを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
また、作中に出てくる印象的なセリフを引用することで、より深みのある感想文にすることができます。
印象的なセリフの例
- 「おれは、もうルドルフとは呼ばない。おまえは、今日からルドルフだ」
- 「文字を覚えることは、生きる力を覚えることだ」
これらのセリフを参考に、物語の核心をついた読書感想文を作成してみて下さい。
『バッテリー』:野球を通して成長する少年たちの青春
『バッテリー』は、野球に情熱を燃やす少年たちの成長を描いた物語です。
主人公の原田巧は、天才的なピッチャーの才能を持ちながらも、周囲との軋轢や葛藤を抱えています。
転校先の学校で出会ったキャッチャーの永倉豪との出会いを通して、彼は自身の才能と向き合い、成長していきます。
この物語の魅力は、登場人物たちの心理描写が丁寧に描かれている点です。
巧の才能に対する嫉妬や葛藤、豪の巧への信頼と友情、そして周囲の大人たちの期待とプレッシャーなど、様々な感情が複雑に絡み合い、物語を盛り上げています。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- 巧の才能は、彼にとってどのような意味を持つのか。
- 豪は、巧にとってどんな存在だったか。
- 物語の中で、巧と豪の関係はどのように変化していったか。
- 自分自身の経験と重ね合わせ、彼らの感情に共感できる部分はあったか。
この物語は、才能と努力、友情と信頼、そして青春の輝きを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、巧と豪のバッテリーとしての関係性に焦点を当てて、友情の重要性や、互いを信頼することの大切さを考察することで、深みのある感想文を書くことができます。
印象的なシーンの例
- 巧が初めて豪のミットにボールを投げ込んだ時の描写
- 二人が互いの才能を認め合い、信頼関係を築いていく過程
これらのシーンを参考に、あなた自身の言葉で、彼らの青春を描写してみて下さい。
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』:ちょっと不思議な駄菓子が紡ぐ物語
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』は、幸運な子供だけがたどり着ける不思議な駄菓子屋を舞台にした物語です。
店主の紅子が売る駄菓子は、それぞれに特別な力を持っており、子供たちの願いを叶える代わりに、思わぬ結果を招くこともあります。
この物語の魅力は、子供たちの欲望や葛藤が、魅力的な駄菓子を通して描かれている点です。
駄菓子を手に入れた子供たちは、一見すると願いを叶えたように見えますが、その結果、大切なものを失ったり、後悔したりすることもあります。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- 銭天堂の駄菓子は、子供たちのどのような欲望を叶えるのか。
- 駄菓子を手に入れた子供たちは、どのような結果を迎えるのか。
- 物語を通して、紅子は子供たちに何を伝えようとしているのか。
- 自分自身が駄菓子を手に入れたとしたら、どんな願いを叶えたいか。
この物語は、欲望のコントロール、選択の責任、そして本当に大切なものを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、駄菓子がもたらす結果に着目し、安易な欲望の実現が必ずしも幸せに繋がるとは限らないことを考察することで、奥深い感想文を書くことができます。
印象的な駄菓子の例
- 「型ぬき人魚グミ」:願いを叶える代わりに、大切な記憶を失う
- 「ホーンテッドアイス」:勇気をくれるが、使いすぎると周りが見えなくなる
これらの駄菓子を参考に、駄菓子の持つ二面性を考察し、読書感想文に活かしてみて下さい。
感動と学びがいっぱい!読書感想文で差がつくおすすめ本
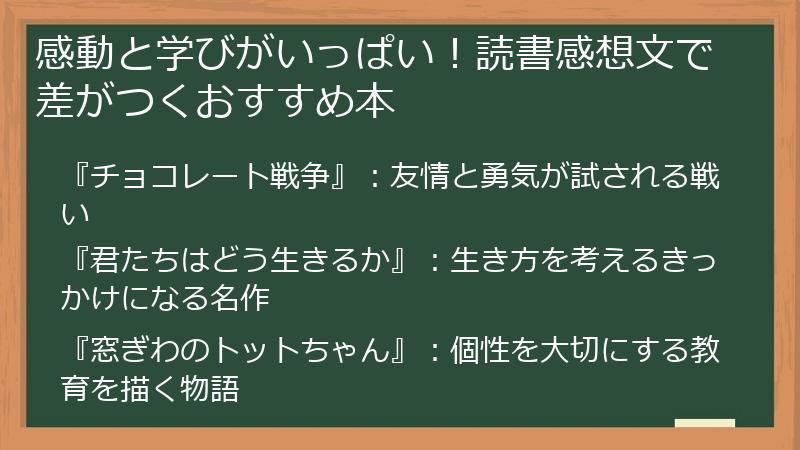
読書感想文を通して、感動を伝え、学びを深めたい。
そんなあなたにおすすめなのが、心に深く響き、考えさせられる物語です。
ここでは、読書を通して様々な感情を体験し、新たな視点を得られるおすすめの本を3冊ご紹介します。
これらの本を読めば、読書感想文を通して、自分自身の成長を表現することができるでしょう。
感動的な物語を通して、読書感想文で周りと差をつけましょう。
『チョコレート戦争』:友情と勇気が試される戦い
『チョコレート戦争』は、小学校を舞台に、子供たちがチョコレートをめぐって繰り広げる騒動を描いた物語です。
主人公の正義感の強い少年、高柳誠を中心に、クラスメイトたちが様々な作戦を立て、チョコレートを独占しようとする大人たちに立ち向かいます。
この物語の魅力は、子供たちの視点から、社会の不条理や大人たちの欺瞞を描いている点です。
チョコレートの販売をめぐる大人たちの思惑や、子供たちを利用しようとする姿勢を通して、社会の様々な問題を浮き彫りにしています。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- 高柳誠は、なぜチョコレート戦争に立ち向かうことを決意したのか。
- チョコレート戦争を通して、子供たちはどのような成長を遂げたのか。
- 物語に登場する大人たちは、どのような役割を果たしているのか。
- 自分自身がチョコレート戦争に参加するとしたら、どのような作戦を立てるか。
この物語は、正義感、友情、そして社会の不条理に立ち向かう勇気を教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、子供たちが大人たちに立ち向かう姿に着目し、勇気を持って行動することの大切さを考察することで、力強い感想文を書くことができます。
印象的なシーンの例
- 高柳誠が、チョコレートの不正販売を暴こうとする場面
- クラスメイトたちが一致団結して、作戦を実行する場面
これらのシーンを参考に、あなた自身の言葉で、子供たちの勇姿を描写してみて下さい。
『君たちはどう生きるか』:生き方を考えるきっかけになる名作
『君たちはどう生きるか』は、主人公のコペル君が、叔父との対話を通して、人間としてどう生きるべきかを考える物語です。
学校生活や友人関係、貧富の差など、様々な問題に直面しながら、コペル君は自分の生き方を模索していきます。
この物語の魅力は、子供にも分かりやすい言葉で、人生における大切なテーマを扱っている点です。
コペル君の成長を通して、読者も自分自身の生き方について考えるきっかけを与えられます。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- コペル君は、どのような問題に直面し、どのように解決していくのか。
- 叔父は、コペル君にどのような影響を与えたのか。
- 物語を通して、一番印象に残った言葉や考え方は何か。
- 自分自身は、どのように生きていきたいか。
この物語は、生き方、友情、勇気、そして自分自身と向き合うことの大切さを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、物語に登場する様々な人物の生き方を比較検討し、自分自身の価値観と照らし合わせることで、深い洞察に満ちた感想文を書くことができます。
印象的な場面の例
- コペル君が友人の家を訪問し、貧困の問題に直面する場面
- コペル君が学校でいじめを目撃し、行動するかどうか悩む場面
これらの場面を参考に、あなた自身の考えや感情を率直に表現してみて下さい。
『窓ぎわのトットちゃん』:個性を大切にする教育を描く物語
『窓ぎわのトットちゃん』は、主人公のトットちゃんが、型破りな教育を行う小学校「トモエ学園」で過ごす日々を描いた自伝的小説です。
トットちゃんは、自由な発想と好奇心旺盛な性格から、小学校を退学になってしまいますが、トモエ学園では、先生や友達との出会いを通して、個性を伸ばし、才能を開花させていきます。
この物語の魅力は、子供の個性を尊重し、可能性を最大限に引き出す教育の重要性を教えてくれる点です。
トットちゃんの成長を通して、読者も自分自身の個性を大切にし、可能性を信じることの素晴らしさを感じることができます。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- トットちゃんは、トモエ学園でどのような経験を通して成長していくのか。
- 小林宗作先生は、トットちゃんのどのような才能を見出し、伸ばしていったのか。
- 物語を通して、一番印象に残った教育方法や考え方は何か。
- 自分自身がトットちゃんのような教育を受けたら、どのように成長できると思うか。
この物語は、個性、自由、創造性、そして教育の可能性を教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、トモエ学園のユニークな教育方法に着目し、自分自身の理想の教育について考察することで、オリジナリティ溢れる感想文を書くことができます。
印象的なエピソードの例
- 運動会の昼食が「海のものと山のもの」だったエピソード
- 子供たちが自由に自分の時間割を作るエピソード
これらのエピソードを参考に、トモエ学園の教育が、トットちゃんにどのような影響を与えたのかを分析し、読書感想文に活かしてみて下さい。
ファンタジーの世界へ!読書感想文で想像力を刺激するおすすめ本
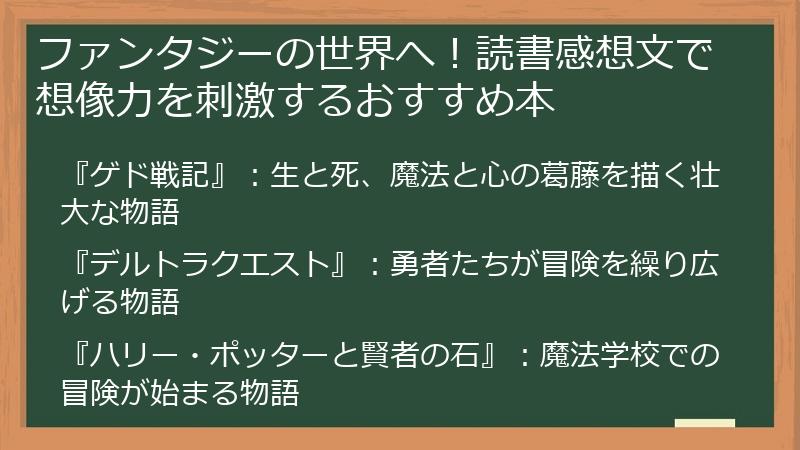
現実世界を離れて、ファンタジーの世界に浸りたい。
そんなあなたにおすすめなのが、想像力を刺激し、心を躍らせる物語です。
ここでは、読書を通して異世界を冒険し、新たな発見ができるおすすめの本を3冊ご紹介します。
ファンタジーの世界を舞台に、読書感想文であなたの豊かな想像力を表現してみましょう。
『ゲド戦記』:生と死、魔法と心の葛藤を描く壮大な物語
『ゲド戦記』は、魔法使いのゲドを主人公に、生と死、善と悪、そして心の葛藤を描いた壮大なファンタジーです。
若き日のゲドが、自身の過ちによって影を呼び出してしまい、その影に追われる中で、彼は自身の内面と向き合い、成長していきます。
この物語の魅力は、単なる冒険物語ではなく、人間の心の奥深くまで掘り下げた哲学的テーマを扱っている点です。
ゲドの葛藤を通して、読者も自分自身の心の闇や、生きていく意味について考えるきっかけを与えられます。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- ゲドは、なぜ影を呼び出してしまったのか。
- 影は、ゲドにとってどのような存在なのか。
- 物語を通して、ゲドはどのような成長を遂げたのか。
- 自分自身は、ゲドの葛藤に共感できる部分はあったか。
この物語は、生と死、善と悪、そして自分自身と向き合うことの大切さを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、ゲドと影の関係に着目し、人間の心の二面性や、自己受容の重要性を考察することで、深い洞察に満ちた感想文を書くことができます。
印象的な場面の例
- ゲドが影と対峙し、名前を呼ぶ場面
- ゲドが自身の過ちを認め、影を受け入れる場面
これらの場面を参考に、あなた自身の心の葛藤と照らし合わせ、読書感想文に活かしてみて下さい。
『デルトラクエスト』:勇者たちが冒険を繰り広げる物語
『デルトラクエスト』は、邪悪な影の大王に支配されたデルトラ王国を舞台に、勇者たちが王国を取り戻すために冒険を繰り広げる物語です。
主人公のリフは、王宮の地図係の息子として育ちましたが、ある日、王国を救うための使命を託され、仲間たちと共に7つの宝石を探す旅に出ます。
この物語の魅力は、個性豊かなキャラクターたちが、困難に立ち向かいながら成長していく姿です。
リフ、バルダ、ジャスミンの3人は、それぞれの得意分野を生かし、互いに協力しながら、数々の試練を乗り越えていきます。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- リフは、どのような困難に立ち向かい、どのように成長していくのか。
- バルダとジャスミンは、リフにとってどのような存在なのか。
- 7つの宝石は、それぞれどのような力を持っているのか。
- 自分自身がデルトラクエストに参加するとしたら、どのような役割を担いたいか。
この物語は、勇気、友情、知恵、そして希望を捨てずに困難に立ち向かうことの大切さを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、3人のキャラクターのそれぞれの個性に着目し、互いに協力することの重要性を考察することで、深みのある感想文を書くことができます。
印象的な宝石の力
- トパーズ:勇気を与える
- ルビー:守護の力
- エメラルド:知恵を授ける
これらの宝石の力を参考に、宝石が物語にどのような影響を与えたのかを分析し、読書感想文に活かしてみて下さい。
『ハリー・ポッターと賢者の石』:魔法学校での冒険が始まる物語
『ハリー・ポッターと賢者の石』は、両親を亡くし、孤独な少年時代を送っていたハリー・ポッターが、魔法学校ホグワーツに入学し、魔法使いとして成長していく物語です。
ハリーは、ロンやハーマイオニーといった仲間たちとの出会いを通して、友情を深め、様々な困難に立ち向かっていきます。
この物語の魅力は、魅力的な魔法の世界観と、ハリーたちの成長物語が巧みに組み合わされている点です。
魔法学校での授業や、クィディッチの試合、そしてヴォルデモートとの戦いなど、読者を飽きさせない要素が満載です。
読書感想文を書く際には、以下のポイントに注目してみましょう。
- ハリーは、ホグワーツでどのような経験を通して成長していくのか。
- ロンとハーマイオニーは、ハリーにとってどのような存在なのか。
- ヴォルデモートは、ハリーにとってどのような脅威なのか。
- 自分自身がホグワーツに入学するとしたら、どの寮に入りたいか。
この物語は、友情、勇気、正義、そして自分自身の可能性を信じることの大切さを教えてくれます。
読書感想文を通して、あなた自身の心に響いたメッセージを伝えてみましょう。
特に、ハリー、ロン、ハーマイオニーの友情に着目し、互いを支え合い、助け合うことの重要性を考察することで、感動的な感想文を書くことができます。
印象的な魔法
- エクスペクト・パトローナム:守護霊を呼び出す魔法
- ウィンガーディアム・レビオーサ:物を浮遊させる魔法
これらの魔法を参考に、魔法が物語にどのような影響を与えたのかを分析し、読書感想文に活かしてみて下さい。また、作中に登場する魔法生物についても言及することで、より深い読書感想文にすることができます。
読書感想文をスラスラ書ける!3つのステップ別攻略法
おすすめの本は見つかったけど、実際にどう書けばいいか分からない。
そんな悩みを抱える小学生のために、読書感想文をスラスラ書けるようになるための、3つのステップ別攻略法をご紹介します。
本の選び方から、読書中のメモの取り方、そして文章構成まで、読書感想文に必要な要素を丁寧に解説。
この攻略法をマスターすれば、読書感想文が苦手なあなたも、自信を持って書き上げることができるはずです。
ステップ1:本を選ぶ前に!読書感想文の基本を知ろう
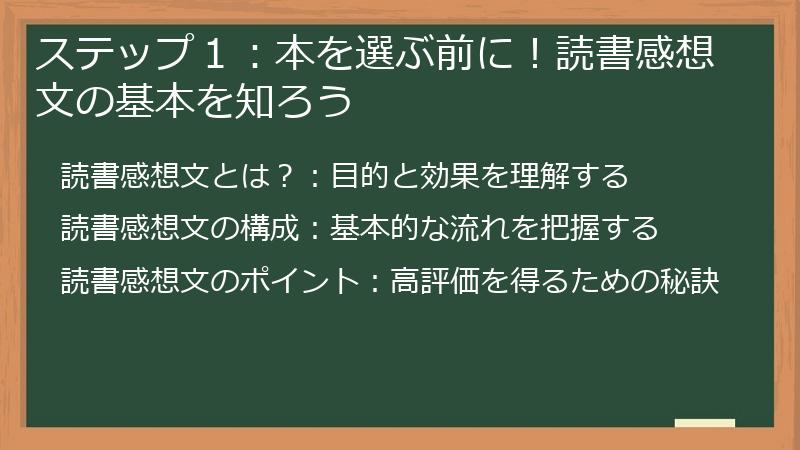
読書感想文を書き始める前に、まずは読書感想文とは何か、どのような構成で書くべきか、そして高評価を得るためにはどのようなポイントを押さえるべきか、基本的な知識を身につけましょう。
このステップでは、読書感想文の目的や構成、そして高評価を得るための秘訣を分かりやすく解説します。
基本的な知識を理解することで、読書感想文の取り組み方が大きく変わるはずです。
読書感想文とは?:目的と効果を理解する
読書感想文とは、単に本の内容をまとめるものではありません。
本を読んで感じたこと、考えたこと、そしてそこから学んだことを、自分自身の言葉で表現するものです。
読書を通して得られた感動や気づきを、文章として表現することで、理解を深め、思考力を高めることができます。
読書感想文を書く目的は、主に以下の3つです。
- 読解力・理解力を高める:本の内容を深く理解し、要点を把握する
- 表現力・文章力を高める:自分の考えや感情を言葉で表現する
- 思考力・分析力を高める:本の内容を分析し、自分なりの解釈を加える
読書感想文を書くことで、これらの能力を総合的に高めることができます。
また、読書感想文は、先生や友達と本の感想を共有し、新たな発見や視点を得るための良い機会にもなります。
読書感想文を書く際には、以下の点を意識してみましょう。
- 本のテーマを理解する:作者が何を伝えたいのかを考える
- 自分の体験と結びつける:本のテーマと自分の経験を照らし合わせる
- オリジナルの視点を持つ:自分なりの解釈や意見を加える
これらの点を意識することで、より深く、よりオリジナリティ溢れる読書感想文を書くことができます。
読書感想文は、自分自身と向き合い、成長するための貴重な機会です。
積極的に取り組み、読書の世界をさらに広げていきましょう。
読書感想文の構成:基本的な流れを把握する
読書感想文には、基本的な構成があります。
構成を理解することで、文章全体の流れがスムーズになり、読みやすい読書感想文を書くことができます。
読書感想文の基本的な構成は、以下の3つの部分に分かれています。
- 導入(はじめ):本の紹介と、なぜその本を選んだのかを書く
- 展開(なか):本のあらすじ、印象に残った場面、自分の考えを書く
- 結論(おわり):本を通して学んだこと、これからの行動を書く
それぞれの部分で、どのようなことを書くべきか、具体的に見ていきましょう。
- 導入:
- 本のタイトル、作者名、簡単なあらすじを紹介する
- なぜその本を選んだのか、読んだきっかけを書く
- 例:「〇〇という本を読みました。この本を選んだのは、〇〇という理由からです。」
- 展開:
- 本のあらすじを簡単にまとめる
- 印象に残った場面を具体的に描写する(登場人物、情景、セリフなど)
- なぜその場面が印象に残ったのか、自分の考えや感情を書く
- 例:「この本の中で一番印象に残ったのは、〇〇の場面です。なぜなら、〇〇と感じたからです。」
- 結論:
- 本を通して学んだこと、考えさせられたことをまとめる
- これからの生活にどのように活かしていきたいかを書く
- 例:「この本を読んで、〇〇ということを学びました。これからは〇〇を心がけて生活していきたいです。」
この構成を参考に、自分の言葉で、読書感想文を組み立ててみましょう。
構成をしっかりと把握することで、論理的で分かりやすい読書感想文を書くことができます。
読書感想文のポイント:高評価を得るための秘訣
読書感想文で高評価を得るためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
これらのポイントを意識することで、先生に「素晴らしい!」と思ってもらえる読書感想文を書くことができます。
高評価を得るための秘訣は、以下の5つです。
- オリジナリティ:自分自身の言葉で、オリジナルの感想を書く
- 具体性:抽象的な表現ではなく、具体的な場面や言葉を引用する
- 論理性:文章全体の構成を意識し、論理的な流れを作る
- 熱意:本に対する熱意や感動を伝える
- 丁寧さ:誤字脱字に注意し、丁寧に書く
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
- オリジナリティ:
- 友達や親の意見をそのまま書くのではなく、自分自身の言葉で感想を書きましょう。
- 自分自身の体験と結びつけることで、オリジナリティを出すことができます。
- 具体性:
- 「面白かった」「感動した」といった抽象的な表現だけでなく、具体的な場面やセリフを引用して、なぜそう感じたのかを説明しましょう。
- 例:「〇〇という場面が特に感動しました。なぜなら、〇〇というセリフが心に響いたからです。」
- 論理性:
- 読書感想文全体の構成を意識し、導入、展開、結論がスムーズにつながるように書きましょう。
- 接続詞(しかし、なぜなら、だからなど)を効果的に使うことで、論理的な流れを作ることができます。
- 熱意:
- 本に対する熱意や感動を、文章全体を通して伝えましょう。
- 感動した場面を熱く語ったり、学んだことを力強く宣言したりすることで、読者の心を動かすことができます。
- 丁寧さ:
- 誤字脱字がないか、丁寧に確認しましょう。
- 漢字、ひらがな、カタカナの使い分けにも注意しましょう。
- 読みやすい字で書くことも大切です。
これらのポイントを意識することで、高評価を得られるだけでなく、自分自身も満足できる読書感想文を書くことができます。
積極的にこれらのポイントを実践し、素晴らしい読書感想文を完成させましょう。
ステップ2:本を読みながら!読書感想文のネタを見つけよう
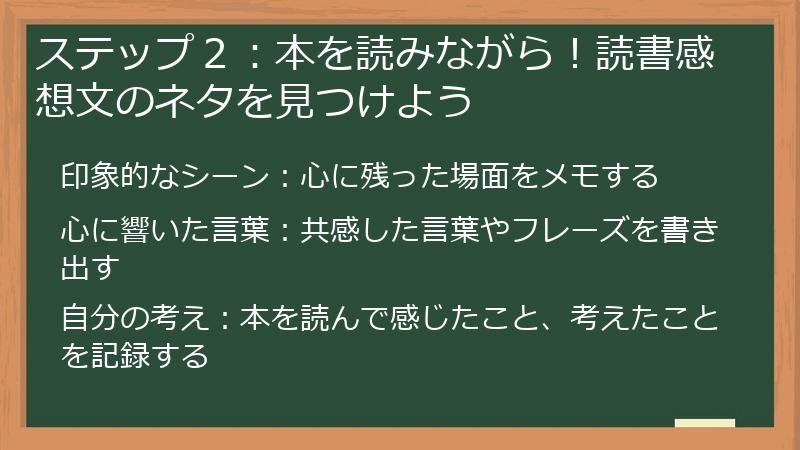
読書感想文を書くためのネタは、本を読んでいる最中に見つけるのが一番効果的です。
印象的なシーンや、心に響いた言葉、そして自分の考えをメモすることで、読書感想文の構成がスムーズになります。
このステップでは、読書中にメモすべき3つのポイントをご紹介します。
これらのポイントを意識することで、読書感想文のネタ探しに苦労することなく、スムーズに書き始めることができます。
印象的なシーン:心に残った場面をメモする
本を読んでいると、心に強く残るシーンに出会うことがあります。
登場人物の行動、風景描写、印象的なセリフなど、心に残った場面をメモしておきましょう。
メモする際には、**なぜその場面が心に残ったのか**、理由も一緒に書き添えることが大切です。
印象的なシーンをメモする際には、以下の点を意識してみましょう。
- 具体的な描写:誰が、いつ、どこで、何をしたのか、具体的に書きましょう。
- 感情の描写:登場人物の感情がどのように表現されていたか、書きましょう。
- 五感を意識する:視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚など、五感で感じたことを書きましょう。
例えば、『チョコレート戦争』を読んでいる時に、高柳誠がチョコレートの不正販売を暴こうとする場面が印象に残ったとします。
その場合、以下のようにメモすることができます。
【印象的なシーン】
高柳誠が、校長室に乗り込み、チョコレートの不正販売を校長に訴える場面。
【理由】
高柳誠の正義感の強さに感動した。
自分の意見を堂々と言う勇気に感銘を受けた。
【具体的な描写】
校長室の重々しい雰囲気、高柳誠の毅然とした態度、校長の戸惑った表情などが印象的だった。
高柳誠の「これは不正です!子供たちを騙すのは許せません!」というセリフが心に響いた。
このように、具体的な描写と理由を一緒にメモすることで、読書感想文を書く際に、**当時の感情や情景を鮮やかに思い出すことができます**。
印象的なシーンをメモすることは、読書感想文をより深く、より感動的にするための第一歩です。
積極的にメモを取り、読書の世界をさらに広げていきましょう。
心に響いた言葉:共感した言葉やフレーズを書き出す
本を読んでいると、まるで自分の気持ちを代弁してくれているかのような、心に響く言葉やフレーズに出会うことがあります。
登場人物のセリフ、物語のナレーション、作者のメッセージなど、共感した言葉やフレーズを書き出しておきましょう。
書き出す際には、**なぜその言葉やフレーズに共感したのか**、理由も一緒に書き添えることが大切です。
心に響いた言葉やフレーズをメモする際には、以下の点を意識してみましょう。
- 言葉の意味を理解する:言葉の表面的な意味だけでなく、背景やニュアンスも理解しましょう。
- 自分の体験と結びつける:その言葉が、自分の過去の経験や現在の状況とどのように関係しているか考えましょう。
- 感情を表現する:その言葉を読んだ時、どのような感情が湧き上がってきたか具体的に書きましょう。
例えば、『君たちはどう生きるか』を読んでいる時に、「人間としてどう生きるべきか」という言葉が心に響いたとします。
その場合、以下のようにメモすることができます。
【心に響いた言葉】
「人間としてどう生きるべきか」
【理由】
自分自身の生き方について、深く考えさせられた。
これからどのように生きていけば良いのか、迷っていた自分にとって、指針となる言葉だと感じた。
【関連する体験】
最近、友達との関係で悩んでいた。
相手のことを思いやる気持ちを持ちながら、自分の意見も伝えることの難しさを感じていた。
このように、言葉の意味、共感した理由、そして関連する自分の体験を一緒にメモすることで、読書感想文を書く際に、**その言葉に対する深い理解と、自分自身の考えを明確に表現することができます**。
心に響いた言葉やフレーズをメモすることは、読書感想文をよりパーソナルで、より感動的にするための重要なステップです。
積極的にメモを取り、読書体験をより豊かなものにしていきましょう。
自分の考え:本を読んで感じたこと、考えたことを記録する
本を読んでいると、物語の内容を通して、様々な感情が湧き上がってきたり、新たな考えが生まれたりすることがあります。
感動、共感、疑問、反発など、本を読んで感じたこと、考えたことを記録しておきましょう。
記録する際には、**なぜそう感じたのか、そう考えたのか**、理由も一緒に書き添えることが大切です。
自分の考えをメモする際には、以下の点を意識してみましょう。
- 正直な気持ちを表現する:無理に良いことを書こうとせず、素直な気持ちを書きましょう。
- 批判的な視点も持つ:物語の内容に共感できない部分や、疑問に思った点も積極的に書きましょう。
- 多角的に考える:物語の登場人物の視点、作者の視点、そして自分自身の視点など、様々な角度から考えてみましょう。
例えば、『窓ぎわのトットちゃん』を読んでいる時に、「個性を大切にする教育」について考えたとします。
その場合、以下のようにメモすることができます。
【自分の考え】
「個性を大切にする教育」は、本当に良いことなのか?
【理由】
個性を伸ばすことは大切だと思うが、協調性も必要なのではないか。
個性を尊重しすぎると、わがままな子供になってしまうのではないかという不安がある。
【多角的な視点】
トットちゃんの視点:自由に学ぶことの楽しさを感じている。
小林宗作先生の視点:子供たちの可能性を最大限に引き出したいと考えている。
自分の視点:個性を伸ばすことと、協調性を育むことのバランスが大切だと考えている。
このように、自分の考え、理由、そして多角的な視点を一緒にメモすることで、読書感想文を書く際に、**より深く、より多角的な考察を展開することができます**。
本を読んで感じたこと、考えたことを記録することは、読書感想文をよりオリジナリティ溢れるものにするための重要なステップです。
積極的にメモを取り、読書体験を自分自身の成長につなげていきましょう。
ステップ3:書き始める前に!読書感想文を構成しよう
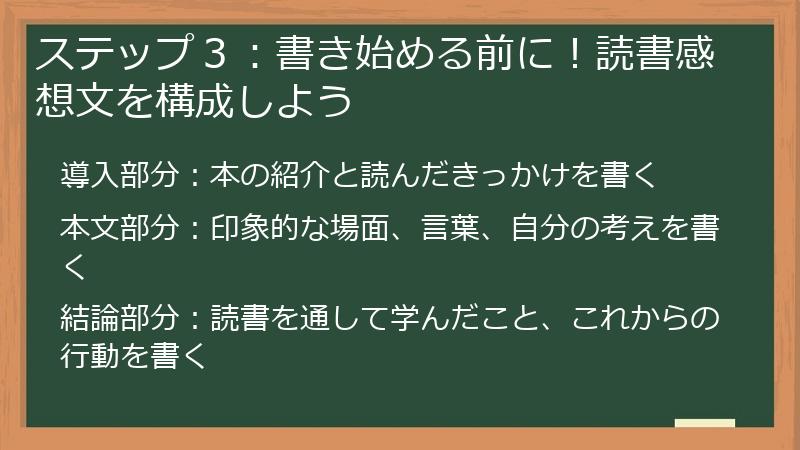
読書感想文を書き始める前に、構成をしっかりと練ることが大切です。
構成を練ることで、文章全体の流れがスムーズになり、伝えたいメッセージがより明確になります。
このステップでは、読書感想文の構成要素である、導入、本文、結論それぞれで書くべき内容と、構成を組み立てる際のポイントをご紹介します。
構成をしっかりと練ることで、迷うことなく、スムーズに読書感想文を書き始めることができるでしょう。
導入部分:本の紹介と読んだきっかけを書く
読書感想文の導入部分は、読者の興味を引きつけ、読書感想文全体への期待感を高めるための重要な部分です。
本のタイトル、作者名、簡単なあらすじを紹介し、**なぜその本を選んだのか、読んだきっかけ**を具体的に書きましょう。
導入部分を書く際には、以下の点を意識してみましょう。
- 簡潔にまとめる:長すぎる導入は、読者の集中力を奪ってしまいます。
- 興味を引く工夫をする:クエスチョン形式、引用形式、エピソード形式など、様々な方法で読者の興味を引きつけましょう。
- 自分らしさを出す:読んだきっかけや本の魅力を、自分自身の言葉で表現しましょう。
例えば、『ハリー・ポッターと賢者の石』を読書感想文の題材にする場合、以下のような導入部分を書くことができます。
【導入部分の例】
「ハリー・ポッターと賢者の石」は、J.K.ローリングによって書かれた、魔法使いの少年ハリー・ポッターが、魔法学校ホグワーツで様々な冒険を繰り広げる物語です。
私がこの本を読んだきっかけは、友達から「絶対に面白いから読んでみて!」と強く勧められたからです。
魔法の世界に足を踏み入れたハリーが、どのような成長を遂げるのか、ワクワクしながら読み進めました。
この例では、本のタイトル、作者名、簡単なあらすじを紹介し、読んだきっかけを具体的に記述しています。
また、「絶対に面白いから読んでみて!」という友達の言葉を引用することで、読者の興味を引く工夫をしています。
導入部分は、読書感想文全体の印象を左右する重要な部分です。
これらのポイントを参考に、**自分らしい、魅力的な導入部分**を書きましょう。
本文部分:印象的な場面、言葉、自分の考えを書く
読書感想文の本文部分は、本のあらすじを簡単にまとめ、**印象的な場面や言葉、そして自分自身の考え**を具体的に記述する中心的な部分です。
導入部分で興味を持った読者を、さらに深く読書の世界へと引き込み、共感や感動を与えることを目指しましょう。
本文部分を書く際には、以下の点を意識してみましょう。
- あらすじは簡潔に:物語全体の流れを理解してもらうために、必要最低限の情報に絞りましょう。
- 場面、言葉は具体的に:抽象的な表現ではなく、五感を使った具体的な描写を心がけましょう。
- 自分の考えを明確に:なぜそう感じたのか、そう考えたのか、理由を明確に述べましょう。
例えば、『ルドルフとイッパイアッテナ』を題材にする場合、以下のような本文部分を書くことができます。
【本文部分の例】
この物語は、都会で迷子になった黒猫ルドルフが、ボス猫イッパイアッテナと出会い、文字を教わりながら成長していく物語です。
特に印象に残ったのは、ルドルフがイッパイアッテナに文字を教えてもらう場面です。
ルドルフは、最初は文字を覚えることに苦労しますが、イッパイアッテナの熱心な指導と励ましによって、少しずつ文字を覚えていきます。
私は、この場面を読んで、努力することの大切さを改めて学びました。
ルドルフが困難に立ち向かい、成長していく姿に、勇気をもらいました。
この例では、物語のあらすじを簡潔にまとめ、ルドルフが文字を教えてもらう場面を具体的に描写しています。
また、その場面から自分が学んだこと、感じたことを明確に記述しています。
本文部分は、読書感想文の最も重要な部分です。
これらのポイントを参考に、**印象的な場面や言葉、そして自分自身の考えを、論理的に、そして情熱的に**表現しましょう。
結論部分:読書を通して学んだこと、これからの行動を書く
読書感想文の結論部分は、読書を通して得られた学びや気づきをまとめ、**これからの行動**に繋げるための重要な部分です。
読者に読書感想文全体のメッセージを改めて伝え、読後感を深めることを目指しましょう。
結論部分を書く際には、以下の点を意識してみましょう。
- 学びを明確に:読書を通して学んだことを、一言で表現できるようにまとめましょう。
- 行動を具体的に:学んだことを、どのようにこれからの生活に活かしていくのか、具体的に書きましょう。
- 未来への展望を示す:読書を通して、どのような未来を描けるようになったのか、希望に満ちた言葉で締めくくりましょう。
例えば、『ゲド戦記』を題材にする場合、以下のような結論部分を書くことができます。
【結論部分の例】
「ゲド戦記」を読んで、私は、自分自身の心の闇と向き合うことの大切さを学びました。
これからは、自分の弱さから目を背けずに、積極的に困難に立ち向かい、成長していきたいです。
ゲドのように、勇気を持って自分の影と向き合い、真の強さを手に入れることができるように、努力していきたいと思います。
この例では、読書を通して学んだことを「自分自身の心の闇と向き合うことの大切さ」と明確に表現しています。
また、学んだことを、どのようにこれからの生活に活かしていくのか、具体的な行動を示しています。
最後に、ゲドのように勇気を持って困難に立ち向かい、成長していきたいという、未来への展望を述べています。
結論部分は、読書感想文全体の印象を決定づける重要な部分です。
これらのポイントを参考に、**読書を通して得られた学びを力強くまとめ、未来への希望に満ちた言葉で締めくくりましょう**。
読書感想文をもっと楽しく!プラスαのテクニック
基本的な書き方が分かったら、さらに読書感想文を魅力的にするためのプラスαのテクニックを身につけましょう。
読者の興味を引きつける書き出し、個性を表現するオリジナリティ溢れる表現方法、そして完成度を高める推敲と見直し。
このセクションでは、読書感想文をさらにレベルアップさせるためのテクニックをご紹介します。
これらのテクニックを活用することで、読書感想文がもっと楽しくなり、周りの友達と差がつく、個性的な読書感想文が書けるようになります。
読書感想文の書き出しで差をつける!魅力的な冒頭を作る
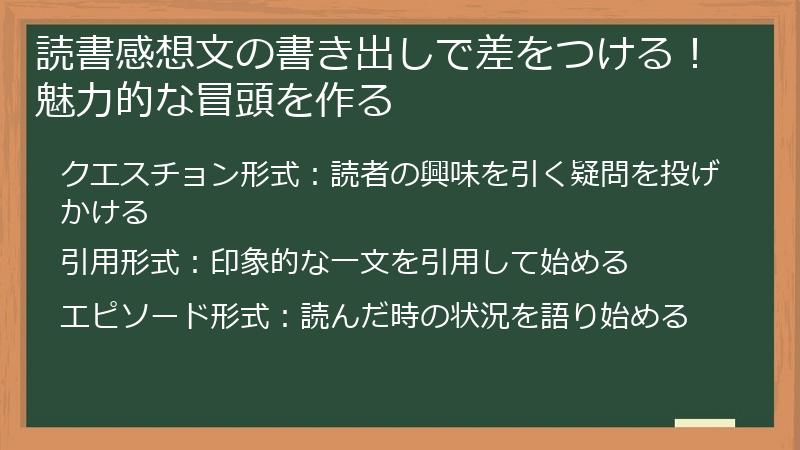
読書感想文の書き出しは、読者の興味を惹きつけ、最後まで読んでもらうための重要な要素です。
平凡な書き出しでは、読者の心を掴むことはできません。
ここでは、読者の興味を惹きつけ、読書感想文の世界へと誘うための3つの魅力的な書き出しのテクニックをご紹介します。
これらのテクニックを活用して、読書感想文の第一印象を劇的に向上させましょう。
クエスチョン形式:読者の興味を引く疑問を投げかける
クエスチョン形式は、読者の興味を惹きつけ、読書感想文の世界へと引き込むための効果的なテクニックです。
物語の核心に触れるような疑問や、読者自身に考えさせるような問いかけをすることで、読者の心を掴み、読書感想文への期待感を高めることができます。
クエスチョン形式を使う際には、以下の点を意識してみましょう。
- 簡潔な疑問文にする:長すぎる疑問文は、読者の集中力を奪ってしまいます。
- 物語の本質に迫る:物語のテーマや、登場人物の心情に深く関わる疑問を選びましょう。
- 読者への問いかけを入れる:読者自身が考え、共感できるような問いかけを意識しましょう。
例えば、『チョコレート戦争』を題材にする場合、以下のようなクエスチョン形式の書き出しが考えられます。
【クエスチョン形式の書き出し例】
「もし、目の前で不正が行われているのを見たら、あなたはどうしますか?」
「チョコレート戦争」は、そんな問いを私たちに投げかける物語です。
この例では、「不正が行われているのを見たら、あなたはどうしますか?」という疑問を投げかけることで、読者の興味を惹きつけています。
また、「そんな問いを私たちに投げかける物語です」という一文を加えることで、読書感想文の内容への期待感を高めています。
クエスチョン形式は、読書感想文の冒頭を印象的に飾り、読者の心を掴むための強力な武器となります。
これらのポイントを参考に、**物語の本質に迫る、魅力的な疑問文**を作成しましょう。
引用形式:印象的な一文を引用して始める
引用形式は、読書感想文の冒頭を印象的に飾り、読者の興味を惹きつけるための有効なテクニックです。
物語の中で最も心に響いた一文や、テーマを象徴する言葉を引用することで、読者に強い印象を与え、読書感想文の世界へと自然に誘導することができます。
引用形式を使う際には、以下の点を意識してみましょう。
- 引用文は短く、印象的に:長すぎる引用は、読者の集中力を奪ってしまいます。
- 引用文を選ぶセンス:物語のテーマを象徴する言葉や、登場人物の心情を深く表
エピソード形式:読んだ時の状況を語り始める
エピソード形式は、読書感想文の書き出しをパーソナルで魅力的なものにするためのテクニックです。
本を読んだ時の状況、場所、時間、そしてその時の自分の気持ちを語り始めることで、読者に親近感を与え、読書感想文の世界へとスムーズに誘うことができます。
エピソード形式を使う際には、以下の点を意識してみましょう。- 具体的な描写:五感を使い、読んだ時の状況を鮮やかに描写しましょう。
- 感情を素直に表現:その時、どんな気持ちだったのか、素直な言葉で表現しましょう。
- 本との出会いをドラマチックに:なぜその本を手に取ったのか、運命的な出会いを演出
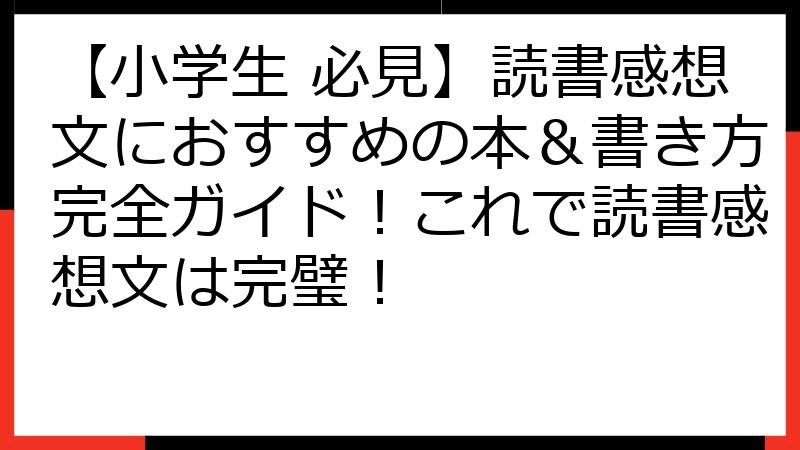
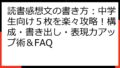
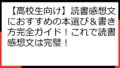
コメント