【税の作文】読後感を左右する「終わり方」をマスター!採点者を唸らせる締めの秘訣
税の作文。書き進めるうちに、一体どのように締めくくれば良いのか悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
どれだけ素晴らしい内容を書いても、最後の締め方が曖昧だと、読後感がぼやけてしまい、せっかくの努力が半減してしまうことも。
この記事では、税の作文の「終わり方」に焦点を当て、採点者(先生)の心に響き、読後感を最高のものにするための具体的な方法を、徹底的に解説していきます。
これまで「終わり方」に悩んでいた方も、さらにレベルアップしたい方も、ぜひ最後までお読みください。
税の作文、なぜ「終わり方」が重要なのか?
税の作文において、終わり方は単なる締めくくりではありません。
それは、読者、特に評価者である先生に、あなたの作文がどのようなメッセージを伝えようとしたのか、そしてそれがどれだけ深く理解されたのかを印象づける、非常に重要な部分です。
ここでは、なぜ「終わり方」がそこまで重要視されるのか、その理由と、評価者の視点に立った「良い終わり方」のポイントを解説します。
作文全体の印象を決定づける最終章
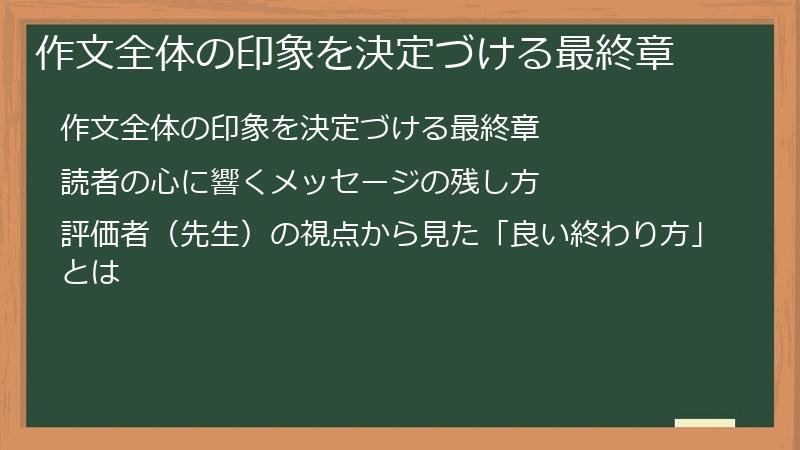
作文の締めくくりは、読者があなたの作文から何を感じ、何を記憶に残すかを左右する、まさに「最終章」とも言える部分です。
どんなに充実した内容であっても、最後の締め方が曖昧だと、読者の心に深く響かず、せっかくのメッセージがぼやけてしまう可能性があります。
ここでは、作文全体の印象を決定づける、効果的な「終わり方」の重要性について掘り下げていきます。
作文全体の印象を決定づける最終章
税の作文における「終わり方」は、読者があなたの作文を読み終えた後に抱く感情や、作文全体から受ける印象を決定づける、極めて重要な要素です。
それは、単に文章を終わらせるという作業ではなく、これまでの論述を締めくくり、読者に強いメッセージや共感を残すための、集大成とも言える部分です。
具体的には、以下のような目的を達成することが期待されます。
-
これまでの論述の要約と再確認
: 作文全体で展開してきた主張や論点を簡潔にまとめ、読者に改めて理解を促します。
-
読者への感動や共感の喚起
: 税金というテーマに対して、読者が自分事として捉えられるような、感情に訴えかける言葉で締めくくります。
-
未来への展望や提言
: 作文で得た学びや気づきを基に、将来への希望や社会への貢献といった前向きなメッセージを伝えます。
-
記憶に残る余韻の創出
: 印象的な言葉やエピソードで締めくくり、読者の記憶に深く刻み込むことを目指します。
これらの目的を達成することで、あなたの作文は単なる課題作文としてではなく、読者の心に響く、価値ある作品として認識されるでしょう。
効果的な「終わり方」をマスターすることは、税の作文の評価を大きく左右すると言っても過言ではありません。
読者の心に響くメッセージの残し方
税の作文の終わり方において、読者の心に響くメッセージを残すことは、作文全体の完成度を大きく高める鍵となります。
単に論点をまとめるだけでなく、読者が「なるほど」と思ったり、共感したり、あるいは税金というテーマについて改めて考えさせられたりするような、余韻のある締めくくりを目指しましょう。
具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。
-
自身の経験や感情との結びつき
: 作文で触れた税金に関する体験や、それを通じて感じた率直な感情を、素直な言葉で表現することで、読者はあなたに共感しやすくなります。
-
普遍的なテーマへの言及
: 税金が社会の仕組みや国民生活にどのように関わっているのか、といった普遍的なテーマに触れることで、読者はより広い視野で税金について考えるきっかけを得られます。
-
感謝の念や貢献意欲の表明
: 税金が社会のために役立っていることへの感謝の気持ちや、将来、自分も社会に貢献したいという意欲を示すことで、前向きで建設的なメッセージを伝えることができます。
-
未来への希望や提言
: 税金制度の改善点や、より良い社会の実現に向けた自身の考えを簡潔に述べることで、読者に示唆を与えることができます。
これらの方法を組み合わせることで、読者の心に深く刻まれる、印象的なメッセージを残すことができるでしょう。
「終わり方」を工夫することで、あなたの税の作文は、より説得力と感動を兼ね備えたものになります。
評価者(先生)の視点から見た「良い終わり方」とは
税の作文の評価者は、あなたの作文を多角的に読み解き、その内容や論理構成、そして表現力を判断します。
評価者が「良い終わり方」だと感じるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これらのポイントを意識することで、あなたの作文はより高く評価される可能性が高まります。
-
明確な主張の再確認
: 作文全体を通して最も伝えたかった中心的なメッセージや主張が、結論部分で明確に再提示されていることが重要です。これにより、読者はあなたの考えをしっかりと理解することができます。
-
論理的な一貫性
: 結論部分が、それまでの本文で展開されてきた論理や根拠と矛盾なく、一貫性を持っていることが求められます。唐突な結論や、本文の内容と乖離した締めくくりは、評価を下げてしまう可能性があります。
-
具体的な内容への言及
: 抽象的な言葉だけでなく、作文の本文で具体的に触れた内容に再度言及したり、それを踏まえた上での考察を示したりすることで、説得力が増します。
-
将来への展望や実践
: 単なる感想で終わるのではなく、作文を通じて得た学びを将来どのように活かしていくのか、といった具体的な行動や考え方を示すことで、主体性や成長意欲が評価されます。
-
読後感への配慮
: 読者(先生)に、ポジティブな印象や、考えさせられるきっかけを与えるような、心地よい余韻を残す締めくくりは、評価者にとって好ましいものです。
これらの要素を意識して「終わり方」を工夫することで、あなたの税の作文は、評価者に「よく書けている」「しっかり考えている」といった好印象を与えることができるでしょう。
評価者の視点を理解し、それに沿った締めくくりを心がけることが、成功の鍵となります。
説得力を高める!論理的な締めくくり方
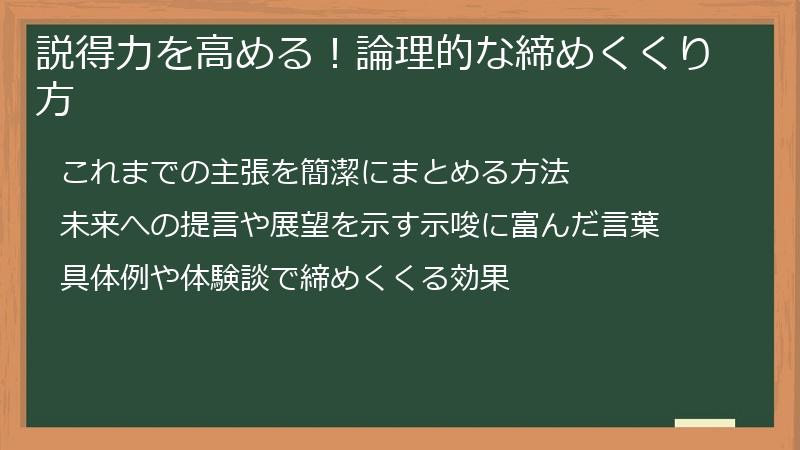
税の作文において、説得力を高めるための論理的な締めくくり方は、読者に「なるほど、そういうことか」と納得感を与えるために不可欠です。
単に感想を述べるだけでなく、これまでの論述を論理的にまとめ上げ、読者があなたの主張をスムーズに受け入れられるような道筋を示すことが重要となります。
ここでは、作文の結論部分で説得力を最大限に引き出すための、具体的な方法論について解説します。
これまでの主張を簡潔にまとめる方法
税の作文の締めくくりとして、これまでの主張を簡潔にまとめることは、読者にあなたの作文の核心を明確に伝えるために不可欠です。
長々と論述してきた内容を、読者が理解しやすい形で再提示することで、作文全体の論理的なつながりが強化されます。
ここでは、効果的に主張をまとめるための具体的な方法を解説します。
-
中心的なテーマの再確認
: 作文の導入で提示した問題提起や、中心的なテーマを改めて簡潔に述べ、読者の記憶を呼び覚まします。
-
主要な論点の列挙
: 作文全体で展開した、最も重要ないくつかの論点や根拠を、箇条書きや簡潔な文章で列挙します。これにより、主張の骨子を分かりやすく提示できます。
-
結論への論理的な誘導
: これまで述べた論点を踏まえ、そこから自然に導き出される結論を提示します。接続詞などを効果的に用いることで、論理的な流れをスムーズにします。
-
専門用語の回避
: 専門用語や難しい言葉は避け、誰にでも理解できる平易な言葉でまとめるように心がけます。
-
断定的な表現の適切さ
: 自分の主張に自信がある場合でも、断定しすぎると反論を招く可能性もあります。状況に応じて、「~と考えられます」といった、やや控えめな表現を用いることも有効です。
これらの方法を実践することで、あなたの作文の結論は、これまでの論述の説得力を増幅させ、読者に深い納得感を与えることができるでしょう。
簡潔かつ論理的なまとめは、作文の「終わり方」における重要なスキルです。
未来への提言や展望を示す示唆に富んだ言葉
税の作文の締めくくりに、未来への提言や展望を示す示唆に富んだ言葉を加えることは、読者に深い思索を促し、作文の価値を一層高めます。
単に事実を述べるだけでなく、そこから将来に向けてどのような可能性があるのか、あるいはどのような行動が望ましいのかを示すことで、あなたの作文はより建設的で、未来志向のメッセージを持つようになります。
ここでは、示唆に富む言葉で締めくくるための具体的なアプローチを解説します。
-
社会のあり方への言及
: 税金がどのように社会を支えているのか、そして将来どのような社会を目指すべきか、といった広い視点から言及します。
-
自身の貢献意欲の表明
: 作文で学んだことを踏まえ、将来どのように社会に貢献していきたいか、といった個人的な目標や決意を述べます。
-
課題解決への示唆
: 税金に関する問題点や課題に触れた上で、その解決に向けた建設的な提案や、読者への問いかけを行います。
-
希望や前向きなメッセージ
: 税金というテーマに対して、悲観的になるのではなく、未来への希望や、より良い社会を築くための前向きなメッセージを伝えることが重要です。
-
普遍的な価値観との結びつき
: 税金と、教育、福祉、環境といった、より普遍的で大切な価値観と結びつけて語ることで、メッセージに深みが増します。
これらの示唆に富んだ言葉を効果的に活用することで、あなたの税の作文は、単なる課題の提出に留まらず、読者の心に深く響き、行動を促すような、影響力のある作品となるでしょう。
未来への視点を含んだ締めくくりは、あなたの作文に更なる奥行きを与えます。
具体例や体験談で締めくくる効果
税の作文を具体例や体験談で締めくくることは、読者の共感を得やすく、作文にリアリティと説得力を持たせる上で非常に効果的です。
抽象的な議論や一般的な事実だけでは伝わりにくい内容も、具体的なエピソードを交えることで、読者の心に強く響くメッセージとなります。
ここでは、具体例や体験談を効果的に用いるためのポイントを解説します。
-
個人的な体験の共有
: 税金にまつわる自身の経験、例えば、親が税金について話していたこと、公共サービスを利用した際に税金の存在を意識したことなどを具体的に語ります。
-
身近な具体例の提示
: 税金がどのように社会に役立っているかの具体例(例:道路の整備、学校の建設、医療費の助成など)を、読者がイメージしやすい形で提示します。
-
事例からの学びの抽出
: 提示した具体例や体験談から、どのような教訓や気づきを得たのかを明確に示します。これが、作文の結論としてのメッセージに深みを与えます。
-
感情的な側面への言及
: 具体例や体験談を通して感じた、喜び、感謝、あるいは疑問といった感情を率直に表現することで、読者の共感を呼びやすくなります。
-
簡潔さと的確さ
: あまり長すぎるエピソードにならないよう、作文の結論として適切な長さにまとめ、最も伝えたいポイントに絞ることが重要です。
具体例や体験談を効果的に用いることで、あなたの税の作文は、読者にとってより親しみやすく、共感しやすいものとなり、記憶に残りやすい締めくくりとなるでしょう。
読者の感情に訴えかける締め方は、作文の説得力を格段に向上させます。
感動を呼ぶ!感情に訴えかける表現術
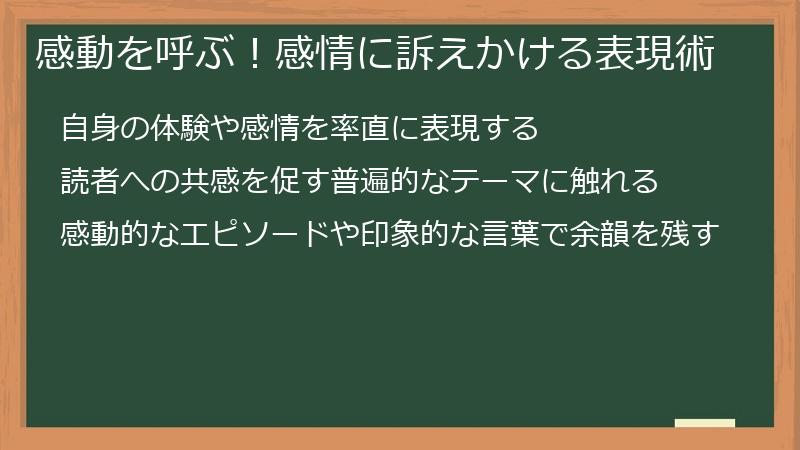
税の作文は、論理的な説明だけでなく、読者の感情に訴えかけることで、より深く心に響く作品となります。
特に、締めくくりにおいて、感動的な表現を取り入れることで、読後感を豊かにし、あなたの作文を忘れられないものにすることができます。
ここでは、読者の感情に訴えかけ、感動を呼ぶための表現術について解説します。
自身の体験や感情を率直に表現する
税の作文の締めくくりにおいて、自身の体験や感情を率直に表現することは、読者の共感を生み出し、感動を呼ぶための強力な手法です。
抽象的な議論だけでは伝わりにくい税金というテーマも、個人的な経験と結びつけることで、読者にとってより身近で、感情に訴えかけるものとなります。
ここでは、自身の体験や感情を効果的に表現するためのポイントを解説します。
-
具体的なエピソードの選択
: 税金に関わる具体的な出来事、例えば、家族が税金について話していた場面、公共サービスを利用した際の感謝の念、あるいは税金に関する疑問や驚きなど、心に残ったエピソードを選びます。
-
率直な感情の描写
: その体験を通じて感じた、率直な感情(喜び、感謝、驚き、疑問、あるいは社会への期待など)を、飾らない言葉で表現します。
-
「なぜそう感じたのか」の説明
: 単に感情を述べるだけでなく、なぜそのような感情を抱いたのか、その背景にある考えや理由を簡潔に説明することで、読者の理解を深めます。
-
読者との共感の橋渡し
: 自分の体験や感情が、読者も共有できる普遍的なものであることを意識して表現することで、共感の輪を広げることができます。
-
自己開示のバランス
: あまりに個人的すぎる内容や、感情的すぎる表現は避ける必要があります。読者に伝わる範囲で、適切に自己開示を行うことが重要です。
自身の体験や感情を率直に表現することで、あなたの税の作文は、表面的な文章から、読者の心に響く、人間味あふれる作品へと昇華するでしょう。
感情に訴えかける締めくくりは、作文の印象を決定づける上で非常に強力な武器となります。
読者への共感を促す普遍的なテーマに触れる
税の作文の締めくくりにおいて、読者への共感を促す普遍的なテーマに触れることは、あなたのメッセージをより多くの人々に響かせるための効果的な方法です。
税金という具体的なテーマから一歩進んで、より広い視点や、人々が共有できる価値観に言及することで、読者はあなたの作文に感情的なつながりを感じやすくなります。
ここでは、普遍的なテーマに触れることで共感を促すためのアプローチを解説します。
-
社会貢献への意識
: 税金がどのように社会全体に貢献し、より良い社会を築くための基盤となっているのか、という普遍的な価値に触れることで、読者は「自分もその一員である」という意識を持ちやすくなります。
-
将来世代への責任
: 現在の税金が、将来世代の社会基盤や福祉にどのように影響するのか、といった視点を示すことで、世代を超えた責任感に訴えかけることができます。
-
地域社会とのつながり
: 税金が身近な地域社会(例:公園の整備、公共施設の維持など)を支えていることに言及し、地域への愛着や貢献意識を喚起します。
-
公平性や公正さの追求
: 税制度が、社会の公平性や公正さを保つ上でどのような役割を果たしているのか、という理想や目標に触れることで、読者の共感を呼び起こします。
-
共有されるべき価値
: 教育、医療、環境保護など、社会全体で共有されるべき価値と税金との関連性を示すことで、読者はより深いレベルであなたの作文を理解し、共感するでしょう。
普遍的なテーマに触れることで、あなたの税の作文は、単なる個人の意見表明に留まらず、社会全体で共有されるべき重要なメッセージとして、読者の心に響くものとなります。
感動を呼ぶ締めくくりは、読者の感情に訴えかけることから始まります。
感動的なエピソードや印象的な言葉で余韻を残す
税の作文の締めくくりに、感動的なエピソードや印象的な言葉を用いることは、読者の心に深く残り、作文全体に忘れがたい余韻を与えるための効果的な方法です。
論理的な構成だけでなく、感情に訴えかける要素を加えることで、あなたの作文はより人間味あふれるものとなり、読者の記憶に強く刻まれるでしょう。
ここでは、感動的なエピソードや印象的な言葉で余韻を残すための方法を解説します。
-
心温まるエピソードの挿入
: 税金が人々の生活を支え、助けとなっている感動的な実話や、自身の体験談を簡潔に紹介します。例えば、災害時の支援や、困難な状況にある人々への援助といった場面です。
-
感謝の念の表明
: 税金を通じて提供される社会サービスや、それらを支える人々への感謝の気持ちを、素直な言葉で伝えます。
-
詩的な表現や比喩の使用
: 税金が社会の「礎」である、といった比喩や、感情に訴えかける詩的な言葉を用いることで、文章に深みと情感を加えることができます。
-
引用の活用
: 歴史上の偉人や著名人の、税金や社会貢献に関する印象的な言葉を引用し、それを自身の考えと結びつけることで、メッセージに重みを持たせることができます。
-
簡潔でありながら力強い言葉
: 長々とした説明ではなく、短くても心に響く、力強い言葉で締めくくることが重要です。余韻を残すためには、情報過多にならないよう注意が必要です。
感動的なエピソードや印象的な言葉で締めくくることで、あなたの税の作文は、読者の心に温かい感動と、考えさせられる余韻を残し、非常に満足度の高いものとなるでしょう。
感情に訴えかける表現術は、作文の「終わり方」において、読後感を大きく左右する要素です。
税の作文、NGな終わり方と改善策
税の作文は、その内容はもちろんのこと、締めくくり方一つで評価が大きく変わる可能性があります。
せっかく一生懸命書いた作文でも、終わり方が適切でないと、読者(先生)にマイナスな印象を与えてしまうことも少なくありません。
ここでは、税の作文で避けるべき「NGな終わり方」の具体例を挙げ、それぞれの改善策を提示することで、あなたの作文の質をさらに向上させるためのヒントを提供します。
具体性がない、漠然としたまとめ方
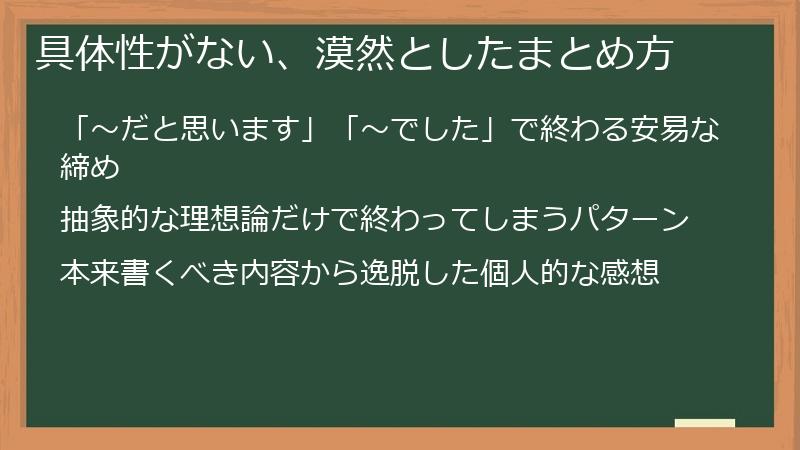
税の作文における「具体性がない、漠然としたまとめ方」は、読者に内容が伝わりにくく、作文全体の説得力を損なう典型的なNGパターンです。
しっかりとした論述を展開しても、結論が曖昧では、せっかくの主張がぼやけてしまい、評価者(先生)に「この作文は何を言いたかったのだろう?」と思わせてしまう可能性があります。
ここでは、具体性に欠けるまとめ方の具体例と、それを改善するための方法を解説します。
「~だと思います」「~でした」で終わる安易な締め
税の作文の締めくくりとして、「~だと思います」や「~でした」といった、曖昧で断定を避けるような表現で終わってしまうのは、残念ながらNGな終わり方の一つです。
これらの表現は、作文全体の主張に説得力を持たせず、読者に「結局、筆者はどう考えているのだろう?」という疑問を抱かせかねません。
ここでは、なぜこのような締め方がNGなのか、そしてそれをどのように改善すべきかを具体的に解説します。
-
主張の弱さ
: 「~だと思います」という表現は、自身の意見に確信が持てない印象を与え、作文全体の論調を弱めてしまいます。評価者(先生)は、明確な意見や考察を求めているため、このような表現は避けるべきです。
-
根拠の不明瞭さ
: 「~でした」という過去の事実の羅列で終わってしまうと、そこから何を感じ、何を学んだのか、といった筆者自身の考察が欠けているように見えます。作文では、事実だけでなく、そこから得られた学びや意見を提示することが重要です。
-
読後感の希薄さ
: これらの表現で終わると、読者に強い印象を残すことが難しく、作文全体が記憶に残りにくいものになってしまいます。
-
改善策:断定的な表現の活用
: 自身の考えや結論を明確に述べるために、「~だと考えます」「~は重要です」といった、より断定的な表現を使用しましょう。
-
改善策:考察や提言の追加
: 単なる事実の羅列で終わるのではなく、「この経験から、私は~することの重要性を学びました。」「今後、~のような社会になることを期待します。」といった、自身の考察や将来への提言を加えることで、説得力が増します。
「~だと思います」「~でした」という安易な締め方を避け、より確信を持った表現や、自身の考察を加えることで、あなたの税の作文は格段に説得力を増し、読者の心に響くものとなるでしょう。
結論部分での言葉遣いは、作文の印象を大きく左右します。
抽象的な理想論だけで終わってしまうパターン
税の作文の締めくくりで、抽象的な理想論だけで終わってしまうのは、具体的な内容が伴わないため、読者に響きにくいNGパターンです。
「皆が税金を大切にすべきだ」「もっと良い世の中になるべきだ」といった、誰でも言えるような一般的な理想論を述べるだけでは、あなたの作文に独自性や深みがなく、評価者(先生)に「ありきたりな作文だ」と思われてしまう可能性があります。
ここでは、なぜこのパターンがNGなのか、そしてどのように改善すべきかを解説します。
-
具体性の欠如
: 抽象的な理想論だけでは、読者はそれをどのように実現するのか、あるいは筆者が具体的に何を感じ、何を考えているのかを理解できません。作文の目的は、具体的な思考や体験を共有することにあります。
-
説得力の低下
: 根拠や具体例が示されていない理想論は、空虚に響くだけで、説得力に欠けます。読者は、抽象的な言葉よりも、具体的な事例や筆者の考えに基づいた結論に納得します。
-
オリジナリティの欠如
: 理想論は誰にでも言えることであるため、あなたの作文にオリジナリティがなく、他の作文との差別化が図れません。
-
改善策:具体的な事例との連携
: 抽象的な理想論を述べる前に、作文の本文で扱った具体的な事例や体験談に触れ、そこから導き出される理想論であることを示すことが重要です。
-
改善策:自身の言葉での表現
: 理想論を述べる際も、ありきたりな言葉ではなく、あなた自身の言葉で、どのようにその理想を実現したいのか、あるいはその理想がなぜ重要なのかを具体的に説明しましょう。
抽象的な理想論だけで締めくくるのではなく、具体的な内容と結びつけ、あなた自身の言葉で表現することで、あなたの税の作文は、より説得力があり、読者の心に響くものとなるでしょう。
結論部分では、抽象論に終始せず、具体的な根拠を示すことが重要です。
本来書くべき内容から逸脱した個人的な感想
税の作文の締めくくりにおいて、本来書くべき内容から逸脱した個人的な感想を述べてしまうのは、作文の目的を見失っていると判断されかねない、避けるべきNGパターンです。
例えば、作文のテーマである「税」から離れて、単に「作文を書くのが大変だった」とか、「もっと別のテーマで書きたかった」といった個人的な不満や願望を述べることは、評価者(先生)にマイナスな印象を与えてしまいます。
ここでは、なぜこのような個人的な感想がNGなのか、そしてどのように改善すべきかを解説します。
-
作文の目的との乖離
: 税の作文は、税金に関する知識、理解、あるいはそれらを通じて得た考えを共有することが目的です。個人的な感想に終始すると、この目的から逸脱してしまいます。
-
評価者への悪印象
: 課題への不満や、テーマへの無関心と受け取られかねない個人的な感想は、評価者(先生)に不快感を与え、作文全体の評価を下げる原因となります。
-
論点の不明瞭化
: 本来伝えるべき税金に関する主張や考察が、個人的な感想に埋もれてしまい、読者に伝わりにくくなります。
-
改善策:作文のテーマへの回帰
: 結論部分では、必ず作文のテーマである「税」に焦点を戻し、そこから得られた学びや考えをまとめるようにしましょう。
-
改善策:建設的な意見の提示
: もし、税金に関する改善点や自身の考えを述べたい場合は、個人的な不満ではなく、建設的な意見や提言として提示することが重要です。例えば、「税金について学ぶ中で、〇〇の重要性を感じました。」といった形です。
作文の結論では、個人的な感情や感想に終始せず、常に「税」というテーマに立ち返り、そこから得られた学びや考えを、建設的かつ具体的にまとめることが大切です。
テーマからの逸脱は、作文の評価を著しく低下させる可能性があります。
論点が不明瞭、主張が弱い終わり方
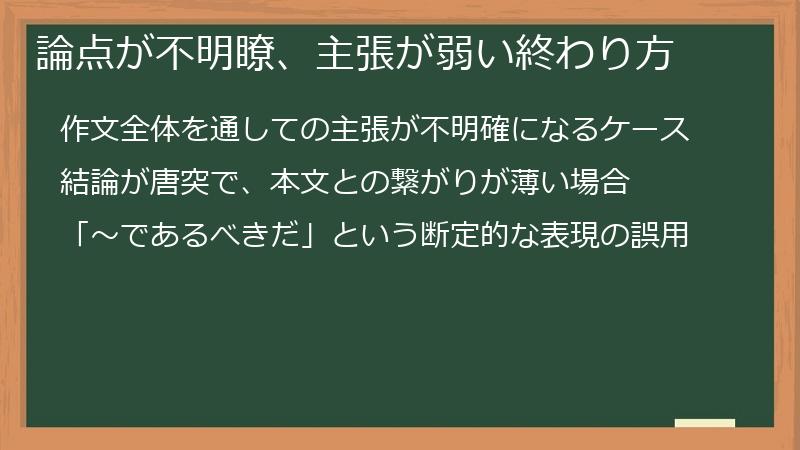
税の作文において、論点が不明瞭であったり、主張が弱々しく聞こえてしまう締めくくり方は、読者に内容がうまく伝わらないだけでなく、作文全体の信頼性を損ねるNGパターンです。
これまで述べてきた内容が、結論部分でしっかりと整理され、力強いメッセージとして伝わらなければ、読者はあなたの考えを深く理解することができません。
ここでは、論点が不明瞭、あるいは主張が弱い終わり方の具体例と、その改善策を解説します。
作文全体を通しての主張が不明確になるケース
税の作文で、作文全体を通しての主張が不明確なまま締めくくられてしまうのは、読者に内容が伝わりきらない、最も避けたいNGパターンの一つです。
本文で様々な論点を展開したとしても、結論でそれらが一つにまとまらず、結局何が言いたかったのかが曖昧になってしまうと、作文全体の価値が大きく低下してしまいます。
ここでは、主張が不明確になってしまう原因と、それを改善するための方法を解説します。
-
論点の分散
: 作文の途中で、本来の中心的な主張から逸れて、多くの論点に触れすぎると、結論でそれらを一つにまとめることが難しくなります。
-
結論と本文の乖離
: 本文で展開してきた論理や根拠と、結論部分での主張が一致していない場合、読者は混乱し、主張が不明確だと感じてしまいます。
-
曖昧な言葉遣い
: 結論部分で「~かもしれない」「~だと思う」といった曖昧な表現を多用すると、主張そのものが弱々しくなってしまいます。
-
改善策:中心的なメッセージの再確認
: 作文を書き始める前に、最も伝えたい中心的なメッセージを明確にし、それを常に意識しながら論述を進めることが重要です。
-
改善策:結論での明確な提示
: 結論部分では、本文で展開した内容を簡潔にまとめつつ、最初に設定した中心的なメッセージを改めて力強く提示します。「結局、税金とは〇〇なものであると私は考えます。」といった形で、明確に述べるようにしましょう。
作文全体を通しての主張を明確にし、結論部分でそれを力強く提示することで、あなたの税の作文は、読者に明確なメッセージを伝え、高い説得力を持つものとなります。
論点の整理と、結論での主張の明確化は、作文の完成度を高めるために不可欠です。
結論が唐突で、本文との繋がりが薄い場合
税の作文の締めくくりが、本文で展開されてきた内容と関係なく、唐突に結論だけが述べられている場合、読者は内容を理解できず、不自然な印象を抱きます。
これは、本文で十分な論拠や理由が示されていないにも関わらず、一方的に結論だけが提示されている状態であり、作文全体の論理性を損なうNGパターンです。
ここでは、結論が唐突で本文との繋がりが薄いケースとその改善策について解説します。
-
本文との論理的欠如
: 本文で展開した議論や事例が、結論部分でどのように活かされ、それがどのように結論を導き出したのか、という過程が不明確です。
-
飛躍した主張
: 本文で十分な根拠が示されていないのに、急に飛躍した主張や結論が述べられている場合、読者は納得できません。
-
接続詞の不使用
: 本文と結論を繋ぐための適切な接続詞(例:「したがって」「これらのことから」「以上の点を踏まえると」など)が使用されていないと、唐突さが際立ちます。
-
改善策:本文と結論の接続詞の活用
: 本文の最後の部分と結論の冒頭に、論理的なつながりを示す接続詞を効果的に使用します。これにより、読者はスムーズに結論へと導かれます。
-
改善策:結論部分での要約と論拠の再提示
: 結論部分で、本文で展開した主要な論点や根拠を簡潔に要約し、それらがどのように結論を支持しているのかを再度示します。これにより、結論の説得力が増します。
本文と結論の間に論理的な繋がりを意識し、適切な接続詞を使用したり、本文の要約を加えたりすることで、唐突な印象をなくし、作文全体の説得力を高めることができます。
結論は、本文の論理的な帰結として自然に導き出されるべきです。
「~であるべきだ」という断定的な表現の誤用
税の作文の締めくくりにおいて、「~であるべきだ」といった断定的な表現を誤用することは、読者に反発されたり、論理的な飛躍と捉えられたりする可能性のあるNGパターンです。
もちろん、確固たる意見や提言を述べる際には断定的な表現も有効ですが、それが根拠なく、あるいは一方的な主張として用いられると、作文の説得力を損なうことになります。
ここでは、断定的な表現の誤用がなぜNGなのか、そしてどのように適切に使うべきかを解説します。
-
一方的な主張
: 根拠や論理的な裏付けが不十分なまま「~であるべきだ」と断定すると、読者は「なぜそう言えるのか」と疑問に思い、一方的な意見だと受け止めてしまいます。
-
感情的な押し付け
: 感情論や主観のみで断定的な表現を用いると、読者に「押し付けられている」と感じさせ、共感を得にくくなります。
-
反論の余地を与える
: 根拠が不明確な断定は、反論を招きやすく、作文の説得力を低下させる可能性があります。
-
改善策:根拠の明確化
: 断定的な表現を用いる場合は、その主張を裏付ける具体的な根拠や論理を、本文でしっかりと展開しておくことが必須です。
-
改善策:婉曲的な表現の検討
: 根拠が弱い場合や、多様な意見が存在するテーマについては、「~と考えるのが妥当ではないでしょうか」「~することが望ましいと考えられます」といった、より丁寧で婉曲的な表現を用いることで、読者の理解を得やすくなります。
-
改善策:共感の醸成
: 断定的な表現を使う場合でも、その後に読者への共感を促す言葉や、共に考える姿勢を示す言葉を加えることで、印象が和らぎます。
「~であるべきだ」という断定的な表現は、その使用法を誤ると作文の質を低下させます。
根拠を明確にし、状況に応じて適切な表現を選ぶことが、説得力のある締めくくりには不可欠です。
時間切れ?未完成で終わってしまうパターン
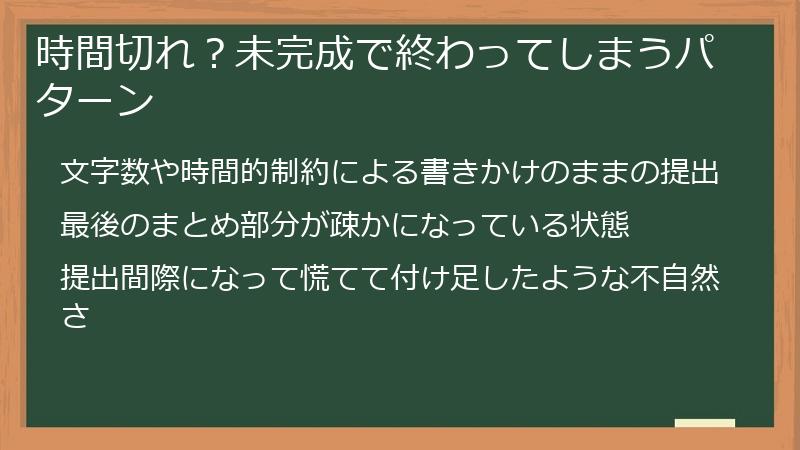
税の作文において、時間切れや準備不足によって未完成のまま終わってしまうのは、最も避けるべきNGパターンの一つです。
どれだけ良いアイデアや構成があっても、書き終えられていなければ評価されることはありません。
特に、結論部分が疎かになっていると、作文全体の質が著しく低下します。
ここでは、未完成で終わってしまう原因と、その改善策について解説します。
文字数や時間的制約による書きかけのままの提出
税の作文で、文字数や時間的な制約のために、本来書きたかった結論部分が書きかけのまま提出されてしまうのは、最も避けたいNGパターンです。
たとえ本文がどれだけ良く書けていても、結論が不完全なままでは、作文全体の評価が大きく下がってしまいます。
ここでは、この状況がなぜ問題なのか、そしてどのように回避すべきかを具体的に解説します。
-
評価の機会損失
: 結論部分が未完成だと、筆者が伝えたい最後のメッセージや、作文全体を通しての主張が伝わりません。これは、せっかくの努力を評価してもらえない、という機会損失に繋がります。
-
不誠実な印象
: 締めの部分が未完成なまま提出されると、読者(先生)からは、時間管理ができていない、あるいは作文に真剣に取り組んでいない、といった印象を与えかねません。
-
作文全体のバランスの悪化
: 本文に十分なボリュームがあっても、結論が未完成だと、作文全体のバランスが悪く見えてしまいます。
-
改善策:事前の時間配分計画
: 作文に取り掛かる前に、全体の構成を考え、各部分にどれくらいの時間をかけるか、計画を立てることが重要です。特に、結論部分には十分な時間を確保しましょう。
-
改善策:最悪のケースを想定した執筆
: どのような状況でも、最低限の結論が書けるように、本文を完成させた段階で、結論の骨子だけでも書き出しておく習慣をつけましょう。
-
改善策:推敲時間の確保
: 全体を書き終えた後、内容の確認や修正、そして何よりも結論部分の推敲(すいこう)のための時間を必ず確保することが大切です。
時間管理を徹底し、結論部分を書き終えることを最優先にすることで、未完成で提出してしまうという事態を防ぐことができます。
作文の締めくくりは、最後まで手を抜かずに完成させることが重要です。
最後のまとめ部分が疎かになっている状態
税の作文において、結論部分、つまり最後のまとめが疎かになっている状態も、評価を下げるNGパターンです。
本文はしっかり書けていても、結論部分が「とりあえず終わらせました」というような、手抜き感のある内容になっていると、読者(先生)に「この作文は最後まで力を入れて書かれていない」という印象を与えてしまいます。
ここでは、まとめ部分が疎かになっている状態がなぜ問題なのか、そしてそれを改善するための方法を解説します。
-
作文全体の印象の低下
: 結論部分が疎かになっていると、作文全体の完成度が低く見え、せっかく本文で築き上げた説得力や感動が薄れてしまいます。
-
メッセージの伝達不足
: 最後のまとめは、作文で最も伝えたいメッセージを再確認する重要な役割を担っています。この部分が疎かになると、読者にそのメッセージが十分に伝わりません。
-
熱意の欠如
: まとめ部分に力がこもっていないと、筆者の作文に対する熱意が不足しているように見え、読者に良い印象を与えません。
-
改善策:結論部分への十分な時間確保
: 作文の執筆時間計画において、結論部分の構成や表現を練るための時間を必ず確保しましょう。
-
改善策:要点の整理と力強い言葉遣い
: まとめ部分では、本文で述べた要点を簡潔に整理し、読者に伝えたいメッセージを力強い言葉で表現します。
-
改善策:最終的な推敲
: 全ての執筆が終わった後、結論部分を特に丁寧に推敲し、内容の整合性や表現の適切さを確認することが重要です。
作文の締めくくりであるまとめ部分を疎かにせず、最後まで丁寧に取り組むことで、あなたの税の作文は、より完成度の高い、読者に良い印象を与えるものとなります。
最後のまとめこそ、作文の「顔」となる部分です。
提出間際になって慌てて付け足したような不自然さ
税の作文の締めくくりで、提出間際になって慌てて付け足したような不自然さが感じられるのは、作文全体の信頼性を損なうNGパターンです。
本来、結論部分は、それまでの論述を論理的にまとめ、読者に伝えたいメッセージを明確にするための重要な箇所です。
しかし、時間がないために、場当たり的な表現や、本文と繋がりのない言葉を付け足してしまうと、読者(先生)に「計画性がなく、真剣に取り組んでいない」という印象を与えかねません。
ここでは、不自然な締めくくりがなぜ問題なのか、そしてそれを回避するための方法を解説します。
-
論理性の欠如
: 慌てて付け足された結論は、本文で展開された論理との繋がりが薄く、唐突な印象を与えます。
-
表現の稚拙さ
: 時間がない状況では、適切な言葉選びができず、幼稚な表現や、誤字脱字が多くなる傾向があります。
-
構成の破綻
: 本来の構成から逸脱した内容が付け足されると、作文全体のバランスが崩れてしまいます。
-
改善策:早期からの計画的な執筆
: 結論部分まで含めて、作文全体の構成と執筆スケジュールを事前に計画し、余裕を持って取り組むことが最も重要です。
-
改善策:結論の骨子の事前準備
: 本文の執筆と並行して、結論で何を伝えたいのか、その骨子を事前にまとめておくことで、時間がない場合でも、ある程度まとまった内容を書きやすくなります。
-
改善策:推敲時間の確保と最終確認
: 執筆完了後、慌てずに推敲する時間を確保し、結論部分が本文と論理的に繋がっているか、表現は適切かなどを最終確認することが不可欠です。
提出間際になって慌てて付け足すような不自然さを避けるためには、日頃からの計画的な執筆と、最終的な推敲が鍵となります。
結論部分を丁寧かつ自然に仕上げることで、あなたの税の作文は、より完成度の高いものとなるでしょう。
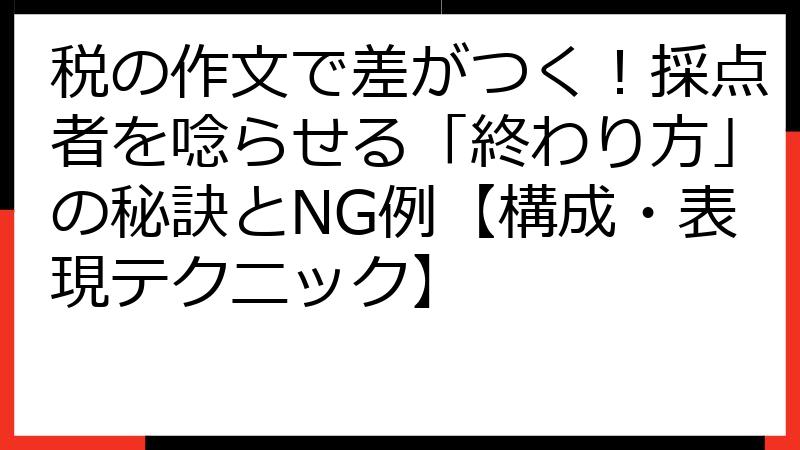

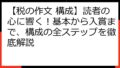
コメント