- 【徹底解説】御朱印帳のサイズ選びで失敗しない!種類・選び方・収納術まで完全ガイド
- 御朱印帳の「サイズ」とは?基本の寸法を知ろう
- サイズだけじゃない!御朱印帳選びで後悔しないための「素材」と「仕様」
- 意外と知らない?御朱印帳の「サイズ」にまつわる豆知識
- 人気の御朱印帳サイズの変遷:時代と共に変化するトレンド
- 海外の御朱印帳とのサイズ比較:日本独自の文化
- カスタムオーダーできる御朱印帳:自分だけのサイズを追求
- 購入前にチェック!御朱印帳のサイズに関する「よくある疑問」を解消
- 初めての御朱印帳、どのサイズを選ぶべき?初心者のためのガイド
- お土産屋さんや寺社で売られている御朱印帳の平均的なサイズ
- ネット購入時の注意点:サイズ表記をしっかり確認する方法
【徹底解説】御朱印帳のサイズ選びで失敗しない!種類・選び方・収納術まで完全ガイド
寺社仏閣巡りでいただく、特別な思い出の証である御朱印。
その御朱印をいただくのに欠かせないのが、御朱印帳です。
一口に御朱印帳と言っても、そのサイズは様々。
「どんなサイズを選べばいいの?」
「集める御朱印の種類によってサイズは違う?」
「持ち運びや収納はどうすればいい?」
など、御朱印帳のサイズ選びで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、御朱印帳のサイズに焦点を当て、その種類や選び方、さらに収納方法まで、あなたが失敗しないための情報を徹底的に解説します。
あなたにとって最適な御朱印帳を見つけるための、第一歩を踏み出しましょう。
御朱印帳の「サイズ」とは?基本の寸法を知ろう
御朱印帳のサイズについて、まず基本となる寸法から理解を深めましょう。
一般的に流通しているサイズだけでなく、携帯性に優れたものや、より多様なニーズに応えるための変形サイズなども存在します。
ここでは、それぞれのサイズの特徴と、具体的な寸法について詳しく解説していきます。
あなたの寺社仏閣巡りのスタイルに合ったサイズを見つけるための基礎知識を身につけましょう。
標準的な「大」サイズ:一般的な寸法と特徴
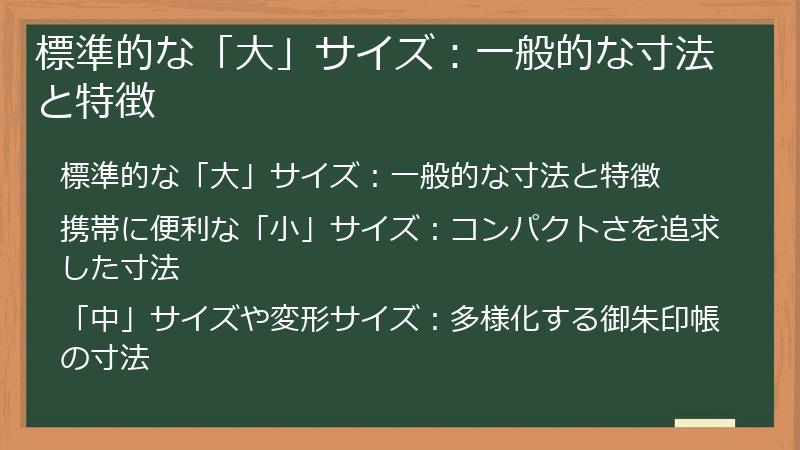
御朱印帳のサイズとして最も一般的で、多くの寺社仏閣で見かけるのが「大」サイズです。
このサイズは、書き置きの御朱印を貼るスペースが十分にあり、直書きの御朱印もゆったりといただくことができます。
具体的な寸法は、縦約18cm、横約12cm程度が一般的ですが、多少の個体差はあります。
どんな御朱印帳を選べばいいか迷ったとき、まずはこの「大」サイズを基準に考えてみるのがおすすめです。
標準的な「大」サイズ:一般的な寸法と特徴
標準的な「大」サイズ:一般的な寸法と特徴
御朱印帳のサイズにおいて、最もスタンダードと言えるのが「大」サイズです。
このサイズは、多くの神社仏閣で一般的に頒布されており、多くの御朱印帳コレクターが最初に手にするサイズとも言えます。
その具体的な寸法は、おおよそ縦が18cm前後、横が12cm前後となっています。
ただし、この寸法はあくまで目安であり、神社仏閣や工房によって若干の誤差が生じることがあります。
例えば、縦が18.2cm、横が12.1cmといった精密な寸法で製造されているものもあれば、もう少しだけゆとりを持たせた寸法になっているものもあります。
「大」サイズのメリット
-
書置き御朱印の収納力
「大」サイズは、書置きの御朱印(あらかじめ印刷された御朱印)をそのまま貼っても、はみ出したり折ったりする必要がほとんどないため、綺麗に収納できます。
広々としたスペースに御朱印を貼ることができるため、見た目も美しく、満足感も高まります。 -
直書き御朱印の書きやすさ
御朱印を直接書いていただく「直書き」の際にも、「大」サイズであれば、墨書きや印を押すスペースが十分に確保されています。
書き手の方にとっても、広いスペースに丁寧に御朱印を記しやすいというメリットがあります。 -
携帯性と十分な収納力のバランス
「大」サイズは、携帯するにはやや大きめですが、一般的なビジネスバッグやリュックサックには問題なく収まるサイズ感です。
多くの御朱印を一度に持ち運ぶことができますし、外出先で御朱印をいただく機会が多い方にとっては、非常に実用的なサイズと言えます。
「大」サイズのデメリット
-
小ぶりのバッグには不向きな場合も
普段から小さめのハンドバッグや、サコッシュなどのコンパクトなバッグを使用している方にとっては、「大」サイズは少し大きすぎると感じるかもしれません。
バッグのサイズによっては、出し入れがしにくかったり、バッグの中身がかさばったりする可能性があります。 -
枚数を重ねると重くなる
御朱印をたくさん集めてページが増えると、御朱印帳自体が厚みを増し、重量も増します。
「大」サイズで多くの御朱印をいただくと、その分重さは増していきますので、長時間の持ち運びには少し負担になることも考えられます。
「大」サイズの具体的な寸法例
「大」サイズと一口に言っても、その寸法には幅があります。
以下に、いくつかの代表的な「大」サイズの寸法例を挙げますが、購入される際は必ず各商品の寸法をご確認ください。
-
例1:縦 約18.0cm × 横 約12.0cm
最も標準的で、多くの御朱印帳で採用されている寸法です。
-
例2:縦 約18.2cm × 横 約12.1cm
JIS規格のB6サイズに近い寸法で、これもよく見られます。
-
例3:縦 約18.5cm × 横 約12.5cm
少し大きめの「大」サイズで、よりゆとりを持たせたい方におすすめです。
これらの寸法を参考に、ご自身のバッグのサイズや、どのような御朱印をいただくことが多いかを考慮して、最適な「大」サイズを選んでみてください。
携帯に便利な「小」サイズ:コンパクトさを追求した寸法
携帯に便利な「小」サイズ:コンパクトさを追求した寸法
「小」サイズは、その名の通り、携帯性に特化したコンパクトな御朱印帳です。
最近では、寺社仏閣巡りを気軽に楽しみたい方や、複数の御朱印帳を持ち歩きたい方を中心に人気が高まっています。
一般的な「大」サイズと比較して、ひと回り、またはふた回りほど小さいのが特徴です。
具体的な寸法としては、縦が15cm前後、横が10cm前後が目安となりますが、こちらも製造元によって多少のバリエーションがあります。
「小」サイズのメリット
-
驚異的な携帯性
「小」サイズの最大の魅力は、その携帯性の良さです。
ポケットにすっと入るサイズ感なので、大きなカバンを持たない方でも、手ぶら感覚で寺社仏閣を訪れることができます。
また、小さめのポーチやショルダーバッグにも楽々収まるため、身軽に移動したい時に非常に便利です。 -
複数持ちにも最適
「大」サイズだと、数冊持ち歩くとかなりのかさばりになりますが、「小」サイズであれば、2~3冊程度であれば比較的楽に持ち運ぶことができます。
例えば、旅行先で訪れる地域ごとに御朱印帳を分けたり、お気に入りのデザインの御朱印帳を気分で使い分けたりする際に重宝します。 -
かわいらしいデザインが多い
コンパクトなサイズ感から、かわいらしいイラストが描かれたものや、和柄が美しく配置されたものなど、デザイン性の高い御朱印帳も多く見られます。
御朱印帳そのものも、お洒落なファッションアイテムとして楽しみたい方にもおすすめです。
「小」サイズのデメリット
-
書置き御朱印の収納に工夫が必要
「小」サイズの場合、書置きの御朱印を貼る際に、そのまま貼るとはみ出てしまうことがあります。
そのため、書置き御朱印をいただく際には、一度たたんで貼るか、御朱印のサイズに合わせて台紙をカットするなどの工夫が必要になります。 -
直書きのスペースが限られる
直書きの御朱印をいただく場合、「大」サイズに比べると、墨書きや印を押すスペースが限られます。
特に、文字数が多い御朱印や、印がたくさん押される御朱印をいただく際には、少し窮屈に感じることがあるかもしれません。 -
書き手の方への配慮が必要な場合も
非常に稀なケースですが、御朱印をいただく際に、あまりにも小さすぎる御朱印帳や、書置き御朱印を貼るスペースの少なさに、書き手の方が戸惑う可能性もゼロではありません。
ただし、これはほとんどの場合問題なく、御朱印をいただけると考えて良いでしょう。
「小」サイズの具体的な寸法例
「小」サイズは、「大」サイズに比べてバリエーションが豊富です。
以下に、いくつかの代表的な「小」サイズの寸法例を挙げます。購入の際の参考にしてください。
-
例1:縦 約15.0cm × 横 約10.0cm
ポケットにも収まりやすい、非常にコンパクトなサイズです。
-
例2:縦 約15.5cm × 横 約10.5cm
少しだけゆとりを持たせた「小」サイズで、書置き御朱印も工夫次第で綺麗に貼れます。
-
例3:縦 約16.0cm × 横 約11.0cm
「小」サイズの中でも、やや大きめですが、携帯性も確保されています。
これらの寸法を参考に、ご自身のライフスタイルに合った「小」サイズを見つけてください。
「中」サイズや変形サイズ:多様化する御朱印帳の寸法
「中」サイズや変形サイズ:多様化する御朱印帳の寸法
御朱印帳のサイズは、「大」と「小」の二極化だけでなく、その中間や、さらにユニークな形状の「変形サイズ」も数多く存在します。
これらは、特定のニーズに応えるために、あるいはデザイン性を重視して作られています。
ここでは、あまり一般的ではないものの、知っておくと御朱印帳選びの幅が広がる「中」サイズや変形サイズについて解説します。
「中」サイズとは
「中」サイズとは、文字通り「大」サイズと「小」サイズの中間の大きさを持つ御朱印帳のことを指します。
明確な規格があるわけではありませんが、おおよそ縦が16cm~17cm、横が11cm~12cm程度のものが「中」サイズとして扱われることが多いです。
-
「中」サイズのメリット
「中」サイズは、「大」サイズの収納力と、「小」サイズの携帯性の良いところを兼ね備えた、いわば「いいとこ取り」のサイズと言えます。
「大」サイズでは少し大きいと感じるけれど、「小」サイズでは物足りない、という方にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。 -
「中」サイズのデメリット
「中」サイズは、その中間の性質ゆえに、どちらのサイズが最適か迷う方にとっては、かえって選択肢が増えてしまうという側面もあります。
また、頒布されている神社仏閣や、販売されている店舗によって寸法のばらつきが大きくなる傾向があるため、購入前に必ず寸法を確認することが重要です。
変形サイズの御朱印帳
最近では、御朱印帳の形状も多様化しており、伝統的な蛇腹式だけでなく、様々な「変形サイズ」が登場しています。
-
横長タイプ
横幅が広く、縦幅が小さい、横長の御朱印帳です。
流れるような文字が特徴の御朱印や、横に広がるデザインの御朱印をいただく際に、その魅力を最大限に引き出すことができます。 -
角丸タイプ
角が丸く加工されている御朱印帳です。
柔らかい印象を与え、手にした際の感触も優しいのが特徴です。デザインのアクセントとしても人気があります。 -
特殊な形状
その他にも、桜の形を模したものや、特定の寺社仏閣をイメージしたユニークな形状の御朱印帳なども存在します。
これらは、コレクターズアイテムとしての価値も高く、訪れた寺社仏閣の特別な思い出として収集するのも楽しいでしょう。
変形サイズの注意点
-
書置き御朱印の収納
変形サイズの御朱印帳の場合、書置き御朱印を貼る際に、サイズが合わないことがあります。
御朱印のサイズも考慮して、変形サイズの御朱印帳を選ぶようにしましょう。 -
収納場所
特殊な形状の御朱印帳は、一般的な御朱印帳ケースやポーチには収まらない場合があります。
専用のケースや、それに合う収納場所を事前に検討しておくことが大切です。 -
入手方法
変形サイズの御朱印帳は、一般的な「大」や「小」サイズに比べて、頒布されている場所が限られることがあります。
特定の寺社仏閣限定であったり、ネット通販のみであったりする場合もあるため、事前に情報収集をしておくことをおすすめします。
このように、御朱印帳のサイズは「大」と「小」だけにとどまりません。
ご自身の寺社仏閣巡りのスタイルや、どのような御朱印を集めたいかによって、最適なサイズは変わってきます。
これらの多様なサイズを知ることで、より自分らしい御朱印帳選びができるはずです。
こんなに違う!御朱印帳のサイズ別「使い勝手」徹底比較
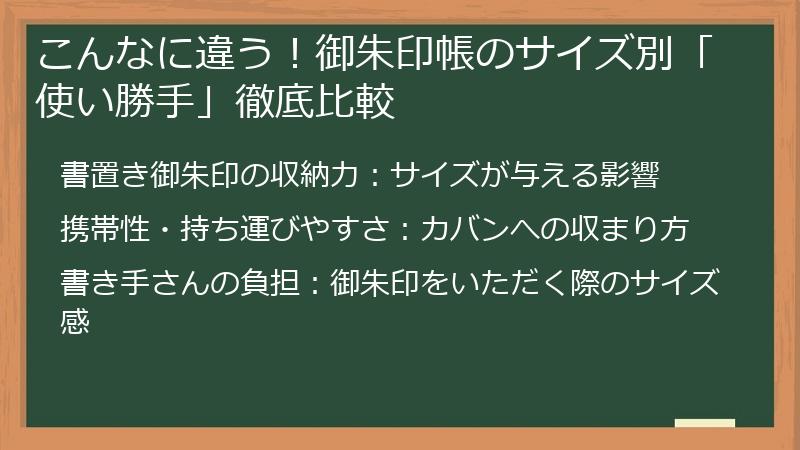
御朱印帳のサイズによって、実際に寺社仏閣で御朱印をいただく際の使い勝手は大きく変わります。
集める御朱印の種類や、持ち運びの頻度、さらには書き手の方への配慮まで、サイズが与える影響は様々です。
ここでは、サイズの違いが具体的にどのような使い勝手の差を生むのかを、詳しく比較していきます。
ご自身の寺社仏閣巡りのスタイルに合ったサイズ選びの参考にしてください。
書置き御朱印の収納力:サイズが与える影響
書置き御朱印の収納力:サイズが与える影響
近年、寺社仏閣によっては、参拝者が持参した御朱印帳に直接墨書きや印を押す「直書き」だけでなく、あらかじめ印刷された「書置き」の御朱印を頒布しているところも増えています。
この書置き御朱印を綺麗に収納できるかどうかは、御朱印帳のサイズ選びにおいて非常に重要なポイントとなります。
「大」サイズと書置き御朱印
-
広々としたスペースで綺麗に貼れる
「大」サイズの御朱印帳であれば、標準的な書置き御朱印は、ほとんどの場合、はみ出したり折ったりすることなく、そのまま貼ることができます。
余白が十分に確保されているため、御朱印の文字やデザインが際立ち、見た目も美しく仕上がります。
貼る際にも、糊や両面テープを均一に塗りやすく、剥がれにくいというメリットもあります。 -
複数枚の収納にも対応
「大」サイズであれば、数枚の書置き御朱印を、見開きページに貼ることも可能です。
例えば、同じ寺社仏閣の異なる授与所や、特別御朱印などを複数いただく場合でも、スマートに収納できます。
「小」サイズと書置き御朱印
-
サイズ調整が必要な場合が多い
「小」サイズの御朱印帳に書置き御朱印を貼る場合、多くの場合、御朱印のサイズに合わせて、あらかじめたたんだり、余白部分をカットしたりするなどの工夫が必要になります。
特に、書置き御朱印が大きめの場合、そのまま貼るとページからはみ出てしまうため、注意が必要です。 -
複数枚の収納は工夫次第
「小」サイズで複数の書置き御朱印を収納したい場合は、1ページに1枚ずつ、かつ御朱印のサイズに合わせて貼る、といった丁寧な作業が求められます。
手間はかかりますが、工夫次第で綺麗に収納することも可能です。 -
「貼ってはがせる」糊の使用も検討
書置き御朱印を貼る際に、後から剥がせるタイプの糊や両面テープを使用すると、万が一貼り間違えても安心です。
特に「小」サイズで、配置に迷う場合には有効な手段となります。
「中」サイズや変形サイズと書置き御朱印
-
「中」サイズ
「中」サイズであれば、「大」サイズほどではないにしても、「小」サイズよりはゆとりを持って書置き御朱印を貼れる場合が多いです。
しかし、やはり御朱印のサイズによっては、たたむなどの工夫が必要になることもあります。 -
変形サイズ
変形サイズの御朱印帳の場合、書置き御朱印との相性が非常に重要になります。
御朱印帳の形状によっては、書置き御朱印をそのまま貼ることが難しかったり、貼っても見た目のバランスが悪くなったりする可能性があります。
購入前に、ご自身が集めたい書置き御朱印のサイズと、御朱印帳の形状をよく確認することが大切です。
書置き御朱印を多くいただく予定がある方は、御朱印帳のサイズを「大」にするか、「小」サイズの場合は、書置き御朱印のサイズを事前に確認し、必要であれば加工してから貼るなどの準備をしておくと良いでしょう。
携帯性・持ち運びやすさ:カバンへの収まり方
携帯性・持ち運びやすさ:カバンへの収まり方
寺社仏閣巡りを楽しむ上で、御朱印帳を常に携帯することになるでしょう。
その際、御朱印帳のサイズが、カバンへの収まり方や、持ち運びの快適さに大きく影響します。
ここでは、サイズごとの携帯性やカバンへの収まりやすさについて、具体的に比較していきます。
「大」サイズの携帯性
-
一般的なカバンには問題なく収納可能
「大」サイズの御朱印帳は、縦約18cm、横約12cm程度が一般的です。
これは、一般的なビジネスバッグ、トートバッグ、リュックサックなど、多くのカバンに問題なく収納できるサイズです。
そのため、普段使いのカバンであれば、特別な配慮なく持ち運ぶことができます。 -
大きめショルダーバッグやマチのあるカバンが便利
「大」サイズをスムーズに出し入れしたい場合は、A4ファイルが余裕で入るサイズのカバンや、マチがしっかりあるカバンを選ぶと良いでしょう。
カバンの形状によっては、御朱印帳が少し窮屈に感じられる場合もあります。 -
複数持ちはかさばる可能性
「大」サイズの御朱印帳を複数冊持ち歩く場合、カバンの中がかさばりやすくなります。
旅行などで多くの御朱印をいただく予定がある場合は、カバンの中身との兼ね合いを考慮する必要があります。
「小」サイズの携帯性
-
ポケットにも収まるコンパクトさ
「小」サイズの御朱印帳は、縦15cm前後、横10cm前後と非常にコンパクトです。
そのため、ジャケットの胸ポケットや、パンツの大きめのポケットにもすっぽりと収まることがあります。
カバンを持たずに、手ぶらで身軽に寺社仏閣を巡りたい方には最適です。 -
どんなカバンにも楽々収納
小さめのショルダーバッグ、サコッシュ、ウエストポーチなど、どのようなカバンに入れても、ほとんど場所を取りません。
カバンの中での迷子になる心配も少なく、すぐに取り出せるという利点もあります。 -
複数持ちでもかさばりにくい
「小」サイズの御朱印帳を2~3冊持ち歩いても、かさばりにくいのが特徴です。
気分によって使い分けたり、地域ごとに分けたりする際にも、手軽に持ち運べます。
「中」サイズや変形サイズの携帯性
-
「中」サイズ
「中」サイズは、「大」と「小」の中間的な携帯性となります。
多くのカバンには問題なく収まりますが、「小」サイズほどの軽快さはありません。
しかし、「大」サイズよりはスマートに持ち運べます。 -
変形サイズ
変形サイズの御朱印帳は、その形状によって携帯性が大きく異なります。
横長タイプは、カバンにすっきりと収まることが多いですが、厚みが出やすいものもあります。
特殊な形状のものは、専用のケースが必要になったり、カバンに入れる際に工夫が必要になったりすることもあります。
御朱印帳のサイズ選びにおいては、ご自身の普段お使いのカバンや、寺社仏閣巡りのスタイルを考慮することが大切です。
「大」サイズなら安心感があり、「小」サイズなら身軽に動けます。
どちらのサイズがご自身のライフスタイルに合っているか、想像しながら選んでみてください。
書き手さんの負担:御朱印をいただく際のサイズ感
書き手さんの負担:御朱印をいただく際のサイズ感
御朱印帳のサイズは、参拝者である私たちだけでなく、御朱印を書いてくださる神職や僧侶の方々にとっても、使いやすさに関わる重要な要素です。
一般的に、御朱印帳のサイズが大きすぎたり、厚すぎたりすると、書き手の方の負担になる可能性があります。
ここでは、御朱印をいただく際のサイズ感について、詳しく解説します。
「大」サイズと書き手さんの負担
-
標準的なサイズで、一般的に問題なし
「大」サイズ(縦約18cm、横約12cm)は、多くの神社仏閣で標準的に扱われているサイズです。
そのため、書き手の方々もこのサイズに慣れており、通常は特別な負担なく御朱印を記すことができます。 -
厚みが増すと少し負担になることも
御朱印をたくさん集めて厚みが増した「大」サイズの御朱印帳は、書き手の方が手に持って、墨書きや印を押す際に、少し重みを感じることがあるかもしれません。
特に、台が設置されていない場所で、手で支えながら書く場合などです。 -
頻繁なサイズ変更への対応
「大」サイズは一般的ですが、それでも工房や神社仏閣によって微妙に寸法が異なる場合があります。
書き手の方にとっては、常に一定のサイズ感で書いているわけではないため、多少の寸法の違いは想定内ですが、極端に大きいサイズの場合は、少し戸惑う可能性も考えられます。
「小」サイズと書き手さんの負担
-
コンパクトで書きやすい
「小」サイズ(縦15cm前後、横10cm前後)は、そのコンパクトさゆえに、書き手の方が片手で持ちやすく、安定した状態で御朱印を記しやすいというメリットがあります。
特に、スペースが限られている場所での授与では、扱いやすいサイズと言えるでしょう。 -
厚みが出ると安定しない可能性も
「小」サイズで御朱印をたくさん集め、厚みが出てくると、逆に安定性が悪くなることがあります。
書き手の方が御朱印帳を支える際に、ぐらつきを感じる可能性も考えられます。
「中」サイズや変形サイズの書き手さんへの配慮
-
「中」サイズ
「中」サイズは、「大」サイズよりもやや軽いため、書き手の方の負担は軽減される傾向があります。
標準的な「大」サイズと同様に、ほとんどの場合問題なく御朱印をいただけます。 -
変形サイズ
変形サイズの御朱印帳の場合、書き手の方も慣れていない形状である可能性があります。
特に、特殊な形状のものは、御朱印を記すスペースが限られていたり、安定して置く場所がなかったりする場合、書き手の方への配慮が必要となることも考えられます。
もし、特殊な形状の御朱印帳をお持ちの場合は、御朱印をいただく際に、書き手の方に一言お声がけすると、よりスムーズに授与していただけるかもしれません。
一般的に、神社仏閣で御朱印をいただく際は、書き手の方の負担を最小限にするために、御朱印帳は両手で丁重にお渡しし、受け取る際も両手で受け取るように心がけましょう。
サイズ選びも大切ですが、それ以上に、感謝の気持ちを持って御朱印をいただくことが最も重要です。
あなたの寺社巡りに最適な御朱印帳サイズの見つけ方
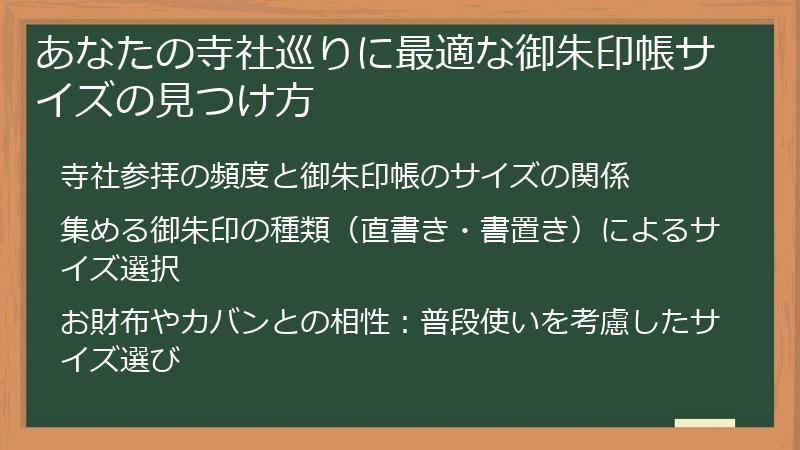
数ある御朱印帳のサイズの中から、ご自身の寺社仏閣巡りに最適なものを見つけるためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。
単に見た目の好みだけでなく、参拝の頻度や集めたい御朱印の種類、普段お使いのカバンとの相性なども、サイズ選びの重要な要素となります。
ここでは、あなたにとってベストな御朱印帳サイズを見つけるための、具体的な方法を解説します。
寺社参拝の頻度と御朱印帳のサイズの関係
寺社参拝の頻度と御朱印帳のサイズの関係
御朱印帳のサイズ選びにおいて、寺社仏閣へ参拝する頻度は、非常に重要な要素となります。
頻繁に参拝するのか、それともたまに気まぐれに訪れるのかによって、適したサイズが変わってきます。
頻繁に参拝する方へのおすすめサイズ
-
「大」サイズがおすすめ
毎週のように、あるいは月に何度も寺社仏閣に足を運ぶ方は、「大」サイズの御朱印帳がおすすめです。
理由は、以下の通りです。-
多くの御朱印を収納できる
頻繁に参拝すれば、それだけ多くの御朱印をいただくことになります。
「大」サイズはページ数が多く、書置き御朱印も綺麗に貼れるため、御朱印帳を頻繁に交換する必要がなく、長く愛用できます。 -
携帯性も問題なし
普段からカバンを持ち歩く習慣があれば、「大」サイズでも携帯に不便を感じることは少ないでしょう。
頻繁な移動でも、安定して持ち運べます。
-
たまに参拝する方へのおすすめサイズ
-
「小」サイズも選択肢に
年に数回程度、あるいは特定の時期に集中して参拝するという方であれば、「小」サイズの御朱印帳も良い選択肢となります。
理由は以下の通りです。-
保管場所を取らない
御朱印をいただく機会が少ない場合、「大」サイズではページがなかなか埋まらず、保管場所を取ってしまうことがあります。
「小」サイズであれば、コンパクトなので、本棚などにすっきりと収納できます。 -
気分転換に新しいサイズを試しやすい
御朱印帳を使い切る前に、新しいデザインの御朱印帳が欲しくなることもあります。「小」サイズであれば、比較的手軽に複数冊持ち歩くこともできるため、気分転換にもなります。
-
「中」サイズもバランスが良い
「たまに参拝する」という方でも、「大」サイズほどの収納力は必要ないけれど、「小」サイズでは物足りない、という場合は「中」サイズがバランスが良いでしょう。
-
参拝頻度と御朱印帳の寿命
御朱印帳は、一般的に1冊で約30~60ページ程度あります。
仮に、毎月2~3ヶ所の寺社仏閣を参拝するとすると、1冊を使い切るのに1~2年かかる計算になります。
参拝頻度が高い方は、それだけ早く御朱印帳がいっぱいになるため、「大」サイズでページ数の多いものを選ぶのがおすすめです。
逆に、参拝頻度が低い方は、「小」サイズや「中」サイズでも十分に対応できるでしょう。
ご自身の寺社仏閣巡りのスタイルを考慮し、無理なく、そして楽しく御朱印集めができるサイズを選ぶことが、長く御朱印帳を愛用するための秘訣です。
集める御朱印の種類(直書き・書置き)によるサイズ選択
集める御朱印の種類(直書き・書置き)によるサイズ選択
御朱印帳のサイズ選びは、どのような種類の御朱印を集めたいかによっても、最適な選択肢が変わってきます。
特に、「直書き」か「書置き」か、あるいは両方か、という点は、御朱印帳の使い勝手に大きく影響します。
直書き御朱印をメインに集める場合
-
「大」サイズが最もおすすめ
直書きの御朱印は、書置き御朱印に比べて、文字や印の配置に個性が出ることも多く、また、書き手の方の丁寧な筆遣いをそのまま受け取ることができます。
「大」サイズであれば、直書きでいただく御朱印は、どのようなものでもゆったりとしたスペースに収めることができます。
特に、文字数が多い御朱印や、複数の印が押される御朱印をいただく場合でも、余裕を持って記してもらえるため、書き手の方の負担も軽減されます。 -
「中」サイズでも十分対応可能
「中」サイズでも、ほとんどの直書き御朱印は問題なくいただくことができます。
ただし、非常に凝ったデザインの御朱印や、縦横に広がるような御朱印をいただく際は、「大」サイズの方がより安心感があります。
書置き御朱印をメインに集める場合
-
「大」サイズが圧倒的に便利
前述の通り、「大」サイズは書置き御朱印をそのまま貼るのに最も適したサイズです。
御朱印のサイズに合わせて、たたんだり、カットしたりする手間なく、綺麗に収納できます。
たくさんの書置き御朱印をコレクションしたい方には、「大」サイズが最適です。 -
「小」サイズでは工夫が必要
「小」サイズで書置き御朱印を集めたい場合は、御朱印のサイズを事前に確認し、貼る際の配置を工夫する必要があります。
御朱印のサイズによっては、複数枚を1ページに貼ったり、余白をカットしたりするなどの手間がかかります。
それでも、デザイン性の高い「小」サイズの御朱印帳を選んで、見栄え良く収納したいというこだわりがある方には、挑戦する価値はあります。
直書きと書置き、両方集めたい場合
-
「大」サイズが最も汎用性が高い
直書きも書置きも、どちらもバランス良く集めたいという欲張りな方には、「大」サイズが最も汎用性が高いと言えます。
書置き御朱印も綺麗に収納でき、直書きでも十分なスペースがあります。
迷った際は、まず「大」サイズを検討するのが良いでしょう。 -
「中」サイズも有力候補
「中」サイズも、直書きと書置きのどちらにも対応できる、バランスの取れたサイズです。
「大」サイズでは少し大きいと感じる方にとって、「中」サイズは有力な選択肢となります。
ただし、書置き御朱印のサイズによっては、工夫が必要になる場合もあります。
ご自身が「どんな御朱印を集めたいか」という点を明確にすることで、御朱印帳のサイズ選びもより具体的になります。
集めたい御朱印のスタイルに合わせて、最適なサイズを選んで、素敵な御朱印巡りを楽しんでください。
お財布やカバンとの相性:普段使いを考慮したサイズ選び
お財布やカバンとの相性:普段使いを考慮したサイズ選び
御朱印帳は、寺社仏閣に参拝する時だけでなく、普段から持ち歩くことも多いアイテムです。
そのため、ご自身が普段お使いのお財布やカバンとの相性を考慮してサイズを選ぶことも、満足度を高める上で重要です。
ここでは、日頃お使いのアイテムとの関係性から、最適な御朱印帳サイズを見つける方法を解説します。
普段使いのカバンとの相性
-
大きめのバッグ(A4サイズ以上)をご利用の方
トートバッグやリュックサックなど、A4サイズの書類やファイルが余裕で入るような大きめのカバンをお使いの方であれば、「大」サイズの御朱印帳でも、問題なく収納できます。
バッグの中で、他の荷物とぶつかることなく、スムーズに出し入れできるでしょう。
「大」サイズはページ数も多いため、頻繁に参拝する方にもおすすめです。 -
小さめ・コンパクトなバッグをご利用の方
ショルダーバッグ、サコッシュ、ボディバッグなど、コンパクトなカバンを普段使いされている方は、「小」サイズの御朱印帳がおすすめです。
「小」サイズであれば、カバンの中で場所を取らず、他の荷物とも干渉しにくいため、スマートに持ち運べます。
また、ポケットに収まるサイズ感であれば、カバンから取り出して御朱印をいただく際にも、スムーズに対応できます。 -
「中」サイズは汎用性が高い
「中」サイズは、「大」サイズと「小」サイズの中間の大きさなので、多くのカバンに比較的無理なく収まります。
「大」サイズでは少し大きいが、「小」サイズでは物足りない、という方にとって、「中」サイズはカバンとの相性も良い選択肢となるでしょう。
お財布やカードケースとの比較
-
お財布と御朱印帳のサイズ比較
お財布と御朱印帳を同じカバンに入れる場合、お財布のサイズ感も考慮に入れると良いでしょう。
例えば、長財布をお使いの場合は、「大」サイズでも比較的余裕がありますが、二つ折り財布や、カードケースをメインでお使いの方は、「小」サイズや「中」サイズの方が、カバンの中での収まりが良いかもしれません。 -
御朱印帳を「お財布」のように持ち歩く場合
普段あまりカバンを持たず、お財布だけを持って出かけることが多い方は、「小」サイズ、あるいはさらにコンパクトな「ミニ御朱印帳」などが最適です。
これなら、お財布と一緒にポケットや小さなポーチに収納できます。
御朱印帳を「見せる」アイテムとして
御朱印帳は、単なる記録帳としてだけでなく、そのデザイン性から、ファッションアイテムの一部として捉える方もいらっしゃいます。
お気に入りの御朱印帳を、カバンから取り出した際にもおしゃれに見せたい、という方は、ご自身のファッションスタイルに合ったサイズやデザインを選ぶのも良いでしょう。
「小」サイズには、かわいらしいデザインのものも多く、アクセサリー感覚で持ち歩くこともできます。
普段お使いのアイテムとの相性を考えることで、御朱印帳はより身近で、愛着の湧く存在になります。
あなたのライフスタイルに合ったサイズを見つけて、毎日の寺社仏閣巡りをさらに豊かにしましょう。
サイズだけじゃない!御朱印帳選びで後悔しないための「素材」と「仕様」
御朱印帳のサイズが決まったら、次はどのような「素材」や「仕様」のものを選ぶか、という点も重要になってきます。
紙質、綴じ方、表紙のデザインや素材など、細部までこだわって選ぶことで、より満足度の高い御朱印帳に出会うことができます。
ここでは、サイズ以外の御朱印帳選びのポイントについて、詳しく解説していきます。
紙質の種類:和紙、奉書紙、その他素材の特徴
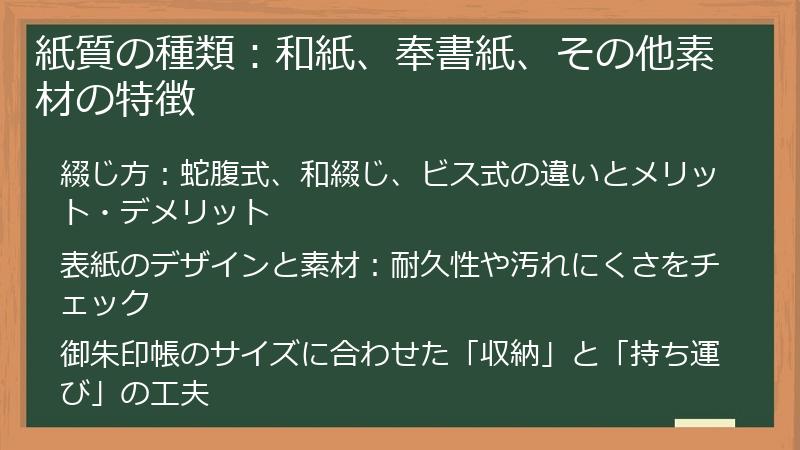
紙質の種類:和紙、奉書紙、その他素材の特徴
御朱印帳に使われる紙の質は、墨の裏移りや滲みに影響するだけでなく、御朱印帳全体の風合いや耐久性にも関わってきます。
ここでは、御朱印帳でよく使用される紙の種類と、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
和紙・奉書紙
-
御朱印帳の定番
和紙、特に「奉書紙(ほうしょし)」は、御朱印帳の紙として最もポピュラーな素材です。
奉書紙は、江戸時代から公文書などに使われてきた、しっかりとした厚みとコシのある紙で、墨が滲みにくく、裏移りしにくいのが特徴です。 -
墨の乗りが良い
奉書紙は、墨の乗りが非常に良く、鮮やかな発色で御朱印を記すことができます。
また、独特の風合いがあり、手に取った時の温かみも感じられます。
多くの神社仏閣で頒布されている御朱印帳は、この奉書紙が使用されていることが多いです。 -
耐久性も比較的高い
上質な奉書紙は、経年劣化にも比較的強く、大切に扱えば長く保存することができます。
湿気や直射日光を避けて保管すれば、御朱印の美しさを長期間保つことができます。
機械漉き和紙
-
均一な品質と安定性
機械漉き和紙は、手漉きの和紙に比べて均一な厚みと品質を保ちやすいのが特徴です。
そのため、裏移りしにくい加工が施されているものも多く、安定した書き心地を提供します。 -
様々なバリエーション
機械漉き和紙の中にも、厚手のもの、薄手のもの、表面の加工が異なるものなど、様々な種類があります。
最近では、インクジェット印刷に適した和紙や、撥水加工が施された和紙なども登場しています。
その他の紙素材
-
洋紙(上質紙など)
一部の御朱印帳では、洋紙が使用されている場合もあります。
上質紙などは、インクジェットプリンターで印刷された書置き御朱印を貼るのに適している場合もありますが、墨の滲みやすさや裏移りには注意が必要です。 -
特殊加工紙
最近では、撥水加工や抗菌加工が施された特殊な紙を使用した御朱印帳も登場しています。
これらの素材は、耐久性や衛生面でメリットがありますが、価格が高くなる傾向があります。
紙質選びのポイント
-
墨の裏移り・滲み
御朱印帳を選ぶ上で最も重要なのは、墨の裏移りや滲みが少ないことです。
奉書紙や、裏移りしにくい加工が施された和紙を選ぶのがおすすめです。 -
厚みとコシ
ある程度の厚みとコシがある紙は、御朱印を貼った際の反り返りを防ぎ、ページ全体を綺麗に保つことができます。
-
手触りや風合い
御朱印帳は、手に取る機会も多いアイテムです。
ご自身の好みの手触りや風合いを持つ紙を選ぶことで、より愛着を持って使うことができます。
御朱印帳の紙質は、直接御朱印の仕上がりに影響します。
可能であれば、実物を手に取って、紙の質感や厚みを確認することをおすすめします。
綴じ方:蛇腹式、和綴じ、ビス式の違いとメリット・デメリット
綴じ方:蛇腹式、和綴じ、ビス式の違いとメリット・デメリット
御朱印帳の綴じ方にも、いくつかの種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
サイズ選びと同様に、綴じ方によっても使い勝手や耐久性が変わってくるため、ご自身の好みに合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、代表的な3つの綴じ方について詳しく解説します。
蛇腹式
-
御朱印帳の伝統的なスタイル
蛇腹式は、御朱印帳の最も伝統的で一般的な綴じ方です。
1枚の紙を折りたたんで両面を使用する形式で、開いた時に見開きで御朱印を並べることができます。 -
メリット
-
見開きで一覧しやすい
御朱印を一覧する際に、見開きで綺麗に並べられるため、集めた御朱印を視覚的に楽しむことができます。
-
ページ数が多く取れる
1枚の紙を折りたたんで使用するため、限られたスペースで多くのページ数(御朱印をいただける面)を確保しやすいのが特徴です。
-
開いた時の安定感
しっかりと糊付けされているものが多く、開いた時にページがばらけることが少なく、安定感があります。
-
-
デメリット
-
ページをめくるのに一手間かかる
一枚の紙を折りたたんでいるため、次のページに進む際に、通常の冊子のようにページをめくるのではなく、折りたたまれた紙の端をめくる、という動作になります。
慣れないうちは、少し戸惑うかもしれません。 -
水濡れに弱い場合も
紙を折りたたんでいる構造上、湿気や水濡れによって紙が劣化しやすい場合があります。
特に、墨書きが乾く前に水滴がつくと、滲みの原因となることもあります。
-
和綴じ
-
日本の伝統的な製本方法
和綴じは、紙を重ねて糸で綴じる、日本の伝統的な製本方法です。
御朱印帳としても、趣のある雰囲気を醸し出します。 -
メリット
-
美しい見た目
糸で綴じられた、手仕事ならではの温かみのある見た目が魅力です。
表紙のデザインと相まって、より一層趣深い印象を与えます。 -
開いた時の見やすさ
蛇腹式とは異なり、一般的な冊子のようにページをめくるため、直感的に使いやすいと感じる方も多いでしょう。
-
-
デメリット
-
ページ数が限られる
蛇腹式に比べて、同じ厚みでもページ数を多く確保するのが難しい傾向があります。
そのため、御朱印をたくさんいただく方には、すぐに使い切ってしまう可能性もあります。 -
糸がほつれる可能性
長期間使用したり、頻繁に開閉したりすることで、綴じている糸がほつれてしまう可能性もゼロではありません。
-
ビス式
-
リフィル交換が可能
ビス式は、金属のビスで綴じられた御朱印帳です。
最大の特徴は、付属のリフィル(紙)を交換できる点です。
御朱印帳が一杯になったら、新しいリフィルと交換して、表紙はそのまま使い続けることができます。 -
メリット
-
表紙をお気に入りのまま使い続けられる
お気に入りのデザインの表紙を、そのまま長く愛用したい方には最適です。
環境にも優しく、経済的でもあります。 -
リフィルの追加・交換が容易
御朱印帳を使い切った後も、リフィルだけを購入すれば、すぐに次の御朱印集めを再開できます。
-
リフィルの紙質を選べる場合も
一部のビス式御朱印帳では、リフィルの紙質を選べるものもあります。
ご自身の好みに合った紙質のものを選んで使用することができます。
-
-
デメリット
-
ビス部分の厚み
ビスで綴じているため、中央部分にビスの厚みがあり、御朱印を貼る際に若干の段差が生じることがあります。
これが気になる方もいるかもしれません。 -
ビスの緩み
長期間使用したり、頻繁にリフィルを交換したりすることで、ビスが緩んでしまう可能性も考えられます。
-
どの綴じ方を選ぶかは、ご自身の御朱印集めのスタイルや、重視する点によって異なります。
伝統的な雰囲気を楽しみたいなら蛇腹式や和綴じ、長く愛用したいならビス式、といったように、ご自身の好みに合わせて選んでみてください。
表紙のデザインと素材:耐久性や汚れにくさをチェック
表紙のデザインと素材:耐久性や汚れにくさをチェック
御朱印帳の表紙は、その御朱印帳の「顔」とも言える部分です。
デザインはもちろんのこと、使用されている素材によって、耐久性や汚れにくさといった実用性も大きく変わってきます。
ここでは、表紙のデザインと素材に注目し、後悔しない選び方について解説します。
表紙のデザイン
-
伝統的な和柄
神社仏閣の御朱印帳では、伝統的な和柄(麻の葉、青海波、市松模様など)が施されたデザインが多く見られます。
これらの柄は、日本古来の美意識が感じられ、落ち着いた雰囲気を醸し出します。 -
寺社仏閣のシンボル
特定の寺社仏閣で頒布されている御朱印帳には、その寺社仏閣のシンボル(仏像、鳥居、風景など)がデザインされているものもあります。
参拝した記念として、これらの御朱印帳を選ぶのも良いでしょう。 -
モダン・オリジナルデザイン
最近では、クリエイターがデザインしたモダンなものや、オリジナルのイラスト、写真などが使用された、個性的でスタイリッシュな御朱印帳も増えています。
ご自身の好みに合わせて、お気に入りのデザインを選ぶことができます。
表紙の素材
-
布製
布製の表紙は、温かみのある風合いが魅力です。
特に、西陣織などの高級な織物を使用した御朱印帳は、重厚感があり、高級感も漂います。
ただし、汚れがつきやすく、水濡れに弱い場合もあります。 -
紙製(特殊紙、ラミネート加工など)
丈夫な和紙や、耐久性のある特殊紙が使用されている場合も多いです。
表面にラミネート加工や、撥水加工が施されていると、汚れや水濡れに強くなり、耐久性が向上します。 -
ビニール・合成皮革
ビニールや合成皮革を使用した表紙は、耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすいため、実用性を重視する方におすすめです。
ただし、素材によっては、プラスチックのような光沢感があり、好みが分かれる場合もあります。
耐久性・汚れにくさを左右するポイント
-
表紙の厚み
表紙が厚手であるほど、御朱印帳全体がしっかりとして、耐久性が増します。
また、カバンの中で他のものに圧迫されても、中の紙が傷つきにくいというメリットもあります。 -
表面加工
ラミネート加工や撥水加工が施されている表紙は、水滴を弾いたり、汚れが拭き取りやすかったりするため、屋外での活動が多い方や、小さなお子様連れで参拝する方にも安心です。
-
綴じ部分の強度
表紙だけでなく、綴じ部分の強度も重要です。
蛇腹式や和綴じの場合、糊や糸がしっかりと処理されているかを確認しましょう。
デザインと実用性のバランス
御朱印帳を選ぶ際には、デザインの好みだけでなく、素材や耐久性といった実用性も考慮することが大切です。
お気に入りのデザインでありながら、長く愛用できる素材のものを選ぶことで、より満足度の高い御朱印帳となるでしょう。
可能であれば、実物を手に取って、表紙の素材感や質感、そしてデザインを確認することをおすすめします。
そうすることで、ご自身の好みにぴったりの、一生ものの御朱印帳に出会えるはずです。
御朱印帳のサイズに合わせた「収納」と「持ち運び」の工夫
御朱印帳のサイズに合わせた「収納」と「持ち運び」の工夫
御朱印帳のサイズが決まったら、次に気になるのは、どのように収納し、どのように持ち運ぶか、という点でしょう。
適切な収納や持ち運びの工夫は、御朱印帳を大切に長く使うために非常に重要です。
ここでは、御朱印帳のサイズに合わせた収納方法や、持ち運びを快適にするためのアイテムや工夫について解説します。
御朱印帳ケース・ポーチ:サイズ別のおすすめアイテム
-
「大」サイズ向け
「大」サイズの御朱印帳は、その大きさと厚みを考慮して、ある程度ゆとりのあるケースやポーチを選ぶのがおすすめです。
A4ファイルが入るような、大きめのポーチや、御朱印帳専用のケースなどが市販されています。-
御朱印帳ケース
御朱印帳専用のケースは、御朱印帳がぴったり収まるように作られており、カバンの中で他の荷物とぶつかるのを防ぎ、折れ曲がりや傷から守ってくれます。
内側にポケットが付いているものもあり、書置き御朱印や、お守りなどを一緒に入れることもできます。 -
大きめのポーチ
デザイン性の高いポーチや、撥水加工が施されたポーチなども、御朱印帳ケースの代わりとして活用できます。
お気に入りのデザインのものを選べば、カバンから取り出す際にも気分が上がります。
-
-
「小」サイズ向け
「小」サイズの御朱印帳は、コンパクトなため、様々なアイテムに収納できます。
-
スリムなポーチ
「小」サイズにちょうど良い、スリムなポーチであれば、カバンの中のちょっとした隙間にも収納できます。
バッグインバッグとして使用するのも便利です。 -
ポケット
ジャケットの胸ポケットや、パンツの大きめのポケットにも収まるサイズのものもあります。
ただし、落下には注意が必要です。 -
お財布やカードケースと一緒に入れる
お財布やカードケースを収納するスペースに、一緒に収まる場合もあります。
-
-
「中」サイズ・変形サイズ向け
「中」サイズは、「大」サイズ向けのケースやポーチに収まることが多いですが、よりぴったりとしたサイズ感のものを選ぶと、カバンの中での安定感が増します。
変形サイズの御朱印帳の場合は、御朱印帳の形状に合う専用のケースがあるか、あるいは汎用的な大きめのポーチなどを検討する必要があります。
バッグの中での整理術:御朱印帳を傷つけない工夫
-
御朱印帳専用の収納場所を決める
カバンの中に御朱印帳を入れる場所をあらかじめ決めておくと、他の荷物との接触を減らすことができます。
例えば、カバンの中にある内ポケットや、ポーチの中に入れるなどです。 -
御朱印帳を保護する
御朱印帳をそのままカバンに入れるのではなく、専用のケースやポーチ、あるいは厚手のビニール袋などに入れて保護することをおすすめします。
これにより、カバンの中の他のもの(鍵やリップクリームなど)で傷つくのを防ぐことができます。 -
書置き御朱印の保管
いただいたばかりの書置き御朱印は、まだ墨が乾ききっていない場合もあります。
すぐに御朱印帳に貼るのではなく、少し時間を置いてから貼るか、通気性の良い袋などに入れて持ち運ぶと、滲みや汚れを防ぐことができます。
自宅での保管方法:湿気や日焼けから守るための注意点
-
直射日光を避ける
御朱印帳は、直射日光に長時間当たると、紙が劣化したり、印刷された御朱印の色褪せを早めたりする可能性があります。
本棚や戸棚など、直射日光の当たらない場所に保管しましょう。 -
湿気を避ける
湿気の多い場所での保管は、カビや紙の劣化の原因となります。
風通しの良い、乾燥した場所に保管するように心がけましょう。 -
重ねすぎに注意
御朱印帳を重ねすぎると、下の御朱印帳に圧力がかかり、紙が傷んだり、御朱印が擦れたりする可能性があります。
平積みにするよりも、立てて保管するか、数冊ずつ重ねる程度に留めましょう。 -
防虫剤の検討
長期間保管する場合は、湿気対策と合わせて、防虫剤などを活用するのも一つの方法です。
ただし、御朱印帳に直接触れないように注意しましょう。
御朱印帳のサイズに合わせた収納や持ち運びの工夫は、御朱印帳を美しく、そして長く保つために不可欠です。
ご自身のライフスタイルに合った方法を見つけて、大切に御朱印帳を扱っていきましょう。
意外と知らない?御朱印帳の「サイズ」にまつわる豆知識
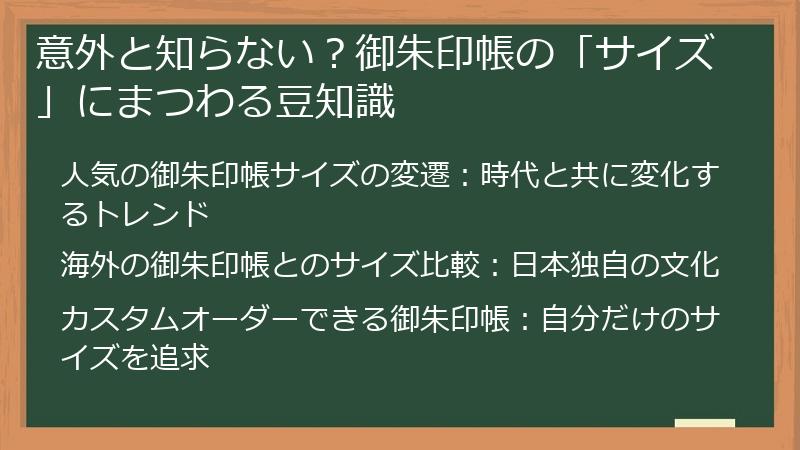
意外と知らない?御朱印帳の「サイズ」にまつわる豆知識
御朱印帳のサイズについて、ここまで種類や選び方を見てきましたが、実はサイズにまつわる興味深い豆知識がいくつか存在します。
時代と共に変化する御朱印帳のトレンドや、日本独自の文化、そして自分だけのサイズを追求する楽しみなど、御朱印帳のサイズをより深く理解するための情報をお伝えします。
人気の御朱印帳サイズの変遷:時代と共に変化するトレンド
人気の御朱印帳サイズの変遷:時代と共に変化するトレンド
御朱印帳のサイズというものは、常に一定であったわけではありません。
寺社仏閣巡りの文化や、参拝者のニーズの変化と共に、人気のサイズも移り変わってきました。
ここでは、御朱印帳のサイズの変遷と、それによって生まれたトレンドについて見ていきましょう。
かつての御朱印帳
-
「大」サイズが主流の時代
かつて、御朱印集めが、現在ほど一般的でなかった時代は、御朱印帳といえば「大」サイズが主流でした。
これは、御朱印をいただく機会が比較的少なく、また、書置きの御朱印も少なかったため、一枚の紙に丁寧に墨書きと印をいただく、というスタイルが中心だったからです。 -
携帯性よりも収納力を重視
当時の御朱印帳は、現在ほど携帯性やデザイン性が重視されるというよりは、御朱印をきちんと保管するための「記録帳」としての側面が強かったと言えます。
そのため、ある程度の大きさがあり、しっかりとした紙質のものが多い傾向にありました。
現代の御朱印帳
-
「小」サイズ、コンパクトサイズの台頭
近年、寺社仏閣巡りや御朱印集めがブームとなるにつれて、参拝者の層も多様化しました。
特に、若い世代や女性の間で、携帯性の良さやデザイン性の高さが重視されるようになり、「小」サイズや、さらにコンパクトなミニ御朱印帳の人気が高まっています。 -
書置き御朱印の普及
現代では、書置きの御朱印を頒布する寺社仏閣が増加したことも、御朱印帳のサイズトレンドに影響を与えています。
書置き御朱印は、そのまますぐに御朱印帳に貼れるため、サイズが合わないと不便を感じることがあります。
そのため、書置き御朱印を綺麗に収納しやすい「大」サイズや、工夫次第で対応できる「小」サイズも、それぞれのニーズに合わせて選ばれるようになりました。 -
多様化するサイズとデザイン
現在では、「大」「小」だけでなく、「中」サイズや、横長、角丸といった様々な変形サイズも登場しています。
また、伝統的な和柄だけでなく、モダンなデザインや、キャラクターものなど、デザインも非常に多様化しており、参拝者は自分の好みやライフスタイルに合わせて、自由に御朱印帳を選ぶことができるようになりました。
御朱印帳サイズ選びのトレンド
御朱印帳のサイズ選びは、単に「大きいか小さいか」だけでなく、
-
参拝頻度
-
集めたい御朱印の種類(直書き・書置き)
-
普段使いのカバンとの相性
といった、ご自身のライフスタイルや好みを反映するようになっています。
過去の「大」サイズ一辺倒だった時代から、現代は「多様化」と「パーソナライズ」が進んでいると言えるでしょう。
今後も、御朱印集めの文化は変化していく可能性があります。
その変化に合わせて、御朱印帳のサイズやデザインも、さらに多様化していくかもしれません。
現在のトレンドを理解しつつ、ご自身にとって最適なサイズを見つけることが大切です。
海外の御朱印帳とのサイズ比較:日本独自の文化
海外の御朱印帳とのサイズ比較:日本独自の文化
御朱印帳は、日本の寺社仏閣で授与される、日本独自の文化に根ざしたアイテムです。
しかし、世界には様々な参拝や祈りの習慣があり、それに伴って、日本とは異なる形式の「記念帳」や「スタンプ帳」が存在します。
ここでは、御朱印帳と、海外の類似したアイテムのサイズを比較しながら、日本独自の御朱印帳文化について考えてみましょう。
海外の「御朱印帳」に相当するアイテム
-
巡礼手帳(ヨーロッパなど)
ヨーロッパの巡礼路(サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路など)では、「巡礼手帳(Credencial)」と呼ばれるものが用いられます。
これは、巡礼中に立ち寄る教会や宿泊施設でスタンプやサインをしてもらうためのもので、一部の場所では記念品としても扱われます。 -
スタンプブック(各地)
観光地やテーマパーク、鉄道の駅などで、記念スタンプを押してもらうための「スタンプブック」も、御朱印帳と似た役割を果たします。
これらは、旅の思い出を記録するためのものです。
サイズ比較
-
御朱印帳(日本)
一般的に、
- 「大」サイズ:縦約18cm × 横約12cm
- 「小」サイズ:縦約15cm × 横約10cm
が主流です。紙は蛇腹式になっていることが多く、墨で文字や印をいただくことが前提とされています。
-
巡礼手帳(ヨーロッパ)
巡礼手帳のサイズは、用途によって様々ですが、一般的には、手のひらサイズから、ノートサイズ(B6~A5程度)まで幅広く存在します。
多くは、冊子状になっており、各ページにスタンプを押すためのスペースが設けられています。
日本のような蛇腹式ではなく、一般的な冊子形式がほとんどです。 -
スタンプブック
スタンプブックも、観光地やイベントによってサイズは大きく異なります。
ポケットに入るような小さなものから、旅行ガイドブックくらいの大きさのものまで様々です。
こちらも、冊子状で、スタンプを押すためのスペースが中心となっています。
日本独自の御朱印帳文化
-
「御朱印」という概念
御朱印帳の最大の特徴は、「御朱印」という、寺社仏閣の参拝の証である「印」と「文字」をいただくことに特化している点です。
これは、仏教や神道における「ご利益」や「ご神徳」を、文字や印という形で授かるという、日本独自の精神文化に基づいています。 -
紙質と墨の特性
御朱印帳の紙質は、墨の滲みにくさや裏移りのしにくさが重視されます。
これは、墨で文字や印をいただくという、日本ならではの書画文化とも関連が深いです。 -
蛇腹式の利便性
蛇腹式は、御朱印を一覧するのに適しており、また、書置きの御朱印を貼る際にも、見開きで綺麗に収まりやすいという利便性があります。
これは、御朱印帳が単なるスタンプ帳とは異なる、記念品としての価値も持つことを示唆しています。 -
デザインの多様性
最近では、御朱印帳のデザインも非常に多様化しており、単なる記録帳としてだけでなく、個人の好みやファッションに合わせて選ばれるようになっています。
これも、御朱印文化がより身近なものになった証と言えるでしょう。
海外の記念スタンプ帳などと比較すると、御朱印帳は「御朱印」という文化に特化し、そのための「紙質」「綴じ方」「サイズ」が洗練されてきた、日本独自の文化遺産と言えるかもしれません。
サイズという一つの要素からも、その背景にある文化の奥深さを感じることができます。
カスタムオーダーできる御朱印帳:自分だけのサイズを追求
カスタムオーダーできる御朱印帳:自分だけのサイズを追求
市販の御朱印帳では、サイズやデザインに満足できない、もっと自分に合ったものを作りたい、と考える方もいらっしゃるでしょう。
近年では、オリジナルの御朱印帳をカスタムオーダーできるサービスも増えています。
ここでは、自分だけのサイズを追求できるカスタムオーダーの魅力について解説します。
カスタムオーダーのメリット
-
理想のサイズを追求できる
カスタムオーダーの最大のメリットは、ご自身の理想とするサイズで御朱印帳を作成できることです。
「大」サイズでも少し大きめにしたい、「小」サイズよりもさらに小さくしたい、あるいは横長サイズにしたい、といった細かな要望にも対応してもらえる場合があります。 -
素材や紙質、綴じ方を自由に選べる
サイズだけでなく、使用する紙の種類(奉書紙、機械漉き和紙など)、綴じ方(蛇腹式、和綴じ、ビス式など)、表紙の素材やデザインなども、ご自身の好みに合わせて選択できることが多いです。
-
オリジナルのデザインで特別感を演出
表紙に、お気に入りの写真やイラスト、家紋などを入れることができるサービスもあります。
世界に一つだけの、自分だけの御朱印帳は、寺社仏閣巡りをより特別なものにしてくれるでしょう。 -
プレゼントにも最適
大切な人への贈り物としても、カスタムオーダーの御朱印帳は大変喜ばれます。
相手の好みや、一緒に訪れた思い出の寺社仏閣にちなんだデザインで作成すれば、心のこもった特別なプレゼントになります。
カスタムオーダーの注意点
-
納期
カスタムオーダーの場合、製作に時間がかかることがあります。
特に、デザインの打ち合わせや、材料の選定などを含めると、数週間から1ヶ月以上かかる場合もあります。
使用したい時期が決まっている場合は、余裕を持って注文することが重要です。 -
費用
市販の御朱印帳に比べて、カスタムオーダーは費用が高くなる傾向があります。
サイズや素材、デザインの複雑さによって価格は変動するため、事前に見積もりを確認することをおすすめします。 -
最低ロット数
一部のカスタムオーダーサービスでは、最低ロット数(最低注文数)が設定されている場合があります。
個人で1冊だけ作りたい場合は、ロット数を確認するようにしましょう。
カスタムオーダーができる場所
-
御朱印帳専門の工房・ショップ
インターネットで「御朱印帳 カスタムオーダー」などと検索すると、専門の工房やオンラインショップが見つかります。
これらのサイトでは、オーダーの流れや料金、過去の作例などが詳しく紹介されています。 -
一部の寺社仏閣
ごく稀に、特定の寺社仏閣で、オリジナルの御朱印帳をカスタムオーダーできるサービスを提供している場合もあります。
お気に入りの寺社仏閣があれば、直接問い合わせてみるのも良いでしょう。
自分だけのサイズ、自分だけのデザインの御朱印帳は、御朱印集めのモチベーションをさらに高めてくれるはずです。
もし、市販の御朱印帳に満足できない場合は、ぜひカスタムオーダーも検討してみてください。
購入前にチェック!御朱印帳のサイズに関する「よくある疑問」を解消
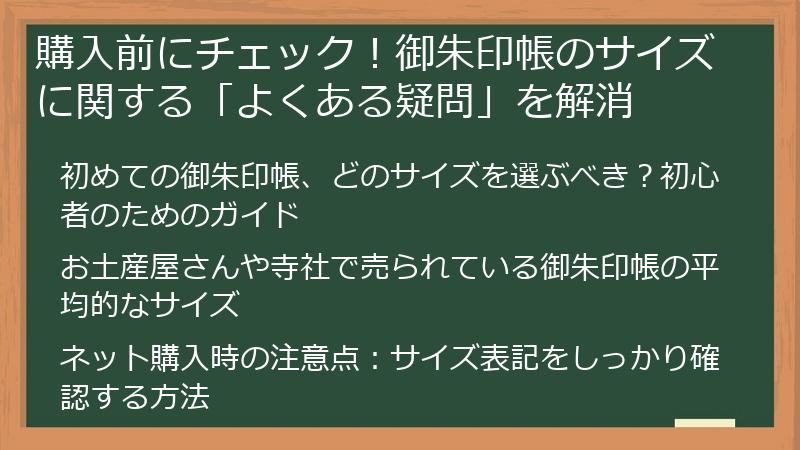
購入前にチェック!御朱印帳のサイズに関する「よくある疑問」を解消
御朱印帳のサイズ選びで、多くの方が抱える疑問や不安をここで解消していきましょう。
初めて御朱印帳を購入する方、お土産屋さんや寺社で御朱印帳を見かけた方、ネットで探している方など、それぞれの疑問に丁寧にお答えします。
サイズ選びで迷わないための、実践的なアドバイスをお届けします。
初めての御朱印帳、どのサイズを選ぶべき?初心者のためのガイド
初めての御朱印帳、どのサイズを選ぶべき?初心者のためのガイド
御朱印集めを始めたいけれど、どのサイズの御朱印帳を選べば良いか分からない、という方も多いでしょう。
初めての御朱印帳選びは、今後の御朱印集めの楽しみを左右する重要なステップです。
ここでは、初心者がサイズ選びで失敗しないためのポイントを、分かりやすく解説します。
初心者はまず「大」サイズを検討
-
汎用性が高く、後悔しにくい
迷ったときは、まず「大」サイズを選ぶことをおすすめします。
「大」サイズは、前述の通り、直書き・書置きのどちらの御朱印も綺麗に収納でき、書き手の方への負担も少なく、携帯性も一般的なカバンには問題なく収まる、という万能なサイズです。
最初の一冊として、最も失敗が少ない選択肢と言えるでしょう。 -
「書置き」を貼ることを想定する
最近では、書置きの御朱印をいただく機会も増えています。
書置き御朱印は、台紙からはがして貼る形式なので、「大」サイズであれば、そのまま綺麗に貼ることができます。
「小」サイズだと、たたんだり、カットしたりといった一手間が必要になる場合があるため、手軽さを重視するなら「大」サイズが有利です。 -
ページ数も多いため長く使える
「大」サイズは、一般的にページ数も多めに作られています。
御朱印集めが軌道に乗って、たくさん御朱印をいただくようになっても、すぐに御朱印帳がいっぱいになる心配が少なく、長く愛用できます。
「小」サイズを選ぶ場合の注意点
-
集める御朱印の種類を考慮
「小」サイズを選ぶ場合は、自分が集めたい御朱印の種類をよく考える必要があります。
もし、書置きの御朱印を多くいただく予定があるなら、「小」サイズでは工夫が必要になることを理解しておきましょう。 -
複数持ちも視野に入れる
「小」サイズを複数冊持ち歩くことも可能です。
もし、デザイン違いでいくつか御朱印帳を持ちたい、という場合は、「小」サイズで揃えるのも良いでしょう。
「中」サイズもバランスが良い選択肢
-
「大」と「小」のちょうど中間
「大」サイズは少し大きいと感じるけれど、「小」サイズでは物足りない、という方には「中」サイズがおすすめです。
携帯性と収納力のバランスが取れており、多くの用途に対応できます。
初心者がサイズ選びで後悔しないためのアドバイス
-
まずは実物を見てみる
可能であれば、お土産屋さんや寺社仏閣で、実際に御朱印帳のサイズを手に取ってみることを強くおすすめします。
サイズ感や重さ、紙の質感などを確認することで、より自分に合ったものを見つけやすくなります。 -
普段使いのカバンとの相性を考える
普段お使いのカバンに、どのくらいのサイズの御朱印帳が無理なく入るか、事前に確認しておきましょう。
-
「迷ったら大」を基本に
それでも迷う場合は、まずは汎用性の高い「大」サイズを選んでみるのが、失敗しないための鉄則です。
初めての御朱印帳は、あなたの御朱印集めの旅の始まりです。
サイズ選びに悩む時間も、楽しみながら、あなたにとって最高のパートナーとなる一冊を見つけてください。
お土産屋さんや寺社で売られている御朱印帳の平均的なサイズ
お土産屋さんや寺社で売られている御朱印帳の平均的なサイズ
寺社仏閣を訪れると、多くの場合、お土産屋さんや授与所で御朱印帳が販売されています。
こうした場所で一般的に売られている御朱印帳は、どのようなサイズが多いのでしょうか。
ここでは、お土産屋さんや寺社でよく見られる御朱印帳の平均的なサイズについて解説します。
「大」サイズが圧倒的に多い
-
標準的な「大」サイズが主流
お土産屋さんや寺社で販売されている御朱印帳の多くは、「大」サイズです。
これは、前述の通り、汎用性が高く、書置き御朱印も貼りやすく、書き手の方への負担も少ないため、最も扱いやすいサイズだからです。 -
具体的な寸法
具体的には、縦が約18cm、横が約12cm前後が平均的な寸法となります。
一部、これよりも若干大きいものや、小さいものもありますが、このサイズ感が標準と言えるでしょう。 -
紙質は奉書紙が多い
素材としては、墨の滲みにくさに優れた奉書紙が使用されていることがほとんどです。
しっかりとした厚みがあり、墨書きも綺麗に映える紙質です。
「小」サイズや変形サイズも
-
近年は「小」サイズも増加傾向
近年、御朱印集めの人気が高まるにつれて、お土産屋さんや寺社でも「小」サイズの御朱印帳を見かける機会が増えています。
特に、デザイン性の高いものや、寺社オリジナルのデザインのものなどで、「小」サイズが用意されていることがあります。 -
変形サイズは限定的
変形サイズ、例えば横長タイプや特殊な形状の御朱印帳は、お土産屋さんや寺社で一般的に販売されているものは少ない傾向にあります。
こうした御朱印帳は、専門の工房やネット通販などで探す方が見つけやすいでしょう。
購入時の確認ポイント
-
必ず寸法を確認する
同じ「大」サイズと表示されていても、微妙に寸法が異なる場合があります。
購入する際には、必ず商品の表示されている寸法を確認し、ご自身の用途に合っているか確認しましょう。 -
紙質や綴じ方もチェック
サイズだけでなく、紙質や綴じ方なども、可能であれば実物で確認できると良いでしょう。
特に、墨の裏移りや滲みが気になる方は、紙の厚みや質感に注目してみてください。 -
デザインも大切に
御朱印帳は、旅の思い出を記録する大切なアイテムです。
サイズや機能性だけでなく、ご自身の好みに合ったデザインのものを選ぶことも、長く愛用するための秘訣です。
お土産屋さんや寺社で御朱印帳を選ぶ際は、まず「大」サイズを基準に、いくつかの選択肢を比較検討してみてください。
そして、その日の気分や、どんな御朱印をいただきたいかに合わせて、お気に入りの一冊を見つけてください。
ネット購入時の注意点:サイズ表記をしっかり確認する方法
ネット購入時の注意点:サイズ表記をしっかり確認する方法
インターネット通販で御朱印帳を購入する際、実物を見ることができないため、サイズ選びで失敗するリスクが伴います。
しかし、いくつかの注意点を押さえれば、オンラインでも安心して、ご自身にぴったりの御朱印帳を見つけることができます。
ここでは、ネット購入時のサイズ確認方法と、注意すべき点について解説します。
サイズ表記の確認
-
具体的な寸法を確認する
商品の説明欄に記載されている「大」「小」といった表示だけでなく、必ず具体的な寸法(縦〇〇cm × 横〇〇cm)を確認しましょう。
「大」サイズと一口に言っても、メーカーによって多少の差があるため、この具体的な寸法が重要です。 -
ページ数もチェック
御朱印帳のページ数も、サイズ選びの参考になります。
「大」サイズでページ数が多いものを選べば、長く使えますし、「小」サイズでページ数が少ないものを選べば、コンパクトに保管できます。 -
「蛇腹式」か「和綴じ」「ビス式」か確認
サイズだけでなく、綴じ方も確認しておきましょう。
蛇腹式、和綴じ、ビス式など、それぞれの特徴を理解しておくと、使い勝手をイメージしやすくなります。
写真だけでは分からない実用性の確認
-
紙の厚みや質感
ネット上の写真だけでは、紙の厚みや質感まで正確に把握することは難しいです。
可能であれば、レビューを参考にしたり、「奉書紙使用」「裏移りしにくい紙」といった表記があるか確認したりすると良いでしょう。 -
表紙の素材感
表紙の素材(布製、紙製、ビニール製など)も、写真だけでは伝わりにくい部分です。
素材の特徴や、耐久性、撥水性などについても、説明文をよく読みましょう。 -
重さ
御朱印帳の重さも、携帯性に関わる重要な要素です。
特に、たくさんの御朱印をいただく予定のある方は、重さも確認しておくと安心です。
レビューや口コミの活用
-
他の購入者の意見を参考にする
ネット通販では、実際に購入した人のレビューや口コミが大変参考になります。
サイズ感や使い心地、紙質などについて、他の購入者がどのような感想を持っているかを確認しましょう。 -
「サイズが思っていたより大きかった/小さかった」という意見に注目
特に、サイズに関するレビューは、購入前に必ずチェックしておきたい情報です。
「想像していたよりも大きかった」という意見が多い場合は、ご自身が希望するサイズよりも一回り小さいものを選ぶ、といった判断材料になります。
注文前の最終確認
-
返品・交換ポリシーを確認
万が一、届いた御朱印帳のサイズが合わなかった場合のために、サイトの返品・交換ポリシーを確認しておきましょう。
返品や交換が可能であれば、安心して購入できます。 -
送料や配送日数も確認
最終的な購入金額や、手元に届くまでの日数も、事前に確認しておきましょう。
インターネットでの御朱印帳購入は、選択肢が豊富で便利ですが、サイズ選びには慎重さが求められます。
今回ご紹介した注意点を参考に、後悔のないお買い物を楽しんでください。
【まとめ】あなたにぴったりの御朱印帳サイズを見つけよう
【まとめ】あなたにぴったりの御朱印帳サイズを見つけよう
ここまで、御朱印帳のサイズについて、その種類、選び方、素材や仕様、収納方法、そしてサイズにまつわる豆知識まで、多岐にわたって解説してきました。
御朱印帳のサイズ選びは、単に見た目の好みだけでなく、ご自身の寺社仏閣巡りのスタイルや、集める御朱印の種類、普段使いのアイテムとの相性など、様々な要素が関係してきます。
この記事で得た知識を元に、あなたにとって最高の御朱印帳サイズを見つけ、より豊かな御朱印巡りを楽しんでください。
これだけは押さえたい!御朱印帳サイズ選びの3つのポイント

これだけは押さえたい!御朱印帳サイズ選びの3つのポイント
数ある御朱印帳の中から、自分にぴったりの一冊を見つけるための、重要なポイントを3つに絞ってご紹介します。
サイズ選びに迷ったときは、この3つのポイントを思い出してください。
あなたの寺社仏閣巡りを、より快適で、より楽しいものにしてくれるはずです。
参拝頻度と集めたい御朱印の種類
参拝頻度と集めたい御朱印の種類
御朱印帳のサイズを選ぶ上で、まず考えるべきは、ご自身の「参拝頻度」と「集めたい御朱印の種類」です。
これら二つの要素を明確にすることで、最適なサイズが見えてきます。
参拝頻度で考えるサイズ
-
頻繁に参拝する方
月に数回以上、あるいは毎週のように寺社仏閣に足を運ぶ方は、「大」サイズがおすすめです。
「大」サイズは、ページ数が多く、書置き御朱印も綺麗に貼れるため、御朱印帳を頻繁に交換する必要がなく、長く愛用できます。
携帯性も、普段カバンを持ち歩く方であれば問題ないでしょう。 -
たまに参拝する方
年に数回程度、あるいは特定の季節に集中して参拝するという方には、「小」サイズや「中」サイズも選択肢に入ります。
「大」サイズではページを持て余してしまう可能性もありますし、「小」サイズであればコンパクトに保管できます。
ただし、書置き御朱印を貼る際には、サイズ調整が必要になる場合があることを考慮しましょう。
集めたい御朱印の種類で考えるサイズ
-
書置き御朱印を多く集めたい場合
書置きの御朱印を綺麗に収納したい場合は、やはり「大」サイズが最も適しています。
御朱印のサイズに合わせて、たたんだり、カットしたりする手間なく、そのまま貼れるため、手軽にコレクションできます。 -
直書き御朱印をメインに集めたい場合
直書きの御朱印を主にいただくのであれば、「大」サイズはもちろん、「中」サイズでも十分対応可能です。
「大」サイズは、書き手の方も書きやすく、また、御朱印の文字や印がゆったりと収まるため、見栄えも良くなります。 -
直書き・書置き両方楽しみたい場合
どちらも楽しみたいという欲張りな方には、「大」サイズが最も汎用性が高くおすすめです。
「中」サイズもバランスが良い選択肢ですが、書置き御朱印のサイズによっては工夫が必要になることもあります。
サイズ選びのヒント
-
まずは「大」サイズを基本に
御朱印帳選びに迷ったら、まずは汎用性の高い「大」サイズを基本に考えてみるのがおすすめです。
-
普段使いのカバンも考慮
「大」サイズは、普段お使いのカバンに無理なく収まるかどうかも、大切な判断材料になります。
ご自身の参拝スタイルと、集めたい御朱印の種類を明確にすることで、御朱印帳のサイズ選びはぐっと具体的になります。
この2つのポイントをしっかり押さえて、あなただけの理想の一冊を見つけてください。
普段使いのカバンとの相性
普段使いのカバンとの相性
御朱印帳は、寺社仏閣に参拝する際に持ち歩くものですが、普段からカバンに入れて携帯する方も多いでしょう。
そのため、ご自身が普段お使いのカバンに、どのくらいのサイズの御朱印帳が無理なく収まるか、という視点も、サイズ選びにおいては非常に重要です。
カバンに合わせたサイズ選びのポイント
-
大きめのカバン(A4サイズ以上)をご利用の方
トートバッグ、リュックサック、ビジネスバッグなど、A4ファイルが楽に収まるような大きめのカバンをお使いの方であれば、「大」サイズの御朱印帳でも問題なく収納できます。
「大」サイズはページ数も多いため、頻繁に参拝される方や、書置き御朱印を多くいただく方には、このカバンサイズに合った「大」サイズがおすすめです。 -
小さめ・コンパクトなカバンをご利用の方
ショルダーバッグ、サコッシュ、ボディバッグ、あるいは小さめのハンドバッグなど、コンパクトなカバンを普段お使いの方は、「小」サイズの御朱印帳が適しています。
「小」サイズであれば、カバンの中で場所を取らず、他の荷物とも干渉しにくいため、スマートに持ち運べます。 -
「中」サイズは汎用性の高い選択肢
「大」サイズでは少し大きいと感じるが、「小」サイズでは物足りない、という方には「中」サイズがおすすめです。
「中」サイズは、「大」サイズと「小」サイズの中間の大きさなので、多くのカバンに比較的無理なく収まり、携帯性と収納力のバランスが取れています。 -
御朱印帳専用ケースの活用
カバンの中に御朱印帳をそのまま入れるのではなく、御朱印帳専用のケースやポーチを使用すると、サイズに関わらず、カバンの中での整理がしやすくなります。
「大」サイズには少しゆとりのあるケース、「小」サイズにはスリムなケースが適しています。
カバンへの出し入れやすさも考慮
-
すぐに取り出せるか
御朱印をいただく際に、カバンから御朱印帳をスムーズに取り出せるかどうかも、意外と大切なポイントです。
頻繁に開閉する方は、カバンの中で御朱印帳がどこにあるか分かりやすいように、工夫しておくと良いでしょう。 -
御朱印帳の保護
カバンの中で他の荷物とぶつかったり、圧迫されたりしないように、御朱印帳を保護することも重要です。
ケースに入れるなどの工夫をすることで、御朱印帳の傷みや折れを防ぐことができます。
普段お使いのカバンと、御朱印帳のサイズとの相性を考慮することで、御朱印帳はより身近で、愛着の湧く存在になります。
あなたのライフスタイルに合ったサイズを見つけて、寺社仏閣巡りをさらに快適に、そして楽しくしましょう。
お財布やカードケースとの比較
お財布やカードケースとの比較
御朱印帳のサイズ選びにおいて、普段お使いのお財布やカードケースとの比較は、その携帯性を具体的にイメージする上で非常に役立ちます。
特に、カバンを持たずに外出することが多い方や、カバンの中身をコンパクトにまとめたい方にとっては、この比較がサイズ選びの決め手となることもあります。
お財布・カードケースと御朱印帳のサイズ感
-
長財布との比較
一般的な長財布は、縦約10cm、横約20cm程度のものが多いです。
これと比較すると、「大」サイズの御朱印帳(縦約18cm、横約12cm)は、長財布よりも縦幅が短く、横幅はやや狭い、といったサイズ感になります。
長財布をお使いの方であれば、「大」サイズの御朱印帳も、カバンの中での収まりが良いと感じられるでしょう。 -
二つ折り財布やカードケースとの比較
二つ折り財布や、キャッシュレス化が進みカードケースのみをお使いの方にとっては、「小」サイズの御朱印帳(縦約15cm、横約10cm)が、お財布やカードケースのサイズ感に近く、携帯しやすいと感じられることが多いでしょう。
「小」サイズであれば、お財布と一緒にポケットや小さなポーチに収納しやすい場合もあります。 -
御朱印帳を「お財布」のように持ち歩く場合
最近は、スマートフォンとカードケース、そして御朱印帳だけで身軽に外出する方も増えています。
こうしたスタイルの方には、さらにコンパクトな「ミニ御朱印帳」や、非常にスリムな「小」サイズがおすすめです。
お財布感覚で持ち歩けるサイズ感は、日々の外出をより快適にしてくれます。
サイズ比較から考える携帯性
-
「大」サイズ
長財布と比べると、携帯性はやや劣りますが、一般的なカバンには無理なく収まります。
-
「小」サイズ
二つ折り財布やカードケースに近いサイズ感で、ポケットにも収まりやすいため、携帯性は非常に高いと言えます。
-
「中」サイズ
「大」サイズよりはコンパクトで、「小」サイズよりは収納力があるため、お財布との相性も悪くありません。
多くの場合、長財布と二つ折り財布の中間的なサイズ感で、カバンへの収まりも良好です。
御朱印帳を「見せる」アイテムとして
御朱印帳のデザインによっては、カバンから取り出した際におしゃれに見せたい、という方もいらっしゃるでしょう。
お財布やカードケースとのサイズ感を考慮し、カバンに入れた際の全体のバランスも考えて選ぶと、より満足度の高い御朱印帳選びができるはずです。
普段お使いのお財布やカードケースのサイズ感を基準に、御朱印帳のサイズをイメージすることで、より具体的なサイズ選びが可能になります。
ぜひ、ご自身の持ち物との相性も考慮して、お気に入りの一冊を見つけてください。
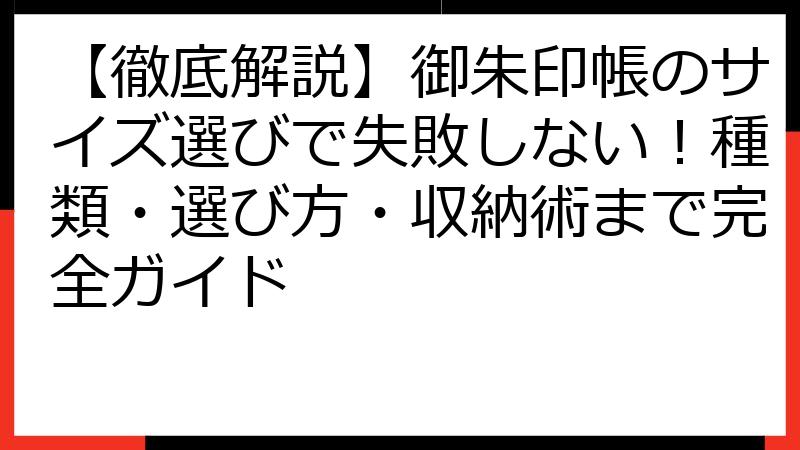
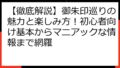
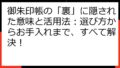
コメント